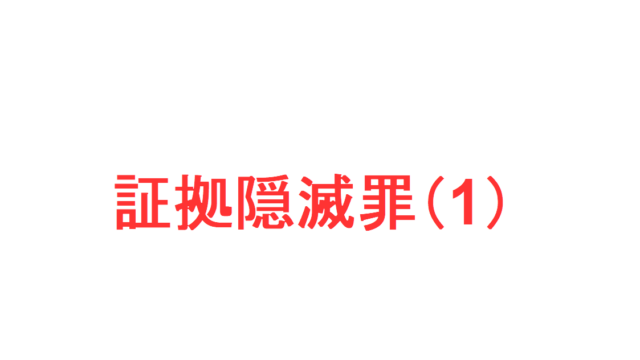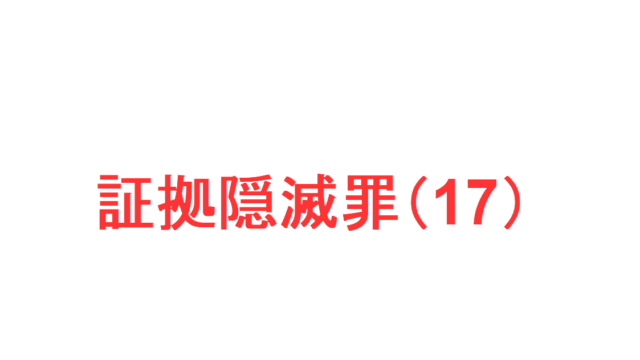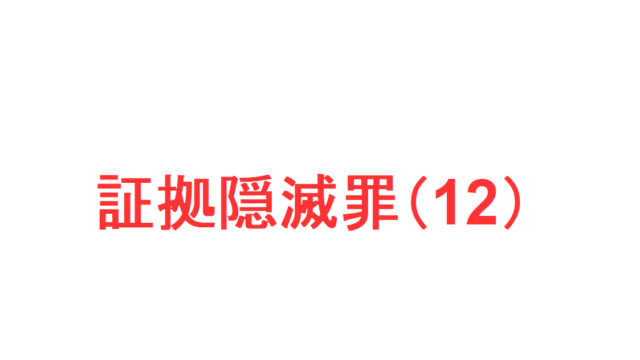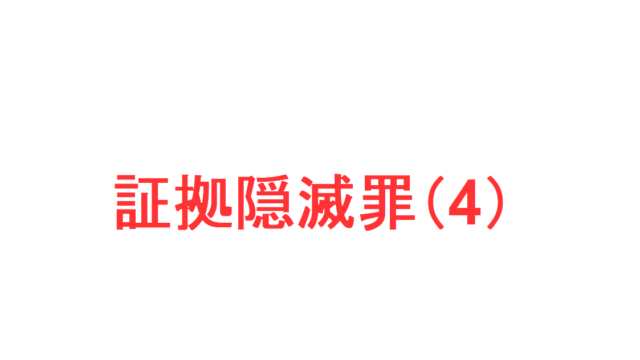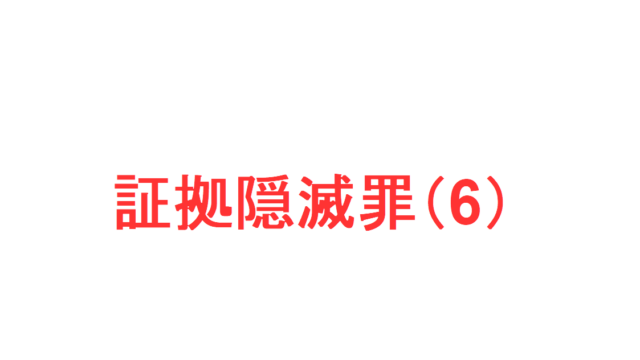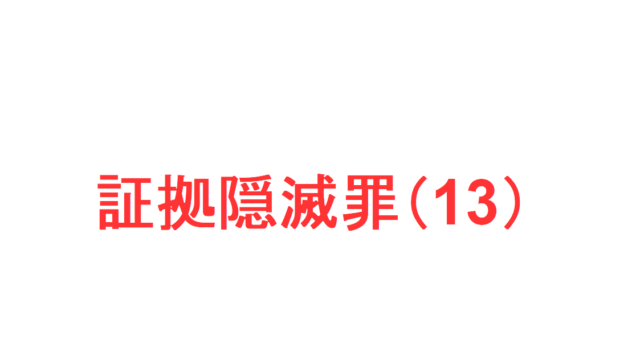前回の記事の続きです。
参考人が検察官や警察官に虚偽の供述をし、供述調書が作成された場合、証拠隠滅罪が成立するか?
捜査中の事件に関し、検察官や警察官が参考人の取調べを行い、参考人が検察官や警察官に対し虚偽の供述(例えば、犯人は無実だとするうその供述)をし、検察官や警察官がその供述内容を基に供述調書を作成した場合、証拠隠滅罪(刑法104条)が成立するかについて、裁判例は証拠隠滅罪は成立しないとしています。
この点を判示した以下の裁判例があります。
千葉地裁判決(平成7年6月2日)
他人の刑事被疑事件について、参考人として検察官に虚偽の供述をし、その旨の供述調書を作成させた行為について、証拠偽造罪は成立しないとした事例です。
裁判官は、
- 他人の刑事被疑事件について、参考人として、取調べを受け、その際、虚偽の事実を供述
 する、特に、本件のように、全く架空の事実関係を作り上げてそれを積極的に捜査担当検察官に供述することは、悪質な捜査妨害というほかなく、供述調書が作成されるに至ったことをとらえてその処罰を求める本件起訴に、ある程度実質的な理由が存することは認めざるを得ないところである
する、特に、本件のように、全く架空の事実関係を作り上げてそれを積極的に捜査担当検察官に供述することは、悪質な捜査妨害というほかなく、供述調書が作成されるに至ったことをとらえてその処罰を求める本件起訴に、ある程度実質的な理由が存することは認めざるを得ないところである - しかし、それが、平成7年法律第91号(刑法の一部を改正する法律)附則2条1項本文により同法による改正前の刑法104条にいう証拠を偽造した場合に当たるといえるかは、一つの問題である
よって、検討するに、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることは、それが犯人隠避罪に当たり得ることは別として、証拠偽造罪には当たらないものと解するのが相当である(大審院大正3年6月23日判決・刑録20輯1324頁、同昭和8年2月14日判決・刑集12巻1号66頁、同昭和9年8月4日判決・
刑集13巻14号1059頁、最高裁昭和28年10月19日第ニ小法廷決定・刑集7巻10号1945頁、大阪地裁昭和43年3月18日判決・判例タイムズ223号244頁、宮崎地裁日南支部昭和44年5月22日判決・刑裁月報1巻5号535頁参照)
- それでは、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をしたにとどまらす、その虚偽供述が録取されて供述調書が作成されるに至った場合、すなわち、本件のような場合は、どうであろうか
- この場合、形式的には、捜査官を利用して同人をして供述調書という証拠を偽造させたものと解することができるようにも思われる
- しかし、この供述調書は、参考人の捜査官に対する供述を録取したにすぎないものであるから(供述調書は、これを供述者に読み聞かせるなどして、供述者がそれに誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができるところ、本件にあっても、被告人が供述調書を読み聞かされて誤りのないことを申し立て署名指印しているが)、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることそれ自体が、証拠偽造罪に当たらないと同様に、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証拠偽造罪を構成することはあり得ないものと解すべきである
- してみると、前記公訴事実は罪とならないから、右公訴事実について、刑事訴訟法336条により被告
人に対し無罪の言い渡しをすることとする
と判示しました。
千葉地裁判決(平成8年1月29日)
刑事被疑事件について、無関係の第三者に依頼して参考人として検察官に虚偽の事実を供![]() 述させ、その旨の供述調書を作成させたとしても、
述させ、その旨の供述調書を作成させたとしても、![]()
![]() 刑法104条の証拠隠滅罪教唆罪は成立しないとした事例です。
刑法104条の証拠隠滅罪教唆罪は成立しないとした事例です。
裁判官は、
- 参考人が捜査官に虚偽の供述をし、捜査官をしてこれに基づく供述調書を作成させる行為については、それが証拠隠滅罪の保護法益である当該刑事事件の適正な捜査、審判を阻害するおそれがあることは否定できない
- ところで、刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)は、刑事事件に関する国家の司法作用(ここでは拘禁作用は除く)を保護の対象とする罪として、宣誓した証人の偽証(169条)、宣誓した鑑定人又は通訳人の虚偽鑑定又は通訳(171条)、他人に誤った刑事処分等を受けさせる目的をもった誣告(172条)、犯人等の蔵匿・隠避(103条、以下「犯人隠避」という。)及び証拠隠滅(104条)を規定している
- そして、犯人隠避のほか証拠隠滅(偽造)についても、規定上明示されていないものの、虚偽供述という方法でこれを犯すことを想定することはできる
- しかし、以下の理由により、刑法は、虚偽供述を手段とする刑事司法作用の妨害については、それが明示的に行為類型とされている偽証、虚偽鑑定又は通訳及び誣告(以下「偽証罪等」という。)と、犯人の身柄の確保ないし特定作用を害する犯人隠避に限って可罰性を認める趣旨であり、それ以外の虚偽供述について証拠隠滅罪が成立することはないと解するのが相当であ (大審院昭和9年8月4日判決・刑集13巻14号1059頁、最高裁昭和28年10月19日決定・刑集7巻10号1945頁等参照)
- 1 前記各処罰規定による保護の対象は、刑事事件に関しては、それぞれ国家の捜査、審判、刑の執行の各作用の全部又は一部であって(ただし、誣告は個人的法益を含む)、必ずしも同一ではないが、いずれも国家の司法作用を保護するものであることに変わりはない
- しかるに、刑法が明示的に虚偽供述を処罰対象としているのは偽証罪等に限られている
- 確かに捜査、審判にとって人の供述は重要な証拠である
- しかし、人の供述にはもともと不誠実で移ろいやすい面がある
- 供述事項との利害関係、事件関係者その他との人間関係、他からの圧力等によって、往々にして、人の供述は真実と虚偽(ないし記憶どおりの内容と記憶に反する内容)の間を変転し、また、虚偽(ないし記憶に反すること)を織り交ぜてなされる
- 人の供述の証拠価値は、このような性格を踏まえて評価されるべきであり、現にそのようになされているのが一般である
- 物的証拠のように、一見動かし難い証拠が捏造される場合に比べると、虚偽供述によって司法作用を侵害する程度は高いものではない
 そうすると、刑法の虚偽供述に対する基本的な態度は、刑事司法作用の中で最も重要な段階である審判手続(及びそれに近い形試の証拠保全や公判前の証人尋問の手続)で宣誓の上なされた虚偽供述と、被申告者の利益をも害する誣告に限って処罰する趣旨であると解すべきである
そうすると、刑法の虚偽供述に対する基本的な態度は、刑事司法作用の中で最も重要な段階である審判手続(及びそれに近い形試の証拠保全や公判前の証人尋問の手続)で宣誓の上なされた虚偽供述と、被申告者の利益をも害する誣告に限って処罰する趣旨であると解すべきである- 2 虚偽供述が証拠隠滅罪に該当することになると、処罰の対象は非常に広範で不明確になる
- すなわち、当該刑事事件に関する虚偽の供述は、これを取扱う捜査・審判機関ばかりでなく、弁護人や一般私人に対してもなされ、関係する民事・行政手続でもなされる
- そのような供述であっても、録取あるいは聴取者の記憶を介して後に当該刑事事件の捜査・審判手続に提出されることは可能であり、刑事司法作用を誤らせるおそれがあるものとして、同罪に該当することになってくる(刑事司法作用を妨害する積極的意図は同罪の要件ではない。)
- しかも、同罪にいう証拠とは、犯罪の態様や刑の軽重、情状に関する資料にも及ぶとされているから、その面でも対象に広がりがある
- こうした処罰対象の問題は、単に起訴裁量によって解決できるものではない
- これに対し、虚偽の供述による犯人隠避では、処罰の対象は犯人の身柄の確保ないし特定を妨げる虚偽供述に限られる
- かつ、それは情状関係などに比べて遙かに重要な事項である
- 供述の機会や方法も、捜査機関への申告や情報提供等、隠避の目的を達するようなものでなければならない
- 右のような刑事司法作用に対する有害性の程度や、処罰対象を画する要件の存在に鑑みると、前記1の理解を前提にしても、虚偽供述
を手段とする犯人隠避罪については、これを肯定する必要性と合理性がある
- 3 偽証罪等に該当しない訴訟上の虚偽供述について一部検討すると、刑事・民事訴訟における宣誓無能力者についてはその能力に照らし、民事訴訟における宣誓拒絶又は免除の証人(実際は稀有と思われるが)についてはその証言事項に照らし、いずれも宣誓をさせても真実の供述を期待することはできないとして宣誓をさせずに証言させるものであるから、刑罰をもって真実の供述を強制することは妥当でない
- また、民事訴訟の当事者尋問では、当事者が訴訟の結果に直接の利害関係があり、陳述の証明力に限界があることを前提として、宣誓の上虚偽の陳述をしても過料の制裁を受けるにとどまっている(民訴法339条)
- 例えば、従業員が起こした犯罪の被害者(原告)が使用者(被告)に民法715条による損害賠償を請求した場合や、犯罪被害者(原告)が犯罪者に処する損害賠償請求権に基づいて第三債務者(被告)に代位訴訟を提起した場合等を考えると、各原告、被告が当該犯罪について虚偽の陳述をしたからといって、これに刑罰を加えるのは前記民事訴訟法の趣旨に反すると考えられる
- 4 捜査官等は既に収集した資料から、事件について一定の見解をもって取調べや事情聴取に臨むことがある
- 参考人の虚偽供述について証拠偽造罪が成立することになると、参考人が捜査官等の見解と異なる供述をした場合、捜査官等の認識としては参考人は同罪を犯すことになる
- 捜査官等のこのような認識が取調べや事情聴取に反映すると、もちろん参考人から記憶どおりの供述が導かれることもあるが、逆に、記憶に反する供述が導かれるおそれも否定できない
- 右に述べたような、刑法における虚偽供述の取扱い、処罰対象の過度の広がりと不明確性、関連法規との
整合性等を考慮すると、前記のとおり、偽証罪等及び犯人隠避罪に該当しない虚偽供述については、証拠隠滅罪によって処罰されることはないと解すべきである
なお、検察官は、参考人の虚偽供述が証拠湮滅罪に該当する根拠として、参考人はその実質を考えれば同人に保存された過去の記憶であり、裁判例(最高裁昭和36年8月18日決定・刑集15巻7号1293頁)において証拠隠滅とされている参考人の隠匿は、その記憶を使用できないようにする行為であり、虚偽を供述する行為は真実の記憶の顕出を妨げる証拠隠滅、あるいは虚偽の外観上の記憶を作り出すとともにこれを使用する証拠偽造及び使用であると主張する
- しかし、右裁判例は、供述して証拠資料を提供しうる立場にある者、すなわち参考人を、捜査機関等が利用することを妨げる行為を証拠隠滅としたまでで、参考人の
「供述」についての結論を左右するものではない
- 前記見解はあたかも「記憶」を「証拠」とするようであるが、証拠とはそれを知覚して事実を認定するものであって、知覚することのできない「記憶」を証拠とみ
ることはできない
- 本件のように、参考人の虚偽供述を捜査官が録取し、参考人が読み聞かせを受け、誤りのないことを申し立てて署名押印し、これによって供述調書が完成すると、供述内容は明確になり、かつそこに固定されることになる
- 右供述調書はいわゆる「証拠方法」として、後にその記載から供述者が知覚した事実を推認することができるようになる
- しかし、その点をとらえて証拠隠滅(偽造)罪の成立を肯定すべきではない(以下、書面が作成された場合のみを対象とするときは証拠偽造罪と表記する。)
- その理由として以下の点を指摘することができる
- 1 単に、供述が何らかの「証拠方法」に転化したことを理由に証拠偽造罪の成立を認めるとすれば、刑法が虚偽供述の可罰性を偽証罪等に限った趣旨を大きく損う結果になる
- すなわち、民事訴訟手続など供述の録取が法定されているものは多数存在する
- そこでは、供述者は録取され(てい)ることを認識しているのが普通であるから、ほぼ全部について録取者を利用した証拠偽造罪の間接正犯が成立することになる
録取が法定されていない場合でも、聴取者が供述中にメモや録音をとったり、署名押印を得るに至らないまでも一応供述録取書を作成したりすることは少なくない
- これらの書類であっても、後記2のとおり、捜査、審判において証拠として使用される可能性のある証拠方法であることに変わりはない
- ここでも、供述者は録取されていることを容易に認識するであろうから、録取内容が供述と全く違っていたとき以外は、ほとんど前同様に間接正犯が成立することになる
- これらのほか、捜査官等が作成した供述録取書に署名押印した場合を含めると、捜査官、弁護人の簡単な事情聴取や単なる私人間の話を除いては、虚偽供述の大半は何らかの証拠方法に転化し、証拠偽造罪の対象となってしまう
- 2 検察官は、供述書との関係で、供述録取書に対する署名押印の意義を強調する
- しかし、署名押印には証拠偽造罪の成否を左右する特段の意義は認められない
- 署名押印は、録取内容の正確性を承認する意義を有しているにすぎない。(検察官も同じ見解)。
- 正確に録取されている限りそれ自体に虚義性はない
- 署名押印は、ニ重の伝聞性を解消する効果を有するが(刑事訴訟法321条1項)、事実上はともかく、法律上は供述内容自体に真実性を付与したり、これを強化したりするわけではない
- 同条1項各号における証拠能力の差は、供述の真実性と関係するようであるが、それは聴取者の立場や供述された機会の違いによる真実性の状況的保障の差に由来するものであって、署名押印とは無関係である
- 他方、署名押印を欠く供述録取書や録音等も、同法326条の同意や録取の正確性を担保する外部的状況の存在等によって証拠能力を取得する余地がある
- 結局、公判段階においても、署名押印の有無は、それを欠くと録取の正確性も問題とされることから生じる証拠能力及び証拠力の程度の差にすぎず、捜査公判を通じてみれば、いずれも証拠として使用されうるものであって、その危険性に決定的な違いはない
- また、供述者は、署名押印をして初めて作成に直接関与するとはいえ、署名押印を欠く供述録取書等でも、録取されていることが分かり切って供述しているのなら、承認尋問調書同様、間接正犯とすべきであって、ここでも署名押印に意味はない
- 更に、参考人が捜査官から署名押印を求められた場合、虚偽の供述であっても、往々にしてそのままこれに応じることも多いと考えられ、供述録取書の作成と署名押印を要件としても、メモ等が除かれる程度で、処罰範囲を限定することはそれぽど期待できない
- 3 前記最高裁昭和28年10月19日決定は「刑法104条の証拠の偽造というのは証拠自体の偽造を指称し承認の偽証を包含しないと解すべきであるから、自己の被告事件について他人を教唆して偽証させた場合に右規定の趣旨から当然に偽証教唆の責を免れるものと解することはできない。」と判示している
- 証言あるいは手続上当然に作成される証人尋問調書の完成によって証拠偽造罪が成立するとすと偽証した証人の行為は偽証と証拠偽造(後者であれば間接正犯)を犯し、特別法としての偽証罪のみが成立する
- 当該被告人については、それぞれの教唆にあたるが、犯人による証拠偽造教唆を肯定する判例の立場(大審院昭和10年9月18日判決・刑集14巻997頁等)からすれば、当然偽証教唆は可罰的となり、同罪のみが成立する
- しかるに、右決定はこうした構成をとらず、犯人である右被告人が「証人の偽証」という証拠を偽造するという構成をとり、「証人の偽証」は証拠偽造の対象にならないとして、偽証教唆の可罰性を理由づけている
- 同決定は本件の問題に直接言及したものではないが、虚偽供述はもちろん、それに基づいて手続上当然に尋問調書が作成された場合も含めて、供述者に証拠偽造罪の成立を認めないことを前提にしたものと理解することができる
- 4 捜査官等は、自己の見解と異なる内容の供述録取書が完成すれば、それによって参考人が証拠偽造罪を犯したと認識することになる
- 証拠偽造罪の成立を供述録取書が完成した場合に限るとしても、前記2の4の虚偽供述が導かれるおそれという問題は依然として存在する
- 以上によれば、偽証罪等及び犯人隠避罪に該当しない参考人の虚偽供述について証拠隠滅罪は成立せず、また、手続上当然に録取され、あるいは、本件のように聴取者の裁量により供述録取書が作成され供述者が署名押印するなどして、右虚偽供述が証拠方法たる書面等に転化した場合についても、同罪として処罰すべきではないことになる
- 付言すれば、捜査官等が聴取した上で参考人に言述させた上申書等についても、供述が転化したといえるものであれば、同様に解すべきである
- なお、検察官主張のとおり、作成名義人による内容虚偽の上申書等の作成を証拠偽造罪とした裁判例が存在する(上申書につき東京高裁昭和40年3月29日判決・高刑集18巻2号126頁等、死亡事故発生報告書につき仙台地裁気仙沼支部平成3年7月25日判決・判例タイムズ789号275頁。内容のみが虚偽の供述書は、作成者が作成時点で記載どおりの意思内容を表現したことに虚偽性はないが、実際の受領日よりも受領日付を遅らせた領収証を作成日付の当日に作成した場合等を考えると、証拠偽造罪の適用が考えられる。)
- しかし、こうした裁判例は、参考人が取調べ等以外の場で、当初から虚偽の書面を作成することを企てて打ち合わせた上、虚偽の内容を書面に表現した事案であり、供述が書面等に転化した場合ではないから、当裁判所の見解と矛盾するものではない
- 最後に、検察官は、本件のように全く関係のない第三者を参考人として偽作した場合は可罰性が高いと主張する
- 確かに、犯人が無関係の第三者を巻き込んで証拠隠滅を企てることは犯人の情状としては悪質であり、第三者が取引に応じて積極的に虚偽の供述をするのは極めて不当な捜査妨害である
- しかし、保護法益との関係では、無関係の第三者の虚偽供述の方が、一般に事件関係者のそれよりも刑事司法作用を阻害するおそれが強いというわけではない
- 無関係の第三者文は積極的な虚偽供述に限るといっても、被疑者の家族、友人、知人が情状関係を聴取されたときに罪体について虚偽供述を始めたらどうか、参考人として聴取されたが実際は何の関係もない者はどうか、捜査機関から関係者として把握されていた者が呼出しもないのに出頭し供述したときはどうか等の疑問が生ずる
- 右のような不明確な基準を適用し
て、敢えて本件について証拠隠滅(教唆)罪の成立を認めるのは相当でない
- 以上のとおりであるから、弁護人主張のとおり、本件における前記xの行為は証拠湮減(偽造)罪に該当せず、前記公訴事実は同教唆罪とならないので、刑事訴訟法336条前段により、被告人に対し無罪を言い渡すこととする
と判示しました。