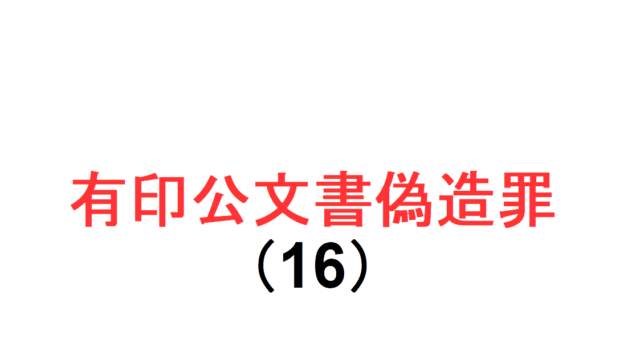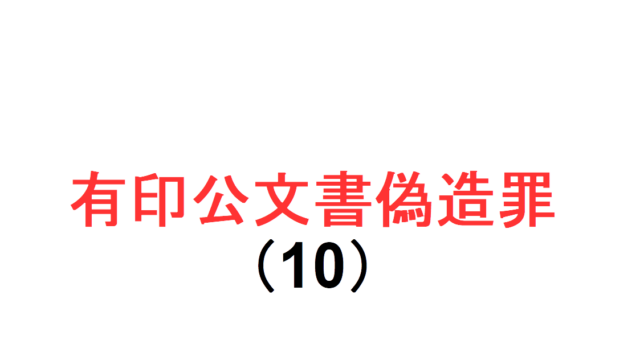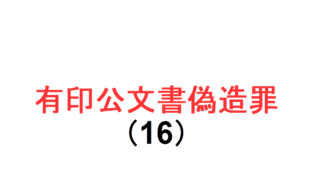有印公文書偽造罪(15)~「他罪との関係」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を説明します。
他罪との関係
有印公文書偽造罪と
- 公印偽造罪(刑法165条1項)、偽造公印使用罪(刑法165条2項)、公記号偽造罪(刑法166条1項)、偽造公記号使用罪(刑法166条2項)
- 詐欺罪(刑法246条)
- 窃盗罪(刑法235条)、横領罪(刑法252条)
- 収賄罪(刑法197条)、贈賄罪(刑法198条)
との関係について説明します。
公印偽造罪・偽造公印使用罪、公記号偽造罪・偽造公記号使用罪との関係
行為者みずから公務所・公務員の印章・署名、公記号を偽造し、これを使用して公文書を偽造したときは、
又は
は、有印公文書偽造罪に吸収されます。
参考となる判例として、以下のものがあります。
大審院判決(昭和8年9月27日)
裁判所は、
- 偽造したる公務所の印章使用による公文書偽造の成立するには、一般世人をして公務所の印章なりと誤信せしむるに足るべき類似の印顆を押捺して、その影蹟(えいせき)を文書に表顕せしめ、これを使用して文書を偽造するをもって足りるものとす
- 印章偽造行使に対し、刑法第166条を適用せざりしは、その偽造行使は、登記済証偽造行使罪中に包括処罰せらるべきにして、別に同条の適用すべきものに非ざる
と判示しました。
大審院判決(大正12年4月23日)
裁判所は、
- 行使の目的をもって他人の印章を不正に使用し、権利義務に関する他人名義の文書を偽造する行為は、刑法第159条第1項に該当するほか、同法第167条の罪名に触れるものに非ず
と判示しました。
詐欺罪との関係
詐欺の手段として、有印公文書を偽造し(有印公文書偽造罪)、偽装した公文書を行使して(偽造有印公文書行使罪:刑法158条1項)、詐欺罪を犯したときは、「有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪」と「詐欺罪」との間に手段結果の関係があるため、「有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪」と「詐欺罪」は牽連犯の関係になります(大審院判決 昭和4年5月11日)
窃盗・横領罪との関係
窃取、横領した用紙で文書を偽造したときは、窃盗罪又は横領罪と文書偽造罪とは併合罪の関係になります。
この点を判示した以下の判例があります。
大審院判決(大正2年2月3日)
裁判所は、
- 他人に属する借用証書の用紙を窃取し、これに窃取に係る本人の印鑑を盗捺し、本人名義の借用証書を偽造したる場合において、借用証書用紙の窃取は、文書偽造の普通手段に非ず
- また、文書偽造は窃取の当然の結果に非ざるをもって、右窃取の行為は、文書偽造に対し、独立の一罪を構成するものといわざるべからず
と判示しました。
大審院判決(大正4年11月29日)
裁判所は、
- 自己の占有する他人の白紙買渡証書を横領し、これを材料として文書を偽造したる場合においては、横領と偽造とは手段又は結果の関係を有せず、各独立罪を構成するものとす
と判示しました。
東京高裁判決(平成20年4月24日)
窃盗(未遂)の手段として偽造有印公文書行使が行われた場合であっても、両罪は、牽連犯の関係にはないとした判決です。
事案は、被告人が、コインロッカー内の金員の窃取を企て、検察事務官の身分証明書である検察事務官証票1通を偽造し、これをコインロッカーの管理会社従業員に提示して行使し、同人にコインロッカー計156台を解錠させるなどしてそのコインロッカー内に保管されていた荷物を物色したが、金員の発見に至らなかったため、窃盗の目的を遂げなかったという有印公文書偽造罪、偽造有印公文書行使罪、窃盗未遂罪の事案です。
裁判官は、
- 偽造有印公文書行使と窃盗未遂については、窃盗未遂の手段として偽造有印公文書行使が行われた場合であっても、両罪は、犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず、刑法54条1項後段所定の牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから、有印公文書偽造とその行使とは牽連犯の関係にあるが、これらと窃盗未遂とは併合罪の関係にあると解すべきである
と判示しました。
なお、横領の手段として文書を偽造したときは、横領罪と文書偽造罪とは牽連犯の関係になります(大審院判決 大正11年3月31日)。
収賄罪、贈賄罪との関係
収賄罪との関係
公務員が公文書を偽造し、このことに関し収賄したときは、有印公文書偽造罪と収賄罪とは併合罪の関係になります(最高裁決定 昭和30年3月31日))
贈賄罪との関係
村役場の書記に贈賄して印鑑証明を偽造することを教唆したときは、有印公文書偽造罪の教唆と贈賄罪とは観念的競合の関係になります。
この点を判示した以下の判例があります。
大審院判決(大正15年11月2日)
裁判官は、
- 町村役場書記に贈賄して、その管掌に係る印鑑証明書の偽造を教唆する行為は、一面においては書記を教唆して町村長若しくは町村長代理の名義をもって印鑑証明書を偽造せしめ、他面においては印鑑証明書作成に関する職務を有する書記に賄賂を交付し、よって印鑑証明書の偽造、すなわち職務に関する不正の処分をなさしめたるものにして、1個の行為が2個の罪名に触れる場合に該当するものとす
- 偽造印鑑証明書の作成名義として、某村長代理某とのみ表示し、助役たる某の職名の記載を欠くも、公文書たるの形式を存する以上は、偽造公文書というを妨げず
- 約束手形偽造の目的をもって、詐欺の手段により他人をして約束手形用紙に振出人として署名せしめたる後、ほしいままに署名者の真意に反する手形要件を記載して手形を完成したるときは、その行為は約束手形偽造罪をもって論ずべく、詐欺罪又は有価証券虚偽記入罪を構成せず
と判示しました。