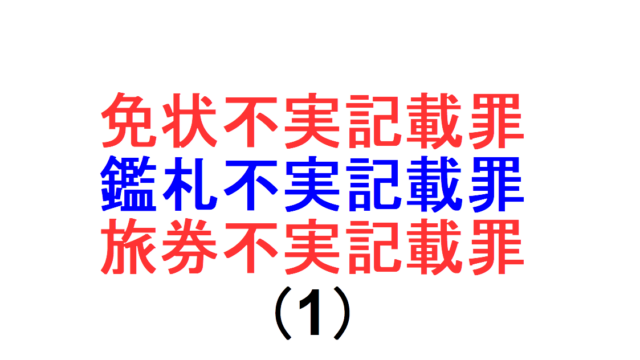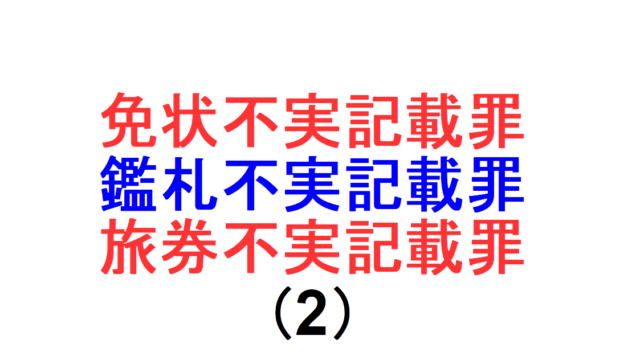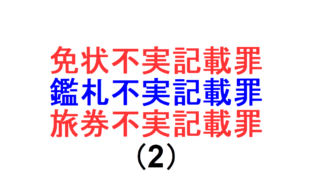免状等不実記載罪(3)~「本罪と①公文書偽造罪、②詐欺罪、③道路交通法違反・旅券法違反(不正受給行為)」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、免状不実記載罪、鑑札不実記載罪、旅券不実記載罪(刑法157条2項)を適宜「本罪」といって説明します。
他罪との関係
この記事では、本罪と
との関係を説明します。
公文書偽造罪との関係
他人の氏名を詐称して虚偽の申立てをして他人名義の自動車運転免許証の交付を受けた上(免状不実記載罪)、これに貼付されている自己の写真を剥ぎ取り、これに代えてその他人の写真を貼付する行為は、免状不実記載罪とは別に公文書偽造罪(刑法155条1項)が成立し、両者は併合罪の関係になります。
参考となる以下の裁判例があります。
札幌高裁判決(昭和34年8月18日)
裁判所は、
- 当初から、不正な手段で、他人名義の免状(自動車運転免許証)を取得する意図の下に、その他人の氏名を詐跡して、一応他人名義の自動車運転免許証の交付を受けた上、これに貼付されている自己の写真を剥ぎ取り、これに代えてその他人の写真を貼付する行為は、真正な自動車運転免許証の作成名義を利用して、これとは全然別個な同免許証を、権限なくして作成するものであって、免状不実記載罪とは別に、刑法155条1項の公文書偽造罪を構成すること疑なく、後者は前者に吸収されることのないのはもとより、後者をもって、前者の事後行為として、不問に付すべきものでもない
- 両者は併合罪として処断すべきである
としました。
詐欺罪との関係
免状、鑑札、旅券は、当該名義人において下付を受けて所持するのでなければその効用が認められないので、本罪には、不実を記載された免状、鑑札、旅券の下付を受ける行為も包含されます。
なので、本罪を犯した者が、不実記載の免状、鑑札、旅券の下付を受けても、別に詐欺罪(刑法246条)を構成することはありません。
この点を判示した以下の判例があります(いずれも旅券に関する事案)。
大審院判決(昭和9年12月10日)
裁判所は、
- 他人名義を偽りて、外国旅券下付を制し、その下付を受けたる事実に対しては、刑法第157条第2項を適用すべきものにして、外国旅券規則違反及び詐欺罪を問擬(もんぎ)すべきものに非ず
と判示しました。
裁判所は、
- 係員を欺罔して旅券の下附を受ける行為は詐欺罪にあたらない
と判示しました。
道路交通法違反・旅券法違反(不正受給行為)との関係
自動車運転免許証や旅券については、その不正受給行為につき、道路交通法(117条の2 の2第9号)や旅券法(23条1項1号)に特別規定があります。
両者が重ならないときは問題はありませんが、両者が重なるときは、本罪と道路交通法違反・旅券法は観念的競合の関係になります。
旅券に関しては、旅券法(法定刑:5年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科)の方が、本罪(法定刑:1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金)の法定刑よりも重いので、旅券法のみで処理すれば足りることから、実際の裁判では旅券法のみで起訴されることが多いとされます。