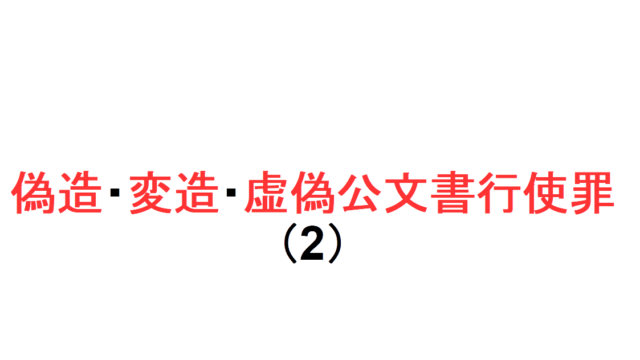偽造公文書等行使罪(8)~他罪との関係③「本罪と詐欺罪との関係」を説明
前回の記事の続きです。
偽造・変造・虚偽公文書行使罪、不実記載公正証書原本行使罪、不実記録電磁的公正証書原本共用罪等(刑法158条)を適宜「本罪」といって説明します。
この記事では、本罪と詐欺罪(刑法246条)の関係を説明します。
詐欺罪との関係
偽造公文書又は虚偽公文書を行使して財物をだまし取った場合、偽造文書の行使は、詐欺罪の構成要件である欺罔そのものではなく、欺罔の手段にすぎない一方で、詐欺罪の実行の方法として普通用いられるものに属し、詐欺罪の手段たる行為というべきであるから、両者は牽連犯(刑法第54条1項後段)の関係にあるとするのが判例・裁判例の立場です。
よくある事例として、身分を詐称して融資金をだまし取るために、偽の身分証として偽造の運転免許証を提出・行使するケースがあり、この場合、偽造公文書行使罪と詐欺罪とは手段と結果の関係にあるので牽連犯となります。
参考となる判例・裁判例として、以下のものがあります。
大審院判決(明治44年11月10日)
裁判官は、
- 刑法第54条1項にいわゆる犯罪の手段たる行為とは、ある犯罪の性質上、普通その実行の方法として用いらるべき行為にして、かつ、その犯罪の構成要件とならざるものをいう
- 故に、偽造又は虚偽の事項を記載したる文書等を行使して、物を騙取したる場合においては、その行為は、詐欺罪構成の要件たる欺罔の手段たるに過ぎずして、欺罔そのものにあらざる
- 従って、その行為は、ただちに詐欺罪の構成要件となるものにあらず、しかも右行為は詐欺罪実行の方法として、普通、用いられるものに属するをもって、すなわち詐欺罪の手段たる行為なりというべきなり
- されば、本件虚偽の記載をなしたる文書の行使と詐欺取財との間に手段結果の関係あるものとし、刑法第54条第1項後段を適用したり
と判示し、文書偽造行使罪と詐欺未遂罪は、牽連犯の関係になるとしました。
大審院判決(昭和7年4月11日)
債権者に対する債務の支払延期を画策して、債権者のために自己所有建物に根抵当権を設定すると偽り、実際にその旨の登記申請をするなどして不実の登記させ、債権者に債務の支払を延期させたときは、「公正証書原本不実記載罪・不実記載公正証書原本行使罪」と「詐欺罪」が牽連犯になるとした判決です。
裁判所は、
- 債権者に対し、自己所有の建物上に根抵当権を設定するにより、債務の支払を延期ありたき旨申し欺き、虚偽の建物を実在する如く装い、裁判所に対し、債権者のため根抵当権設定登記の申請を為し、登記官吏をして登記簿原本にその旨不実の記載を為さしめ、これを同所に備え付けしめたる上、債権者をして債務の支払を延期せしめたるときは、公正証書原本不実記載・行使による詐欺の牽連一罪成立す
と判示しました。
被告人が、Aから金員をだまし取るために、抵当権設定登記申請手続を委任する旨のB名義の委任状を偽造し、これを関係書類と共に登記官吏に提出して行使し、登記簿の原本に抵当権が設定された旨の不実の記載をさせてこれを行使するとともに、Aに対し、抵当権設定登記を経由した事実を証明する登記済権利証を示して、Aをその旨誤信させ、同人から借用金名下に現金をだまし取った場合には、「公正証書原本不実記載罪・不実記載公正証書原本行使罪同行使罪」と「詐欺罪」とは罪質上、通例手段結果の関係にあるものであり、これらは牽連犯に当たるとしました。
不実記載公正証書原本行使罪は成立するが、詐欺罪は成立しないケース
不実記載公正証書原本行使罪は成立するが、詐欺罪は成立しないケースとして、以下の判例があります。
大審院判決(大正12年11月12日)
偽造に係る土地の売買契約書を付属書類とともに登記所に提出して行使し、登記官吏をして土地登記簿の原本に不実の記載をさせ、これを行使したというだけでは、単に公正証書原本不実記載罪・不実記載公正証書原本行使罪が成立するにとどまり、別段土地に対する詐欺罪は成立しないとした判決です。
裁判官は、
- B者、A者のため、金員借用抵当権設定登記を為すものの如く装いて、これを欺罔し、その印顆を不正に使用して、A者よりB者に対し土地を売り渡したる旨の証書を偽造し、付属書類と併せてこれを登記所に提出行使し、登記官吏をして土地登記簿の原本にその旨不実の記載を為さしむる行為は、公正証書原本の不実記載およびその行使の罪を構成するにとどまり、土地に対する詐欺罪を構成するものに非ず
と判示しました。