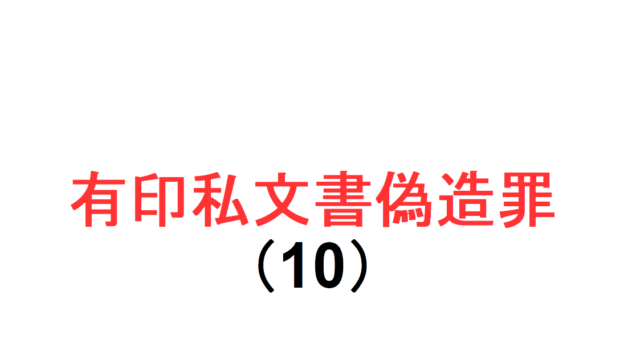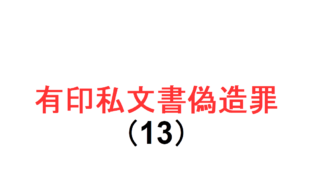有印私文書偽造罪(12)~行為⑧「肩書や資格を冒用・詐称して文書を作成した場合、文書偽造罪が成立する」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印私文書偽造罪(刑法159条)を説明します。
肩書や資格を冒用・詐称して文書を作成した場合、文書偽造罪が成立する
従来の通説では、法学博士や医師でないAが、自宅建物の賃貸借契約に際し、「法学博士A」「医師A」と虚偽の肩書や資格を記載して契約書を作成しても、軽犯罪法1条15号の称号詐称罪が成立するのは格別、作成名義の冒用にはならないと解されてきました。
しかし、以下の3つの判例では、虚偽の肩書や資格を冒用・詐称した場合に、文書偽造罪の成立を認めています。
いずれの判例も、人格の同一性のそご(偽り)が生じているかという観点から文書偽造罪の成否を判断しています。
その際、文書の名義人の特定に当たっては、当該文書中の印章・署名部分だけを取り上げて形式的に判断するのではなく、文書の性質をも踏まえて実質的な判断を行っています。
被告人を指称するものとして相当広範囲に定着していた名称を用いて再入国許可申請書を作成行使した行為が私文書偽造同行使罪にあたるとされた事例です。
裁判所は、
- 日本に密入国し、外国人登録申請をせず、密入国後25年以上にわたり、適法な在留資格を有するAの名義で生活していた被告人が、A名義で発行された外国人登録証明書を取得し、その名義で登録事項確認申請を繰り返すことにより、自らが同登録証明書のAであるかのように装って本邦に在留を続けていたため、被告人がAという名称を永年自己の氏名として公然使用した結果、それが相当広範囲に被告人を指称する名称として定着し、他人との混同を生ずるおそれのない高度の特定識別機能を有するにいたったとしても、被告人が外国人登録の関係ではAに成り済ましていた事実を否定することはでぎないとし、再入国の許可を取得しようとして、再入国許可申請書をA名義で作成・行使した場合には、再入国許可申請書の性質にも照らすと、同文書に表示されたAの氏名から認識される人格は、適法に本邦に在留することを許されているAであって、密入国をして何ら在留資格をも有しない被告人とは別の人格であることが明らかであるから、名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じているというべきである
として、外国人登録違法違反、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪の成立を認めました。
自己の氏名が弁護士Aと同姓同名であることを利用して「弁護士A」の名義で文書を作成した行為が私文書偽造罪に当たるとされた事例です。
裁判所は、
- 弁護士資格を有しない被告人が、自己の氏名が弁護士Aと同姓同名であることを利用して、弁護士Aの名義で弁護士の業務に関連した形式・内容の文書を作成し、行使した所為は、たとえ名義人として表示された者の氏名が自己の氏名と同一であったとしても、文書の名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じさせたものというべきであり、私文書偽造罪・同行使罪に当たる
としました。
正規の国際運転免許証に酷似する文書をその発給権限のない団体の名義で作成した行為が私文書偽造罪に当たるとされた事例です。
裁判所は、
- 正規の国際運転免許証に酷似する文書をその発給権限のない団体A名義で作成した行為は、上記文書が、一般人をして、その発給権限を有する団体であるAにより作成された正規の国際運転免許証であると信用させるに足りるものであるなどの事実関係の下では、団体Aから上記文書の作成を委託されていたとしても、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽るものであり、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪に当たる
としました。