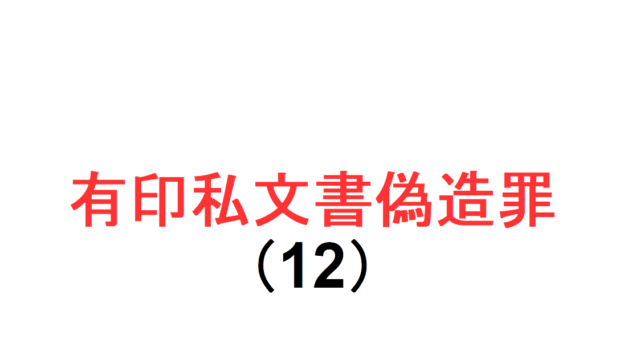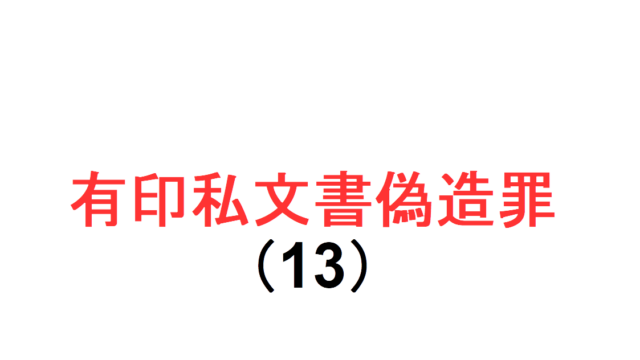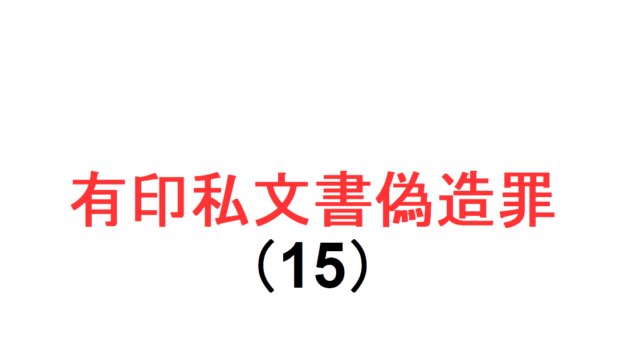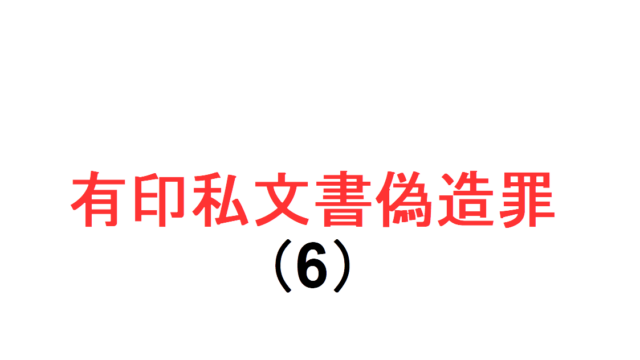前回の記事の続きです。
この記事では、有印私文書偽造罪(刑法159条)を適宜「本罪」といって説明します。
主体(犯人)
本罪の主体(犯人)に制限はありません。
私人も公務員も本罪の主体となり得ます。
客体
本罪の客体は、
他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画(とが)
です。
ここでいう「文書」は「私文書」、「図画」は「私図画(しとが)」と呼ばれます。
電磁的記録は本罪の客体とはなりません。
本罪の客体である「私文書」とは?
1⃣ 本罪の客体である「私文書」とは、
作成名義人が私人である文書
をいいます。
2⃣ 作成名義人が公務員の文書であっても、その職務の執行上作成すべき文書でなければ私文書となります。
例えば、
- 村役場の書記の退職届書は、村役場書記の肩書を用いて作成されても、その身分を辞退する意思表示であるにすぎず、職務の執行について作成されたものではないから、私文書である(大審院判決 大正10年9月24日)
- 労働基準局長という肩書を付しても、政党の新聞紙に掲載された「祝発展」という広告文は、機関紙の発展に祝意を表明する趣旨を記載した公務員名義の私文書である(最高裁決定昭和33年9月16日)
とした判例があります。
3⃣ 作成名義人は自然人であると、法人であると、その他の団体であるとを問いません。
法人格がなくとも独立の人格者と同様に扱われるべき一定の管理者のもとに存在するものであれば、団体名義の文書も本罪の客体になります。
例えば、
- ある会社の工場(大審院判決 大正7年5月10日)
- 青年団(大審院判決 大正8年12月17日)
- 独立の人格をもたない宗教上の組合である真言宗大師教会(大審院判決 大正2年4月17日)
の団体名義で作成した文書が本罪の客体になるとした判例があります。
具体的に、判例は、
- 私法人である日本鋳物工業組合連合会がその名義で発行した鉄鋼割当証明書(大審院判決 昭和17年2月2日)
- 農業団体法に定める県農業会(公務所ではない)がその名義で発行した木炭出荷指図書(最高裁判決 昭和26年4月27日)
を私文書と認定しています。
4⃣ 作成名義人は必ずしも実在することを要しません。
判例は、当初、私文書については、公文書と異なり、虚無人名義の文書の偽造罪の成立を一般的に否定し(大審院判決 明治45年2月1日)、名義人が生存中に作成したかのように偽ったときに限って同罪の成立を認めていました(大審院判決 明治45年12月2日)。
しかし、その後、団体の機関である個人が実在しない場合でも団体が存在するときには偽造罪の成立を認めました(最高裁判決 昭和23年10月26日、最高裁判決 昭和24年4月14日)。
さらに、その後、ついに、個人としての自然人を名義人とする場合にも実在者が真正に作成した文書と誤信せしめるおそれがあるときは偽造罪の成立を認めるに至りました(最高裁判決 昭和26年5月11日、最高裁判決 昭和28年11月13日)。
なお、学説では、―見して虚無人(実在しない人)であることが明らかな場合(例えば、豊臣秀吉名義のもの)には、 偽造罪は成立しないとされています。
5⃣ 作成名義人は、外国人、外国の団体も含まれます。
外国の公務所、公務員の作成すべき文書ば本罪によって保護されます。
米合衆国軍人用販売機関名義の輸入免税申告書は私文書であるとした判例があります(最高裁決定 昭和32年4月25日)。
6⃣ 本罪の客体となる私文書は、保管者が誰であるかを問いません。
公務所に保管されていても、私文書、私図画としての性質を失うものではありません。
なので、公用文書毀棄罪(刑法258条)にいう「公務所の用に供する文書」(現に公務所が使用し又はそのために保管している文書)であっても、作成名義が私人の資格であれば私文書であることに変わりありません。
例えば、村役場に備え付けられた印鑑簿は、各個独立の私文書たる性質を有するとされます。
大審院判決(昭和9年10月22日)は、
- 村役場備え付けの印鑑簿は、それぞれ独立した私文書である
と判示しています。
7⃣ 有価証券は本罪の客体になりません。
有価証券も文書の一種ですが、経済取引におけるその特殊性に鑑み、独立の保護が与えられており、別に有価証券偽造罪(刑法162条)が定められていることから、有価証券は本罪の客体になりません。
その理由として、最高裁判決(昭和34年12月4日)は、
- 刑法が文書偽造罪の外特に有価証券偽造の罪を設けた所以のものは、本来有価証券はその効用において一般私文書よりも高度の信用性を担保する必要あるがためである
としています。
判例が、有価証券ではなく、本罪の客体である私文書としたものとして、
- 郵便為替証書における受領証(大審院判決 明治43年5月9日)
- 無記名定期預金証書(最高裁決定 昭和31年12月27日)
があります。
上記①②のいずれも権利化体性(権利を証券に結合させ、その取り扱いを容易にすること)を欠き、免責証券にすぎないものと解されます。
これに対し、私文書ではなく、有価証券とされたものとして、
- 株式会社の増資新株申込証拠金領収証(新株を取得する者が新株式の対価を拠出したことを証する書類)(最高裁判決 昭和34年12月4日:同領収証は、証券取引界において株券類似の証券作用を営んでいるので有価証券であるとされた)
- 郵便為替証書(大審院判決 昭和6年3月11日)
があります。
本罪の客体である「私図画」とは?
「私図画」とは、
作成名義人が私人である図画(とが)
をいいます。
私図画の例として、
- 日本音楽著作権協会の英文略称JASRACを図案化したシール(東京高裁判決 昭和50年3月11日)
があります。