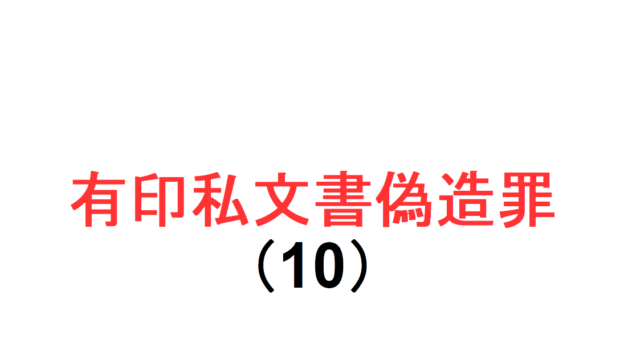有印私文書偽造罪(4)~「本罪の客体である『事実証明に関する文書・図画』」「署名・捺印しただけの場合における私文書偽造罪の成否」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印私文書偽造罪(刑法159条)を適宜「本罪」といって説明します。
本罪の客体である「事実証明に関する文書・図画」の説明
本罪の客体は、
他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画(とが)
です。
ここでいう「文書」は「私文書」、「図画」は「私図画」と呼ばれます(「私文書」「私図画」の説明は前の記事参照)。
この記事では、本罪の客体である「事実証明に関する文書」を説明します。
「事実証明に関する文書」とは?
「事実証明に関する文書」について、判例は、
実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書
であると解しています(大審院判決 大正9年12月24日、最高裁決定 昭和33年9月16日)。
これに対し、学説では、
「われわれの実社会生活に交渉を有する事項に関する文書の数はほとんど無限であり、そのすべてを、刑法的保護の対象とすることは不適当であるから、本罪の客体となるべきものは、法律的にも何らかの意味のある、社会生活の重要な利害に関係のある事実を証明し得る文書に限られるべきである」
との見解が有力説となっています。
「事実証明に関する文書」の具体例
判例が「事実証明に関する文書」と認めた文書として、以下のものがあります。
① 郵便局に対する転居届(大審院判決 明治44年10月13日)
居所移転の事実を証明するものと認めた事案。
② 作成者が某時・某所で書き添えた旨を記載した画賛(大審院判決 大正2年3月27日)
画賛が真正であることを表示したものと認めた事案。
③ 書画の箱書(大審院判決 大正14年10月10日)
書画が真筆であることを証明するものと認めた事案。
④ 衆議院議員候補者の推薦状(大審院判決 大正6年10月23日)
推薦の事実を直接証明するものと認めた事案。
⑤ 議員候補者を推薦する旨の新聞広告(大審院判決 昭和5年6月17日)
⑥ 特定人に対する会議を催告する文書(大審院判決 大正9年12月24日)
⑦ 寄付金の賛助員芳名簿(大審院判決 大正14年9月22日)
⑧ 他人を紹介し、かつ、その事業についての後援を依頼する旨を記載した名刺(大審院判決 昭和14年6月26日)
⑨ 政党の機関紙である新聞紙に掲載された「祝発展、佐賀県労働基準局長某」という広告文(最高裁判決 昭和33年9月16日)
⑩ 交通事件原票(道路交通法違反事件を処理するために警察官が作成する書類)中の供述書(最高裁決定 昭和49年2月19日)
⑪ 私立大学の入学選抜試験の答案(最高裁決定 平成6年11月29日)
私立大学の入学選抜試験の答案を志願者の学力の証明に関するものと認めた事案。
⑬ 運転免許の構造試験の答案(釧路地裁網走支部判決判 昭和41年10月28日)
⑭ 硫酸購入の際に毒物及び劇物取締法上提出が必要な毒物及び劇物譲受書(東京地裁判決 昭和56年6月22日)
⑮ 私立大学の成績原簿(東京地裁判決 昭和56年11月6日)
⑯ 国土利用計画法23条1項に基づく県知事に対する土地売買等届出書(仙台高裁判決 平成2年10月1日)
⑰ 自動車登録事項等証明書交付請求書(東京高裁判決 平成2年2月20日)
⑱ 公立高校の入試答案(神戸地裁判決 平成3年9月19日)
⑲ 就職先に提出された履歴書(東京高裁判決 平成9年10月20日、上告審 最高裁決定 平成11年12月20日)
⑳ 一般旅券発給申請書(東京地裁判決 平成10年8月19日)
事実証明に関する図画
事実証明に関する図画とされたものとして、
- 日本音楽著作権協会の英文略称JASRACを図案化したシール
があります(東京高裁判決 昭和50年3月11日)。
署名・捺印しただけの場合における私文書偽造罪の成否
1⃣ 署名・捺印しただけの場合でも私文書偽造罪が成立することがあります。
例えば、
- 借用証書に保証人として他人名義で署名した場合(大審院判決 大正2年5月5日)
- クレジットカード売上票に窃取したカードの名義人の氏名を署名した場合(名古屋高裁判決 平成19年10月4日)(売上票の一部である確認書部分につき私文書偽造罪が成立)
には私文書偽造罪が成立します。
これに対し、署名・捺印しただけでは私文書偽造罪は成立せず、署名偽造にすぎないので、私印偽造罪(刑法167条)が成立するにすぎないとした事例として、
- 公正証書に嘱託人として他人名義で署名した場合(大審院判決 明治42年5月13日)
- 供述録取書末尾に供述人として他人名義で署名した場合(京都地裁判決 昭和56年5月22日、東京地裁判決 昭和63年5月6日)
があります。
2⃣ 他人あての書留通常郵便物配達証書の受取人証印欄に合印を押捺しても、配達証書と別個の受取証という私文書を作成したことにはならないとした判例があります(大審院判決 大正8年7月17日)。
一方で、郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書すれば同人名義の受領書を偽造したものとして、有印私文書偽造罪を構成したことになるとした判例があります(最高裁決定 平成16年11月30日)。
3⃣ 道路交通法違反(酒気帯び酒酔い)事件捜査報告書末尾の被疑者署名印欄に他人の氏名を冒書指印しても、当該捜査報告書の署名・指印は、外形上、公文書である捜査報告書から独立性のある文書とはいえないから、私文書偽造罪は成立せず、私印偽造罪・私印不正使用罪(刑法167条)が成立するにすぎないとした裁判例があります(福岡高裁判決 平成15年2月13日)。
4⃣ 書画に筆者の落款・押印を加えただけでは、印章・署名偽造(私印偽造罪:刑法167条)の客体になるにすぎず私文書ではないとし、私文書偽造罪・偽造私文書行使罪は成立せず、私印偽造罪・偽造私印行使罪が成立するとした判例があります。
大審院判決(大正2年12月19日)
裁判所は、
- 書画は、ただこれに筆者の落款及び押印を加えることのみによりて直ちに権利義務又は事実証明に関する文書若しくは図画となるものに非ず
- 原審の確定する事実によれば、被告Aは、単に書家Bの筆致を模写するのみなる絵画に落款をBと偽書し、かつ、あらかじめ他人に彫らしめたる印をこれに押捺してBの印章及び署名を偽造し、Cと共謀してこれを行使したるというにとどまるをもって、その所為は、刑法第167条第1項・第2項(私印偽造罪、偽造私印行使罪)に該当し、決してこれに同法第159条第1項(私文書偽造罪)、第161条(偽造私文書行使罪)を適用すべきものにあらざる
と判示しました。