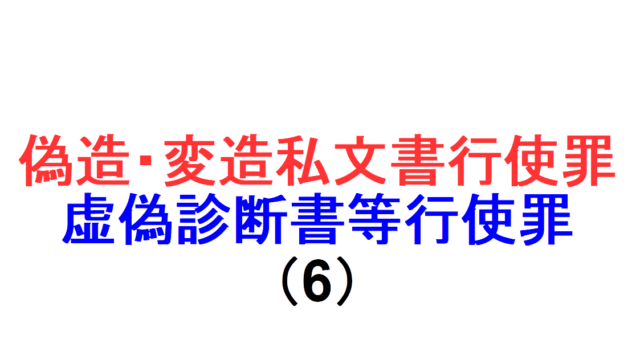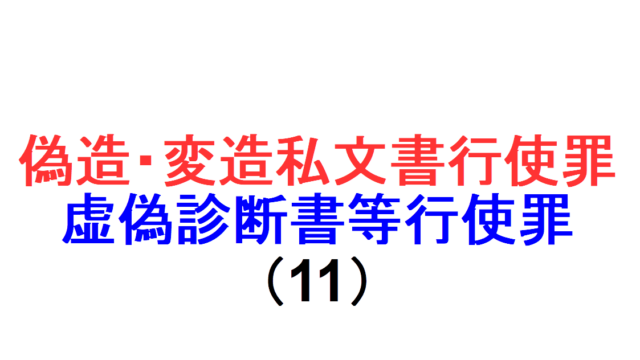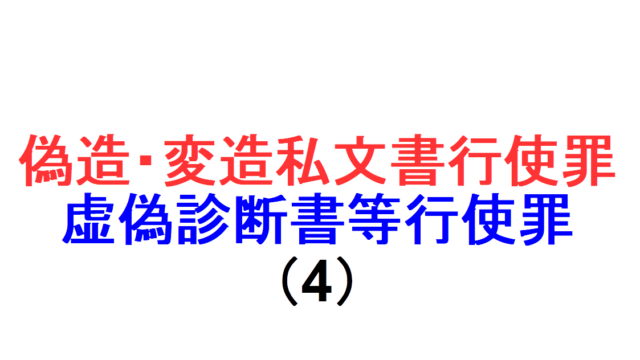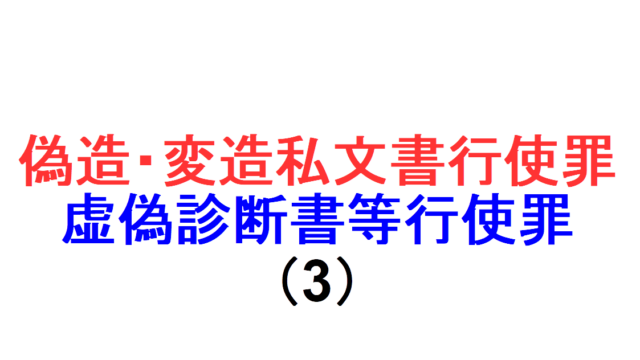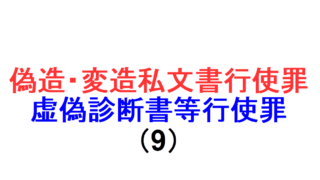偽造私文書等行使罪(10)~他罪との関係⑤「本罪と①虚偽告訴罪罪、②殺人罪との関係」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、刑法161条の罪(偽造有印私文書行使罪、変造有印私文書行使罪、偽造無印私文書行使罪、変造無印私文書行使罪、虚偽診断書行使罪、虚偽検案書行使罪、虚偽死亡証書行使罪)を「本罪」といって説明します。
他罪との関係
本罪と
との関係を説明します。
① 虚偽告訴罪との関係
他人に刑事の処分を受けさせる目的で、文面に虚偽の事実を記載した上、第三者名義を冒用した偽造文書を捜査機関に郵送で送付して申告する行為は、本罪と虚偽告訴罪(旧罪名:誣告罪:ぶこくざい)との観念的競合に当たります。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正14年1月21日)
裁判所は、
- 偽造文書を行使して誣告したるときは、1個の行為にして数個の罪名に触れるものとす
と判示しました。
② 殺人罪との関係
相手に毒物入りの供物を届けて毒殺しようと企て、相手の実父名義の文書(供物の服用を勧める内容のもの)を偽造し、この文書を毒物にそえて相手方に送付したが、服用前に毒物混入の事実が発覚したため、殺害目的を遂げなかったという事案において、「私文書偽造罪・偽造私文書行使罪」と「殺人未遂罪」とは観念的競合に当たるとした裁判例があります。
大審院判決(大正13年6月14日)
裁判官は、
- Aを殺害する目的をもって毒物を服用せしめんと欲する者が、毒物を装って神社の供え物のごとき外観を呈せしめ、かつ、Bの名義を冒用し、これが服用を勧誘する文書を偽造して、毒物と共にAに送致し、Aをして受領の上、これを誤信して服用の決意をなさしめ、Aにおいて、誤ってこれを服用せんとするに瀕し、事実発覚して殺害の目的を遂げざるときは、その文書偽造行使の点と殺人未遂の点とは、1個の行為にして数個の罪名に触れるものなれば、刑法第54条規定の趣言に従い、一罪として処分すべきものとす
と判示し、「私文書偽造罪・偽造私文書行使罪」と「殺人未遂罪」とは観念的競合の関係になるとしました。