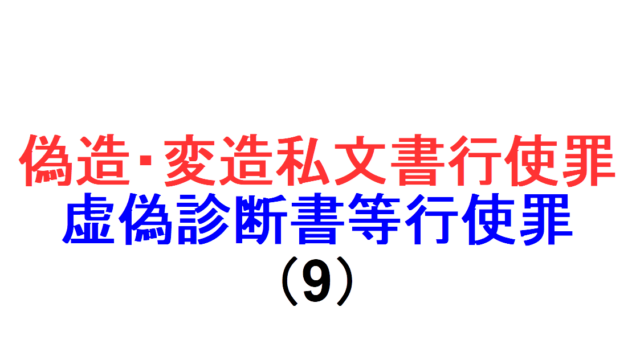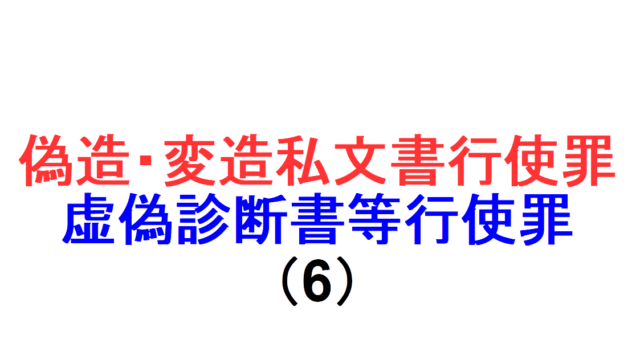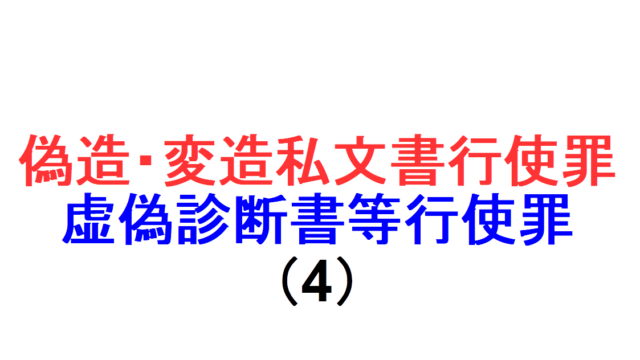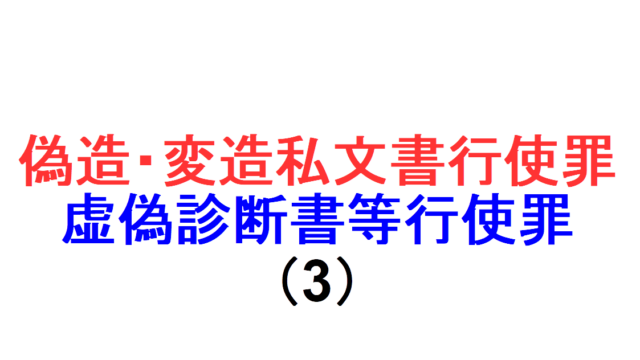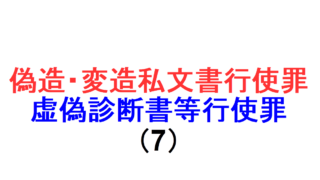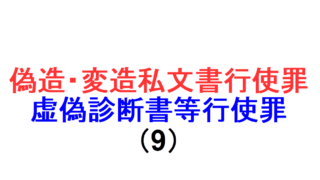偽造私文書等行使罪(8)~他罪との関係③「本罪と詐欺罪との関係」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、刑法161条の罪(偽造有印私文書行使罪、変造有印私文書行使罪、偽造無印私文書行使罪、変造無印私文書行使罪、虚偽診断書行使罪、虚偽検案書行使罪、虚偽死亡証書行使罪)を「本罪」といって説明します。
他罪との関係
本罪と
との関係を説明します。
詐欺罪との関係
牽連犯の関係になる場合
1⃣ 偽造に係る借用証書等を交付するなどした上、金員をだまし取った場合には、本罪と詐欺罪とは牽連犯になるとするのが判例です。
大審院判決(明治43年12月16日)
この判例で、裁判官は、
と判示し、文書偽造行使罪と詐欺未遂罪は、牽連犯の関係になるとしました。
2⃣ 偽造公文書行使罪と詐欺罪との関係について同様に判示した以下の判例があります。
大審院判決(明治44年11月10日)
この判例で、裁判官は、
- 刑法第54条1項にいわゆる犯罪の手段たる行為とは、ある犯罪の性質上、普通その実行の方法として用いらるべき行為にして、かつ、その犯罪の構成要件とならざるものをいう
- 故に、偽造又は虚偽の事項を記載したる文書等を行使して、物を騙取したる場合においては、その行為は、詐欺罪構成の要件たる欺罔の手段たるに過ぎずして、欺罔そのものにあらざる
- 従って、その行為は、ただちに詐欺罪の構成要件となるものにあらず、しかも右行為は詐欺罪実行の方法として、普通、用いられるものに属するをもって、すなわち詐欺罪の手段たる行為なりというべきなり
- されば、本件虚偽の記載をなしたる文書の行使と詐欺取財との間に手段結果の関係あるものとし、刑法第54条第1項後段を適用したり
と判示し、文書偽造行使罪と詐欺未遂罪は、牽連犯の関係になるとしました。
包括一罪の関係になる場合
詐欺の手段として偽造文書を用いる場合、その先後関係としては、上記のとおり、偽造文書行使行為が詐欺行為に先行するのが通例ですが、事案によっては必ずしもそうとは限らない場合もあります。
例えば、一般に銀行預金を担保として第三者から融資を受ける場合には、当該第三者に質権設定承諾書を交付し、その後融資金の交付を受けるのが通常予想される形態と考えられます(偽造に係る質権設定承諾書をこうした形態により交付して、融資金を詐取したというのであれば本罪と詐欺罪とは牽連犯となる)。
しかし、そうではなく、まず融資元を欺罔して銀行預金の原資となるべき融資金を詐取した上、これを銀行に預金した後に、その質権設定承諾書を偽造して融資元に交付するといったケースもあります。
このような事案において、「詐欺罪」と「有印私文書偽造罪、偽造私文書行使罪」とが包括一罪の関係になるとした裁判例があります。
東京高裁判決(平成7年3月14日)判決(高集48巻1号15頁)は、
- 一般的には有印私文書偽造、同行使、詐欺との間には順次手段結果の牽連関係があると認められるが、本件の事実関係においては詐欺が既遂に達してから偽造質権設定承諾書を行使していることが認められるから、偽造有印私文書行使が詐欺の手段となっているとはいい難く、両者を牽連犯とするのは相当でない
- 一般に銀行預金を担保として第三者から融資を受ける場合には、当該第三者に質権設定承諾書を交付し、その後融資金の交付を受けるのが通常予想される形態と考えられる
- ところが、本件においては、融資金が銀行預金の原資となっている関係で、まず融資金が入金されて預金に当てられてこれに関する質権設定承諾書が作成され、それが融資先に交付されているのである
- しかし、元々(偽造)質権設定承諾書の交付は、融資金の入金(騙取)につき必要不可欠なものとして、これと同時的、一体的に行われることが予想されているのであって、両者の先後関係は必ずしも重要とは思われないところである
- 事実、本件と同様の不正融資事件において、事務処理の都合等から融資金の入金前に預金通帳等を作成して質権設定承諾書を偽造し、これを交付するのと引き換えに不正融資金が振込入金された事例もあることは当裁判所に顕著な事実であり、かつその場合には当然のことながら、有印私文書偽造、同行使、詐欺とは順次手段結果の関係にあり結局一罪であるとして処断されているのである
- そして、右の場合とたまたまその担当者の事務処理の都合等から偽造質権設定承諾書の交付と振込入金との時間的先後が逆になった本件のような場合とで罪数処理に関する取り扱いを異にすべき合理的な理由を見い出し難いことからすると、偽造有印私文書行使罪と詐欺罪との法益面での関連性が必ずしも強くないことを考慮に入れても、両者は包括一罪として処断するのが相当と解される
との判断を示しました。