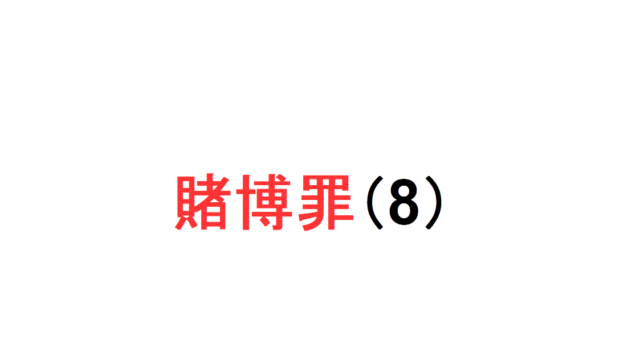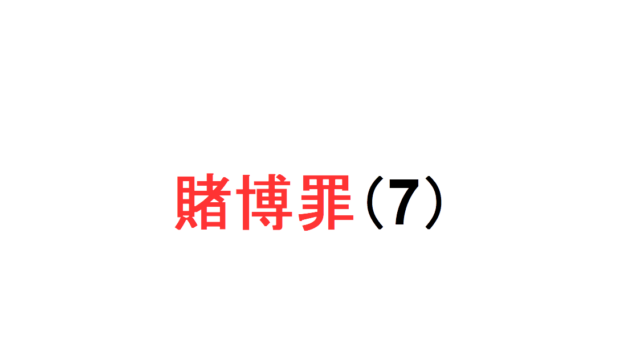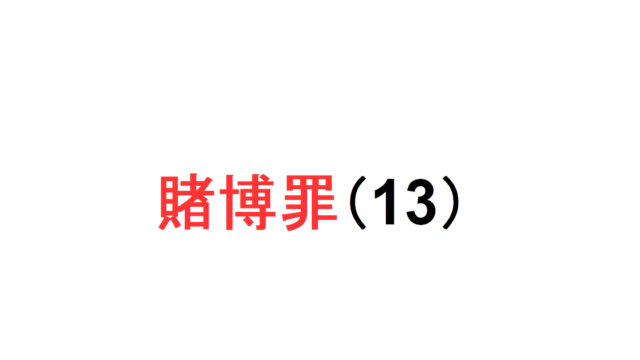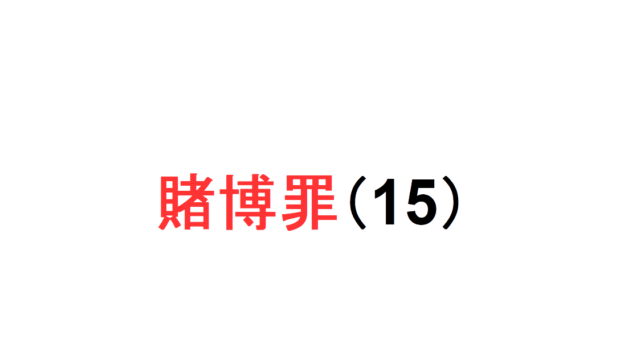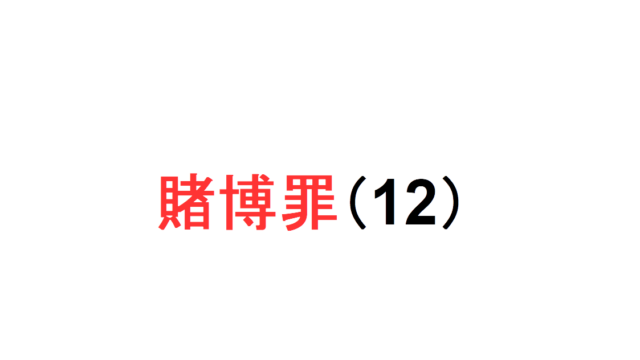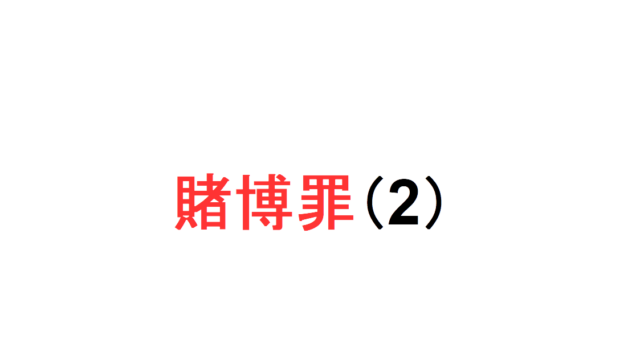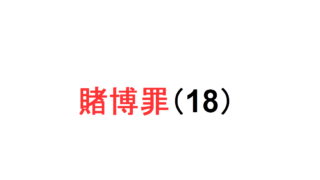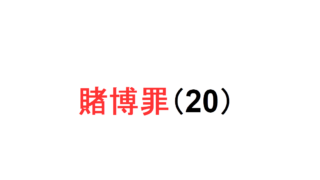賭博罪(19)~「賭博罪と金融商品取引法違反との関係」を説明
前回の記事の続きです。
賭博罪と金融商品取引法違反との関係
賭博罪(刑法185条)と金融商品取引法違反(202条違反)(旧証券取引法201条)の罪との関係を説明します。
取引所金融商品市場(金融商品取引法80条1項の免許を受けた者の開設に係る金融商品市場)の外で同市場相場による差金の授受を目的とする行為をすることは、一面において金融商品取引法違反(202条違反)を構成するとともに、賭博罪も構成するため、両罪の関係が問題となります。
- 取引所金融商品市場によらないで、取引所金融商品市場における相場(取引所金融商品市場における金融商品の価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)により差金の授受を目的とする行為をした者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第186条の規定の適用を妨げない
と規定します(同条2項は、一定の店頭デリパティブ取引を処罰対象から除外する)。
なお、大正3年の取引所法改正により新設された取引所法32条の5「取引所によらずして取引所の相場により差金の授受を目的とする行為を為したる者は1年以下の懲役又は2000円以下の罰金に処す。但し刑法186条の適用を妨げず」及び昭和18年に制定された日本証券取引所法84条「有価証券市場によらずして有価証券市場における相場により差金の授受を目的とする行為を為したる者は1年以下の懲役又は3000円以下の罰金に処す。但し刑法186条の適用を妨げず」は、金融商取法202条と同趣旨の規定です(大阪高裁判決 昭和27年11月1日)。
以下は、旧取引所法32条の5の時代の判例ですが、旧取引所法32条の5(現行の金融商品取引法202条又は旧証券取引法201条)は、賭博行為中特殊の場合に関する制裁法規であって、賭博罪の適用を排除するが、常習者がこれを行った場合には常習賭博罪(刑法186条)が成立するとします。
大審院判決(大正11年7月3日)
裁判所は、
- 取引所によらずして取引所の相場により差金の授受を目的とする行為は、偶然の輸贏(勝敗)により財物を賭する行為にしてその性質賭博に属す
- 取引所法第32条の58は、賭博行為中特殊の場合に関する制裁法規なるをもって刑法第185条の適用を排除し、常習としてその賭博行為を為す者に対しては刑法第186条第1項を適用すべき旨を定めたるものとす
と判示しました。
大審院判決(昭和11年4月2日)
裁判所は、
- 取引所法第32条の5前段所定の行為は賭博罪の行為要件を具備するものにして、同法第32条の5を設けたるは刑法第185条に比し刑を加重したるものなりとす
と判示しました。
したがって、例えば賭博の常習者が旧取引所法32条の5(現行の金融商品取引法202条又は旧証券取引法201条)の行為を行った場合において、賭博の常習者については常習賭博罪(刑法186条)が成立しますが、これを幇助した賭博の非常習者については、賭博罪(刑法185条)ではなく旧取引所法32条の5 (現行の金融商品取引法202条又は旧証券取引法201 条)の罪の従犯(幇助犯)が成立するとされます。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正7年1月16日)
裁判所は、
と判示しました。
なお、取引所の相場ではなく、法令によらずして単に事実上行われているにすぎない株式現物市場の相場により差金授受を目的とする行為をするのは、「取引所の相場」(現行の証券取引法201条では「有価証券市場における相場」)により差金の授受を目的とする行為をするのではないので、旧取引所法32条の5 (現行の金融商品取引法202条又は旧証券取引法201 条)ではなく賭博罪(刑法185条)に該当することとなります。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正12年11月27日)
裁判所は、
- 取引所によらずして単に事実上行わるる株式現物市場の相場により差金の授受を目的とする行為を為したるときは当然刑法第185条の賭博罪成立するものと論定せざるを得ず
と判示しました。