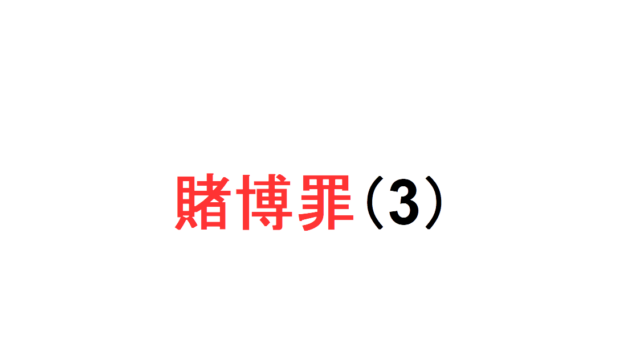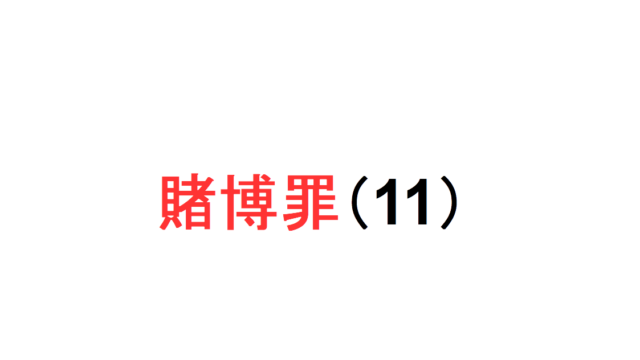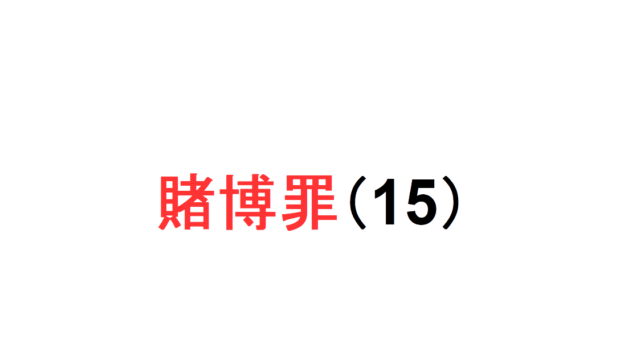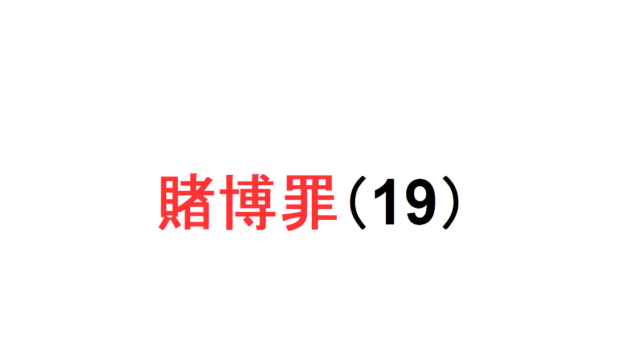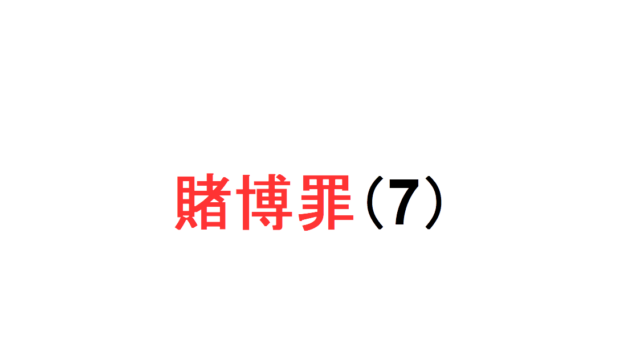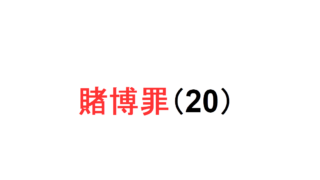賭博罪(21)~「賭博罪の『賭金』の没収の考え方」を説明
前回の記事の続きです。
賭博罪の「賭金」の没収の考え方
1⃣ 賭博罪(刑法185条)において、現に提供された賭金は、犯罪組成物件(刑法19条1項1号)として没収できます。
没収とは、物の所有権をはく奪して国の物にする処分のことをいいます。
没収は、裁判の判決において言い渡されます。
没収の対象となる物は以下の6種類です。
- 犯罪組成物件(犯罪行為を組成した物。例えば、賭博罪における賭金)
- 犯罪供用物件(犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物。例えば、殺人罪で使用したナイフ)
- 犯罪産出物件(犯罪行為によって生みだされた物。例えば、文書偽造罪の偽造文書)
- 犯罪取得物件(犯罪行為によって犯人が得た物。例えば、賭博罪で勝って得た金銭)
- 犯罪報酬物件(犯罪行為の報酬として得た物。例えば、窃盗罪の見張りをした報酬)
- 犯罪産出・取得・報酬物件の対価(③産出物件、④取得物件、⑤報酬物件の対価として得た物。①組成物件と②供用物件の対価は該当しない。例えば、窃盗罪で盗んだ物を売って得た金銭)
2⃣ 賭博罪の賭金は、①の犯罪組成物件として没収されます(②の犯罪供用物件ではない)。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正3年4月21日)
裁判所は、
- 賭博罪において賭したる財物は、すなわちその犯罪行為を組成したる物なりとす
と判示しました。
大審院判決(大正12年5月1日)
賭博罪の賭金は、刑法第19条第2号の犯罪供用物件ではなく、1号の犯罪組成物件であるとした判決です。
裁判所は、
と判示しました。
3⃣ 賭博罪の賭金は、財物の得喪が生じた後においては、③の犯罪取得物件(犯罪行為によって犯人が得た物、刑法19条1項3号)として没収することも可能です。
この点に言及したのが以下の裁判例です。
東京地裁判決(昭和58年9月27日)
裁判所は、
- 客の賭金は、客のする賭博罪についての組成物件であるのみならず、ゲーム機設置者のする常習賭博罪についての組成物件でもあると解されるし、また、このような組成物件である賭物も、賭博行為の結果得喪を生じた後は、賭博により得た物として刑法19条1項3号の要件を具備すると解するととに何の支障も存しない
と判示しました。
4⃣ 賭博に供しようとした現金は、②の犯罪供用物件(犯罪行為の用に供しようとした物、刑法19条1項2号)として没収できます。
しかし、賭博に供しようとした現金とそれ以外の現金を区別できない状態で所持していたときは、全体を犯罪行為に供しようとした物として没収できます。
この点を判示したのが以下の裁判例です。
名古屋高裁金沢支部判決(昭和31年9月25日)
裁判所は、
- 被告人は、賭博の用に供すべき金員と、然らざる金員とを区別分離することだぐ、現金全部(9460円)をそのまま携帯して賭博の席に臨み、所携の金員を賭金として使用した結果、その内1140円を既に喪失し、しかも賭博を中止しようとせず、なお残余の金員を賭銭として使用しようとしていたこと、すなわち、被告人は証第一号の現金(9460円)を、少くとも、犯行の用に供しようとしていたものであったことを認定するに足る
とし、被告人が所持していた現金全部について没収ができるとしました。
大阪高裁判決(昭和40年3月11日)
裁判所は、
- およそ反覆継続して犯罪行為に供する目的で準備された物のうち一部のみが使用された場合において、その残余の物は、もしこれを使用して犯罪行為が継続実行されたとすればその行為とそれまでに遂行された行為とが包括一罪を構成するものと解すべきかぎり、刑法第19条1項2号にいわゆる犯罪行為に供しようとした物としてこれを没収することができるものと解するのが相当であるところ、本件現金はまさに右にいう「残余の物」にあたることは明らかであるから、原判決が本件現金を本件賭博に供しようとした物であるとしこれを没収することとしたのはもとより正当である
- もっとも、被告人Xは、司法警察員の面前(中略)では、本件現金のうち3万円は前記Dに対する債務の返済に当てるつもりの金で賭博に使うつもりはなかった、という
- しかしながら、仮りに同被告人のいうとおりであったとしても、同被告人は本件現金4万1732円を一括して懐中に所持していたのであって、そのうちいずれがDへの返済予定の分であるかこれを特定することが全くできないのであるから、本件現金は全体として本件賭博に供しようとした物と解して妨げないのである
と判示しました。
ゲーム機賭博におけるゲーム機内に投入された現金の没収
1⃣ ゲーム機賭博における金銭の授受は、賭客が現金をゲーム機内に投入してゲームを行い、後に、ゲーム機画面上の獲得点数に応じて店員から現金を受け取る形態のものがあります。
そのゲーム機内に投入された現金を没収する際の根拠法条につき、裁判例において、
があります。
①の裁判例として以下のものがあります。
東京地裁判決(昭和58年9月27日)
裁判所は、
- ゲーム機在中金の没収について、検察官は、本件ポーカーゲーム機中8台のゲーム機内に在中した金員(残りの1台には金員が在中しなかった)について、刑法19条1項3号の物件に該当するとして没収の求刑をしている
- 思うに、客が賭博のためゲーム機内に投入した現金(本件では千円札)は、その時点において、ゲーム機設置者のする賭博行為との関連においても刑法19条1項1号にいう犯罪行為を組成した物に該当し、しかもその後これを賭博の結果としてゲーム機設置者が得たときは、さらに同条項3号の犯罪行為により得たる物にも該当すると解すべきである
- なぜならば、ゲーム機設置者の側の常習賭博罪は対向犯である性質上、客の賭金なくしては成立しないのであるから、客の賭金は客のする賭博罪についての組成物件であるのみならず、ゲーム機設置者のする常習賭博罪についての組成物件でもあると解されるし、また、このような組成物件である賭物も、賭博行為の結果得喪を生じた後は、賭博により得た物として刑法19条1項3号の要件を具備すると解することに何の支障も存しないからである
- さらにまた、本件の如きポーカーゲーム機においては、客の投入した現金はすべて遅くともゲーム開始と共に機械設置者の所有に帰し、客がゲームに勝った場合にも別に用意された金銭から支払、交付を受けるに過ぎないのであるから、賭博の結果が判明し、これにより得喪を生じた後はもちろんゲーム開始となった以上、客がすでに投入し終った千円については、 これによるゲームの勝負がまだついていないときであっても、ゲーム機設置者が犯罪行為によって得た物と考えられる
と判示しました。
②の裁判例として以下のものがあります。
東京地裁判決(昭和58年10月24日)
裁判所は、
- 本件においては、昭和58年10月1日から昭和57年7月21日までの間にゲーム機を使用して行われたすべての賭博行為を罪となるべき事実として認定できるので、右期間内にゲーム機に投入された現金はすべて刑法19条1項3号にいう犯罪行為により得た物ということができ、従って、このうち没収不能な部分は、同法19条の2によりその価額を追徴することになる
と判示しました。
2⃣ 賭客が店員に現金を支払うことによりゲーム機に点数が入力され、遊技終了後、残点数に応じて店員から現金を受け取るというゲーム機賭博の場合は、賭客が店員に支払った現金(賭金)全額が犯罪行為によって得た物(刑法19条1項3号)であり、組織的犯罪処罰法2条2項1号の「犯罪収益」として没収・追徴の対象となるのであって、その後賭客に支払った勝ち金を控除した額が没収・追徴の対象となるのではありません。
この点に関する以下の裁判例があります。
裁判所は、
- 財産上不正な利益を得る目的で行う回胴式遊技機による常習賭博においてあらかじめ賭客から取得した賭金は、賭客に支払った勝ち金を控除することなく、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律13条1項1号、16条1項本文により、その全額を没収・追徴することができる
と判示しました。