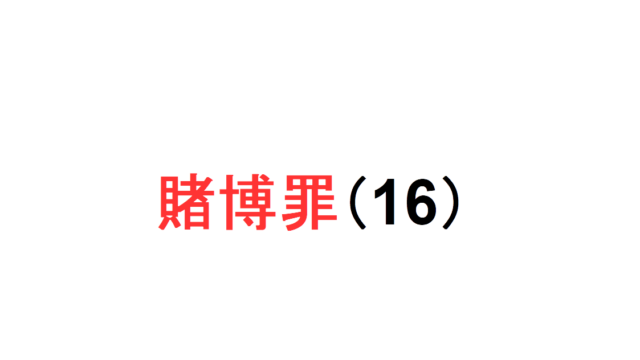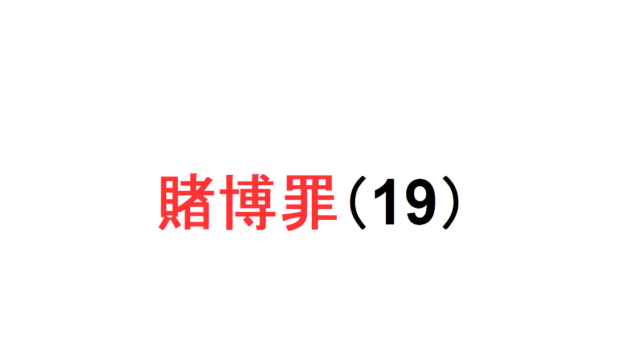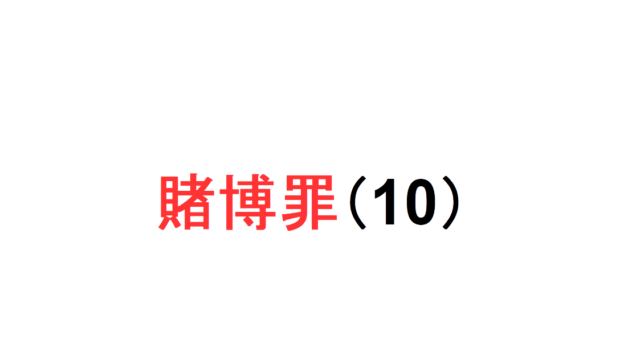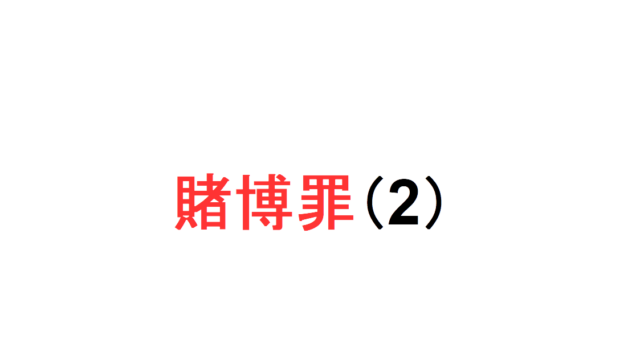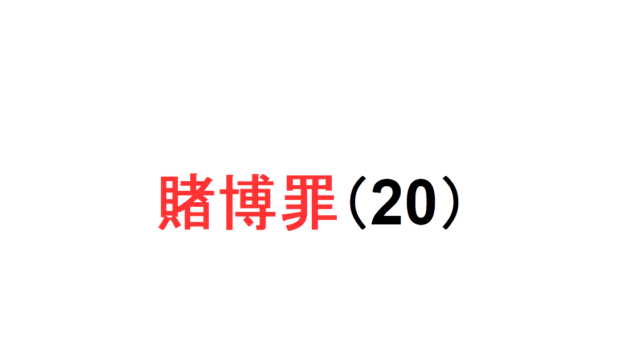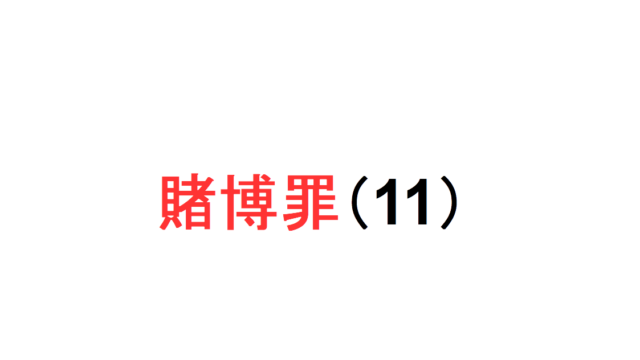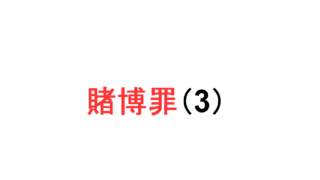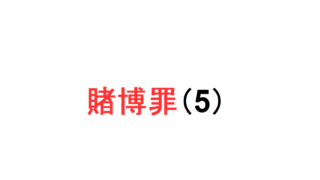賭博罪(4)~「賭博罪とは?」「賭博罪の成立要件」「『偶然の勝敗』とは?」を説明
前回の記事の続きです。
賭博罪とは?
賭博罪は、刑法185条において、
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない
と規定されます。
賭博罪は、賭博罪の基本となる犯罪類型を規定したもので、「賭博をした者」について成立します。
賭博罪は、賭博行為の着手があれば直ちに既遂に達する単純行為犯です。
また、相手方の存在を前提とする必要的共犯であると解されています。
賭博罪の成立要件
賭博罪の成立要件として、
- 「偶然の勝敗」に関するものであること
- 財物を賭けてその得喪を争うこと
という要件が必要になります。
まずは、「偶然の勝敗に関するものであること」について説明します。
「偶然の勝敗」とは?
「偶然の勝敗」の意義
「偶然の勝敗」とは、
勝敗が偶然性によって決定されること
をいいます。
「偶然」とは、
当事者において確実に予見できず、又は自由に支配し得ない状態
をいいます。
また、「偶然」は、
主観的に不確定であることをもって足り、客観的に不確定であることまでを要しない
と解されています。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正3年10月7日)
裁判所は、
- 賭博罪を構成するには、敗者が犯人の観念において不確実なる事実に繋がるをもって足れりとし、その事実客観的に不確定のものなることを必要とせず
と判示ました。
大審院判決(大正11年7月12日)
裁判所は、
- 偶然の輸贏(※勝敗)とは、当事者において確実に予見し、又は当事者の意思をもって自由に支配することを得ざる事実に関して勝敗を決することをいう
と判示しました。
技量の優劣と偶然性
当事者の技量等が勝敗の結果に影響を及ぼすような場合に偶然性が認められるかについて、判例は、
技量等の差異により勝敗があらかじめ歴然としているときは別段、多少とも偶然の事情により勝敗が左右され得るような場合には偶然性ありとする
としています。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(明治44年11月13日)
裁判所は、
- 博戯の勝敗が一に当事者の技量の優劣によるものにして勝敗の数があらかじめ確定し得べきものならば、これを偶然の輸贏(※勝敗)に関するものというべからずといえども、通例行わるる博戯の勝敗は、必ずしも当時者の技量のみによりて決するものにあらず技量の優劣を平均して勝敗の運命を逆賭すべからざらるしむる射倖的条件自ら存するものとす
と判示しました。
判例上、偶然性が認められたものとして、
- 囲碁の勝敗(大審院判決 大正4年6月10日)
- 麻雀の勝敗(大審院判決 昭和6年5月2日)
- 将棋の勝敗(大審院判決 昭和12年9月21日)
が挙げられます。
技量の差が大きいことを理由に偶然性が認められず、詐欺罪が成立するとした以下の裁判例があります。
名古屋高裁金沢支部判決(昭和34年11月10日)
裁判所は、
- 相対的な技量の巧拙といえども、その差異極めて懸隔し勝敗の決定に偶然性の支配する要素がほとんど認められない場合には客観的に勝敗の帰趨は明白であるといい得る
- 而して、被告人ら共謀の上、被告人Xのかかる巧妙なる技量を有することを秘匿隠蔽し、よってかかる巧者であることを知らぬ客のA、Bを誘引して金銭の得喪を争う賭博の形式のもとに勝敗を決し被告人Xが偶然に勝利を勝ち取ったものの如く誤信させたことは詐欺罪における欺罔手段たるを失わぬ
と判示しました。
賭博の動機が偶然の勝敗に左右することはない
動機の内容によって、偶然の勝敗であることは左右されません。
例えば、詐欺賭博であることを糊塗するために行われた賭博であっても、偶然性を失うものではありません。
この点を判示した以下の判例があります。
大審院判決(大正3年9月4日)
裁判所は、
- 詐欺賭博によりて被告より金員を騙取したる後、被告をして該賭博をもって通常賭博なるが如く信ぜしめんがため、X、Yは、被告と「ヨシ」と称する博戯を為し、もって偶然の事実によりて財物の得喪を争いたるものなること明なれば、原審が「ヨシ」と称する右賭博をもって真実の博戯なりと判定し、被告の所為を賭博罪として処断したるは正当
と判示しました。