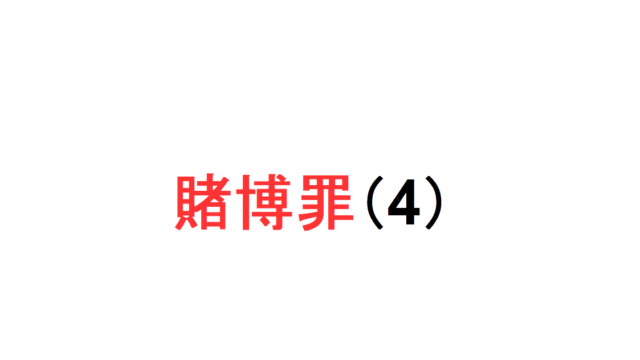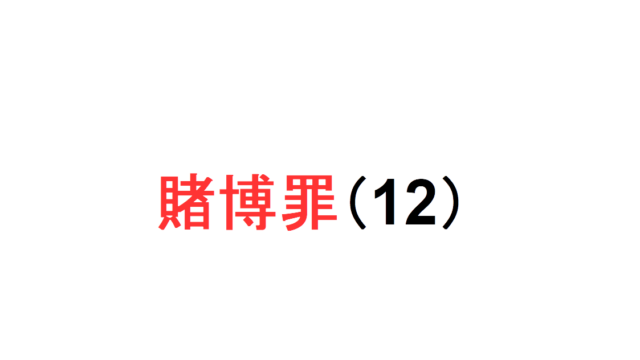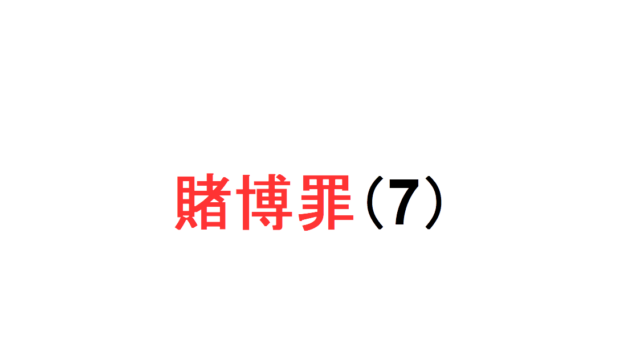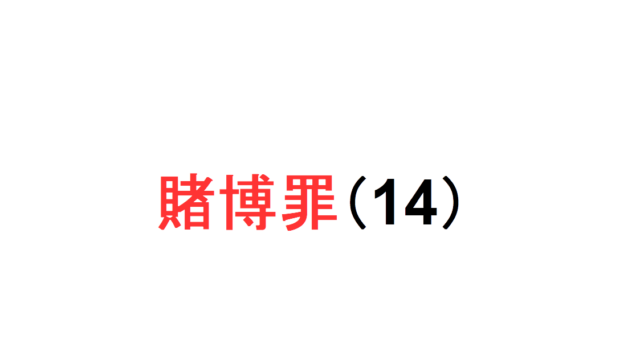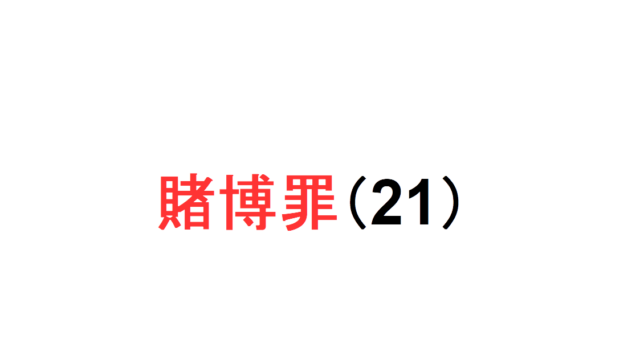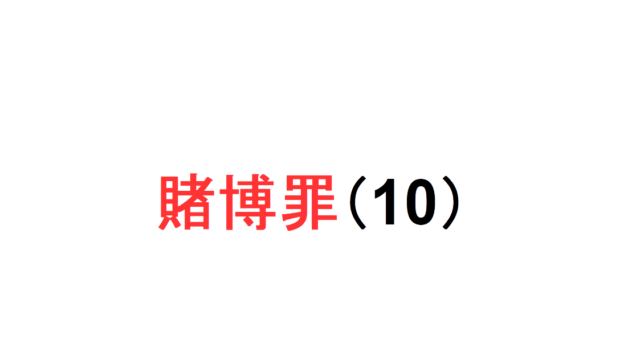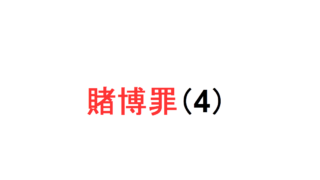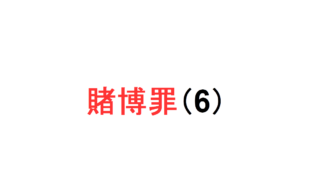賭博罪(5)~「詐欺賭博と偶然の勝敗」「詐欺賭博を行った場合、詐欺罪が成立し、賭博罪は成立しない」を説明
前回の記事の続きです。
詐欺賭博と偶然の勝敗
賭博罪(刑法185条)の成立要件として、
- 「偶然の勝敗」に関するものであること
- 財物を賭けてその得喪を争うこと
という要件が必要になります。
この記事では、①の「偶然の勝敗」に関し、「詐欺賭博と偶然の勝敗」について説明します。
詐欺賭博を行った場合、詐欺罪が成立し、賭博罪は成立しない
あらかじめ勝敗の結果を知っている者が、これを知らない者との間で賭博的行為をした場合に、当該欺罔者及び相手方に賭博罪が成立するかについては争いがあります。
これは、偶然性は当事者双方について存在することを要するか、片面的に存在すれば足りるかにかかわります。
通説
通説は、偶然性は当事者双方に存在する必要があるとの立場から、
賭博罪はいずれに対しても成立せず、欺罔者に詐欺罪が成立するのみ
とします。
これに対し、被欺罔者側に片面的に賭博罪の成立を認める見解、欺罔する際の技巧が絶対的なものでなく、いくらかの偶然性を伴うときは欺罔者について詐欺罪と賭博罪が観念的競合として成立するとした上、相手方にも賭博罪が成立し得るとする見解もあります。
判例(欺罔者には詐欺罪が成立する)
判例は、欺罔者に対し、従来から一貫して詐欺罪の成立を認めています。
大審院判決(昭和9年6月11日)、大審院判決(昭和10年11月28日)
米穀取引所の立会相場をあらかじめ電話照会により知ったにもかかわらず、これを知らないように装って賭博勝負をした事案で、欺罔者に詐欺罪が成立するとしました。
大審院判決(大正10年6月11日)
豆札を使用し、札に表示された点数により勝敗を争う方法の「ヨシ」と称する賭博を行うに際し、角の部分に細工を施した「ソグリ札」を密かに使用し、任意に特定の札を抽出できるようにした事案で、欺罔者に詐欺罪が成立するとしました。
大審院判決(大正12年11月17日)、最高裁判決(昭和26年5月8日)
金を賭けた見物人には勝つ機会が全くない「モミ」と称する詐欺賭博の事案で、欺罔者に詐欺罪が成立するとしました。
東京高裁判決(昭和32年12月25日)
万年筆買受代金名義で現金を提供せしめた詐欺賭博の事案で、裁判所は、
- 勝負の偶然性は賭博に参加する当事者全員について存在しなければならないものであり、参加者のうちに偶然性のない者の存する場合は賭博行為は成立しないものといわねばならない
- 射倖方法であるように装いながら、内実は被告人の予定した勝負を自由に実現させる方法をその手段のうちに交え施し、しかも相手方に対しては単純な射倖方法なりと誤信させて万年筆買受代金名義で現金を提供せしめたものであって詐欺をもって目すべき筋合のものであると考えられる
と判示ました。
判例(賭博罪は欺罔者、被欺罔者のいずれにも成立しない)
上記のとおり、詐欺賭博は、欺罔者に対して詐欺罪が成立する一方で、賭博罪は欺罔者、被欺罔者のいずれに対しても成立しません。
この点に関する判例・裁判例として、以下のものがあります。
大審院判決(大正12年11月17日)
裁判所は、
と判示しました。
東京高裁判決(昭和32年12月25日)
裁判所は、
- 勝負の偶然性は賭博に参加する当事者全員について存在しなければならないものであり、参加者のうちに偶然性のない者の存する場合は賭博行為は成立しないものといわねばならない
と判示しました。
甲府地裁判決(昭和46年6月25日)
裁判所は、
- 被告人らが、花札を使用し、俗に「アトサキ」と称する賭博行為をしたことは認められるが、その賭博における勝敗は、Aが隠し鏡を使用してこれを左右していたことが明らかであるから、勝敗が偶然性にかかっていたものとはいえず、被告人らに賭博罪は成立しない
- よって、この点については、刑事訴訟法336条により、被告人らに対し無罪の言渡をなすべきである
としました。
詐欺賭博の偶然性が否定される場合の判断基準
以上のとおり、あらかじめ勝敗の結果を知っている者が行う詐欺賭博については、賭博罪ではなく詐欺罪が成立することとなります。
ここで、どのような場合に当事者が勝敗の結果を知っていたといえるか、つまり、偶然性が否定されるのはどのような場合かについては、一律の基準を定立するのは困難であり、具体的事件ごとに判断されることになるとされます。
この点、参考となる裁判例として、以下のものが挙げられます。
名古屋高裁金沢支部判決(昭和34年11月10日)
勝率は約80%にすぎないとして詐欺罪の成立が争われた事案で、勝敗の結果は明白であるとして詐欺罪の成立を認めた事例です。
裁判所は、
- 両者間には単に技量上の巧拙が存するにすぎないとはいえ、相対的な技量の巧拙といえども、その差異極めて懸隔し勝敗の決定に偶然性の支配する要素がほどんど認められない場合には客観的に勝敗の帰趨は明白であるといい得る
として詐欺罪の成立を認めました。
京都地裁判決(昭和36年11月6日)
相手の錯覚を誘発する行為が欺罔手段とまではいえないとして詐欺罪の成立を否定し、常習賭博罪(刑法186条)の成立を認めた事案です。
裁判所は、
- 右の方法は被告人らのピース箱の巧みな操作により相手方の錯覚を招くことがあるにとどまり、箱の隠蔽、取り替え、その他相手方を錯誤に陥れる程度の欺罔手段に用いられたと認めるべきでなく、結局、被告人の所為は、刑法第186条第1項の常習賭博罪を構成するに過ぎないものと断定するほかはない
と判示しました。