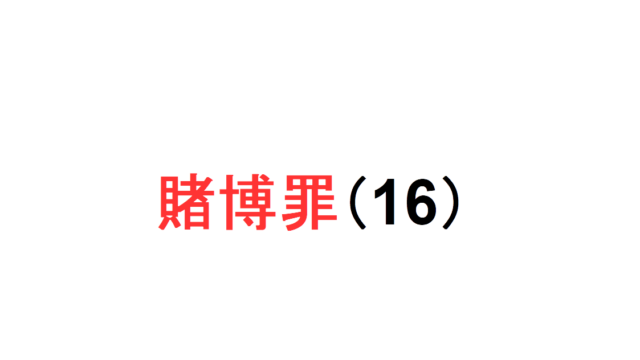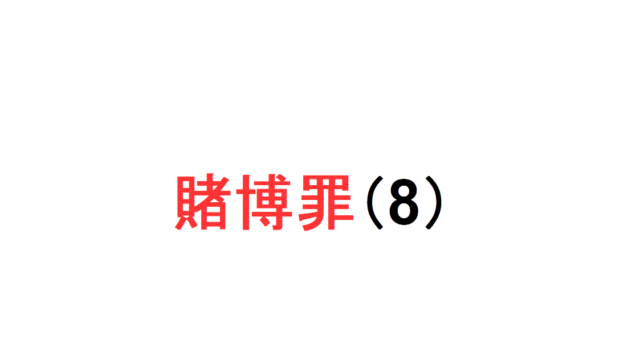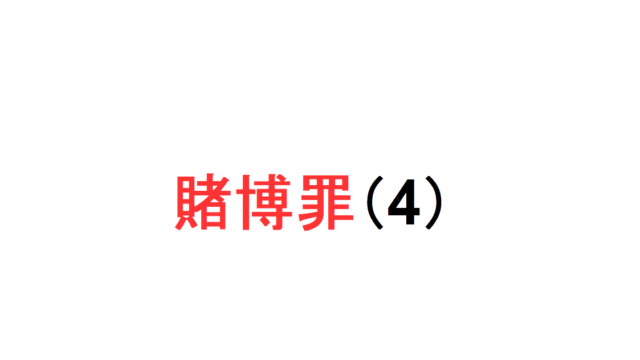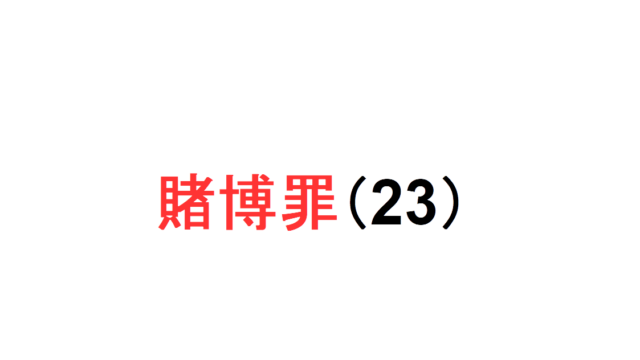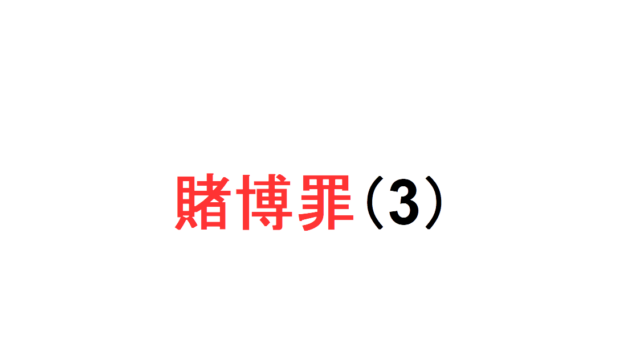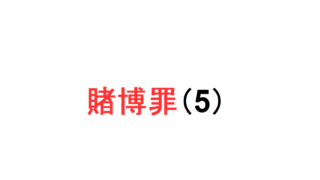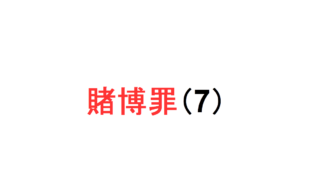賭博罪(6)~「『偶然の勝敗』に関し、偶然性が認められた判例・裁判例」を説明
前回の記事の続きです。
「偶然の勝敗」に関し、偶然性が認められた賭博の事例
賭博罪(刑法185条)の成立要件として、
- 「偶然の勝敗」に関するものであること
- 財物を賭けてその得喪を争うこと
という要件が必要になります。
「偶然の勝敗」に関し、偶然性が認められた賭博の事例として、以下のものがあります。
① 闘鶏
大審院判決(大正11年7月12日)
② 取引所の相場
大審院判決(明治45年5月23日)米穀取引所相場の事案
大審院判決 明治45年7月1日)
- 真実売買を為すの意思なく単に相場n高低なる偶然の事実による差金の授受のみを目的としてその得喪を争いたる以上は、その行為は定取引にあらずして賭博罪を構成するやまことに明なり
と判示。
大審院判決(明治35年9月25日)米穀取引所の定期米相場の事案
大審院判決(大正2年3月18日)米穀取引相場の事案
大審院判決(大正3年2月4日)
- 取引の相場を標準として、その高低により生じたる差額を得喪する場合においても、まことに売買取引を為すの意思ありと認められる時は、その行為は売買取引にして賭博にあらずといえども、その意思なく単に賭け事を為すの意思に出たるときは、賭博罪を構成す
- 何となれば、相場の高低は偶然の事情にして、その高低によりて生じたる差額を得喪するは、すなわち偶然ノの輸贏(勝敗)に関し財物をもって賭け事を為すものなればなり
と判示。
大審院判決(大正12年11月27日)株式現物市場相場の事案
大審院判決(昭和5年9月26日)株式取引相場の事案
③ 競馬
大審院判決(明治44年5月6日)
大審院判決(昭和10年3月28日)
④ 麻雀
大審院判決(昭和6年5月2日)
大審院判決(昭和10年3月28日)
と判示。
朝鮮高等法院判決(昭和13年8月25日)
- 麻雀遊戯の勝敗は主として偶然の事情に繋がるものなるが故に、反対の意見に立脚する論旨は採用するを得ず
と判示。
⑤ 囲碁
大審院判決(大正4年6月10日)
大審院判決(昭和16年5月3日)
⑥ 将棋
大審院判決(昭和12年9月21日)
⑦ ジャン拳札、花札
大審院判決(大正12年11月14日)
⑧ チーハ
大審院判決(明治38年2月2日)
チーハの内容について、
- 原判決に認めたる「チーハ」なるものは、抽選により当選者に利益を得せしむるにあらずして賭者においてその見込みに従い「チーハ」用紙記載の36種の解答中の1あるいは2以上を選み適意の金銭を賭し、その選みたる解答が親元の選みたる解答に偶中するときは、親元は賭者に対して賭銭の30倍を支払い、もしこれに偶中せざるときは賭者はその賭銭を損失し、親元においてこれを利得するもの
と説示。
⑨「ピン倒し」と称する撞球遊技
大審院判決(昭和13年8月30日)
ビン倒しの内容について、
- 撞球壷の中央にピンと呼ぶ象牙製棒を立て置き、四つ球ゲームを為し、得点すると共に球をもってピンを倒せば、相手方よりその得点に応じ所定の賭金を取得し、得点なくしてピンを倒せば、罰として一定の金員を差し出し、一上りの者は相手方より各自所定の賭金及び右罰金、取得するものにして…
と説示。
⑩「ABC三色ゲーム」と称する球入れ遊戯
札幌高裁判決(昭和28年6月23日)
「ABC三色ゲーム」の内容について、
- 設備としてはすり鉢型台の底平面下にゴムボールの落み込む程度の寸法の穴が30個あるポール受けを取り付け右30個の穴を青色(A)14個、白色(B)14個、赤色(C) 2個の色分けをしたもので、勝負を決する方法は10個のゴムボールを右ポール受けに転じ込ませ、そのポールがA、B、C の穴に入る数によって決するもの…
と説示。