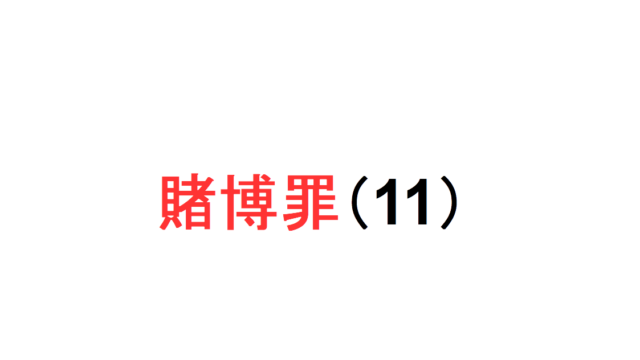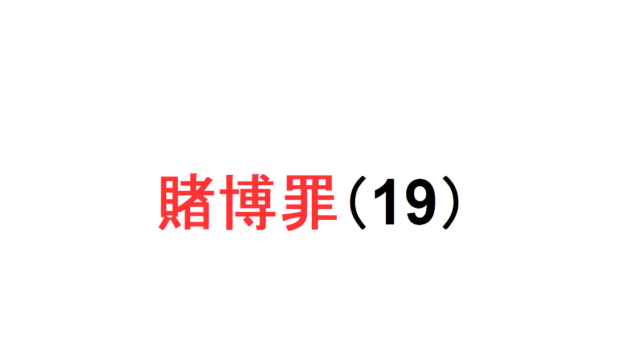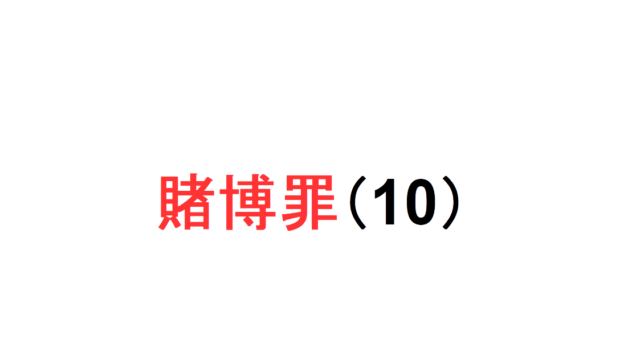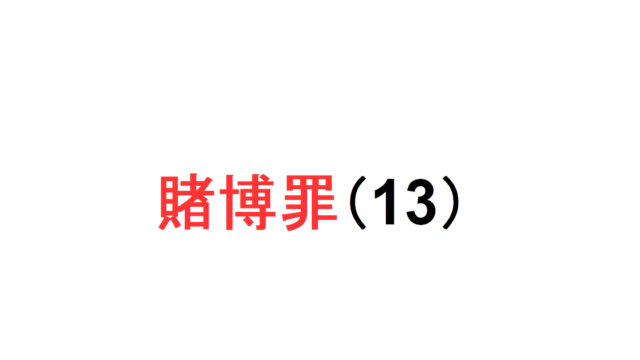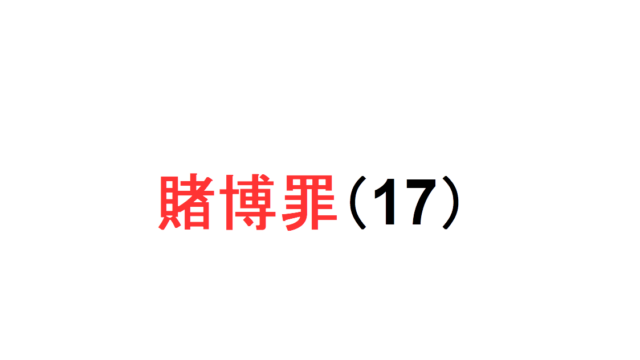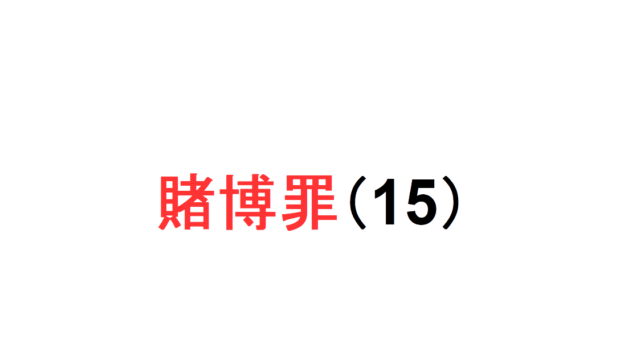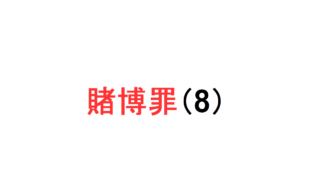賭博罪(9)~「『財物を賭けて』とは?」を説明
前回の記事の続きです。
「財物を賭けて」とは?
賭博罪(刑法185条)の成立要件として、
- 「偶然の勝敗」に関するものであること
- 財物を賭けてその得喪を争うこと
という要件が必要になります。
前々回は、賭博罪の成否を決するに当たり、財物の得喪の有無が争われた判例・裁判例を説明しました。
前回は、②の「財物を賭けてその得喪を争うこと」の意義を説明しました。
今回は、「財物を賭けて」の意義を説明します。
① 財物を賭けたというために、現に財物を賭場に提出することを要しない
財物を賭けたというためには、現に財物を賭場に提出することを要するかについて、判例・裁判例は、
- 財物授受の約束があれば足り、現に賭場に提出することを要しない
とします。
大審院判決(明治45年7月1日)
裁判所は、
- 財物を賭するとは、偶然の輸贏(勝敗)により一定の財物を勝者に交付すべきことをあらかじめ約束するのいうにして、現実に財物を拠出してこれを提供することは必要にあらず
と判示しました。
大審院判決(大正12年4月19日)
裁判所は、
- たとえ現場に財物を掛けず、輪贏(勝敗)の決了後、未だ財物を授受するに至らざる場合といでども、その行為は、財物を賭して博戯を為したるものにほかならずして、賭博罪として犯罪の成立に欠くるところなきものとす
と判示しました。
札幌高裁判決(昭和31年5月29日)
裁判所は、
- 賭博罪の成立要件としてのいわゆる財物を賭するとは、現実に財物の授受がなくても、約束があれば足りるものと解すべきところ、本件についてみるに、原判決挙示の証拠を総合し検討すると、被告人はなるほど賭銭をその場に出して勝負の都度その授受はしていないが勝敗の決した暁には精算してそれに相応する金銭を授受する約束のもとに原判示のような賭博をしたものであることを優に認め得る
と判示しました。
名古屋高裁金沢支部判決(昭和59年10月23日)
裁判所は、
- 本件において被告人らが自らの財物を現実に提供していないことが認められるけれども、財物を賭するというためには財物の得喪を約束する行為があれば足り、必ずしも現に財物を拠出し、提供することを要しないと解すべきところ、本件ポーカー式遊技機の遊技方法は、まず、客が機械に1000円札を投入すると同遊技機盤上に100円を1点に換算した客の持ち点10点が表示され、次いで、客は機械を操作して、持ち点の範囲内で点数を掛け、盤面上に表示されるトランプのポーカーゲームと同様の方法、すなわちカードの組み合わせによって役を作り、役ができて客が勝った場合は、役に応じた点数に掛け点を乗じて得た勝ち点を、1点を100円の割合で換算して営業者において現金を客に渡し、役ができなかったときは、客の負けとして、掛け点=金銭を失うという方法で行われており、右機械の操作によって得られる役は全くの偶然によるものであって、機械が介在している点で典型的な賭博と異なる面があるものの、右のような方法によって営業者及び遊技機の設置者と客との間で金銭の得喪を争うことの了解のもとに、営業者らが遊技機を使用させ、客がこれで遊技をすれば、右所為が賭博に当たることは明らかである
と判示しました。
② 金銭の代用物を賭けた場合でも、金銭を賭けたとされる
金銭に代えてあらかじめ購入させた遊技券を提供させるような場合でも、それが金銭の代用物として使われたにすぎないときは、金銭を賭けたものとされます。
この点に関する以下の裁判例があります。
札幌高裁判決(昭和28年6月23日)
裁判所は、
- 財物を賭するとは現物を賭することを要せず財物の代用物であってもよいのであって、原判決挙示の証拠によると、本件ゲームにおいては、三色のうち自ら好色玉の遊戯券を買うのであって、これはあらかじめ賭ける色を定めるためと、現金の代用をするものであって、その券の表示する額によって、勝者の取得額が定まりその金額に相当する景品又は客の好みによりて景品引替券を被告人から渡しこの引替券で次のゲーム券を買求め得られ、あるいはこれに相当する現金を取得し得るものであって、本件は自ら好色玉の遊戯券を買うことは、その色に金銭を賭けることであり、またその券は金銭の代用をなすものであるから財物を賭したものというべく、そして被告人に(中略)客の勝敗に関し財物の得喪を生ずるものであるから正に財吻を賭したものというべく、この点においても原判決に事実の誤認はない
と判示しました。
裁判所は、
- 勝敗を争うために賭客にそれぞれ金額を表示したチケットを購入さ賭金代用のチケットを購入させてこれを賭けさせ、勝敗が決すればいつても自由に同額の現金と交換していた場合、右チケットは金銭と同一視すべきである
- 客がこれによって勝敗を争うため客にそれぞれ金額を表示したチケットを購入させてこれを賭けさせ、勝敗が決すればいつでも自由に同額の現金と交換していたと認められ、たまたま少数の希望者の余ったチケットを現金に交換したに過ぎないとはいえない
- 右所為が賭博罪に該当すること明白である
と暗示しました。
③ 財物(金銭等)の数額は当初から確定している必要はなく、確定し得るものであればよい
金銭等を得喪の目的とした場合、その数額は当初から確定していることを要するかについて、判例は、
- 確定し得るものであればよい
としています。
大審院判決(明治45年7月1日)
裁判所は、
- 賭博罪の成立には、得喪の目的たる財物の数額が確定し得べきものなるをもって足り、当初より確定し居ることは必要にあらず
と判示しました。
大審院判決(大正14年1月31日)
裁判所は、
- 輸贏(勝敗)の決するに及び始めて得喪せらるる金銭の数額が確定するに至ることは、独り空米相場の場合に限るものに非ず
- 得喪せらるる金銭の数額が賭事着手の際に既に確定せると偶然の輸贏の決着するに及び始めて確定するのとは、その行為が賭博たる性質を構成することに消長なきものとす
と判示しました。