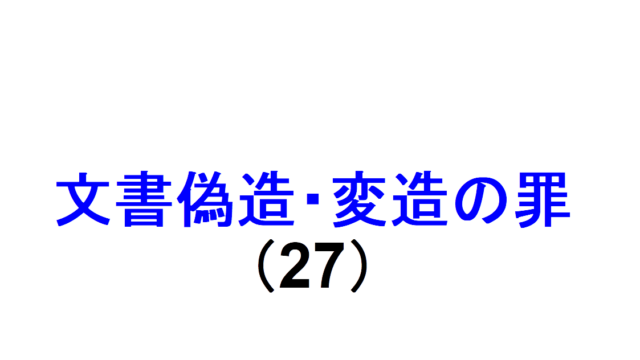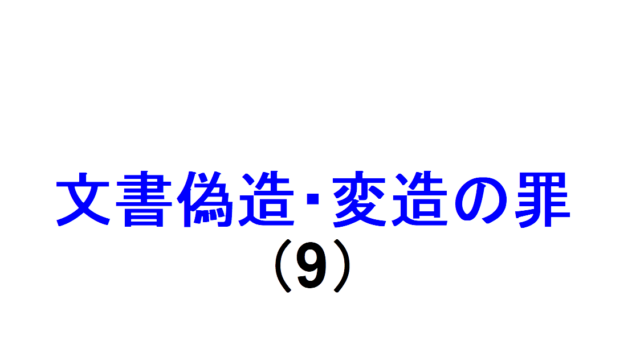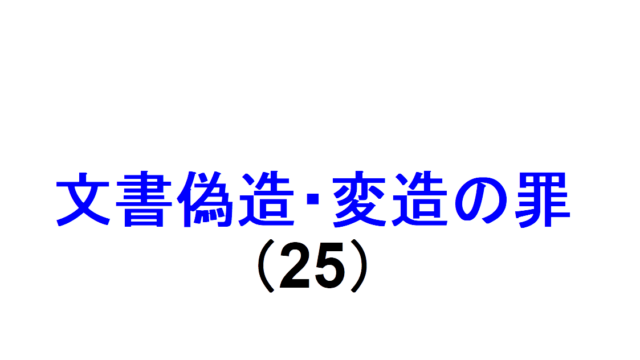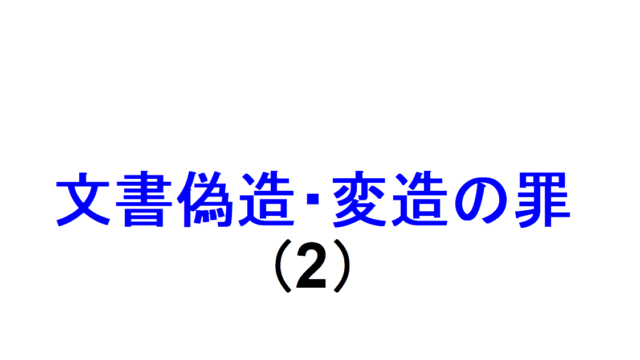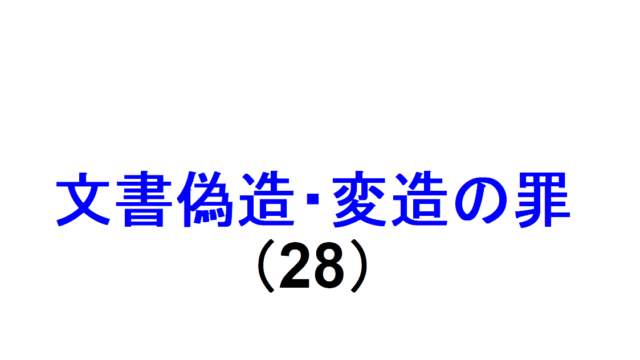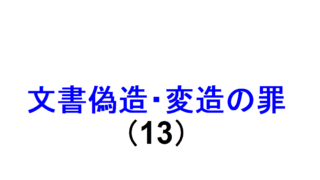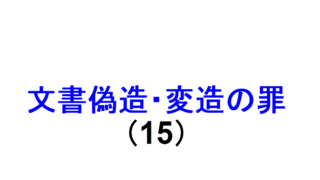文書偽造・変造の罪(14)~偽造の概念⑥「偽造文書を作成するに当たり、文書の名義人の承諾があった場合の私文書偽造罪の成否」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
原則、名義人の承諾があれば私文書偽造罪は成立しない
私文書について、名義人の有効な承諾を得て他人名義の文書を作成する場合、私文書偽造罪(刑法159条)の構成要件該当性が阻却され、私文書偽造罪は成立しないというのが原則的な考え方です。
これは、名義人の有効な承諾の下に作成した私文書は、名義人の名義を冒用したものではなく、真正文書にほかならないためです。
承諾は黙示的でもよいです。
なお、こうした承諾が可能なのは私文書についてのみであり、公文書については名義人の承諾の概念は当てはまりません。
名義人の承諾は有効なものでなければならない
名義人の承諾は有効なものでなければなりません。
名義人の承諾が有効でない場合は、作成者は、現実に当該文書を作った者となり、名義人との人格の同一性が認められないため、私文書偽造罪が成立します。
名義人の承諾は私文書作成の当時に存在することを要する
名義人の承諾は私文書作成の当時に存在することが必要です。
私文書作成当時に名義人の承諾がない場合は、
- 承諾が予想されるとき
又は
- 事後に承諾を得たとき
であっても、私文書偽造罪の成立を免れません。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(明治43年2月21日)
裁判所は、
- 他人の承諾を得ずしてその署名を偽り文書を作成するにおいては、爾後、承諾を承知し得べき場合なると否とを論ぜず、直ちに文書偽造罪を構成するものとす
と判示しました。
大審院判決(昭和9年11月22日)
裁判所は、
- 行使の目的をもってほしいままに他人の文書を作成する以上は、後日承諾を得ることを予見したる場合においても文書偽造罪の成立を妨げざるものとす
と判示しました。
大審院判決(大正8年11月5日)
裁判所は、
- 行使の目的をもって他人の氏名印章を冒用して文書を偽造する以上は、直ちに文書偽造罪を構成するものにして、犯人が本人の将来の承諾を予想し、かつ事後において名義人の承諾を得るも、これがために犯罪の成立を妨げるものに非ず
と判示しました。
大審院判決(昭和11年1月31日)
裁判所は、
- 行使の目的をもって他人の署名を偽造し、有合印を押捺して債権保証に関する文書を偽造したるときは、事後における名義人の承諾あるも文書偽造罪の成立を阻却するものに非ず
と判示しました。
名義人の承諾が適法な目的ではないものであっても、承諾があれば、私文書偽造罪は成立しない
名義人の承諾が、適法な目的ではないものであっても、名義人の承諾を得て作成された文書は真正文書であるため、私文書偽造罪は成立せず、その内容いかんにより虚偽文書罪の作成が問題となり得るにすぎないとされます。
しかも、私文書は、公文書と異なり、虚偽記載が社会生活に大きな影響を持ち得る医師作成の診断書のような一定の文書を除き(虚偽診断書作成罪:刑法160条)、内容の真実性をも刑罰をもって確保しなければならないという要請はそれほど高くないと考えられるため、私文書の虚偽作成・変造は不処罰となっています。
なので、刑法では、虚偽私文書作成罪、私文書変造罪はありません。
例えば、第三者を欺罔する目的で行われた承諾に基づき文書を作成した場合は、たとえ他人を欺罔するために承諾が与えられたとしても、名義人の承諾を得て作成された文書は真正文書であり、私文書偽造罪は成立しないこととなります。
名義人の承諾があっても私文書偽造罪の違法性が阻却されない例外的な場合
上記のとおり、AがBの承諾を得て、B名義の文書を作成する場合、私文書偽造罪は成立しないのが原則ですが、例外として、名義人の承諾があっても私文書偽造罪が成立するとした以下の裁判例があります。
① 交通事件原票(交通切符)の私文書偽造
運転免許を有しないAが、事前に運転免許を有するBから、Aが速度違反等の交通違反を犯して検挙された場合には、Bの名前で交通事件原票(交通切符)中の供述書に署名することの承諾を得ており、現実に検挙された際に、無免許運転の発覚を免れようと企て、Bに成り済まして同供述書にBの署名をしたとしても、私文書偽造罪は成立しないと解すべきかが問題になったことがありました。
この問題のリーディング・ケースとなったのが以下の裁判例です。
作成名義人の事前の承諾があっても有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪が成立するとした判決です。
裁判所は、
- 交通切符中の違反者が作成すべき供述書末尾に他人の氏名を用いて署名をしたときは、右署名につき、あらかじめ当該他人の承諾を得ていても、刑法159条1項の私文書偽造罪が成立する
と判示しました。
裁判所は、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪が成立する理由として、
- その文書の性質からして名義人本人によって作成されることだけが予定されており、他人の名義使用は許されず、名義人の承諾があっても、その名義を用いて文書を作成する権限は生じ得ないこと
- 専ら道路交通法違反事件処理という公の手続内において用いられるべぎ文書であること
- 文書の内容が違反者個人に専属する事実に関するものであること
- 実際には違反をしていない者につき、違反者としての手続が進められるのを放置すべきではなく、本件のような文書が名義人につき効力を生じることはあり得ないこと
を挙げています。
この東京高裁判決後、以下の最高裁判例が登場し、交通事件原票(交通切符)に対しては、名義人の承諾があっても私文書偽造罪が成立することが判例として確立しました。
裁判所は、
- 交通事件原票中の供述書その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであって、同供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立すると解すべきである
とし、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪の成立を認めました。
裁判所は、
- 被告人がAの名義で作成した本件文書は、いわゆる交通切符又は交通反則切符中の供述書であり、「私が上記違反をしたことは相違ありません。事情は次のとおりであります」という不動文字が印刷されていて、その末尾に署名すべきこととされているものであるが、このような供述書は、その性質上、違反者が他人の名義でこれを作成することは、たとい名義人の承諾があっても、法の許すところではないというべきであるから、Aがその名義の使用を事前に承諾していたという事実は、被告人の本件所為につき私文書偽造罪の成立を認めることの妨げにはならないと解すべきである
とし、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪の成立を認めました。
なお、この判決に付された谷口裁判官の補足意見は、
- わたしは、本件供述書は、その性質上作成名義人たる署名者本人の自署を必要とする文書であると考える
- 法律上もそうなっている(刑訴322条、刑訴規則61条2項参照)
- したがって、他人名義でこれを作成することは許されず、他人の向意、承諾を容れる余地のない文書というべきである
- されば、被告人がAの承諾を得ていたにしても、同人名義を用いて本件供述書を作成することは、法律上許されないところであって、作成名義を冒用したものとして、私文書偽造罪を構成するものと考える
などとしています。
② 運転免許申請書、一般旅券発給申請書の私文書偽造
交通事件原票(交通切符)のほか、他者から事前に承諾を得て、その者の名義で文書を作成したことが私文書偽造罪に当たるとされた裁判例として、
- 運転免許申請書(大阪地裁判決 昭和54年8月15日)
- 一般旅券発給申請書(大阪高裁判決 平成2年4月26日)
があります。
大阪地裁判決(昭和54年8月15日)
運転免許申請書について、裁判所は、
- 運転免許は、道路交通法に従い、公安委員会が申請者に下付するものであって、名義を偽って運転免許申請をした場合には、たとえ名義人が事前にこれを承諾していたとしても、その結果が名義人に生じるものではない
と判示し、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪の成立を認めました。
大阪高裁判決(平成2年4月26日)
一般旅券発給申請書について、裁判所は、
- 発給申請書は、申請者本人につき一般旅券の発給交付を受け得る資格が認められるか否かを審査するという公の手続内において用いられる文書であり、したがって、もともと申請者が他人の名義を用いて右発給申請書を作成・提出することは法令上許されないことが明らかであり(中略)、一般旅券発給申請書の法的性質、被告人が他人名義を使用した動機・目的等諸般の事情に照らせば、一般私人間で授受される契約書等の場合と異なり、たとえ名義人の事前承諾を得ていたとしても、その名義を用いて本件申請書を作成する権限を生ずる余地はない
と判示し、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪の成立を認めました。
③ 入試答案の私文書偽造
大学への入学を希望する者に成り済まし、替え玉受験をして、入学試験答案を作成したことが文書偽造罪に当たるかが問われました(明治大学替え玉入試事件)。
これは、私立大学の入学試験には、運転免許証の申請手続や一般旅券の発給申請手続等に相当するような法令の規制はなく、大学独自に「不正な手段による受験は無効とする」等の入試要項や学内規則が設けられているにすぎず、最高裁判例にいう「法令」ないしは「法」に相当するものが、文字どおりには存在しないためです。
同事件で、最高裁決定(平成6年11月29日)は、名義人の承諾と文書偽造罪の成否に関する論点について、明示の判断を示していませんが、一審(東京地裁判決 平成4年5月28日)及び控訴審(東京高裁判決(平成5年4月5日))は判決の中で述べられた付随的な意見として、名義人の承諾があっても私文書偽造罪が成立することを認め、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪が成立するとしました。
名義人の承諾があっても私文書偽造罪が成立する場合の共犯の成否
上記のように、名義人の承諾があっても私文書偽造罪が成立すると解する場合に、承諾を与えた名義人が、当該文書偽造罪の共犯(共同正犯)となり得るかについて、裁判例は、共謀共同正犯になるとしています。
東京地裁判決(平成10年8月19日)
一般旅券発給申請書はその性質上名義人たる署名者本人の自署を必要とする文書であるから、被告人の事前の承諾があったとしても、他人が被告人名義の右申請書を作成してこれを行使した行為は有印私文書偽造、同行使罪に該当し、本件における被告人の具体的な関与の状況に照らせば、名義の使用を承諾した被告人は、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪の共謀共同正犯としての責任を負うとした事例です。
事案は、被告人Aが、不正に日本人名義の一般旅券を得ようと企てた者Bからの依頼で自己名義(Aの名義)の使用を承諾し、Bにおいて一般旅券発給申請書に被告人Aの氏名等を記載し、Aの写真を貼付して申請書を作成して行使したというものです。
裁判所は、
- 本件一般旅券発給申請書は被告人名義であるが、一般旅券発給申請書は、その性質上名義人たる署名者本人の自署を必要とする文書であるから、例え名義人である被告人が右申請書を自己名義で作成することを承諾していたとしても、他人である共犯者が被告人名義で文書を作成しこれを行使すれば、右申請書を偽造してこれを行使したものというべきである
- そして、被告人は文書偽造及び同行使の実行行為自体は行っていないものの、前記認定した事実、殊に、本件犯行の実現のためには被告人の関与が不可欠であったこと、65万円という多額の報酬を受領していることなどに照らせば、被告人は自己の犯罪として右犯行に関与したものというべきであって、共謀共同正犯としての責任を負うものである
- 被告人が右偽造文書の名義人であり、単独では正犯にはなり得ないことは右結論には影響しない
と判示し、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪の共謀共同正犯が成立するとしました。