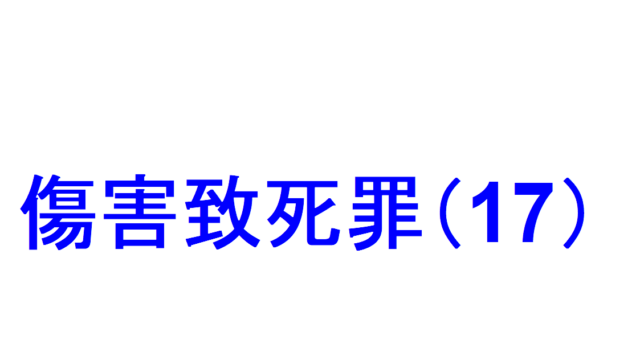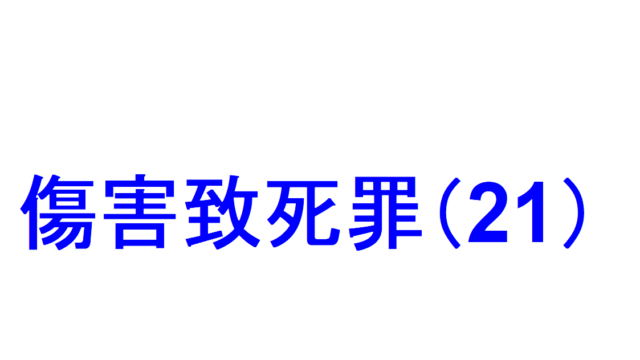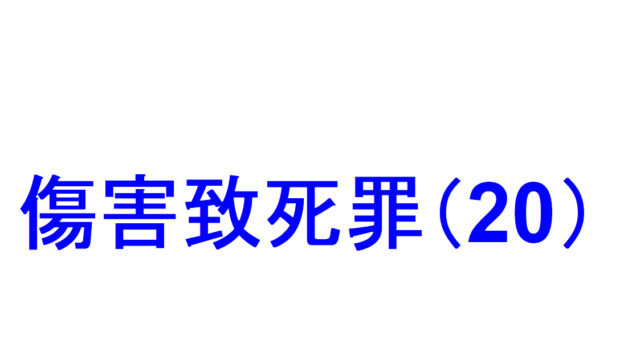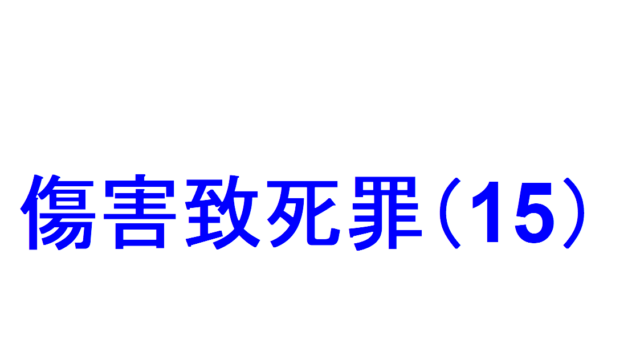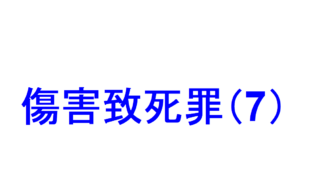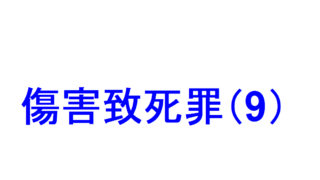傷害致死罪(8) ~暴行・傷害と死の結果の因果関係②「暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした大審院判例」を紹介~
前回の記事では、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認定するに当たり、条件説と相当因果関係説の考え方が採用されることについて説明しました。
これから、暴行・傷害と死の結果の因果関係が争点となった判例を示しながら、因果関係の認定のされ方について説明します。
今回の記事では、大審院判決について紹介します(なお、次回の記事で最高裁判決について紹介します)。
暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした大審院判例
暴行・傷害と死の結果の因果関係を認定について、判例は条件説を採用しているといわれています。
以下の判例は、条件説を採用したと評価され、その主要判例とされている判例です。
大審院判決(明治43年10月3日)
この判例で、裁判官は、
- 被害者が直接に身体の衰弱によって死亡した場合といえども、その衰弱にして傷害に基因したる以上は、傷害をもって直ちに死亡の原因と判断するも失当にあらず
と判示し、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
続いて、条件説というよりは、相当因果関係の有無を検討したような判例(相当因果関係説によるような判例)として、以下の判例があります。
大審院判決(大正2年9月22日)
老衰した祖母を殴打したところ、右肩関節を脱臼し、病床につき衰弱死した事案で、裁判官は、
- 結果の発生に対する原因を与えたる時は、その原因は直接原因なると、間接原因なるとは、これを論ずるを要せず
- また、その原因のみにては、結果を発生せずして、他の原因と相合して結果を発生したる場合なると否とは、これを問うところにあらずして、特定の行為が原因となり、特定の結果を発生し、または、これを発生することあるべきことが、吾人の知識経験により、これを認識し得べき場合は、その行為を為したる者は、その結果発生につき、原因を与えたるものとす
- 被告が79歳の老衰者に対し、上述の如き傷害を加えるときは、上述の如き経過により、その死亡を来すべきことあるは、吾人の知識経験により、これを認識し得べきところなれば、原審が被告の右所為に対し、刑法第205条を適用したるは相当である
と判示し、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
その後の大審院判例において、暴行・傷害と死の結果の因果関係の存在を認めた主な事例として、以下の判例があります。
①大審院判決(大正7年11月30日)
暴行の結果、死亡したと思って水中に投げ込んだ結果溺死した事案で、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 人の身体を不正に侵害するの認識をもって為したる意思活動により被害者を死に致したるときは、傷害致死罪を構成するものにして、この意思活動が一原因たるにおいては、かかる認識なき犯人の挙動がこれに付加結合して致死の結果を生ずるに至りたる場合といえども、該意思活動と致死の結果との間に因果関係の存在を認むることを得るものとす
- 被告が被害者に対し、暴行傷害を加えたる後、既に死亡したるものと誤信して、水中に投入したるときは、被告の行為は、包括的に単一の傷害致死罪を構成するものとす
と判示しました。
②大審院判決(大正8年7月31日)
船に乗った被害者に対し暴行を加えたため、被害者が海中に飛び込み溺死した事案で、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 甲が乙の暴行に関する動作により、意志の自由を失い、水中に飛び込み溺れたるは、あたかも陸上にして同様の状態に陥りたる者が、逃走転倒すると同一にして、乙の動作との間に因果の連結あるものというべし
- 従って、甲の溺死は、暴行を原因とするものにして、乙は、これが結果つき、刑法上の罪責に任すべきものとす
と判示し、暴行と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
③大審院判決(大正8年9月4日)
動脈切断に気付かず、静脈が切断されたのみとして治療を行った医師の誤診が死因であるとの弁護人の主張に対し、裁判官は、
- 人の身体に傷害を加え、その傷害が被害者死亡の結果に対する一原因をなしたるときは、その行為は刑法205条の罪とあるべき事実を構成し、傷害致死罪に該当することもちろんにして、たとえその傷害に対する医師の診療適切ならざるものありとするも、これがために同罪の成立を阻止すべきものにあらず
と判示し、被告人の暴行により傷害を負い、医師の治療を受けることになった被害者が、医師の治療ミスで死亡した場合でも、暴行・傷害と死の結果の因果関係があるとして、傷害致死罪の成立を認めました。
④大審院判決(大正12年5月26日)
上記判例と同様に、暴行・傷害の結果に、他人の過失行為が介入し、被害者が死亡した場合でも、暴行・傷害と致死との因果関係があるとして、傷害致死罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 暴行が傷害致死の一原因となれる以上は、たとえ被害者の身体に対する医師の診療よろしきをえざりしことが、他の一因を成したるとするも、暴行と致死との間に因果関係を認めるべきものとす
と判示し、暴行・傷害と致死の結果に医師の誤診療が介在しても、暴行・傷害と致死との因果関係が認められ、傷害致死罪が成立するとしました。
⑤大審院判決(大正12年7月14日)
被害者の治療が不適当であり、傷口から病菌が入り丹毒症を起こして死亡した事案で、暴行・傷害が「死亡の一因をなしていればよい」として、暴行・傷害と致死との因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 他人の行為によりて生じたる傷口より、病菌の侵入したるため、丹毒症を起こしたるといは、たとえその間において、被害者が治療の方法を誤りたり事実ありとするも、犯人の行為と被害者の疾病との間に因果関係の成立を認むべきものとす
と判じました。
⑥大審院判決(大正14年12月23日)
脳血管硬化症の持病ある者が暴行を受け、憤激の余り脳出血により死亡した事案で、被害者の病気についての予見可能性は不要であることを明言し、暴行と致死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪の成立するとしました。
裁判官は、
- 被告人が、被害者の頭部を突き、座敷より土間に墜落せしめ、その起き上がろうとするところを、更に2、2回手をもって頭部を殴打したるより、被害者は、その不法なる暴行に憤激し、互いに争闘したるため、その精神の興奮と争闘時における筋肉の激動とが相俟って、かねてより脳血管硬化症にかかれる被害者の血圧を急激に上昇せしめ、その結果、脳出血を発作し、衰弱のため死亡した
- たとえ、被告人が本件犯行の当時、被害者の脳血管硬化症にかかれることを知らず、従って、その死亡の認識し得ざりしとするも、右犯罪の成立を妨げるものにあらず
- 被告人の暴行は、単に被害者を激して精神を興奮せしめたるに止まりたるものにあらずして、その精神の興奮は、さらに被害者の筋肉激動と共同して脳出血を発作せしめたるものなれば、被害者は被告人の暴行により傷害を受たるものといい得べし
と判示しました。
⑦大審院判決(昭和2年9月9日)
被害者に高度の火傷を負わせ、被害者は苦痛に耐えられず又は新たな暴行を避けるため、自ら水中に投じ、よって生じた急速な体温流出が火傷による心臓麻痺の程度を加え死亡した事案で、裁判官は、
- 上述の如き経過により、その死亡を来すべきことあるは、吾人の知識経験により、これを認識し得べきところ
との述べ、相当因果関係説的な表現により、傷害と死亡の結果の因果関係を認め、傷害致死罪の成立を認めました。
⑧大審院判決(昭和5年10月25日)
脳震盪を起こした被害者を、第三者が水中に投げ込んで死亡させた事案で、暴行・傷害と致死との因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 犯人の加えたる傷害が、同一被害者に対する第三者の暴行に基づく致死の結果発生の共同原因たる関係あるときは、犯人は、傷害致死の罪責を免れるを得ず
と判示し、暴行・傷害と致死との間に、第三者の暴行を介入した場合でも、暴行・傷害と致死との因果関係が認められるとして、傷害致死罪が成立するとしました。
⑨大審院判決(昭和6年8月6日)
暴行・傷害と致死の因果関係の間に、被害者側の不注意が介在した場合でも、暴行・傷害と致死の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 被告の傷害行為が原因となりて、直接に幾多の疾病を醸し、その間接に生じたる余病が主因となり、被害者の死亡を招来したる以上、たとえ食事に関する被害者の不注意が副因となりとするも、被告人は傷害の罪責を免れざるものとす
と判示しました。
⑩大審院判決(昭和17年4月11日)
川に突き落とし溺死させた事案で、暴行と致死の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 人の身体に対し、暴行を加えうる認識ありて、暴行を加え、よって溺死の結果を生ぜしめたる以上、刑法第205条の傷害致死罪成立す
と判示しました。
次回記事に続く
次回の記事では、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした最高裁判例を紹介します。