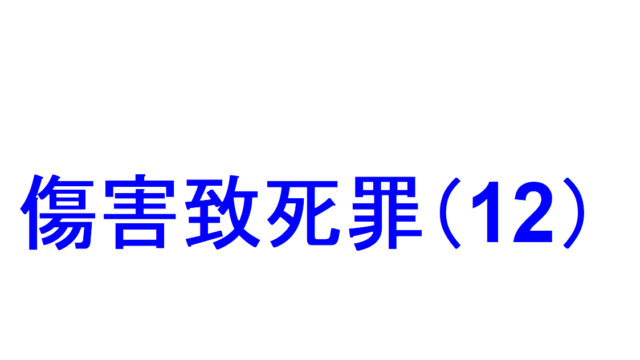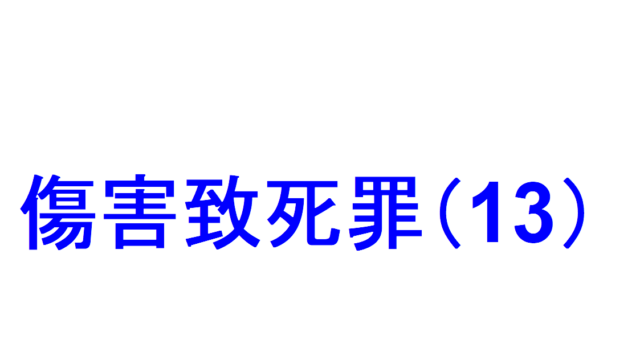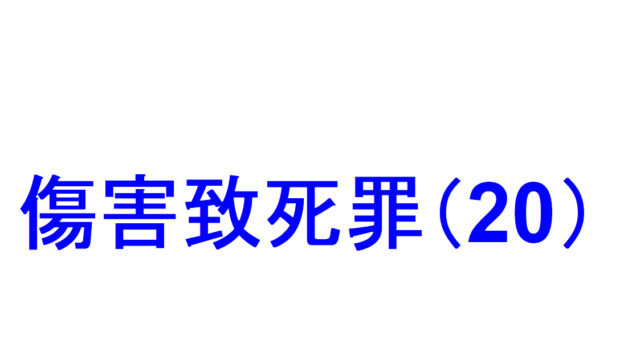傷害致死罪(刑法205条)における責任能力について説明します。
責任能力とは?
まず、責任能力について説明します。
責任能力とは、
犯罪の行為時において、自分が実行した犯罪行為の是非善悪を弁別し、かつ、その是非善悪の弁別に従って行動し得る能力
をいいます。
責任能力がない人は、たとえ殺人罪などの凶悪犯罪を行ったとしても、処罰されません。
(責任能力については、前の記事でより詳しく説明しています)
傷害致死罪における責任能力
傷害致死罪における責任能力の認定の考え方は、傷害罪と同様です(傷害罪における責任能力については前の記事参照)。
傷害致死罪の裁判で、責任能力が争点となるのは、酩酊者・薬物中毒者の責任能力の事例が多いです。
以下で判例の事例を紹介します。
この判例で、裁判官は、
- 覚せい剤中毒患者が、薬物注射をすれば、精神異常を招来し、他人に暴行を加えることがあるかも知れないことを予想しながら、敢えてこれを容認して薬物注射をなし、心神喪失の状態に陥り、短刀をもって人を殺害したときは、殺人の犯意を認めることはできないが、暴行の未必の故意が成立し、傷害致死の罪責を免れない
と判示しました(原因において自由な行為の理論)。
東京地裁判決(昭和40年11月30日)
病的酩酊による心神喪失の状態において犯した傷害致死の行為について、過度の飲酒を抑制する義務を怠って飲酒した重過失による重過失致死罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 被告人は、かねてからいわゆる酒癖が悪く、酒に酔うと短気粗暴になり、かつ、病的銘酊となる素質があって、過度に飲酒するとしばしば病的銘酊に陥り、心神喪失の状態で、特に家庭内で家人に対し手で殴打したり、手当り次第、物を投げつけたりなどする粗暴な行動におよぶ習癖があり、被告人もこれらの習癖を充分自覚していた
- 被告人が過度に飲酒した場合には、病的銘酊に陥って、子供らに粗暴な振舞におよぶおそれがあり、かくては、保護する者もなく、避難する能力も防衛する能力もないかかる幼児らが死傷の結果を招く危険性は極めて大であって、このようなことは、容易にこれを認識することができる状況にあったのである
- 前示のような習癖を自覚する者は、過度の飲酒を抑制し、病的銘酊に陥って心神喪失の状態で右子供らに危害を加えるに至ることを未然に防止する義務があるのにもかかわらず、被告人は、これを著しく怠り、右のような危険について認識せず、清酒五合を飲んだ重大な過失により、病的銘酊に陥り、就寝中の幼児Kに対し、心神喪失の状態で、暴行を加え、頭部打撲傷等の傷害を負わせ、頭部打撲による硬膜下血腫のため死亡させた
と判示し、酒を飲み、自ら心神喪失状態を招いて、子どもに暴力を振るったことを過失と捉え、重過失致死罪を認定しました。
仙台高裁判決(昭和29年11月11日)
この判例は、飲酒酩酊による心神耗弱を認めなかった事例です。
裁判官は、
- 被告人の言葉はろれつが回らないといっても聞きとれない程ではなく、普通の時とは言葉が違っていた程度であった
- 被告人は、本件犯行直後、自転車に乗っていたことが認められる
- 被告人は、本件犯行に至るまでの自己の行動、犯行の動機、犯行の模様、犯行後の行動を逐一詳細に供述しているのであって、このことは被告人が犯行当時における自己の行動に関し明確な認識のあったことを物語るものである
- 以上を総合すれば、被告人が本件犯行当時、飲酒酩酊していで、事物の理非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が多少減退していたとしても、その能力が著しく減退した状態、すなわち刑法にいわゆる心神耗弱の状態にあったものとは到底認めるを得ない
と判示し、飲酒酩酊による心神耗弱を認めず、傷害致死罪が成立するとしました。
熊本地裁八代支部判決(昭和55年5月23日)
傷害致死の事案について、被害者らの異常な言動を「つきもの」による仕業であるとする「支配観念」に陥ったことにより心神耗弱が認められた事例です。
まず、被告人の弁護人は、被告人の犯行時の精神状態について、
- 本件犯行前から犯行当時にかけて、妻H、長女R、長男である被害者Tが次々と祈祷性精神病にかかり、被告人も家族らの異常な言動は「つきもの」の仕業であると確信し、精神医学上の「支配観念」に陥り、そのために被告人の弁別能力は著しく阻害され、心神耗弱の状態にあった
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 被告人の精神状態、犯行当時の状況、被告人の信仰歴などを総合して判断すると、被告人の責任能力は、被告人の家族が次々と「感応」し合って、いわゆる祈祷性精神病に陥り、被告人は、その状態にまでは至らなかったものの、同人らと同程度に家族の異常な言動を「つきもの」による仕業であると確信し、このような特定の強い思考が、他の全ての思考に優先し、長時間持続する状態、すなわち「支配観念」に陥り、被告人の意識は相当程度減弱されたために、正しく自己の行為を判断し、その行為のもたらす結果を充分に認識する能力が著しく欠けていたものであり、心身耗弱の段階にあったものと認めるのが相当である
- なお、検察官は、被告人は鳶口で殴打し始めてから、金具のついた方で殴るのは危険だと悟り、持ち替えて柄の方で殴っていること、また殴打中、他人が来たので、犯行状況を見せるのを恥ずかしいと考え中止していること、犯行後、長男である被害者Tの死亡を知ってから鳶口を家の庭先の畑に捨て、警察にも当初そのことを隠していたこと等の被告人の行動、判断等に照らせば、被告人の犯行時の精神状態が刑法上の心神耗弱に該当する程度のものではない旨主張し、一応もっともな指摘と思われる点であるが、なるほど犯行の間に右にいわゆる支配観念が短時間うすれ、判断能力が一時回復した時があり、そのような状態下で被告人は検察官指摘のような行動をとったが、それも間もなく圧倒的な支配観念にかき消されてしまっている精神状態にあったと認めるのが相当である(逆に、判断能力が一時回復することがあり得る程度の精神状態であったという事実は、被告人自身は祈祷性精神病にかかっておらず従って心神喪失状態までには至らない、判示のように心神耗弱の状態にあった事実を裏付けるものと評価することができる)
と判示し、被告人が犯行当時、心神耗弱の状態であったと認定し、そのことを考慮して傷害致死罪の成立を認め、刑の重さを判断しました。
大阪地裁判決(昭和47年12月20日)
この判例は、精神病者の祈祷治療に当たった祈祷者の傷害致死事案につき、祈祷者が祈祷性精神病にかかっていたことを理由に、その責任能力が否定し、傷害致死罪は成立しないとして、無罪を言い渡した事例です。
裁判官は、
- 被告人は、本件犯行当時、その宗教的確信、被暗示性が強い性格特徴、精神生理学的に混乱状態に陥りやすいような脳機能の不安定さに加わえて、精神異常者をお祈りで癒してほしいという被告人にとっては未経験で困難なことを依頼されたことによる緊張状態のもとで、精神異常者が病的症状を示しているという異様な雰囲気に直面し、長時間の祈祷による肉体的疲労もあって一種の心因反応に陥ったものであり、自我意識が障害され、被告人は自分の言動が自己に所属するという実感はなく、自分の言動か他者の言動かどちらともいえない漠然としてた状態、ないし自我意識が高度に障害されて全く第三者によってあやつられていると感じている状態との間を動揺していた
- 被告人は、判断の方向が一方的に宗教的迷信の範囲にとどまる、いわゆる祈祷性精神病(平素、憑依、神罰、精神的感通などの迷信を有する者が、偶然これらに関係する恐怖すべき事件に遭遇するか、または自ら異様なりと思う症状に際会した折などに発症するもので、錯乱状態、昏迷状態および一時的な人格変換などの状態を呈し、この反応の際の人格変換は自己催眠によりおこる不随意言行に基づく人格変換であり、自我意識を失い、神、狐等の人格になって、それに相当する挙動をなし種々なことを口走る状態をいう)に陥っていたもので、その自我意識の障害の程度は強いものであったことを認めることができる
- 従って、当裁判所は右のような精神状況の被告人には、本件犯行当時、自己の行為の是非善悪を判断し、それに従って行動する能力を失っていたのではないかとの合理的疑いが十分にあり、本件全証拠を検討しても被告人が本件犯行当時、責任能力を有し、あるいは責任能力が心神耗弱の程度に止まっていたとの心証を形成することができなかった
と判示し、被告人の心神喪失を認め、傷害致死罪は成立しないとしました。
京都地裁判決(昭和56年12月14日)
この判例は、低血糖誘発効果を有するインシュリン注射をした約30分後に、かつ、ビールを飲んだ上で傷害致死の犯行に及んだ事案について、右犯行当時まだ右注射による低血糖症状下にはなかった等として、心神耗弱の主張を排斥した事例です。
裁判官は、犯行直前のインシュリン注射による意識喪失を否定し、責任能力に影響しないとしました。
大阪地裁判決(昭和58年3月18日)
傷害致死の事案につき、暴行行為の途中から酒の酔いが深まり、錯乱状態で暴行を続けた場合であっても、前半の暴行時に責任能力に疑いがなく、暴行が前後で態様を異にしないときには、全体を一体として評価すべきであるとして、刑法39条の適用を否定した事例です。
裁判官は、
- 被告人は、本件犯行に着手した時点においてはもとより、犯行の前半部分にあたる、金網のフェンス付近に転倒した被害者に暴行を加えた段階においては、その責任能力に疑いはなかったものであるところ、その段階において被害者に加えた暴行は、優に致死の結果をもたらしうるものと認められるうえ、その後の被告人の錯乱状態は、被告人自らの飲酒及びそれに先き立つ暴行等の行動によって招かれたものであり、かつ、右状態で行われた暴行は、前段階におけるそれと態様を異にするものでもないから、本件における被告人の暴行は、その全部を一体として評価すべきである
- 仮りに犯行の後半部分において、被告人がその責任能力に何らかの影響を及ぼすべき精神状態に陥っていたとしても、刑法39条1項又は2項は適用されないものと解すべきである
と判示し、被告人の心神喪失と心神耗弱を否定し、傷害致死罪の成立を認めました。
長崎地裁判決(平成4年1月14日)
上記判例と同じく、犯行開始前後にわたる飲酒により、犯行途中から心神耗弱状態(複雑酩酊)に陥って致命傷を負わせるに至った傷害致死の事案について、刑法39条2項の適用を否定した事例です。
裁判官は、
- 本件は、同一の機会に同一の意思の発動にでたもので、実行行為は継続的あるいは断続的に行われたものであるところ、被告人は、心神耗弱下において犯行を開始したのではなく、犯行開始時において責任能力に問題はなかったが、犯行を開始した後に更に自ら飲酒を継続したために、その実行行為の途中において複雑酩酊となり心神耗弱の状態に陥ったにすぎないものであるから、このような場合に、右事情を量刑上斟酌すべきことは格別、被告人に対し非難可能性の減弱を認め、その刑を必要的に減軽すべき実質的根拠があるとは言いがたい
- そうすると、刑法39条2項を適用すべきではないと解するのが相当である
と判示し、被告人の心神耗弱を否定し、傷害致死罪の成立を認めました。
大阪地裁判決(平成元年6月28日)
この判例は、重度のパラノイア病者の惹起した傷害事件につき、責任能力がないとして無罪が言い渡された事例です。
裁判官は、
- バラノイアにおいては全人的な人格の解体は存せず、妄想が中核となるものであるから、妄想に基づく行為以外の行為については、通常は責任能力が存するといえるが、妄想に基づく行為についての責任能力の有無は、パラノイアの程度、犯行の動機、態様、状況、犯行にいたる経過等の諸事情を総合して判断するのが相当であると解する
- これを本件についてみるに、被告人は強度の被害妄想等の妄想が存し、パラノイアとしては症状は重いものであること、本件は被告人の被害妄想に基づく幻覚症状下において惹起されたものであり、被告人は、これまでにも嫌がらせと感じる騒音を聞くと、再三にわたり執拗に相手方に苦情を言い、あるいは抗議をしており、本件においても被害者に音を出すのを止めさせようと抗議を行うについて、場合によっては脅すつもりでドライバーを携帯したものであること、被害者の部屋の鎖錠を引きちぎって部屋に侵入し、被害者が被告人の抗議に反論するや、いきなり本件犯行に及んでいること等の諸事情に照らすと、被告人は嫌がらせの騒音に対して抗議することは正当な行為である旨の意識を有しているものと推認され、右騒音が幻覚ではないという被告人の認識を訂正させることはできないのであって、被告人は、被害妄想に基づく幻覚症状下においては、正常な判断能力及び行動制御能力を欠いているといわざるを得ない
- 結局、被告人は本件犯行当時重度のパラノイアに罹患しており、右犯行はその症状である被害妄想に基づくものであって、被告人は、本件犯行当時、行為の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力を欠いていたと認めるのが相当である
と判示し、被告人の心神喪失を認め、傷害致死罪の成立を否定しました。
東京地裁判決(平成3年10月15日)
この判例は、妄想型精神分裂病に罹患している被告人の犯行(傷害)につき、精神分裂病に基づく明らかな幻覚妄想の上に行われたもので心神喪失状態にあった旨の精神鑑定の結果を排斥し、心神耗弱を認めた事例です。
裁判官は、
- 鑑定書及び鑑定医証言中には、本件犯行は精神分裂病に基づく明らかな幻覚妄想の上に行われたもので、当時、被告人は物事の是非善悪を弁別し、それに従って行動する能力に欠けていたとする部分がある
- しかしながら、本件犯行当時における被告人の責任能力の有無、程度については、裁判所において、鑑定書の右鑑定部分の結論に至る経過等をも斟酌しつつ、犯行当時の被告人の精神分裂病の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様、犯行前後の行動等の諸般の事情を総合して判断すべきものである
- 被告人が本件犯行に及んだのは、被告人としてはHが自分の金を盗んだと考えていたものの、確証がないため、直接Hに文句を言うこともできないままに、Hに対する憤まんを抱き、これに、Hらしい声で被告人を愚弄するような幻聴等が加わり、Hに対する憤まんを一層募らせていたところへ、当のHから、「友達じゃないか。」などと、被告人からすれば神経を逆撫でするようなことを言われたため、それまでHに対して募らせていた憤まんが一挙に爆発した結果であると認められる
- 被告人が、本件犯行当時罹患していた妄想型精神分裂病による幻聴や妄想により、被告人のHに対する憤まんが増幅された結果、被告人の本件犯行に対する自己制御が著しく困難になっていたことは明らかである
- 被告人は、本件犯行当時、妄想型精神分裂病に起因する妄想や幻聴により、自己の行為の是非を弁識し、これに従って行動する能力が著しく減じており、心神耗弱状態にあったと認めるのが相当である
と判示し、被告人の心神耗弱を認定した上で、傷害致死罪の成立を認め、刑を減軽しました。