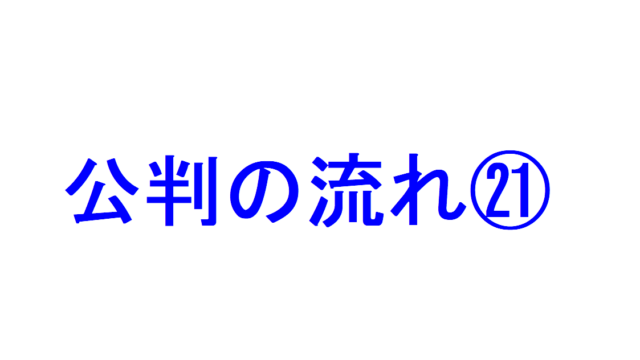即決裁判手続とは?
即決裁判手続とは?
即決裁判手続は、
争いのない明白・軽微な事件について、被疑者の同意等を要件として、検察官が起訴と同時に申立てをし、早期に開かれる公判期日において、簡略・効率化した証拠調べを行い、罰金又は執行猶予付きの懲役若しくは禁錮の判決を原則として審理当日に言い渡す手続
です(刑訴法316条の16~316条の29)。
即決裁判手続の創設の経緯
即決裁判手続は、簡易公判手続(刑訴法291条の2)があまり利用されていないことから、 刑事裁判の迅速化を図る目的の下、簡易公判手続より利用しやすい新たな制度として、平成18年に創設された制度です。
【簡易公判手続との異同】
即決裁判手続は、「証拠調べ手続の簡略化」「伝聞法則の不適用」などの公判手続の簡略化の点で簡易公判手続と共通します。
一方で、
- 即決裁判手続を行うのに検察官の申立てが必要であること(刑訴法350条の16)
- 即日判決が言い渡されるのが原則であること(刑訴法350条の28)
- 科刑制限があること(刑訴法350条の29)
- 上訴制限があること(刑訴法403条の2)
は即決裁判手続にしかないものであり、簡易公判手続とは異なります。
即決裁判手続の対象事件
即決裁判手続の対象事件は、
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く事件
です(刑訴法350条の16) 。
検察官による即決裁判手続の申立て
検察官は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除き、事案が明白かつ軽微であり、公判での証拠調べが速やかに終わると見込まれること、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、被疑者の同意を得た上で、公訴の提起と同時に即決裁判手続の申立てをすることができます 。
被疑者に弁護人がある場合には、弁護人が同意し、又は意見留保をする場合でなければ、検察官は即決裁判手続の申立てをすることができません(刑訴法350条の16)。
即決裁判手続は必要的弁護事件である
即決裁判手続で行う裁判は、必要的弁護事件となります(刑訴法350条の23)。
即決裁判手続の申立てがあった場合に被告人に弁護人がいないときは、裁判長はできる限り速やかに職権で国選弁護人を付すことになります。
裁判所はできる限り14日以内に公判を開かなければならない
裁判所は、検察官から即決裁判手続の申立てがあった場合、できる限り早い時期に公判期日を開かなければなりません。
公判期日を開くのは、「できる限り、公訴が提起された日から14日以内の日」とされています(刑訴規則222の18)。
なお、この「14日以内の日」は、
- 申立て後に弁護人が選任された場合
- 申立ての段階では弁護人が即決裁判手続に同意するか否かの意見を留保した場合
には、弁護人が即決裁判手続に同意をした時点から起算されます。
公判手続
裁判所は、公判期日の冒頭手続において、被告人が有罪である旨の陳述をしたときは、事件が即決裁判手続によることが相当でないものと認めるときなどを除き、即決裁判手続によって審判をする旨の決定をします。
そして、簡略な手続による証拠調べを行った上、原則として即日判決を言い渡します(刑訴法350条の22、350条の24、350条の28)。
即日判決とは、第1回目の公判期日において判決を言い渡すということです(原則、次回の公判期日に判決の言渡しを持ち越すことはできません)。
判決における科刑制限
裁判所は、即決裁判手続において、判決で懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、
の言渡しをしなければなりません(刑訴法350条の29)。
ただし、罰金刑については実刑を科すことができます(起訴猶予を付す必要はありません)。
なお、即決判手続においては、刑の一部執行猶予(刑法27条の2)の言渡しはできません。
上訴制限
即決裁判手続による判決に対しては、再審事由がある場合を除き、判決において示された罪となるべき事実の誤認を理由として控訴を申し立てることができません(刑訴法403条の2、413条の2)。
上訴が制限されるのは、
- 上訴を許すと、上訴に備えて、即決裁判手続による審理を念入りに行わなければならなくなり、裁判の迅速化という手続の趣旨が損なわれるおそれがあるため
- 即決裁判手続は、争いのない明白・軽微な事件について、被告人の意見を慎重に確認した上で行われることから、上訴を制限したとしても被告人の権利保護に欠けるところはないと考えられるため
です。
なお、即決裁判手続において事実誤認を理由とする控訴を制限する刑訴法403条の2第1項が憲法32条に違反しないことは判例(最高裁判決 平成21年7月14日)で示されています。
公訴取消しによる公訴棄却と再起訴
裁判所が即決裁判手続の申立てを却下する決定をした場合で、検察官が、証拠調べが行われる前に公訴を取り消した場合(刑訴法257条)において、検察官は、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、刑訴法340条の規定(公訴取消し後の再起訴の規定)にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができます(刑訴法350条の26)。
本来、検察官が公訴を取り消した場合は、公訴の取消後犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合に限り、検察官は同一事件について更に公訴を提起することができます(刑訴法340条)。
しかし、即決裁判手続では、刑訴法340条の規定にかかわらず、検察官は同一事件について更に公訴を提起することができます。
これは、即決裁判手続の対象となり得る簡易な自白事件について、裁判所が即決裁判手続の申立てを却下した場合に、検察官が公訴を取り下げて捜査に戻ることができるようにしたものです。