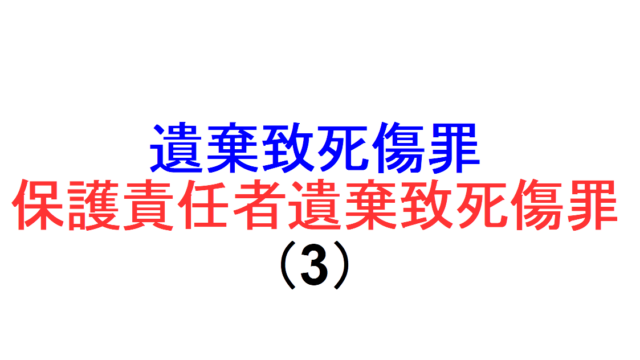遺棄致死傷罪・保護責任者遺棄致死傷罪(2) ~「遺棄・不保護と死傷結果との因果関係」を説明~
前回の記事の続きです。
遺棄致死傷罪・保護責任者遺棄致死傷罪が成立するためには、遺棄・不保護と死傷結果との間に因果関係を要する
遺棄致死傷罪・保護責任者遺棄致死傷罪(刑法219条)が成立するためには、遺棄又は不保護と死傷結果との間に因果関係が存在しなければなりません。
作為による遺棄の類型
作為による遺棄の事案で、遺棄と死との間に因果関係を認めた参考判例として、以下のものがあります。
大審院判決(昭和3年4月6日)
条件説的な立場から因果関係を認めた判決です。
精神病者を保護する責任ある被告人が、当該精神病者を極寒の気候である中、戸外に遣棄し、持病の肺気腫症に悪変を来させて死亡させた事案です。
裁判所は、
- 行為当時には被告人も一般人も被害者の肺気腫症を認識しえなかったとしても、遺棄されなければ死亡することはなかったという関係が認められるときは因果関係が肯定できる
と判示し、保護責任者遺棄致死罪の成立を認めました。
不作為による遺棄の類型
不作為による遺棄の事案で、遺棄と死との間に因果関係を認めた参考判例として、以下のものがあります。
保護責任者が救急医療を要請しなかった不作為と被害者の死の結果との間の因果関係を認めた判決です。
被告人は、少女を札幌市内のホテルに連れ込んで覚せい剤を注射し、その後、少女が午前0時半頃から異常な言動を始め錯乱状態になったのに何らの措置もとらず、午前2時15分頃ホテルを立ち去り、まもなく同女が死亡したという事案です。
一審判決(札幌地裁判決 昭和61年4月11日)は、遺棄行為がなければ確実に死ななかったことが証明されなければならないとした上、被害者は被告人が立ち去った後すぐに死亡した疑いがあること、救急医療と法医学の各専門家が救命可能性が100パーセントであったとはいうことができないとも述べていること等から、被害者の異常な言動が発生した後、直ちに医師の診療が求められたとしても、同女は死亡していたのではないかとの合理的な疑いが残るとし、被告人の不保護及び立ち去りと死亡との因果関係を否定して、保護責任者遺棄罪の限度で有罪としました。
控訴審判決(札幌高裁判決 平成元年1月26日)は、札幌市内の救急医療体制、被害者の年齢、従来の健康状態を踏まえて、同女が錯乱状態に陥った午前0時半頃に救急医療を要請していれば救命することは十分可能であったと認め、鑑定人が100パーセントの救命可能性を認めていなくとも刑法上の因果関係を否定すべきことにはならないとして、保護責任者遺棄致死罪の成立を認めました。
最高裁は、控訴審判決を支持し、
- 原判決の認定によれば、被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により錯乱状態に陥った午前0時半頃の時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女が年若く(当時13年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである
- そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と午前2時15分ころから午前4時ころまでの間に同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係があると認めるのが相当である
と判示し、保護責任者遺棄致死罪の成立を認めました。
この最高裁決定は、通説的見解である
- 不作為犯においては、期待された行為がなされていれば結果は生じなかったであろうといえる場合に、当該不作為と結果との因果関係(条件関係)が認められる
- この点は合理的な疑いを超える程度に立証されなければならず、期待された行為をしても結果が発生したかもしれないという合理的な疑いが残れば因果関係は否定される
という立場をとったものです。
不作為犯の因果関係においては、作為犯の場合と異なり、正面から「期待された行為がなされていれば」という仮定的事情を加えた判断となるため、そこに暖昧さ、不確実さが伴うことは避けられないところ、これを緩やかに認定すると疑わしきは罰せずの原則に反するおそれがあり、厳格に過ぎると実際上証明にかなりの困難を来すことになります。
この最高裁決定は、十中八九救命が可能であったという医学専門家の見解に基づく事実判断をもとに、救命は確実であるとして、不作為(不保護)と死亡との因果関係を肯定したものです。
広島地裁判決(平成22年11月9日)
延命可能性を肯定して不保護と死亡との因果関係を認めた判決です。
被告人が同居の実母(77歳)に必要な医療措置を受けさせず自宅軒下に放置して、栄養消耗症及び熱中症により死亡させた事案です。
裁判所は、実母が極度に衰弱した時点で医療措置などの保護義務を尽くせば、実際に死亡した日頃に死亡することを避け、延命させることができた認め、保護責任者遺棄致死罪の成立するとしました。
救命可能性が認められないとして不保護と死亡との因果関係を否定した裁判例
上記判例・裁判例とは逆に、救命可能性が認められないとして不保護と死亡との因果関係を認めず、保護責任者遺棄致死罪の成立を否定して同遺棄罪の限度で有罪とした裁判例として、以下のものがあります。
札幌地裁判決(平成15年11月27日)
実母及び妻らと同居していた被告人が、自宅において、実母に頭部を階段の角等に打ち付けられた妻が多量に出血していたのを発見したにもかかわらず、止血の措置もせず、救急車を呼ぶこともなく放置し、妻は死亡した事案で、救命可能性が認められないとして、裁判所は、保護責任者遺棄致死ではなく、保護責任者遺棄罪の限度で認定しました。
東京地裁判決(平成22年9月17日) 控訴審:東京高裁判決(平成23年4月18日)
被告人と共にMDMAを服用した女性が重篤な急性MDMA中毒症状を呈し、その後死亡した事案です。
裁判所は、
- 被告人は、直ちに119番通報をして救急車の派遣を求めて専門的な医療措置を受けさせるという女性の生存に必要な保護をすべき責任があったのに、119番通報をして救急車の派遣を求めることなく女性を放置し、もって同人の生存に必要な保護をしなかった
とした上、
- 女性は錯乱状態に陥り、明らかに異常な状態を呈して、もはや一般人の手に負える状況にはなかった
とし、救命可能性が認められないとして、保護責任者遺棄致死ではなく、保護責任者遺棄罪の限度で認定しました。
遺棄罪、保護責任者遺棄罪、遺棄致死傷罪、保護責任者遺棄致死傷罪の記事一覧