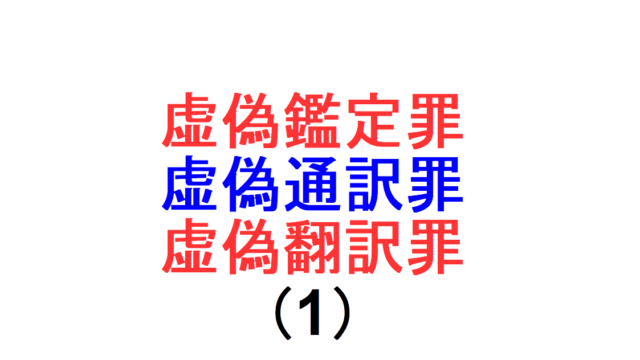偽証罪(5)~「偽証罪の主体である『証人』とは?」を説明
前回の記事の続きです。
偽証罪の主体である「証人」とは?
1⃣ 偽証罪(刑法169条)の主体(犯人)は、
「法律により宣誓した証人」
であり、偽証罪の主体(犯人)は「証人」に限定されます。
「証人」とは、
人が五官の作用により経験した事実を裁判所等の審判機関に直接に言語的手段を用いて報告する者
をいいます。
2⃣ 偽証罪が成立するためには、証人自身が宣誓した上で虚偽の証言をする必要があります。
なので、証人以外の者が宣誓しても偽証罪の主体とはなりません
例えば、民訴法207条により、証人ではなく、民事訴訟の当事者(裁判の被告と原告)が宣誓した場合は、その証人自身が宣誓をしていないので、その証人が虚偽の証言をしても偽証罪は成立しません。
3⃣ 刑事事件の被告人が偽証罪の主体になることはありません。
刑事事件の被告人が自己の刑事被告事件につき証人となることができるかどうかについては、刑事訴訟法の解釈上被告人と被告人質問に答える形などで任意に供述することができる(刑訴法311条)のみで、証人となることはできないと解すのが通説です。
ただし、刑事事件の被告人であっても、審判が分離している共犯者の被告事件(例えば、共犯者A、Bが一緒に一つの裁判を受けるのではなく、共犯者Aが単独で一つの裁判を受け、共犯者Bも単独で一つの裁判を受ける場合)において、共犯者の一人が相手共犯者の裁判に立つ場合には、被告人ではなく証人として裁判に立つことになるので、偽証罪の主体となります。
この点、最高裁決定(昭和29年6月3日)は、共同被告人を分離して証人として尋問することは憲法38条1項に違反しないとしており、これは、共同被告人でも、審判が分離されれば、共犯者の裁判においては証人として尋問を受けることになることを示しています。
4⃣ 起訴前の証人尋問でも、その証人が宣誓した上で虚偽の証言をすれば、偽証罪が成立します。
刑事事件に関し、第1回公判期日前の証人尋問における証人(刑訴法179条、226条、227条、228条)であっても偽証罪の主体になります。
民事事件においても、訴提起の前後を問わず、例えば、訴提起前の証拠保全手続(民訴法234条以下)における証人も偽証罪の主体になります。
旧刑法223条の規定する民商事等に関する偽証罪につき、大審院判決(明治42年12月16日)は、偽証罪は「証拠保全申請事件につき法律により宣誓を為したる上虚偽の陳述を為したる場合も包含す」と判示しています。
証人たる資格の要否
証人資格のない者を証人として尋問した場合、例えば、当該監督官庁の承諾なしに公務員を証人として尋問した場合(民訴法191条、刑訴法144条)にも、その者は偽証罪にいう「証人」として偽証罪の主体となります。
この点を判示した以下の判例があります。
大審院判決(明治42年11月1日)
裁判所は、旧々民訴法310条、旧々刑訴法123条、124条により証人資格を有しない者につき、
- 事実証人たる資格なきものといえども、宣誓の上、虚偽の陳述を為したるときは、その所為が偽証罪を構成すべきことは旧刑法における同罪の成立につき当院従来の判例において認むるところにして刑法における偽証罪の成立についてもまたこれと同趣旨に解するを相当なりとす
と判示して、旧刑法の下で、証人資格のない者についても偽証罪の主体たることを認めていた判例(大審院判決明治35年2月27日)を現行刑法の偽証罪についても踏襲し、証人資格を有しない者についても偽証罪にいう「証人」であることを認めました。