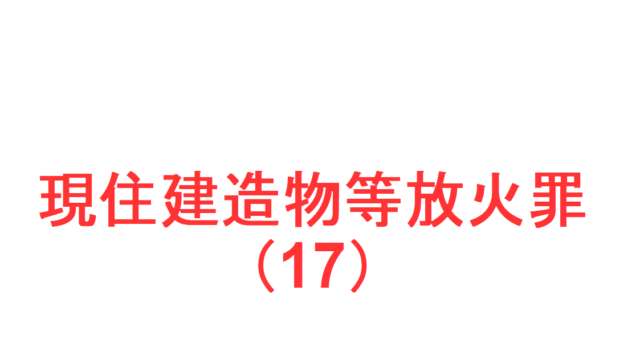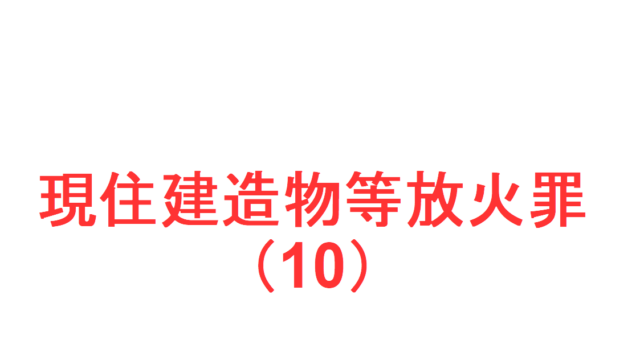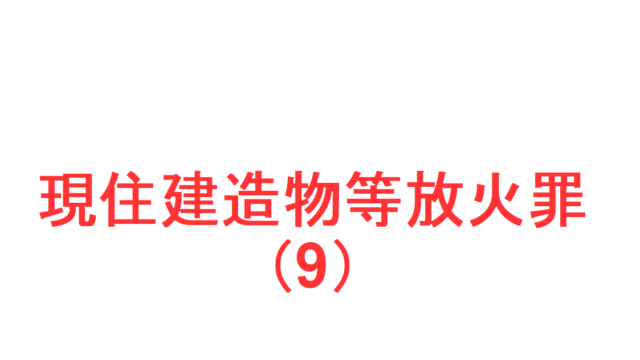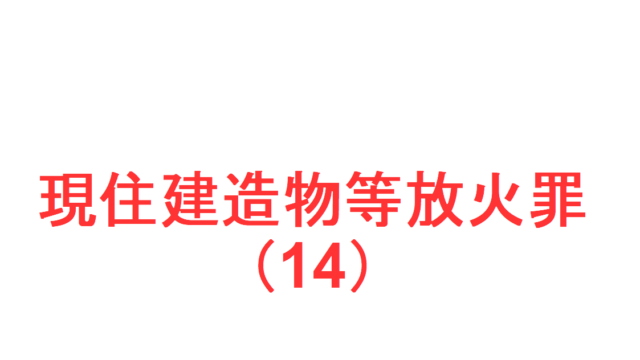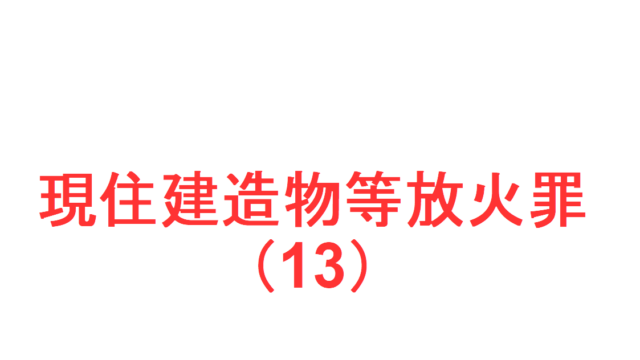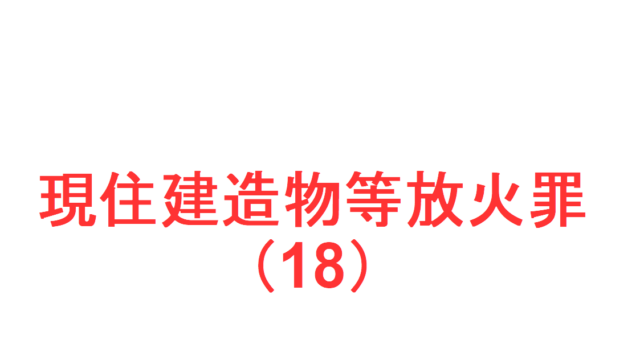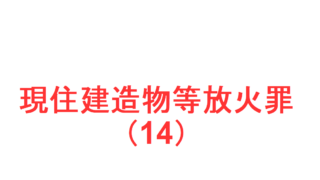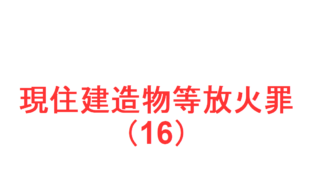現住建造物等放火罪(15) ~「錯誤と現住建造物等放火罪の故意の成否」を説明~
前回の記事の続きです。
錯誤と現住建造物等放火罪の故意の成否
現住建造物と法律上認められるための基礎となる事実関係をすべて認識しながら放火した建物が、法律上は非現住建造物にすぎないと思っていた場合は、現住建造物等放火罪の故意を阻却せず、現住建造物等放火罪が成立する
放火の客体が建造物、汽車、電車、艦船に属するか否かの点に錯誤(勘違い)がある場合、言い換えると、
その客体に関し、現住建造物と法律上認められるための基礎となる事実関係をすべて認識しながら、その客体は法律上、非現住建造物にすぎないと思っていた場合
は、法律の錯誤であり、故意の前提事実の認識に欠けることがないから、故意を阻却するものではありません。
例えば、
- 学校であるから現住建造物放火でないと誤信していた場合(学校に宿直室があれば現住建造物となり得る)
- 一時期外出中の住宅は非現住建造物になると誤信していた場合
が該当し、このような錯誤ある場合でも現住建造物等放火罪の故意を阻却せず、現住建造物等放火罪の成立が認められます。
※ 錯誤の詳しい説明は前の記事参照
※ 法律の錯誤の詳しい説明は前の記事参照
現に人の住居に使用し、又は現に人がいる建物であることの認識を欠く場合は、現住建造物等放火罪の故意は認められず、非現住建造物等放火が成立する
現に人の住居に使用し、又は現に人がいる建物であることの認識
が必要です。
なので、錯誤により、「現に人の住居に使用し、又は現に人がいる建物であることの認識」を欠く場合には、非現住建造物等放火罪の限度で処断されることになります。
この点、参考となる裁判例として以下のものがあります。
神戸地裁判決(昭和36年6月21日)
窃盗犯が家人に発見されたため、家人を木槌で連打し、被害者がすでに死亡しているものと誤信してその居住家屋に放火したが、当時被害者は存命していた事案です。
裁判官は、
- 刑法108条(現住建造物等放火罪)に該当するが、刑法38条2項(重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない)に則り、刑法109条1項(非現住建造物等放火罪)により処断すべき
とし、殺人罪のほか、現住建造物等放火罪ではなく、非現住建造物等放火罪が成立するとしました。
福岡高裁判決(昭和38年12月20日)
被告人が、自宅において、妻A子を刺殺し、二女C子(生後9月)に瀕死の重傷を与えて死亡したものと誤認し、被告人も自殺しようと決意し、自宅は住居として必要ないと考え、自宅に放火した事案です(なお、長女B子(3歳)は祖母に預けられていた)。
- 本件放火当時、被告人は妻A子と二女C子は死亡したものと考え、長女B子はすでに祖母方に行き本件家屋に居ないことを知って、本件家屋はもはや必要がないものとして火を放ったものであるから、被告人は放火直前本件家屋を住居とすることを放棄し火を放ったものと認めるのが相当である
- ところで長女B子はその当時3年月余の幼児であったので、その住居は母A子亡きあとは、当然父であった被告人の意思に従って定まるものであるから、被告人が放火直前、本件家屋をその住居とすることを放棄した以上、長女B子は本件家屋に住居するものではないというべきであり、したがって、これと同一の見解の下に本件につき現住建造物放火未遂罪の成立を否定した原判決は正当である
と判示し、殺人罪のほか、現住建造物等放火罪ではなく、非現住建造物放火罪が成立するとしました。
※「犯人のみが単独で住居に使用し又は犯人のみが現在する建造物」を放火すれば、現住建造物等放火罪ではなく、非現住建造物等放火罪が成立することについての説明は前の記事参照
現住建造物と思い放火したが、非現住建造物であった場合には、非現住建造物放火の故意が認められ、非現住建造物等放火罪が成立する
現住建造物と思い放火したが、非現住建造物であった場合には、非現住建造物放火の故意が認められ、非現住建造物等放火罪が成立します。
放火犯人が本来の目的物である現住建造物を非現住建造物と誤信していても、更に付近の現住建造物に延焼する可能性を認識していたときは、現住建造物等放火罪の故意が認められ、現住建造物等放火罪が成立する
放火犯人が本来の目的物である現住建造物を非現住建造物と誤信していても、更に付近の住宅に延焼する可能性を認識していたときは、現住建造物放火の罪責を負うことになります。
参考となる裁判例として以下のものがあります。
東京高裁判決(昭和51年9月21日)
会社事務所に人の居住する認識がなかったとしても、その事務所から隣接する住宅まで約6 メートル程度で、乾燥し強風の吹く気象であったことなどから、住宅に延焼することは当然予見していたと認めるのが相当であるとして、現住建造物等放火罪の罪責を負うとした事例です。
裁判官は、
- 当時被告人において事務所建物を非現住建物と誤信していた事実があったとしても、民家の類焼を認識していた点において現住建造物放火の罪責を負わねばならないことはいうまでもない
と判示し、非現住建造物等放火罪ではなく、現住建造物等放火罪が成立するとしました。
名古屋高裁金沢支部判決(昭和28年12月24日)
住宅の一部を構成する倉庫を独立の非現住建造物と誤認して放火した場合でも、住宅部分に延焼する可能性を予見しつつ、倉庫部分すなわち住宅の一部分を焼損したときは、現住建造物等放火罪が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 原審認定の事実を再び要約摘示すれば、「被告人は、住宅の一部を構成する倉庫を、住宅と別個独立の建造物(人の現住又は現存しない建物)であると誤信し、もし該建造物に放火すれば住宅(母屋)に延焼することあるべきを予見つつ、火を放って該倉庫、すなわち住宅の一部を焼燬したものである。」と言うに帰着するのである
- 思うに、いやしくも自己の行為より、住宅焼燬の結果が発生すべきことを認識しながら、しかも放火行為を敢てし、これによって、現に住宅焼燬の結果を発生せしめるにおいては、その認識が未必的であると確定的であるとを問わず、また、直接放火の対象となった建造物の性質について、錯誤があったと否とによらず、該所為は住宅放火の既逐罪を構成すること、多言を要せずして明かなところである
と判示し、非現住建造物等放火罪ではなく、現住建造物等放火罪が成立するとしました。