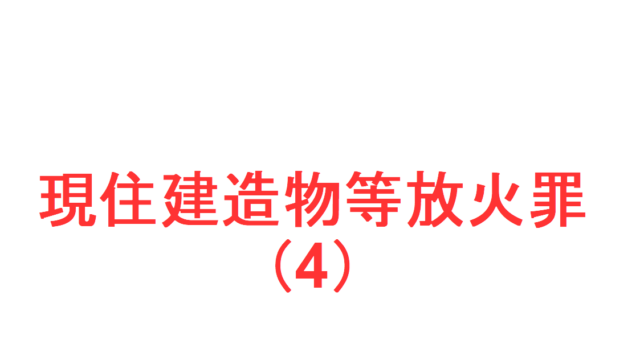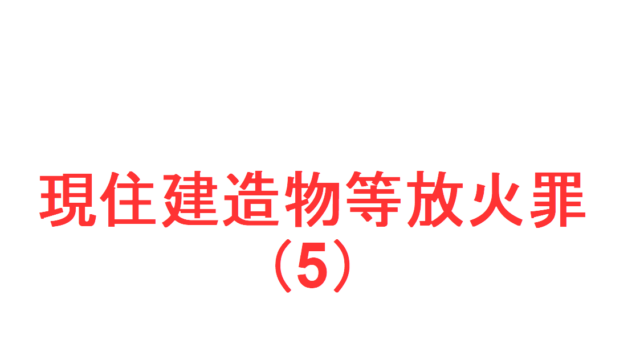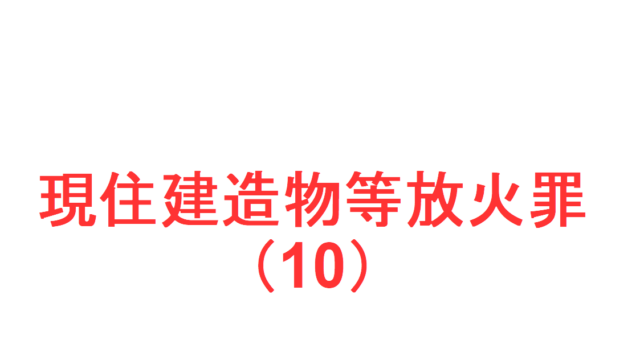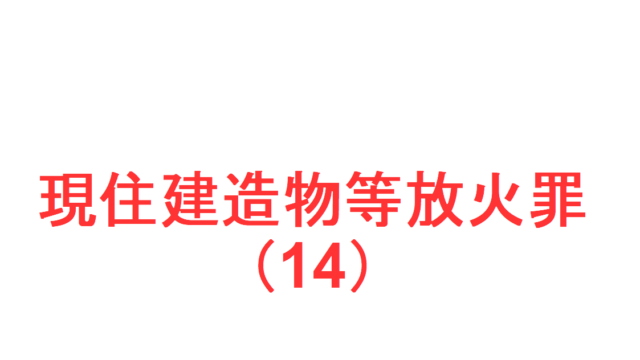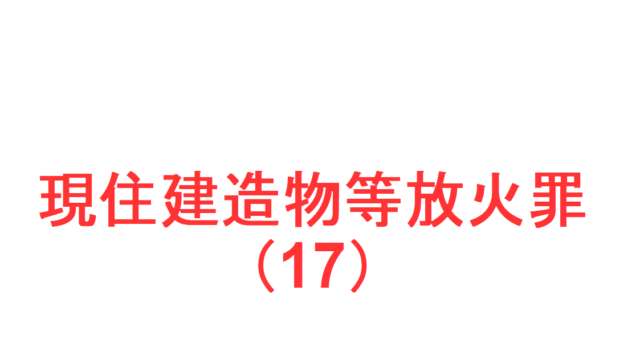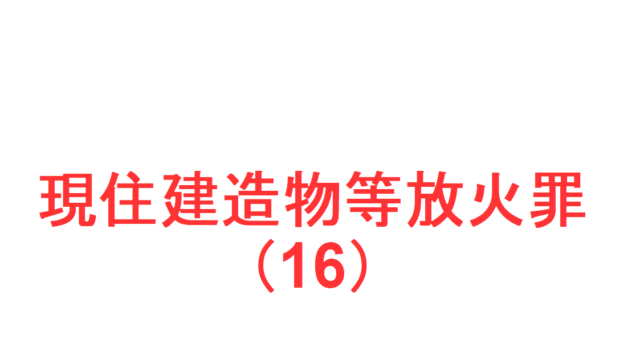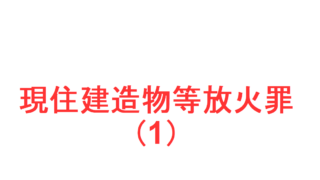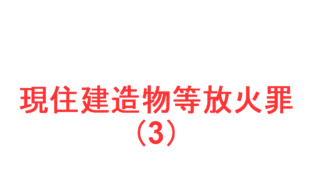現住建造物等放火罪(2) ~「住居に使用する部分が建造物と一体をなしている場合、その建造物全体が1個の建造物として現住建造物放火罪の客体となる」などを説明~
前回の記事の続きです。
現住建造物等放火罪(刑法108条)は、
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する
と規定します。
今回の記事では、現住建造物等放火罪における住居性について説明します。
「現に住居に使用し」とは?
刑法108条の条文にある「現に人が住居に使用し」とは、
現に人の起臥寝食の場所として日常使用すること
をいいます。
さらに、「現に人が住居に使用し」というに当たり、
昼夜間断なく人の現在することを必要としない
とされます。
この点、参考となる判例として以下のものがあります。
大審院判決(大正2年12月24日)
裁判官は、
- 刑法第108条にいわゆる現に人の居住に使用する建造物とは、現に人の起臥寝食の場所として日常使用せらるる建造物をいうものとす
と判示しました。
裁判官は、
- 被害者B方はCという看板で待合業を営んでおり、被害家屋はAが住んで居る母屋とは別棟で所謂離れではあるが、同人の営業用に使用しているもので同建物には押入のある座敷があり、その押入には常に寝具を準備してあって被告人も同建物内に数回寝泊りした事実、並に犯行のあった晩も同離れには一人の客が来て使用した事実を認め得る
- 以上の事実により、同建物には昼夜間断なく人が現在するとはいえないがAの経営している待合業のため日夜人が出入し、且つ起臥寝食の場所として使用している建物であることを認め得るから、被害建物は現に人の居住に使用して居ることの証拠がないとはいえない
- そして原判決は挙示の証拠によって被害家屋は人の居住に使用している家屋であると認定したのであり、前説明のとおりその認定には何ら法則に違反するところは認められないから、判示事実に対し刑法第108条を適用したことは当然である
と判示しました。
「現に人が住居に使用し」の「住居」とは?
「現に人が住居に使用し」の「住居」とは、通常、人の生活の本拠をいいますが、刑法第108条が人の生命・身体に対する危険性を考慮して特に重く処罰する趣旨からすれば、生活の本拠といえなくとも、
日常において起臥寝食の場所として使用する場所であれば、人の生命・身体に対する危険性があるといえるので、その程度の場所で足りる
と解されます。
現に人の住居に使用する建物であれば、放火の当時、犯人以外の者が現に建物内にいることは必要でありません。
日常起臥寝食の場所として使用する場所であれば、必ずしもその使用が継続する必要はなく、使用が断続するのも妨げません。
例えば、炭焼きの山仕事に従事する時に利用する山腹の一軒家で、年間の半分以上をそこで寝泊まりし、日常生活に必要な寝具、炊事用具等の設備のある家屋は、現住建造物といえるとした裁判例があります(東京高裁判決 昭和38年12月23日)。
また、建物に現実に泊まり込んだのは約1か月半の間に十数回であり、比較的短期間で、その頻度も3、4日に一回程度にとどまる場合であっても、日常生活上必要な設備等もあることなどから、住居性を肯定した判例があります(最高裁決定 平成9年10月21日)
建物本来の用途が住居として使用することを主たる目的としたものであることを要しない
「現に人が住居に使用し」の「住居」は、
- その本来の用途が住居として使用することを主たる目的としたものであること
- 同一人が間断なく起臥寝食すること
を要しません。
異なる者の出入りする場所も、起臥寝食の場所として使用する以上、住居に使用するものと認定されます。
この点につき、現住建造物等放火罪の成立が認められる住居として、以下のものが挙げられます。
- 料理店兼浴場の客室としての使用を主目的とする建物のうち、一室のみを経営者らの住居に使用していた建物(大審院判決 昭和9年11月15日)
- 学校の校舎の一室を宿直室に充て宿直員を夜間宿泊させている場合の校舎(大審院判決 大正2年12月24日、大審院判決 明治45年3月12日)
- 人の寝泊まりしている劇場(最高裁判決 昭和24年2月22日)
- 待合業を営む家の母屋とは別棟の営業用の離れ座敷(最高裁判決 昭和24年6月28日)
- 夜間守衛やガードマンが巡回し、神職とガードマンが社務所、守衛が守衛詰所で就寝している神社社殿(最高裁判決 平成元年7月14日)
- 勤務員である警察官の仮眠休憩施設のある派出所(札幌地裁判決 平成6年2月7日)
住居に使用する部分が建造物と一体をなしている場合、その建造物全体が1個の建造物として現住建造物等放火罪の客体となる
住居に使用する部分が建造物と一体をなしている限りにおいて、その建造物全体が1個の建造物として現住建造物等放火罪の客体となります。
現住建造物等放火罪における住居性は、人の起臥寝食の場所として日常使用する点が判断基準となります。
そのため、専ら業務・職務の執行の場所として使用する建造物(例えば、会社、店舗、官公署、工場)でも、その一部に人の起臥寝食の場所として日常使用される住居部分(例えば宿直室)が存在すれば、現住建造物等放火罪の客体になります。
宿直室がある官公署の建物を放火した事案について、現住建造物等放火罪の成立を認めた以下の判例があります。
大審院判決(大正3年6月9日)
本館庁舎及びこれとは別個独立した付属建物からなり、宿直室がその付属建物内にある場合において、本館庁舎を放火した事案で、裁判官は、
- 官庁等は執務時間以外においては常に宿直員あり
- 宿直員は非常を警戒すべき責任を有するをもって執務時限後といえども庁中の各部分を巡視するを通例となすが故に、宿直室が庁舎と独立したる建造物内にありたる場合といえども庁舎をもって人の住居に使用せる建造物なりというを妨げず
と判示しました。
建物を使用する者が住居として使用することを放棄した場合は現住建造物とはいえない
居住者が建造物を住居として使用することを放棄した場合(住居として使用する意思がない場合)は、現住建造物とはいえず、現住建造物等放火罪の客体になりません。
住居として使用する意思の有無は、現住建造物等放火罪の成否に影響するため、裁判で争われることがあります。
住居として使用する意思の有無が争点となった事例として以下の裁判例があります。
高松高裁判決(昭和31年1月25日)
被告人が立ち戻った姿を見かけ、被告人からの無心、暴行を避けるため、家財を隣家に預けて宿泊し、一時的に住居から離れ、被告人から身をかくしていたところ、その住居に被告人が放火した事案で、裁判官は、
- 住居として使用することをやめたものではなく、単に一時不在と認めるのが相当であり、現住建造物に当たる
とし、現住建造物等放火罪が成立するとしました。
被告人の中学1年の次男、小学5年の長女が、被告人の放火の意図を知らず、親戚訪問の名目で自宅を連れ出されたところ、被告人がその自宅に放火した事案で、裁判官は、
- 当時、我家につき居住の意思を放棄したと認められない
とし、現住建造物等放火罪が成立するとしました。
松江地裁判決(昭和33年1月21日)
就寝中の老夫婦を絞殺して金品を強奪し、その証拠を隠蔽するため放火して、老夫婦の死体を損壊するとともに家屋を焼損した事案で、裁判官は、
- 老夫婦が生前5歳の幼女を預かり、殺害時、同女も就寝中であったが、放火前に被告人自ら同女をその生家に連れて行き、老夫婦が旅行に出掛けたことを理由として同女をその両親のもとに帰らせ、その監護の下に復せしめた場合には、非現住家屋となる
とし、現住建造物等放火罪ではなく、非現住建造物等放火罪(刑法109条)が成立するとしました。
東京高裁判決(昭和54年12月13日)
妻との夫婦生活が破綻状態にあり、犯行時、妻子の衣類・調度品のほとんどが他に運び去られていても、離別の意思が固まっていないことなどから、妻子の住居たる性質は失っていないとした事例です。
裁判官は、
- 被告人による放火の対象となった本件建物は、右犯行の行われた時点においてA子と子供2人の衣類、調度品等のほとんどすべてが他に運びさられていたとしても、その数時間前まではこれらが同女らの居住に伴う生活用具として相応の場所に存在する状態が長く継続していた経過もあいまって、右犯行の当時においても依然被告人の妻であるA子とその子供2人の居住したる性質を失うに至っていなかったものと解するのが相当といわなければならない
と判示しまし、現住建造物等放火罪が成立するとしました。
横浜地裁判決(昭和58年7月20日)
妻が家出をした家を夫が放火した事案で、
- 妻が離婚を相当に固く決意して家出したものの、着の身着のままの状態で家出した状況、従前家出しては戻っている経過等を考慮すると、依然、被害家屋は妻が住居に使用する建物と認められる
とし、現住建造物等放火罪が成立するとしました。
競売手続の妨害目的で自己の経営する会社の従業員を交替で泊まり込ませていた家屋を放火した事案で、裁判官は、
- 放火前に従業員を旅行に連れ出していても、同家屋に日常生活上必要な設備、備品等があり、従業員らが犯行前の約1か月半の間に十数回交替で宿泊し、旅行から帰れば再び交替で宿泊するものと認識していたなどの事情がある場合には、この家屋は現住建造物に当たる
と判示し、現住建造物等放火罪が成立するとしました。