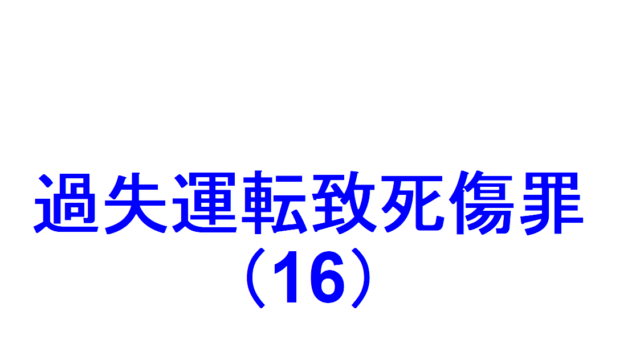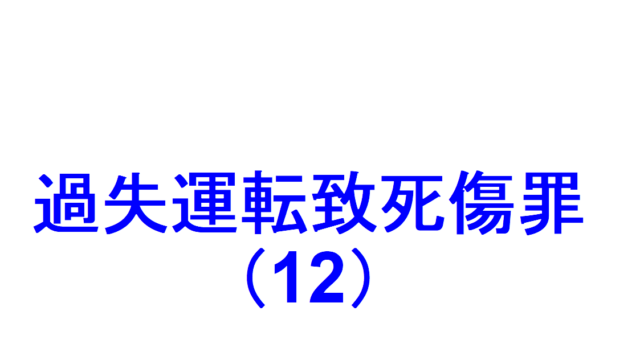過失運転致死傷罪(31)~「過失運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪、重過失傷害罪の『公訴の時効』」「訴因と異なる態様の過失を認定する場合には訴因変更手続を要する」を説明~
前回の記事の続きです。
過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)と業務上過失致死傷罪、重過失傷害罪(刑法211条前段・後段)の
の考え方について説明します。
なお、訴因変更とは、検察官が、起訴状に記載された公訴事実の内容を、裁判の途中で変更することをいいます。
公訴時効
業務上過失傷害罪の公訴時効について判示した以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 業務上過失傷害罪の公訴時効は、被害者の受傷の時点から進行するが、業務上過失致死罪の公訴時効は、被害者の受傷から死亡までの間に業務上過失傷害罪の公訴時効期間が経過したか否かにかかわらず、死亡の時点から進行する
- 結果の発生時期を異にする業務上過失致死傷罪が観念的競合の関係にある場合には、その全部を一体として観察すべきであり、したがって、最終の結果が生じたときから起算して同罪の公訴時効期間が経過していない以上、その全体について公訴時効は未完成である
としました。
このことは、過失運転致死傷罪、重過失致死傷罪についても当てはまります。
訴因と異なる態様の過失を認定する場合には訴因変更手続を要する
訴因と異なる態様の過失を認定する場合には、裁判において、訴因変更手続(起訴状に記載された公訴事実の内容を変更する手続)を要します。
ここで、検察官が公訴事実に記載した注意義務違反の態様(たとえば、前方不注視、ハンドル操作ミスなど)にどの程度の変動があった場合に、訴因変更を要するかが問題となります。
この点について、参考となる判例として、以下のものがあります。
「濡れた靴をよく拭かずに履いていたため、一時停止の状態から発進するに当たり、アクセルとクラッチペダルを踏んだ際、足を滑らせてクラッチペダルから左足を踏みはずした」ことを過失とする訴因に対し、訴因変更しないで、「交差点前で一時停止中の他車の後に進行接近する際、ブレーキをかけるのを遅れた」ことを過失として認定したのは、訴因と異なる態様の過失を認定したものであり、被告人に防御の機会を与えるため訴因変更手続を要するとしました。
東京高裁判決(昭和54年12月26日)
前方注視、安全運転義務違反を、前方を注視し認識した状況を前提とした減速・徐行義務違反と認定する場合について、訴因変更を要するとしました。
過失の態様の前提となる事実の変動も、それが過失の態様の変動に及ぶ場合には訴因変更が必要となる
過失の態様の前提となる事実についての変動も、それが過失の態様の変動に及ぶ場合には訴因変更が必要となります。
この点について、参考となる裁判例として以下のものがあります。
東京高裁判決(昭和54年11月28日)
同じ前方注視義務違反であっても、義務違反の時期、過失の程度等が異なる場合は、訴因変更手続を要するとしました。
大阪高裁判決(昭和60年10月2日)
被害車の位置が変わることにより過失の態様が変動した場合として、訴因では被害車が左後方の後続車であり、同車との安全確認義務違反が過失とされていたのを、被害車が左側併進車であり、同車との安全確認義務違反が過失であると認定するのは、異なる被害車の位置及び被告人の過失を認定することになるから訴因変更手続を要するとしました。
訴因変更手続を要しないとした事例
訴因と判決認定事実との間に相違があっても、訴因の基本的構成要素としての過失内容に異なるところがない場合には、訴因変更手続を要しません(東京高裁判決 昭和57年11月29日)。
参考となる判例として以下のものがあります。
雨で滑りやすくなっていた道路を走行していた被告人が速度調整義務を怠ったため、対向車とすれ違う際に急制動したところ滑走し、対向車と衝突したという事案について、注意義務の根拠となる路面の滑りやすさの原因と程度に関する具体的事実について訴因としての拘束力を認めませんでした(つまり、その具体的事実を変更をするに当たり、訴因変更は不要としました)。
この事案では、当初の訴因(路面に落下した石灰が融解して滑走しやすい)を一審で訴因変更(『降雨によりアスファルトが湿潤して滑走しやすい』)したところ、その認識が否定され無罪となりました。
そこで、控訴審で検察は当初の訴因を追加したところ、控訴審は、『石灰が融解したところに降雨で湿潤して滑走しやすくなっていた』と認定しました。
最終的に裁判は最高裁までいき、最高裁は、「過失犯に関し、一定の注意義務を課す根拠となる具体的事実については、たとえそれが公訴事実中に記載されたとしても、訴因としての拘束が認められない」と判示し、原判決に違法はないとしました。
被告人の運転する乗用車が対向車線に進出したため、対向して進行してきた大型トラックと正面衝突した事案で、一審は前方不注視、進路の安全不確認の過失について合理的疑いが残るとして無罪としました。
しかし、控訴審は、前方注視を欠いたとしても、ハンドルを右方向に回転させることなく握持していれば事故を回避できたとして、一審に事実誤認はないとしつつ、被告人は進路前方を注視し、自車が対向車線にはみ出さないようハンドルを握持して、道路左側部分を進行すべき注意義務に違反しており、過失内容について検察官に訴因変更を促し又はこれを命じなかった一審判決には審理不尽の違法があるとしました。
最終的に最高裁は、「原判決が認定した過失は、被告人が『進路前方を注視せず、ハンドルを右方向に転把して進行した』というものであるが、これは被告人が『進路前方を注視せず、進路の安全を確認しなかった』という検察官の当初の訴因における過失の態様を補充訂正したにとどまるものであって、これを認定するためには必ずしも訴因変更の手続を経ることを要するものではないというべきである」とし、訴因変更は不要とする判断をしました。
業務上過失致死傷の訴因を重過失致死傷として認定する場合は訴因変更手続を要しない
業務上過失致死傷(刑法211条前段)の訴因を重過失致死傷(刑法211条後段)として認定する場合は訴因変更手続を要しません(最高裁決定 昭和40年4月21日)。
裁判官が、検察官に対し、訴因変更を命令・勧告しないまま無罪の言渡しをした場合には、審理不尽の違法があるとされる
重大事案について、裁判官が、検察官に対し、訴因変更を命令ないし勧告しないまま無罪の言渡しをした場合には、審理不尽の違法があるとされます(最高裁決定 平成15年2月20日、名古屋高裁判決 昭和63年12月12日)。
裁判官は、検察官からの訴因変更請求がなければ、訴因変更を行うことができないという裁判上のルールになっています。
裁判官が、独断で訴因変更をすることはできません。
裁判官が、検察官に対し、訴因変更を命令ないし勧告したにもかかわらず、検察官が、裁判官に対し、訴因変更請求を行わなかったのであれば、裁判官は無罪の言渡しをしても、審理不尽の違法にはなりません。
この点について、参考となる事例として、以下のものがあります。
東京地裁判決(平成15年7月8日)
裁判官が、警察や検察の捜査段階の被告人の供述ではなく、公判廷における被告人の供述に従って犯罪事実を認定しようとした事案です。
裁判官は、検察官に対し、訴因と別の過失が認められる余地があるとして求釈明(きゅうしゃくめい)を行ったのに対して、検察官が被告人の公判供述に沿って訴因変更を検討する意思はない旨釈明したため、裁判官は、当初の訴因に基づいて無罪を言い渡しました。
業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪の記事まとめ一覧