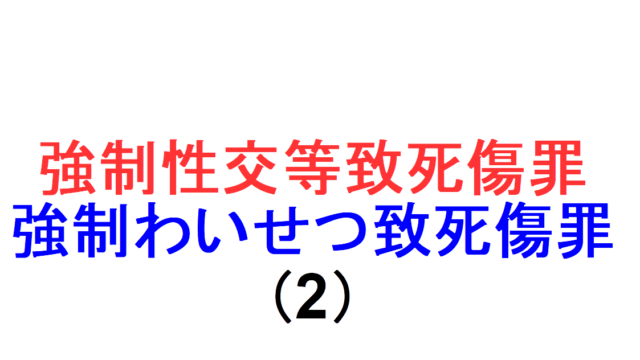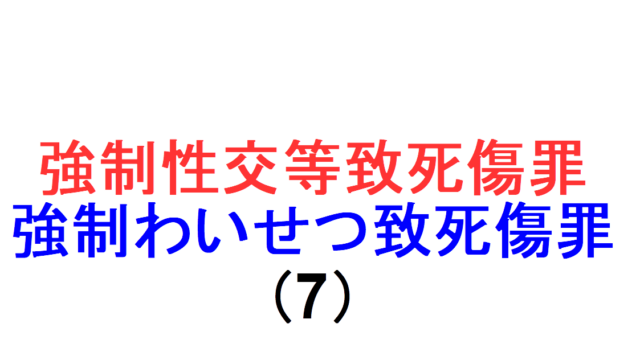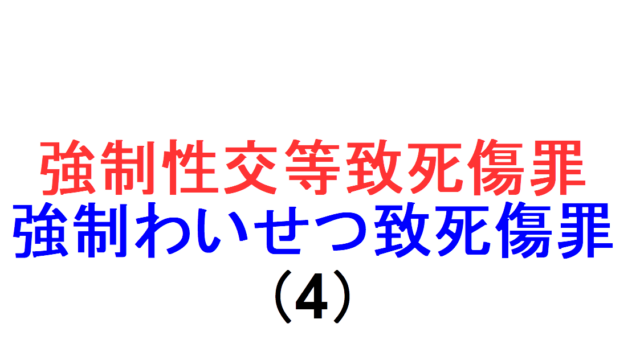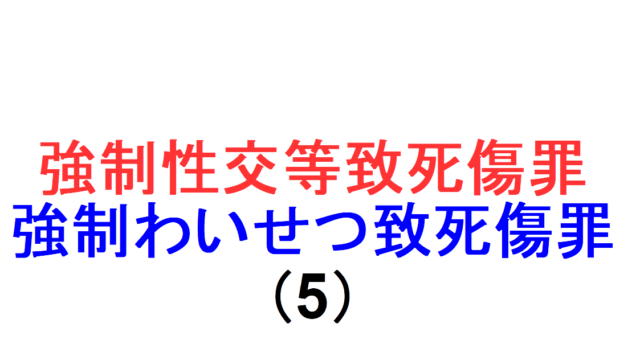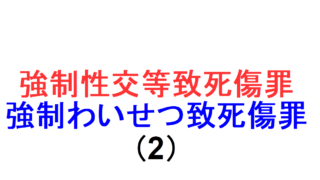強制性交等・強制わいせつ致死傷罪(3) ~「傷害の程度(傷害罪における傷害と差異はない)」「軽微な傷害の事例」「傷害に当たらないとされた事例」「パニック障害、ストレス障害、意識障害、急性薬物中毒は傷害に当たる」を判例で解説~
傷害の程度(傷害罪における傷害と差異はない)
強制性交等致死傷罪、強制わいせつ致死傷罪(刑法181条)の成立を認めるには、傷害・死亡の結果が生じていることが必要になります。
そして、本罪の傷害の程度は、傷害罪(刑法204条)における傷害の程度と統一的に解釈すべきとされます。
つまり、傷害罪において傷害を認定できる傷害の程度であれば、強制性交等致傷罪、強制わいせつ致傷罪の成立が認められるということになります。
参考となる判例として、以下のものがあります。
大審院判決(明治44年4月28日)
強制性交等致傷罪における傷害の意義について、裁判官は、
- 刑法第181条所定の罪は、同第176条ないし第179条の罪を犯し、その結果、人を死傷に致すことによって成立するものにして、被害者の死傷に関し、故意又は過失あることを必要とせず
- 刑法にいわゆる人を傷害すとは、他人の身体の現状を不良に変更するのいうにして、必ずしも身体の組織を物質的に破壊することを要せず
と判示しました。
大阪高裁判決(昭和34年6月23日)
強姦致傷罪(現行法:強制性交等罪)における傷害と傷害罪における傷害の意義に差異はない旨を判示した事例です。
強制性交に際し、安静加療4、5日を要し、被害者が疼痛を訴えた処女膜裂傷の傷害を負わせた強制性交等致傷罪の事案です。
まず、被告人の弁護人は、強姦致傷の事実について、
- 本件のようなごく軽微な処女膜裂傷の如きは強姦致傷罪(強制性交等罪)にいうところの傷害には当たらない
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 被害者の被った処女膜裂傷は安静治療4、5日を要するもので、診察の際、被害者は疼痛を訴えたとあるので、これを刑法にいう傷害というにはばからない
- もとより強姦致傷罪(強制性交等罪)における傷害についても、同断であって、普通、傷害罪における強姦致傷罪におけるとその傷害の意義に所論(弁護人の主張)のような差別のあるべき理は認められない
- 従って、原判決が本件を強姦致傷罪(強制性交等罪)をもって問擬(もんぎ)したのは正当であって、その事実認定及び法令の適用に誤はない
と判示しました。
裁判官は、
と判示しました。
軽微な傷害の事例
強制性交等致死傷罪、強制わいせつ致死傷罪について、判例は、かなり軽度の傷害についても傷害を認定しています。
参考になる判例として、以下のものがあります。
最高裁判決(昭和24年7月26日)
裁判官は、
- 強姦行為を為すに際して、相手方に傷害を加えた場合には、たとえその傷害が、メンタム(※皮膚の塗り薬)1回つけただけで、後は苦痛を感ぜずに治った程度のものであったとしても、強姦致傷(現行法:強制性交等致傷罪)の罪が成立する
としました。
放っておいても治る程度の傷について、裁判官は、
- 本件傷害が軽微なものであっても、それは明かに人の健康状態に不良の変更を加えたものであるから傷害と認めるのが正当である
と判示し、強制性交等致傷罪の成立を認めました。
加療約1週間を要する顔面打撲傷等の傷害について、裁判官は、
- 軽微な傷でも、人の健康状態に不良の変更を加えたものである以上、刑法所定のいわゆる傷害に該当するものであって、同法181条所定の傷害を同法204条所定の傷害と別異に解すべき特段の事由が存しないことは当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかである
と判示しました。
名古屋高裁判決(昭和37年10月29日)
裁判官は、
とし、強制性交等致傷罪の成立を認めました。
岡山地方裁判所津山支部判決(昭和45年6月9日)
軽い上皮剥脱は強姦致傷の致傷にはあたらないとして強姦罪のみを認めた事例です。
裁判官は、
- 少なくとも強姦致傷(現行法:強制性交等致傷罪)ないし強盗致傷罪などにいう傷害は、その法定刑の重さからいっても、その傷害の程度において、日常生活上看過される程度の発赤、表皮剥脱などのたぐいであって、これに対して格別の治療措置を必要とせず、極く短期間内に、具体的には数日内に自然に快癒する程度の極めて軽微な損傷は、厳密な意味においては身体の完全性を害し、生活機能に障がいを与えたものといえるけれども、今問題としている傷害にはあたらないものと解するのを相当と考える
- 今これを本件の前記傷害についてみると、被害者自身右傷害に気付かず、たまたま被害直後に腟内検査などをした医師によって発見されたものであり、しかも、同医師成作の前記診断書によっても、当該傷害は爪などによる軽度擦過傷と思われる、との記載がある一方、これに要する加療日数はもちろん、全治に要する日数さえ記載がないのである
- このような事情および同被告人の加担後における前記犯行態様などを合わせ考えると、右傷害は、さきにみた少なくとも強姦致傷罪(強制性交等致傷罪)などにおいていう傷害にはあたらぬ程度のものと認められるのである
- 従って、右傷害をもつて同被告人を強姦致傷罪(強制性交等致傷罪)として問擬することはできない
と判示しました。
軽微な傷害の具体例
上記各判例のほか、軽微な傷害で強制性交等致傷罪の成立が認められた事案を列挙します。
- 陰部付近に軽度の炎症を生じさせた事案(高松高裁判決 昭和29年1月12日)
- 陰毛の抜き取りの事案(大阪高裁判決 昭和29年5月31日)
- 医学上治療の必要のない全治3日間程度の打撲傷の事案(東京高裁判決 昭和31年10月9日)
- 全治2日問の皮膚剥離の事案(名古屋高裁判決 昭和32年1月30日)
- 直接被害者の生活機能に影響がない圧迫擦過傷(高松高裁判決 昭和32年8月6日)
- 全治3日間の自然に治癒する程度の傷害の事案(広島高裁判決 昭和37年7月19日)
- 粟粒大の擦過傷の事案(高松高裁判決 昭和38年10月3日)
- 加療5日間を要する皮下溢血の事案(東京高裁判決 昭和39年4月7日)
- 加療10日間を要する傷害の事案(広島高裁判決 昭和43年11月8日)
- 全治3日間程度の擦過傷の事案(仙台高裁秋田支部判決 昭和44年3月4日)
- 全治約10日間の打撲傷等の創傷の事案(最高裁決定 昭和45年7月28日)
- 被害者の乳房の上部にキスマークをつけた事案(東京地裁判決 昭和45年10月22日)
- 姦淫前に被害者の乳房にキスマークをつけた事案(東京高裁判決 昭和46年2月2日)
- 特段の治療をするととなく約1週間で全治した傷害の事案(大阪高裁判決 昭和46年8月6日)
- 加療約3日間程度の傷害の事案(広島高裁判決 昭和49年6月24日)
傷害に当たらないとして強制性交等致傷罪の成立を否定した事例
強制性交等致傷罪にいう傷害に当たらないとして、本罪の成立を否定した事例として以下のものがあります。
大阪地裁判決(昭和41年1月31日)
かき傷を傷害と認めず、強制性交等致傷罪の成立を否定し、強制性交等罪が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 本件公訴事実は、被告人らは強姦によりA子の両大腿部中央背面に治療約2日間を要する掻傷を与えたというにある
- そこで、この点について証拠を検討すると、診断書には同女の両大腿部中央背面に爪等様のものによる掻傷数条を認め、この治癒には約2日間を要するものと認める旨の記載がある
- また、当公廷における証人(右診断書を作つた医師)の供述によれば、診断の際、被害者は全然痛みを訴えおらず、何らの手当てもせず、治療の必要もなく、捨ておいても2日くらいで治るものと認めたとあり、被害者も別段治療しなかつたが直ぐ治ったとのべている
- 傷害とは、人の生理機能に障害を生ぜしめ、その健康状態を不良ならしめることであるが、きわめて軽微な創傷で、健康状態にほとんど障害を与えない場合には、これを傷害と目するには足りないのであって、たんなる暴行と考えるべきである
- してみると右証拠をもっては、果して傷害と目すべき程度の創傷を生じたものかどうか、なお幾分の疑問を生ずる
- そして、他にこの疑いを解くに足る証拠がない
- よって、本件は強姦罪(現行法:強制性交等罪)と認定した次第である
と判示しました。
大阪地裁判決(昭和41年2月11日)
強制性交に際し、被害者のA子に全治3日間を要する右小陰唇内側上部擦過創等の傷害を負わせた事案で、裁判官は、
- 被告人は、A子をモーテルの浴場において、2回又は3回、A子を姦淫しているのであるから、検察官の主張するA子の傷害は右の3つの機会におけるいずれかの姦淫の際に生じたことは認められるにしても、その傷害の程度が右のとおり軽微なことと相俟って、そのうちのいずれの姦淫の際に生じたものであるか明確に認定しうる証拠がない
- 従って、傷害の点は、結局、証明がないことに帰し、その責任までも被告人に負わせることはできないというべきである
と判示し、強制性交等致傷罪の成立を否定し、強制性交等罪が成立するとしました。
宮崎地裁都城支部(昭和42年6月22日)
軽徴な擦過傷が刑法上の傷害に該らないとして強姦致傷罪(強制性交等致傷罪)の成立を否定した事例です。
裁判官は、
- 検察官は、被告人らが暴行により、B子に対し、治療約3日間を要する大腿内部擦過傷を負わせたものであると主張する
- なるほど証拠によれば、本件犯行の約2時間後にB子を診断した医師は、B子の両大腿部に合計3か所くらいの拇指頭大よりやや小さい擦過傷を認め、それが全治するまでに約3日間を要すると判断したことが認められる
- そして、各証拠によると、右創傷が被告人らの姦淫行為自体、もしくは、その際の暴行により生じたものであることは、これを認めるにかたくない
- しかしながら、証拠によると、B子は医師の診断をうけるまで全く傷の存在を自見せず、全然痛みも感じなかったこと、前記の擦過傷というのは、表皮が少し破壊されただけで、何らの治療はもとより、その箇所の消毒すらも必要でなく、放置しておけば自然に2、3日で跡かたもなく消え去る程度のものであることが認められるのである
- このように、一般日常生活において看過される程度のきわゆて軽微な損傷であって、人の生理機能に障害を生ぜしめたとも、あるいは健康状態を不良に変更したともいいえないのみならず、生理機能の障害と同視しうる程度に身体の完全性をき損したともいいえないものは、かりに、医学上の概念として創傷といいうるとしても、直ちに刑法上の傷害にあたると断ずることはできないものと解さなければならない
- したがって、被告人らの行為が強姦致傷罪(強制性交等致傷罪)にあたるという点については、結局、犯罪の証明がないことに帰する
と判示し、強制性交等致傷罪の成立を否定し、強制性交等罪が成立するとしました。
大阪地裁判決(昭和42年12月16日)
強姦致傷罪(強制性交等致傷罪)の致傷が刑法上の傷害にあたらないとした事例です。
裁判官は、
- 検察官は、被告人は強姦行為の際に被害者A女に対し、加療約1週間を要する外陰部裂傷を負わせたと主張する
- 医師が犯行当日、A女を診察したところ、A女の右腟前庭部(外陰部)に長さ5ミリ幅、3ミリくらいの線条の裂創を認め、4、5日で治癒すると判断したことが認められる
- 右創傷は、被告人の本件強姦行為の際に(おそらく手指でひっかいたことによって)できたものと認められる
- しかしながら、右創傷はA女において気がついていなかったものであり、医師は放置しておいても右の期間で治癒すると診断し、何の手当も施さなかったことが認められる
- 本件の裂創は、被害を受けた本人も気づかず、格別の治療も受けないで4、5日のうちに自然に治癒したもので、一般日常生活において看過される程度のきわめて軽微な損傷であって、傷害の構成要件が予定している程度の被害者の生理機能に障害を生ぜしめたとも健康状態を不良に変更したともいいえないから、医学上の創傷とはいいうるとしても、刑法上の傷害にあたるものとは認め難い
- 従って、強姦(現行法:強制性交等罪)のみを認定した次第である
と判示し、強制性交等致傷罪の成立を否定し、強制性交等罪が成立するとしました。
処女膜裂傷は傷害に当たる
強制性交による致傷罪に特有の問題として、処女膜裂傷があります。
処女膜裂傷は、強制性交に当然含まれる軽微な傷であるから、強制性交等致傷罪にいう傷害に当たらないのではないかという疑問が提起されることがありますが、判例は、傷害に当たるとしています。
裁判官は、
- 論旨(弁護人の主張)は、刑法第177条の法意は、13歳以上の婦女を強姦した場合は、強姦のため処女膜裂傷の結果を生じても、これを放任行為となし、強姦罪が成立するだけであって強姦致傷罪は成立しないという趣旨であると主張する
- しかし、強姦に際して婦女の身体の如何なる部分に傷害を与えても強姦致傷罪は成立するのである
と判示し、処女膜裂傷を傷害と認め、強制性交等致傷罪が成立するとしました。
裁判官は、
と判示しました。
パニック障害、ストレス障害は傷害に当たる
強制性交・強制わいせつ行為の被害者が、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたにとどまらず、精神疾患の一種であるパニック障害、外傷後ストレス障害(PTSD)等を発症した場合にも、因果関係が認められるのであれば、強制性交等致傷罪や強制わいせつ致傷罪が成立し得ます。
参考となる判例として、以下のものがあります。
広島高裁岡山支部判決(平成25年2月27日)
被告人の強制わいせつ行為により被害者が発症した急性ストレス反応及び全治期間不明のパニック障害が傷害に当たると認定し、強制わいせつ致傷罪が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 被害者の負ったパニック障害等は、国際的な診断基準に基づくものであること、その症状の程度は、パニック障害については全治期間不明、急性ストレス反応についてもその症状が1か月程度続いたことなどから、本件被害者の精神的傷害はこれを超える重篤なものであり、強制わいせつ致傷罪にいう傷害に当たるというべきである
と判示しました。
最高裁決定(平成24年7月24日)
この判例は、監禁致傷罪(刑法221条)の事案ですが、不法に被害者を監禁し、その結果、被害者に外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させたことケースで、外傷後ストレス障害(PTSD)を傷害と認定した事案であり、参考になるので紹介します。
不法に被害者を監禁し、その結果、被害者が、医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したと認められる場合、同障害の惹起は刑法にいう傷害に当たり、監禁致傷罪が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 被告人は、本件各被害者を不法に監禁し、その結果、各被害者について、監禁行為やその手段等として加えられた暴行、脅迫により、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、いわゆる再体験症状、回避・精神麻痺症状及び過覚醒症状といった医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから、精神疾患の一種である外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)の発症が認められたというのである
- 所論(弁護人の主張)は、PTSDのような精神的障害は、刑法上の傷害の概念に含まれず、したがって、原判決が、各被害者についてPTSDの傷害を負わせたとして監禁致傷罪の成立を認めた第1審判決を是認した点は誤っている旨主張する
- しかし、上記認定のような精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たると解するのが相当である
- したがって、本件各被害者に対する監禁致傷罪の成立を認めた原判断は正当である
と判示しました。
意識障害、急性薬物中毒は傷害に当たる
睡眠薬等を摂取させて約6時間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた場合も、健康状態を不良に変更し、その生活機能の障害を惹起したものとして傷害罪が成立します。
傷害罪の事案ですが、この点について判示したのが以下の判例です。
最高裁決定(平成24年1月30日)
睡眠薬等を摂取させ、数時間にわたり、意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた行為につき、傷害罪の成立が認められた事例です。
裁判官は、
- 被告人は、病院で勤務中ないし研究中であった被害者に対し、睡眠薬等を摂取させたことによって、約6時間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせ、もって、被害者の健康状態を不良に変更し、その生活機能の障害を惹起したものであるから、いずれの事件についても傷害罪が成立すると解するのが相当である
と判示し、意識障害、急性薬物中毒を傷害と認め、傷害罪の成立を認めました。