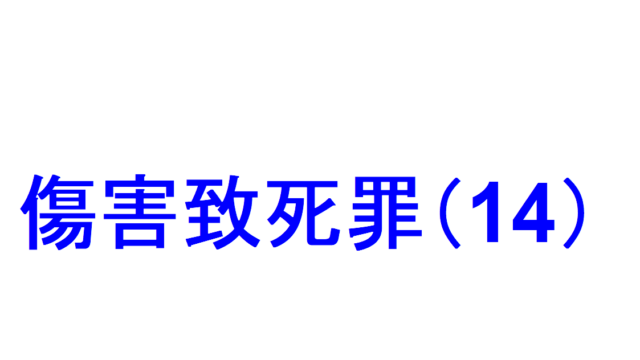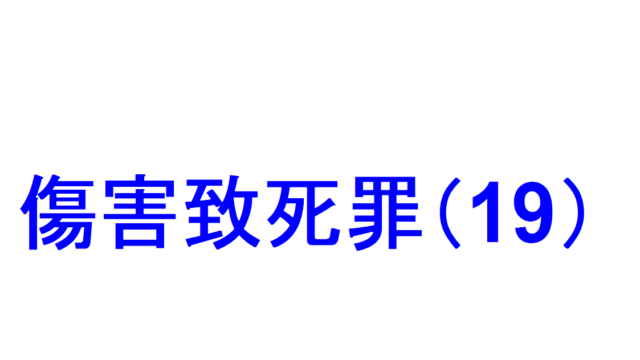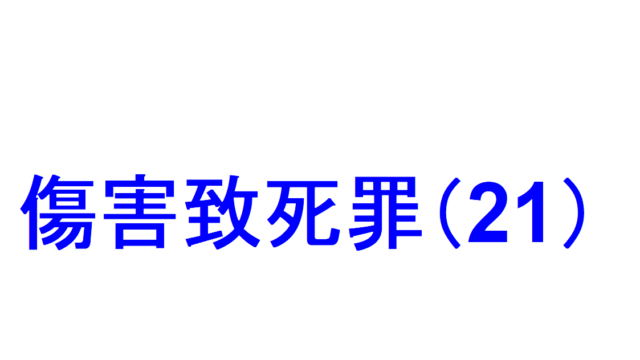傷害致死罪(3) ~「自動車を使った傷害罪・傷害致死罪①」を判例で解説~
自動車を使った傷害罪・傷害致死罪
自動車の運転者が、故意に自車を他の自動車に接触衝突させたり、自車に触れている者を振り離すために疾走するなどし、人に傷害を負わせ、あるいは死亡させるような場合、自動車の運転という方法による他人に対する暴行が成立し、暴行罪、傷害罪、傷害致死罪が成立します。
自動車を使っての傷害罪・傷害致死罪の「暴行・傷害の故意」
自動車を使っての暴行・傷害・傷害致死については、「暴行・傷害の故意」が認定できなければ、暴行罪、傷害罪、傷害致死罪は成立せず、単なる過失による自動車事故として過失運転致死傷罪が成立するに過ぎなくなります。
なので、自動車を使っての暴行・傷害・傷害致死については、いかにして「暴行・傷害の故意」を認定するのかがポイントになります。
自動車を使っての暴行で、「暴行・傷害」の行為を認めて、暴行罪・傷害罪・傷害致死罪を認めた事例として、以下の判例があります。
「暴行・傷害の故意」を認めた判例
この判例は、飲酒して正常に運転できない状態で、多数の歩行者がある道路上を、前照灯が故障した自動車を運転して10名を死傷させた行為について、歩行者に対する傷害の故意を認め、傷害罪と傷害致死罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 被告人には、運転開始に先立ち、被害者らに対し、自己の運転する貨物自動車を突き当てて、同人らを転倒させ、あるいは跳ね飛ばすことにつき、いわゆる未必の犯意があったものと認むべきであるから、被告人は暴行と因果関係あることの明らかな傷害あるいは死の結果につき、傷害罪あるいは傷害致死罪としての刑責を負うものといわなければならない
と判示し、自動車を使って被害者に傷害を負わせる故意があったとして、傷害罪と傷害致死罪の成立を認めました。
札幌高裁判決(昭和59年12月25日)
暴力団間の喧嘩闘争の場から逃走しようとした際、これを阻止しようとした抗争相手の暴力団員に対し、 自己の運転する普通乗用自動車を衝突させた上、轢過するなどして死亡させた事案で、傷害の故意を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 被告人の行動の態様自体から、被害者に対する加害の故意をほぼ推認することができ、その他、被告人が検察官に対し、被害者との衝突前後の状況とその際の心理状態について詳細に自供し、原審第一回公判においても傷害の故意を認めていたことなどを総合すると、被告人は本件喧嘩闘争の場から自動車を運転して逃走するに際し、自車の前方に立ちはだかった被害者の身体に対する加害を避けようとする意思がなく、むしろ被害者に自車を衝突させこれを轢過するもやむを得ないとの意思のもとに運転を続けて自車を衝突させたものであり、被告人に傷害の故意があったことを認めるに十分である
と判示し、傷害の故意を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
高松地裁判決(昭和38年4月9日)
先行車の運転方法に立腹し、先行車を追越し中、急転把して接触し、相手に傷害を負わせた事案で、自車を故意に相手車に接触させたとして、傷害罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 自車の前方約100mの国道上を同一方向に直進していた同僚F運転の三輪貨物自動車が、Mの自動車との衝突を避けるため、急停車を余儀なくされたことに立腹し、時速約60kmで進行を続け、Mの車の右側にわずかに約40cmの間隔を置いただけで追越を開始した後、Mの車を未だ完全には追越し終らないうちに、Mの車の右側前方部に自車の左側後方部を接触させて、Mに対し暴行を加えるかもしれないことを認識しながら、敢えて自車のハンドルを左に切り自車を左側寄りに進行させ、道路左端から約1mのところを時速約40kmで進行していたMの車の運転席と至近か所である右側ドアとフェンダー部に自車の左側後部を接触させて、Mに暴行を加え、Mをして右自動車運転の自由を失わしめて、同所付近路上に自動車もろとも横転させ、よってMに対し、右顔面打撲擦過傷、右肘部打撲症等約1週間の通院加療を要する傷害を負わせた
と判示しました。
東京高裁判決(昭和37年11月6日)
対向車を脅す目的で、自車を対向車の進路直前に進出させ、瞬間的に転把して対向車の右側すれすれに通行しようとして、目測を誤り、対向車と衝突した行為に対し、傷害罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 被告人の行為は、たとえ衝突接触の寸前に自車を巧みに転把して、その危険を回避する措置をとる意図であったにしても、自ら目測あるいは操作を誤るか、相手方乗用車の運転者が驚愕 狼狽して適切な操作をなし得ないかして、衝突、接触の事故を惹起し、これに乗車中の者に傷害を被らしめる可能性が極めて大きいのである
- かかる行為がかかる危険性を有することは、自動車運転者の当然の常識に属するところであり、またかかる行為自体を認識しながらこれを敢えてするからには、かかる危険な結果を生ずるかも知れないとの認識、すなわち未必の故意をも当然これを有していたものと認めざるを得ないのである
- 現に、被告人も、検察官に対し、「自分は必ずぶつけてやろうという気持ではなかったが、急にハンドルを切って行けば、普通なら相手の車がびっくりして、ハンドルを左に切ってぶつかるのを避けようとするはずだが、場合によっては驚いてそのままハンドルを切る余裕もなく、もしかしたら自分の車が相手の車にぶつかるかもしれないという気持か自分にあった」旨及び「自分の車がぶつかっても、自分のはダンプであるし、相手の車は小型であるから自分の方は大したことはないと思った」旨述べて未必の故意を肯定しているのである
- 被告人の前記運転措置は、正常の業務上の運転行為とは異り、暴行あるいは脅迫の手段としての行為であり、従って右運転措置により惹起した本件傷害は、これを被告人の自動車運転者としての業務上の過失行為として論じ得べき筋合のものではないのである
- されば、原判決が、被告人の犯した本件傷害につき未必の故意を認め、これを傷害罪として処断したことは正当である
と判示しました。
東京高裁判決(昭和38年7月4日)
無謀・乱暴な運転が、相手車両の運転者等に対する暴行にあたり、暴行の故意があると認定した事例です。
この判例は、ダンプの運転者が、対向車の運転態度に立腹し、その進路前面に進出した事実を認め、ダンプの性能、構造をも考慮し、これが高速度で疾走中の同車と一体の立場にある相手方自動車の運転手と同乗者の身体に対する有形力の行使にほかならないものと認め、無謀・乱暴な運転に対する暴行を故意を認定しました。
裁判官は、
- 被告人は癪にさわり、自車のハンドルを急激に右に切り、約45度の角度で右側道路の中央辺まで、対向車の進路前面に進出したことが認められる
- 原判決は、この事実と被告人運転の巨大な機動力を有する大型貨物自動車の性能、構造とあいまって、かかる被告人の所為は、対向車に対する物理的な力の行使たると同時に、高速度で疾走中であって、車内から一歩も外部に出ることのできない状況の下に自動車と一体となって進行する立場にある相手方自動車の運転手及び塔乗車の身体に対する有形力の行使にほかならないものと認めたものであって、単に被告人運転の車が被害者運転の乗用車に比しより重量が大で、構造堅固であることを根拠として被告人に暴行の故意があったものと認定しているわけではないのである
- なお、対向車に運転手のほか同乗者がいるかどうかは、被告人が対向車とわずか70mの近距離に接近したとき急激にハンドルを右に切り、被害者の運転する対向車の進路前面に進出して行ったのであるから、反証なき限り、対向車に運転手のほか同乗者のあることは被告人において認識していたものと認めるのほかはなく、これを要するに被告人には、対向車に対する有形力の行使、更に進んで人に対する有形力の行使の認識が全然なかったものとなすことはできない
と判示しました。
東京高裁判決(昭和50年4月15日)
並進走行中の自動車に対し、嫌がらせのため故意に自車を著しく接近させる行為が暴行に当るとされた事例です。
嫌がらせ目的でした自動車の幅寄せ行為について、運転していたのが大型自動車であること、現場の交通量や道路状況を考慮し、相手車両の車内にいる者に対する不法な有形力の行使であって、これを意欲・認容していた被告人には暴行の故意があったと認めました。
事案は、被告人が大型車を運転して都内の高速道路を進行中、先行車の動きが緩慢すぎると感じて神経をいらだたせ、同車を追い越す際いわゆる幅寄せをして嫌がらせをしたところ、運転を誤って先行車と衝突し、その結果、先行車が、中央分離体を越え、対向車線上にまで暴走したうえ、対向車と正面衝突し、死者1名、重軽傷者4名を出すという惨事に至った傷害罪、傷害致死罪の事案です。
裁判官は、
- 本件のように、大型自動車を運転して、傾斜やカーブも少なくなく、多数の車両が二車線上を同一方向に毎時50、60キロメートルの速さで、相い続いて走行している高速道路上で、しかも進路変更禁止区間内において、いわゆる幅寄せという目的をもって、他の車両を追い越しながら、故意に自車をその車両に著しく接近させれば、その結果として、自己の運転方法の確実さを失うことによるとか、相手車両の運転者をしてその運転方法に支障をもたらすことなどにより、それが相手方に対する交通上の危険につながることは明白で、右のような状況下における幅寄せの所為は、刑法上、相手車両の車内にいる者に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると解するのが相当である
- すなわち、被告人としては、相手車両との接触・衝突までを意欲・認容していなかったとしても、前記状況下において意識して幅寄せをなし、相手に対しいやがらせをするということについての意欲・認容があったと認定できることが前記のとおりである以上、被告人には暴行の故意があったといわざるを得ないのである
と判示し、被告人には暴行の故意があったとして、傷害罪と傷害致死罪の成立を認めました。
「暴行・傷害の故意」を否定した判例
この判例は、「単にどこかで事故を起こす危険のあることを自覚しながら運転を継続した」というだけでは、まだ、傷害罪の成立に必要な暴行の故意があるということはできないとし、一審判決において、暴行の行為があるとして傷害罪を認定したのは誤りであるとして、一審の裁判所に裁判のやり直しを命じました。
裁判官は、
- 被告人が、夜ひどく酩酊して普通乗用自動車を連転中、Aの普通乗用自動車に接触する事故を起こし、このとき、Aからも、酔っていて危険だから運転をやめるように注意をされたし、自分自身でも、このまま運転を続ければ、どこかで事故を起して、他人に傷害を負わせる危険のあることを認識しながら、あえて、時速約40キロートルで運転を続けた結果、それから約20分後には、市内の路上で、進路の前方右側に停車中の普通乗用自動車に正面衝突し、同車の運転者らに傷害を負わせるに至ったというにある
- この事実によれば、原判決は、被告人には、各被害者に対する暴行のいわゆる未必的故意があるとした趣旨と解されるが、刑法にいわゆる故意とは具体的な犯罪事実の認識(予見)をいうのであるから、被告人が、単に、どこかで事故を起す危険のあることを自覚しながら運転を継続したというだけでは、衡突の相手方を認識したわけでもなく、具体的事実を対象としない抽象的な事故発生の危険意識に過ぎないのであるから、また、傷害罪の成立に必要な暴行の故意があるということはできない
- その後、現実に被害者が乗車している自動車を発見した際に、これと衡突の危険のあることを認識しながら、あえて、これを容認して進行したという場合であってこそ、初めて、暴行の未必的故意があるといい得るのである
- ところが、原判示の事実は、いずれの点を採り上げて、被告人に暴行の未必的故意があるとしたかは文義上必ずしも明確ではないのであるから、同事実だけでは、被告人の所為が傷害罪を構成するか否かも不明なことになり、この点で、原判決には理由不備の誤りがあるといわなければならない
- 被告人は、路上で、進路前方右側に停車中の普通乗用自動車(運転者B)を約30メートル手前で発見したときには、酩酊のため、同車が停車中であることにも、また、自車が道路の右側を進行していることにも、全く気がつかず、相手の車が交通規則に違反して、道路の右側を対面進行して来るものと錯覚したが、すくに、ブレーキをかけるなどして(衝突地点まで全長約28.10メートルのブレーキ痕がある)、衝突を回避すべく努力したことが認められるから、故意に衝突したものとは必ずしも認め難いのである
- 被告人は、原審第一回公判においては、傷害の公訴事実はそのとおり相違ない旨陳述しており、原判決もこの供述を証拠に引用したが、同公訴事実は、原判示第一の事実と全く同様で、故意の存否の点で重大な疑問があるのであるから、この事実を自白したからといって、被告人の暴行の故意を認定するに足る証拠とはならないのである
- その他、記録を精査しても、被告人が過失によって本件の事故を起して、各被害者に傷害を負わせたと疑うべき資料ならばともかく、(業務上過失傷害罪で処罰するためには訴因の変更が必要)、故意に傷害したと認めるに足る証拠は存しないことになるから、原判決が、その挙示する証拠によって、原判示第一の事実を認定したことは、審理不尽のそしりを免れないとともに、判決の理由にくいちがいのある場合に該当し、この点でも、また、破棄を免れない
と判示しました。
この判例は、「単なる無謀運転」と「暴行・傷害の故意に基づく運転」とに質的な差異があることを意識した判例とされています。
大阪高裁判決(昭和47年3月6日)
驚愕させる目的で、被告人運転の車両を、その右側直近を併進する車両の前面に進出させ、同車両に接触転倒させてその運転者らに傷害を与えた事案について、暴行の故意が否定され、傷害罪は成立せず、業務上過失傷害罪(認識ある過失)が成立するとされた事例です。
驚かす目的で相手車両の前面に進出して接触した行為について、一応の危険は認めながらも、その危険は恐らく避けられるであろうとの認識の下に行動したものと解するのが相当であるとして、暴行の故意を否定しました。
裁判官は、
- ハンドルを右に切って被害車両の進路前方に進出するが如き行為は、自己又は被害車両の運転者の操縦の過誤を誘発し、両車両の接触事故あるいは被害車両の転倒事故を惹起し、被害車両の乗員に傷害を与える可能性が高い(被害車は自動二輪車であるから、接触した場合転倒する危険は大である。)ものであることは原判決説示のとおりである
- 被告人も、当時両車両の位置関係から、接触の可能性の認識があったものと認めるべきであって、当時被告人の認識する両車両の位置関係が右認定の状況と多少相違するところがあっても、右接触の可能性ありとの認識があったことを否定することはできない
- そして、かような認識を有しながら、本件行為に出た以上、被告人は、被害車両と接触しても止むなしとして結果の発生を認容していたのではないかとの疑もないわけではない
- しかし、この点について、被告人は、司法警察職員に対する供述調書2通において「今度こそ追い抜いていやがらせをしてやろうと思ってハンドルを右に切った」旨供述し、検察官に対する供述調書において「単車を転倒させる気はなかった。しかししやくにさわっていたので驚かしてやろうと思ってハンドルを右に切った」旨供述し、原審においてもその旨供述している
- そして、被告人が本件行為に出た動機は、一面識のない被害者らと競走してこれに勝てなかったという些細なものであり、被害者らに対し、恨みや殊更な悪感情を抱いていたわけではないこと、これに反し、万一接触した場合に発生する結果は重大であり、被告人自身も甚大な不利益を被る結果になることはみやすい道理であり、動機の単純なことに比し、結果があまりにも重大であり、かように単純な動機でかような重大な結果の発生を認容して行為に出たと考えることには疑問が存する
- また、本件において、被告人車と被害車両とは同一方向に相当高速度で進行していたものであり、その間、被告人はわずかにバックミラーを通じて後方を見ただけであり、相互の進路、速度、位置関係等につき慎重に検討した上、行動したとは認められない
- これらの諸点から考えると、被告人は、本件行為当時、自車と被害車両との位置関係が前記の通りであることを確認した上、自車を被害車両に接触せしめても止むを得ないとして本件行為に出たものとは解し難く、むしろ自車と被害車との位置関係の判定を誤まり、被害車の進路の前面に進出しても、被害者を驚かすだけで、被害車との接触あるいは被害車の転倒は避け得られるものと軽信して本件行為に出たもの、すなわち、被害車との接触あるいは転倒を未必的に認容して行動したと解するよりも、一応の危険は認めながらも、その危険は恐らく避けられるであろうとの認識の下に行動したものと解するのが相当である
- 原判決は、被告人が、警察官に対し「相手に当ててやろうとは思っていなかったが、急に相手車の前に割り込んでびっくりさせてやろうと思った、相手方はびっくりして急ブレーキをかけたりハンドルを切ったりして、時に慌ててひっくり返ることもあると思う」旨述べていること、検察官に対し「単車を転倒させてやる気はなかったが、しゃくにさわっていたので、ことによったら単車が転ぶかも知らんと思ったが、腹立ち紛れに右にハンドルを切った」と供述していることを暴行の未必的故意を認めた一資料となしているが、右司法警察職員に対する供述調書は、接触転倒の結果の発生を認容する旨の供述記載は全くなく、検察官に対する供述調書は、微妙で原判示説示のような供述記載もみられるけれども、しさいに検討すると、結局、本件発生後、冷静になって反省すると、接触転倒のおそれも十分考えられるという趣旨の供述記載と解せられるのであって、右各供述をもって前記認定を左右するには足りない
- そうすると、被告人は、本件行為当時、被害車両との接触、あるいは被害車両の転倒の未必的故意があったものということはできず、いわゆる認識ある過失と解すべきであるから、暴行の未必的故意があると認定した原判決は事実を誤認したもので、この誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、破棄を免れない
と判示しました。
名古屋高裁判決(昭和47年3月7日)
道路、センターラインをはみ出していることを知りながら走行した大型貨物自動車の運転者が、対向車と衝突し、その運転者に傷害を負わせた事案につき、傷害罪を認定した原判決が破棄され、業務上過失傷害罪と認定された事例です。
裁判官は、
- 被告人の当時の認識状態は、(一)被告人は、原判示国道上において、先行する軽四輪さらにそれに先行する大型車を追い越すべく、センターラインより右側に車体半分位をはみ出したまま進行し、対向してくるNの車が、センターライン寄りを進行してくるので、両車がそのままの状態で進行すれば衝突することは必定であると認識していたこと。(二)被告人はN車との衝突を回避する余地があったのにかかわらず、これらの回避措置をとらないでそのまま進行したこと。(三)被告人としては、N車側において、被告人車との衝突をさけるために左方に避譲することができる余地があると考えていたので、むしろN車側の方で避譲してくれるであろうから、衝突事故はおそらく発生することがないであろうと認識していたものであったと認めるのが相当である
- 本件において、右(一)(二)の事実のみが認められるときは、傷害の故意を認め得る余地があると考えられるけれども、加えて(二)の事実が認められる以上は、被告人において、自己本位的ではあったけれども、最終的には衝突による結果の発生を認容しなかった認識状態にあったものであることが明らかであるから、このような場合においては、いわゆる「認識ある過失」の問題として捉えるべきものであると考えられる
- 本件における被告人の運転態度が、極めて自己本位的で危険であり、交通倫理のうえからいって強く非難さるべきものであることはもちろんであるけれども、本件においては、以上の理由により、被告人に衝突による傷害の故意があったものと認定することはできず、業務上過失傷害罪の成否を判断すべき事案であると思料される
と判示しました。
次回記事に続く
次回の記事では、自動車による傷害について、
- 「暴行・傷害の未必の故意」と「認識ある過失」の認定の判断
- 警察官からの逃走を図り、警察官を死傷させる場合は、暴行の故意が明確である
について説明します。