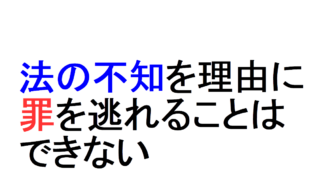前回の記事では、「事実の錯誤」について説明しました。
前回の記事の要点は、
- 「事実の錯誤」とは、犯人が認識していた犯罪事実と、実際に発生した犯罪事実が食い違う場合をいう
- 「事実の錯誤」は、「具体的事実の錯誤」と「抽象的事実の錯誤」に分類できる
- 「具体的事実の錯誤」を起こしても、故意(犯罪を犯そうとする意志)が認められ、犯罪は成立する
というものでした。
今回は、「抽象的事実の錯誤」について詳しく説明します。
「抽象的事実の錯誤」の場合でも、「具体的事実の錯誤」と同じく、故意(犯罪を犯そうとする意志)が認められ、犯罪は成立するのでしょうか?
「具体的事実の錯誤」と「抽象的事実の錯誤」の違い
まず、「具体的事実の錯誤」と「抽象的事実の錯誤」の違いを説明します。
具体的事実の錯誤とは?
具体的事実の錯誤とは、
Aを殺すつもりだったのに、Bを殺してしまった…というように、同一構成要件内の錯誤
をいいます。
この場合、殺す相手は間違ってしまったものの、殺人罪を犯すつもりで殺人罪を犯したことに間違いはないので、殺人罪という「同一構成要件内」における錯誤になります。
抽象的事実の錯誤とは?
抽象的事実の錯誤とは、
物を壊すつもりだったが、対象が物ではなく、人であり、人を殺してしまった…というように、異なる構成要件間の錯誤
をいいます。
たとえば、器物損壊罪(物を壊す)を犯すつもりで、殺人罪(人を殺す)を犯してしまった場合、器物損壊罪と殺人罪は、構成要件が異なるので、抽象的事実の錯誤になります。
「具体的事実の錯誤」と「抽象的事実の錯誤」の違い
両者の違いをまとめると、
- 具体的事実の錯誤は、同一構成要件内の錯誤である
(ex 内容に食い違いはあれど、殺人罪を犯すつもりで、殺人罪を犯した)
- 抽象的事実の錯誤は、異なる構成要件間の錯誤である
(ex 器物損壊罪を犯すつもりで、殺人罪を犯してしまった)
となります。
【本題】「抽象的事実の錯誤」をした場合、故意が認められるか?
「具体的事実の錯誤」については、故意(犯罪を犯そうとする意志)が認められ、犯罪が成立します。。
では、「抽象的事実の錯誤」をした場合、故意(犯罪を犯そうとする意志)は認められ、犯罪は成立するでしょうか?
結論をいうと、
条件付きで故意が認められ、犯罪が成立する
となります。
その条件とは、法定的符合説という考え方から説明され、結論が導かれます。
まず、法定的符合説を説明する前に、比較対象として、抽象的符合説を説明します。
抽象的符合説とは?
抽象的符合説とは、
犯罪行為者の認識した事実と、現実に発生した事実とが一致する範囲で、軽い故意犯の成立を認めうる
とする説です。
例として、
マネキンを壊そうとを思ってハンマーを振りおろしたが(器物損壊罪:3年以下の懲役刑)、実はそれがマネキンではなく本物の人間で、人を殺してしまった場合(殺人罪:死刑)
に当てはめて考えます。
対象を傷つけるという認識と、対象を傷つけるという現実に発生した事実は一致するので、軽い方の犯罪が成立することなります。
よって、軽い方の罪の器物損壊罪が成立することになります。
しかし、これでは、勘違いとはいえ、人を殺しておいて、器物損壊罪が成立するという筋の通らない結果となります。
そのため、抽象的符合説は、主流の考え方になっていません。
主流の考え方になっているのは、これから説明する法定的符合説です。
法定的符合説とは?
法定的符合説とは、
錯誤が異なる構成要件にまたがる「抽象的事実の錯誤」において、原則として、故意は阻却される
しかし、例外的に、認識していた構成要件と、実現された構成要件との間に実質に重なり合う面があるときは、その重なり合う限度で軽い罪の故意を認める
というものです。
そもそも、重い罪ではなく、軽い罪の故意を認めるのは、刑法38条2項に「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と規定されているためです。
法定符合説は、「構成要件どうしの重なり合い」を深掘りして考えていきます。
法定符合説は、以下の2パターンの考え方があります。
① 錯誤が異質で重なり合わない2個の構成要件間にまたがっているときは、発生した事実について故意は認められず、発生した事実どおりに犯罪は成立しない。しかし、過失罪や未遂罪が成立する。
たとえば、
マネキンだと思ってハンマーで殴ったところ(器物損壊罪)、実はマネキンではなく人であり、人を殺してしまった(殺人罪)…
という「客体の錯誤」の場合は、「人を殺すな」という規範に直面していないから、故意犯である殺人罪は成立せず、過失犯である過失致死罪(間違って人を殺した)が成立することになります。
なお、器物損壊罪は未遂となりますが、器物損壊に未遂の規定はなく、器物損壊未遂という犯罪は存在しないので、器物損壊罪については成立しないことになります。
次のたとえとして、
Aを殺すつもりで拳銃を発砲したところ、弾が外れて、Aの隣にいたペットの犬に当たってしまい、過失によりペットの犬を殺した(器物損壊罪)…
という「方法の錯誤」の場合は、過失器物損壊罪と殺人未遂罪となりますが、器物損壊罪に過失の規定はなく、過失器物損壊罪は存在しないので、殺人未遂罪のみが成立することになります。
② 錯誤が同質的で重なり合う2個の構成要件にまたがっている場合、構成要件が重なり合う限度で、軽い罪の故意犯が成立する
これは、
錯誤があったとはいえ、構成要件が重なり合う範囲においては、「~してはならない」という規範に直面したにもかかわらず、規範を破って犯罪行為に及んだのであるから、非難できる
少なくとも、軽い方の罪では処罰すべき
という考え方をするからである。
たとえ話を使って、具体的に説明します。
人が住んでいる家を、人が住んでいない空き家だと思って放火したが(非現住建造物放火罪:2年以上の懲役刑)、実は人が住んでいる家だった場合(現住建造物放火罪:5年以上の懲役)、人が住んでいない家に放火する罪である非現住建造物放火罪が成立します。
現実には、人が住んでいる家を放火ているのですが、
- 人が住んでいない家に放火する故意(犯罪を犯そうとする意志)で犯行に及んでいる
- 構成要件が同質的で重なり合っている
- 重い罪と軽い罪とはでは、軽い罪の方が成立する
ことから、軽い罪の非現住建造物放火罪の方が成立するという考え方になります。
反対に、人が住んでいる家だと思って放火したが(現住建造物放火)、実は人が住んでいない空き家だった場合は(非現住建造物放火)、人が住んでいる家に放火する現住建造物放火罪の故意で犯行に及んでいますが、軽い方の罪が成立するので、軽い方の罪の非現住放火罪が成立します。
判例
最後に、抽象的事実の錯誤の事案について、法定的符合説を使って判決をしている判例を紹介します。
事件の内容
共謀して、被告人7名が警察官に暴行・傷害を加え、そのうち1人の被告人Aが小刀で警察官の腹部を刺し、警察官を失血死させた事件
争点
警察官を殺した被告人Aに殺人罪が成立することに争いはありません。
警察官に暴行・傷害を加えただけの被告人6名に、「殺人罪の共犯」と「傷害致死罪の共犯」のどちらが成立するかが争点になります。
判決の内容
裁判官は、
『殺人罪と傷害致死罪とは、殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで、そのほかの犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから、殺意のなかった被告人6名については、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で、軽い傷害致死罪の共同正犯が成立する』
と判示しました。
解説
被告人6名については、警察官を殺すつもりはなく、共謀の上、警察官に暴行・傷害を加えようとしただけです。
しかし、被告人Aが、勝手に暴走して警察官を殺してしまったため、暴行・傷害で終わらせるつもりが、殺人という結果を生じさせてしまいました。
傷害のつもりで殺人の結果が生じているので、「抽象的事実の錯誤」が起こったわけです。
人を死に至らしめたので、成立する犯罪として、「殺人罪の共犯」と「傷害致死罪の共犯」の2択が浮上します。
ここで、「抽象的事実の錯誤」の考え方が用いられ、『認識していた構成要件と、実現された構成要件との間に実質に重なり合う面があるときは、その重なり合う限度で軽い罪の故意を認める』というルールが採用され、判断がくだされます。
殺人罪はもっとも重くて死刑、傷害致死罪はもっとも重くて3年以上の懲役刑なので、傷害致死罪の方が軽い罪になります
したがって、軽い方の罪である傷害致死罪(の共犯)が成立するという結論が導かれます。





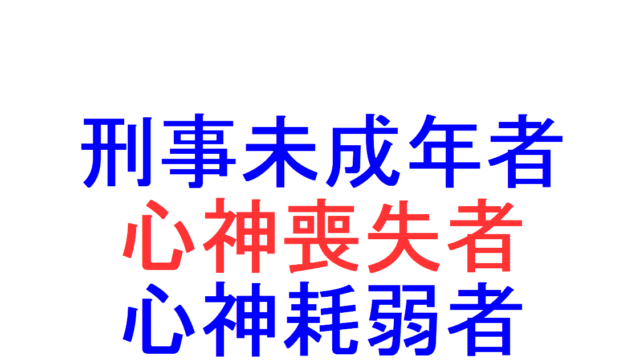
しても犯罪は成立する-320x180.png)