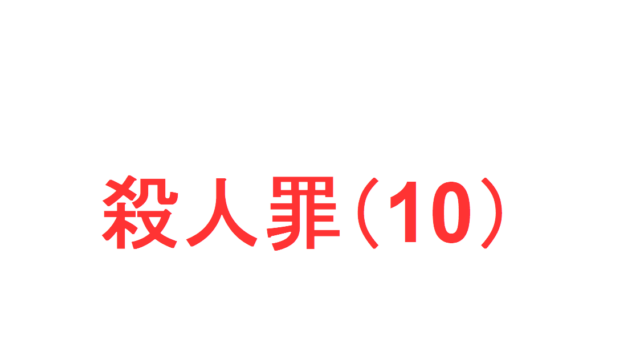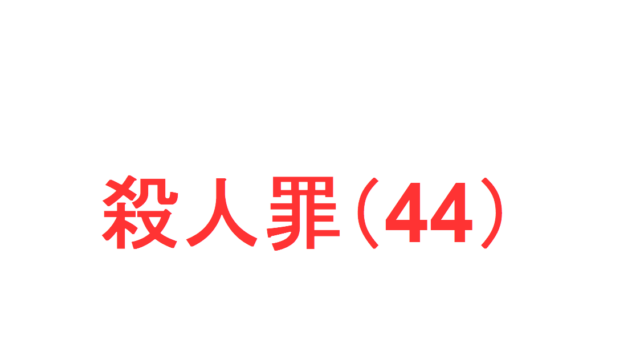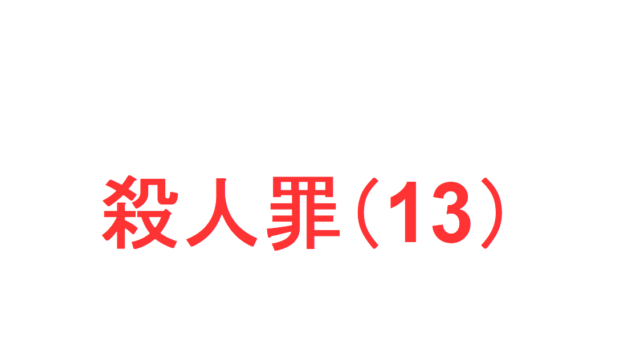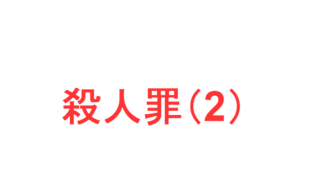交通事故のひき逃げに伴う殺人罪の成否
交通事故のひき逃げをして、被害者をその場に放置したことで、被害者が死亡した場合に、過失運転致傷罪と道路交通法違反(道交法72条:事故の不申告、被害者の不救護)のほかに、殺人罪(又は殺人未遂罪)が成立するか否かについては、見解が分かれています。
最高裁においては、殺人罪(又は殺人未遂罪)ではなく、保護責任者遺棄罪(刑法218条)が成立するとした判例があります。
地方裁判所においては、殺人罪が成立するとした裁判例があります。
最高裁判例
最高裁は、
- 自動車の運転中、過失により通行人に自車を接触させて約3か月の入院加療を要する左下腿骨開放性骨折等の歩行不能の重傷を負わせながら、救護措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、折から降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んできてやる旨申し欺いて被害者を車から降ろし、同所に放置したまま自動車を運転して立ち去ったときは、刑法218条の「病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し」た場合にあたる
とし、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)、道路交通法違反のほかに、保護責任者遺棄罪が成立するとしました。
なお、この事案において、自動車運転手に殺意が認められた場合は、殺人未遂罪が成立する余地はあると考えられます。
地方裁判所の裁判例
下級審では、交通事故のひき逃げ事案で、殺人罪の成立を認めた事例があります。
横浜地裁判決(昭和37年5月30日)
貨物自動車の運転手である被告人Aと上乗りの被告人Bが、上乗りで運転免許のないCに無免許運転を教唆し、Cの運転で進行中、前方不注視の過失により自転車で対向してきた被害者に衝突して加療約3か月を要する頭蓋骨骨折、右正中神経麻痺等の傷害を負わせたが、被害者を救護すべく貨物自動車の助手席に乗せて6、7km通行したところで、無免許運転や事故の犯行の発覚を免れるため、被害者を路上に置去りにすることをABC3名で共謀し、さらに9キロメートル走行し、人家から離れた畑の中の県道上に被害者を放置して逃走したが、たまたま被害者が意識を回復して最寄りの人家に救護を求めたため助かったという事案です。
裁判官は、未必の故意による殺人未遂罪が成立するとしました。
東京地裁判決(昭和40年9月30日)
東京都港区内において、自動車を高速度で運転したため歩行者に激突させ頭蓋骨骨折等の傷害を負わせるという事故を起こした被告人が、いったんは被害者を病院へ運ぼうとし、意識不明に陥っている被害者を自車の助手席に乗せて事故現場を出発したが、自己が業務上過失傷害(現行法:過失運転致傷罪)の犯人であることが発覚し、刑事責任を問われるのをおそれるあまり、出発後まもなく病院に運ぶ意図を放棄し、千葉県の山林まで約29キロメートルの間、なんらの救護措置も採らずに走行したため、走行中の車中において被害者を死亡させたという事案です。
裁判官は、直ちに最寄りの病院に運べば、結果の防止は十分に可能であったとし、未必的殺意を認定して、殺人罪の成立を認めました。
浦和地裁判決(昭和45年10月22日)(控訴審:東京高裁判決 昭和46年3月4日)
午後11時すぎ頃、交差点で前方注視を怠った過失により横断中の歩行者をはねて約6か月の入院加療を要した左大腿骨複雑骨折等の傷害を負わせ、被害者を病院に運ぶため、自車の助手席に乗せて走行中、事故の発覚を免れるため被害者を人通りのない場所に運んで置去りにしようと決意し、事故現場から約2.9キロメートル離れた人車の交通がない場所の道路脇のくぼみに、失神している被害者を放置したが、被害者を探しに来た家人が被害者を発見したため死を免れた事案です。
裁判官は、未必の故意による殺人未遂罪の成立を認めました。
殺人罪の成立を否定した事例
上記裁判例とは反対に、殺人罪の成立を否定した以下の事例があります。
岐阜地裁大垣支部判決(昭和42年10月3日)
午後7時40分頃、橋の上で普通乗用自動車を被害者の乗っていた自転車に追突させ、その結果、被害者を自転車もろとも約2.3メートル下の水深50センチメートルの川に転落させ、被害者に加療約5か月を要した右臀部腰部挫傷等の傷害を負わせながら、無免許運転が発覚するのを恐れ、なんらの救護措置も採らずそのまま逃走したが、被害者は他人によって救助されたという事案です。
裁判官は、作為義務はあったが殺意を認めるに足りる証拠がないとして、殺人未遂罪は成立しないとしました。
盛岡地裁判決(昭和44年4月16日)
自動車を運転中、過失により歩行者をはねて頭部損傷等の瀕死の重傷を負わせたが、犯行の発覚を免れるため救護を断念して逃走を図り、被害者を自車に乗せて約89kmの間、なんらの救護措置も採らず走行し、その間に被害者を傷害により死亡させた事案です。
裁判官は、被害者を事故後、直ちに最寄りの病院に運んで救護措置を受けたとしても死の結果を回避することができたとは認め難く、かつ、被告人が救護可能性を認識しながらあえて本件行為に出たとも認められないとして、不作為による殺人罪の成立を否定しました。
①殺人罪、②殺人予備罪、③自殺教唆罪・自殺幇助罪・嘱託殺人罪・承諾殺人罪の記事まとめ一覧