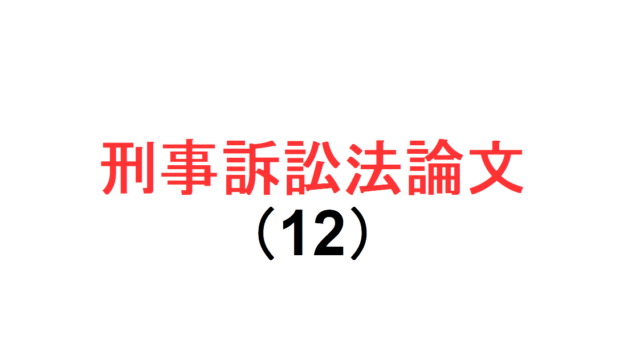刑訴法論文(16)~令和2年司法予備試験の刑事訴訟法論文問題から学ぶ~
令和2年司法予備試験の刑事訴訟法論文問題から学ぶ
令和2年司法予備試験の刑事訴訟法論文問題の答案を作成してみました。
この論文からは、「常習罪と一事不再理の原則の関係」が学べます。
問題
法務省ホームページの「令和2年司法予備試験問題」参照(問題文PDFリンク先)。
答案
第1 設問前段
1 弁護人の主張の趣旨は、①事件の確定判決の一事不再理効が②事件に及ぶため、②事件は刑事訴訟法(以下、法令名省略)337条1号により免訴になるべきであるというものである。
2 裁判が確定すると、同一の事件については、再び公訴を提起することも、審理を行うことも許されなくなる。
これを一事不再理の原則という。
一事不再理の原則の根拠は憲法39条後段にあり、被告人が同一の犯罪について再度の訴追を受けるという二重の危険を防止することを趣旨とする。
3 一事不再理効は、公訴事実の同一性が認められる範囲において生じる。
刑事裁判において、審判対象は訴因である。
訴因は公訴事実の同一性がある限りにおいて、これを変更することができる(312条1項)。
そのため、公訴事実の同一性がある限りにおいて、被告人は裁かれる危険があったといえるから、一事不再理効は公訴事実の同一性が認められる範囲において生じるものである。
4 「公訴事実の同一性」(312条1項)とは、公訴事実の単一性又は狭義の同一性があることをいう。
公訴事実の単一性は、実体法上一罪であるか否かによって判断する。
弁護人は、②事件は既に有罪判決が確定した①事件とともに常習傷害罪の包括一罪を構成すると主張しているから、広義の公訴事実の同一性のうち、公訴事実の単一性が問題となる。
訴因制度を採用する現行法において、審判対象は訴因であり、検察官は一罪の一部を起訴することもできると考えられる以上、一事不再理効の範囲の判断における公訴事実の単一性の判断についても、前訴と後訴の訴因のみを対照して行うべきである(最高裁判決 平成15年10月7日)。
①・②事件の訴因はいずれも単純傷害罪であり、併合罪(刑法45条前段)の関係に立つと考えられ、両罪が常習傷害罪の包括一罪を構成するとうかがわせる要素はないから、両罪の公訴事実の単一性を認めることはできない。
以上から、①事件の確定判決の一事不再理効は、②事件に及ばない。
4 なお、検察官が恣意的に事件を分割した場合には公訴権濫用の問題が生じうるが、②事件は①事件の判決確定後に判明したから、検察官が恣意的に事件を分割して起訴したとは認められない。
5 よって、裁判所は、免訴の判決を言い渡すべきでなく、②事件の審理を行うべきである。
第2 設問後段
1 ①事件の訴因が常習傷害罪の事実であることから、②事件の訴因がその常習傷害罪の一部といえるかを判断する。
常習傷害罪は、常習として行った傷害罪が全て包括一罪になるという性質を有する。
そうすると、和元年6月1日に行われた①事件が、その前の令和元年5月15日に行われた②事件の常習性の発露として行われたものである場合は、①事件と②事件は包括一罪であるという判断が可能である。
常習性の発露が認められる場合は、②事件は、既に起訴されて確定判決を経ている①事件の一部ということになりうる。
2 よって、裁判所は、まず②事件が①事件の常習傷害罪としての包括一罪の関係にあるかを判断すべきである。
そして、包括一罪になるのであれば免訴の判決を言い渡し、包括一罪にならないのであれば②事件の審理を行うべきである。