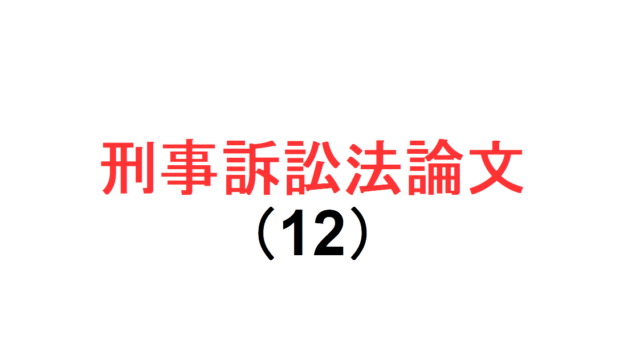刑訴法論文(19)~令和5年司法予備試験の刑事訴訟法論文問題から学ぶ~
令和5年司法予備試験の刑事訴訟法論文問題から学ぶ
令和5年司法予備試験の刑事訴訟法論文問題の答案を作成してみました。
この論文からは以下のテーマが学べます。
1⃣ 逮捕前置主義(逮捕事実に逮捕されていない犯罪事実を加えて勾留することの適法性)
2⃣ 同一被疑事実についての再逮捕及び再勾留の適法性
問題
法務省ホームページの「令和5年司法予備試験問題」参照(問題文PDFリンク先)。
答案
設問1
1 本件暴行事実は、逮捕の被疑事実である本件住居侵入・強盗致傷の事実に含まれていない。
勾留段階において、逮捕に係る犯罪事実に含まれていない犯罪事実を追加することは、逮捕前置主義(刑事訴訟法(以下、法令名略)203条、204条、205条)に反しないか。
2 逮捕前置主義は、被疑者を勾留するためには、適法な逮捕を前置しなければならない原則をいう。
逮捕前置主義の趣旨は、最大20日間(国を脅かす罪について最大25日)にも及ぶ長期的な身体拘束である「勾留」の前に、短期間(最大72時間)の「逮捕」を先行させることで、司法審査を二重に経て、不必要な身体拘束を避けて被疑者の人権を保障することにある。
具体的には、逮捕状請求の段階で一度司法審査を経た後、同じ事実について勾留請求の段階で再度司法審査を経ることで、二重のチェックにより司法的抑制が徹底される。
3 検察官が勾留請求をするあたり、逮捕事実に逮捕されていない犯罪事実を加えて勾留請求し、裁判官から勾留状を発付を得ることは認められる。
これは、逮捕事実に逮捕されていない犯罪事実を加えることは、逮捕の回数を少なくすることになり、被疑者に有利に働くことから許されるものである。
4 本件住居侵入・強盗致傷及び本件暴行は共に勾留の理由及び必要性を満たす。
本件暴行事実を付加して勾留請求して勾留状の発付を得ることは、甲が本件暴行事実で再逮捕・勾留されることがなくなり、実質的に逮捕勾留期間の短縮となり、甲に有利に働く事情となる。
5 よって、本件住居侵入・強盗致傷の事実に、本件暴行の事実を付加して勾留することは許される。
設問2
1 下線部②は同一の被疑事実での勾留であるが、このような再逮捕及び再勾留は適法か。
2 刑事訴訟法が被疑者の身体拘束期間を厳格に制限している(203条、204条、205条、208条等)ことに鑑みれば、同一被疑事実についての再逮捕及び再勾留は、これらの期間制限の潜脱手段になり、逮捕権が濫用されて被疑者の人権が侵害されることになり得るため、許されないのが原則である。
しかし、被疑者を釈放した後に新証拠が見つかるなど、新たな逮捕の必要性が出てきた場合にまで同一被疑事実による再逮捕及び再勾留が常に許されないとすると、真実発見(1条)の見地から妥当でない。
また、199条3項及び刑事訴訟法規則142条1項8号は、再逮捕を予定した規定となっている。
再勾留については明文規定がないが、逮捕手続と一連一体をなすものであることから、逮捕と同様に再勾留を認めるべきである。
そこで、新たな逮捕・勾留の必要性があり、かつ法の身体拘束期間制限の潜脱とはいえないような場合、具体的には、①釈放後に新証拠が見付かるなどの新たな逮捕・勾留の必要性があり、②被疑事実が重大であるなど、再び身体を拘束される被疑者の不利益を考慮してもなお再逮捕・再勾留をすることが社会通念上相当といえ、③逮捕・勾留の不当な蒸し返しとはいえないような場合には、再逮捕及び再勾留も適法であるというべきである。
3 本件につき、甲が釈放された後、乙が本件住居侵入・強盗致傷について、V方に侵入して金品を強取することを甲と相談し、乙が実行し、甲が換金する旨の役割分担をして犯行に及んだことを供述した。
そして、乙の携帯電話機から、本件住居侵入・強盗致傷について、甲との共謀を裏付けるメッセージにやり取りがあったことが判明した。
上記各事情は、甲釈放前には判明していなかった甲と乙との共謀を立証する有力な新証拠となる。
また、本件住居侵入・強盗致傷は、生命、身体、財産に対して強い侵害要素を持つ重大犯罪であることからすれば、再逮捕及び再勾留を認めて犯罪を解明すべき必要性は高い。
新証拠の存在及び事案の重大性からすれば、同一の被疑事実で再逮捕及び再勾留を行っても、逮捕・勾留の不当な蒸し返しとはいえず、甲の身体の自由を不当に害するとまではいえないので、なお相当性を有する。
4 よって、下線部②の勾留は適法であり、裁判官は甲を勾留することができる。