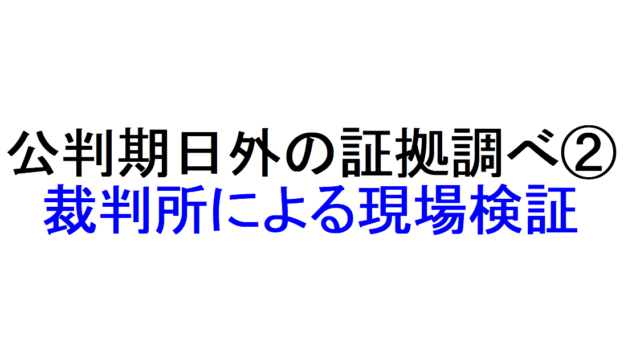公判の流れ⑲~「裁判官の職権による証拠調べ」を説明
前回の記事の続きです。
公判手続は、冒頭手続→証拠調べ手続 →弁論手続→判決宣告の順序で行われます(詳しくは前の記事参照)。
前回の記事では、証拠調べ手続のうち、
- 物証の証拠取調べの方法は「展示」によること
- 証拠物たる書面の証拠調べの方法は「展示」と「朗読又は要旨の告知」によること
などを説明しました。
今回の記事では、証拠調べ手続のうち、
- 裁判官の職権による証拠調べ
を説明します。
裁判官の職権による証拠調べ
通常は、検察官、被告人又は弁護人が、裁判官に対し、それぞれが用意した証拠を証拠調べ請求し、裁判官がその証拠を取り調べます。
しかし、裁判官が必要と認めるときは、裁判官が自ら職権で証拠調べをすることができます(刑訴法298条2項)。
当事者主義(公判手続における主導的役割を当事者である検察官と被告人に果たさせる主義)を基調とする日本の刑事訴訟法は、第一次的には、検察官、被告人又は弁護人からの請求によって証拠調べを行うことにしています(刑訴法298条1項)。
しかし、真実発見の要請から、補充的、二次的なものとして、裁判官が職権により証拠調べをすることが認められているものです(刑訴法298条2項)。
裁判官の職権による証拠調べは、原則、裁判官の裁量に委ねられる
裁判所は、原則として、職権で証拠調べをなすべき義務はなく、職権で証拠調べをするかどうかは、裁判所の裁量に委ねられています。
判例も、刑事訴訟法止、裁判所は、原則として、職権で証拠調べをしたり、検察官に対して立証を促したりする義務はないとしています。
ただし、検察官が不注意により被告事件に対して一定の証拠を提出することを遺脱したことが明白なような場合には、例外的に裁判所は、少なくとも検察官に対してその提出を促す義務があるとされます。
この点を判示した以下の判例があります。
裁判官は、
- わが刑事訴訟法上裁判所は、原則として、職権で証拠調をしなければならない義務又は検察官に対して立証を促がさなければならない義務があるものということはできない
- しかし、被告事件と被告人の共犯者又は必要的共犯の関係に立つ他の共同被告人に対する事件とがしばしば併合又は分離されながら同一裁判所の審理を受けた上、他の事件につき有罪の判決を言い渡され、その有罪判決の証拠となった判示多数の供述調書が他の被告事件の証拠として提出されたが、検察官の不注意によって被告事件に対してはこれを証拠として提出することを遺脱したことが明白なような場合には、裁判所は少くとも検察官に対しその提出を促がす義務あるものと解するを相当とする
と判示しました。
裁判官が職権により証拠調べをしなければならない場合
例外として、以下の①~②の場合には、裁判官は職権により証拠調べを行わなければなりません。
① 公判準備において裁判所が収集した証拠がある場合
公判準備(公判の審理を円滑に行なうために、裁判所が公判の日ではない日に行う公判の準備のための手続)おいて行った
- 証人等の尋問(公判期日外の証人尋問)、検証、押収、捜索の結果を記載した書面(刑訴法規則38条、40条、41条、43条、52条の2)
- 押収した物
につき、公判期日において、裁判官は職権で証拠書類・証拠物として取り調べなければなりません(刑訴法303条)。
これは、公判の日ではない日に、公判準備として行われた証拠調べの結果と証拠収集の結果は、これを公判廷で改めて証拠調べをしなければ、証拠とすることができないことをルール付けたものです。
② 公判手続の更新が行われた場合
裁判の途中で裁判官が交代すると、口頭主義、直接主義の要請にこたえるために、新たな裁判官のもとで手続をやり直す必要があります(刑訴法315条、315条の2)。
この手続のやり直しを「公判手続の更新」といいます。
裁判官の交替により公判手続を更新するため(公判手続をやり直すため)、
- 更新前の公判期日において行われた被告人・証人等の供述を録取した書面
- 裁判所の検証の結果を記載した書面
- 証拠調べをした証拠書類・証拠物
につき、再度、裁判官の職権で証拠書類・証拠物として証拠調べをしなければなりません(刑訴法規則213条の2第3項・4項)。
次回の記事に続く
次回の記事では、証拠調べ手続のうち、
検察官、被告人又は弁護人が証拠調べ請求した証拠の裁判官への提出
を説明します。