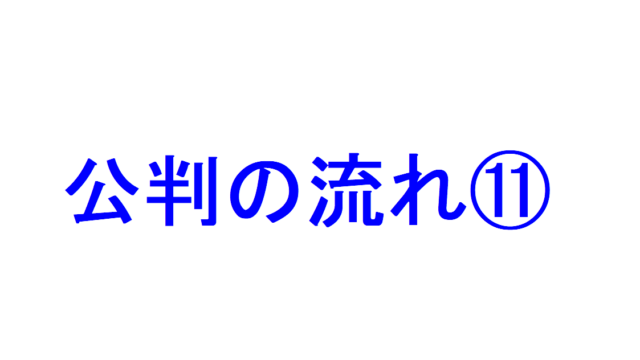公判手続とは?④ ~「直接主義とは?」「継続審理主義とは?」を説明
前回の記事の続きです。
前回の記事では、公判手続における6つの基本ルールである
- 公開主義
- 当事者主義
- 口頭弁論主義
- 直接主義
- 継続審理主義
- 予断排除の原則
のうち、③口頭弁論主義を説明しました。
今回の記事では、④直接主義と⑤継続審理主義を説明します
直接主義とは?
直接主義は、
裁判所が公判廷で直接に取り調べた証拠に基づいて裁判をしなければならないという原則
をいいます。
直接主義は、直接審理主義ともいいます。
直接主義は、裁判所が証拠を直接に取り調べるものなので、裁判官が事件の真相をつかむことに役立ちます。
日本の刑事裁判が直接主義を採っていることが分かる法の規定として、以下のものがあります。
- 被告人の証人に対する反対尋問権が憲法上の権利として保障している(憲法37条2項)
- 公判準備の結果は、その後、公判廷で必ず取り調べなけれはならない(刑事訴訟法303条)
- 証拠書類の取調べは「朗読」、証拠物の取調べは「展示」という方法でしなければならない(刑事訴訟法305条、306条)
- 被告人の反対尋問を経ていない証拠(伝聞証拠※)は、原則として証拠能力がない(刑事訴訟法320条)
※ 伝聞証拠について
伝聞証拠とは、検察官や警察官が、被害者や目撃者などの事件関係者から聞いた話を記載した供述調書や捜査報告書などの書面が該当します。
これらの書面(伝聞証拠)は、被告人に対し、その書面の内容の正確性に対し、意見を述べる機会が与えられていないので、そのような状況のままで裁判官が証拠として採用することは、被告人に不利益となります。
なので、伝聞証拠は、原則として証拠能力がなく、そのままで証拠として採用されないというルールになっています。
しかし、被告人が、裁判の内容を争っておらず、「伝聞証拠を証拠として採用しても良い」という意思表示(同意)をすれば、伝聞証拠は証拠として採用できることになります(刑訴法326条)。
もし被告人が、伝聞証拠が証拠として採用されることに同意しない場合は、検察官や警察官が作成した被害者や目撃者などの供述調書や捜査報告書は、証拠として採用されないことになり、検察官は犯罪事実を証明することができなくなります。
その場合、被害者や目撃者を裁判に呼んで、被害者や目撃者に、裁判官の面前で事件のことを話してもらうことで(証言してもらうことで)、検察官は犯罪事実を証明することになります。
こうなることで、直接主義が実現します。
継続審理主義とは?
継続審理主義は、
公判期日(裁判を行う日)はできるだけ継続(集中)して開かなければならないという原則
をいいます。
継続審理主義は、集中審理主義ともいいます。
継続審理主義の法的根拠は、憲法37条1項にあり、
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する
と規定されています。
継続審理主義は、憲法37条1項にある被告人の迅速な裁判を受ける権利を実現させるものであるといえます。
また、継続審理主義は、裁判所は新鮮にして正確な心証によって裁判すべきであるという、裁判本来の要請からも導き出される原則でもあります。
迅速裁判の要請に反し、違法とされた裁判例
迅速裁判の要請に反し、違法とされた判例として、以下のものがあります。
裁判官が10か月半後を公判期日として定めた公判期日変更決定に対し、最高裁は、事件の審理が判決に熟しており、公判期日の変更は、審理を続行あるいは再開する必要上なされたものでなく、専ら10か月半の時の経過を図る目的でなされたものと認め、
と判示し、公判期日変更決定を取り消しました。
被告人の留学の便宜を考慮し、5年後に被告人が帰国した後に判決宣告をしようとする意図で、判決宣告期日をおって指定するとした裁判長の処分に対し、最高裁は、
- 迅速裁判の要請は、刑事訴訟法1条に明らかなように、刑事訴訟手続の基本的要請の1つである
- このことは独り被告人のみの利益のために定められているものではない
- 刑事訴訟法273条は、「裁判長は、公判期日を定めなければならない。」と規定し、期日の指定については、裁判長の裁量権が認められているけれども、右裁量権の行使は、刑事訴訟手続の基本的要請にしたがってなされなければならないのであって、迅速裁判の要請に著しく反する意図の下に期日を指定しないことは、裁量権を濫用するものとして許されないものと解すべきである
- 本件についてみると、原裁判所の裁判長が被告人Aの判決宣告期日をおって指定する旨宣したのは、被告人Aの留学の便宜を考慮し、5年後に同被告人が帰国した後に判決宣告をしようとする意図によるものであること、記録によって明らかであって、かように訴訟とはなんら関係のない被告人の個人的事情のみを考慮して5年後に判決宣告をしようとするのは、迅速裁判の要請に著しく反するものというべきである
と判示し、裁判長の処分を取り消しました。
15年余りの長きにわたって審理を中断していた裁判所の措置に対し、最高裁は、
- 憲法37条1項は、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が著しく害せられたと課められる異常な事熊が生するに至った場合には、その審理を打ち切るという非常救済手段が採られるべきことを認めており、このような場合は、判決で免訴の言渡しをするのが相当である
としたものである。
上記判例とは逆に、事件の内容が複雑であるという事情から、公訴提起が遅れたのは、憲法37条の迅速裁判の要請に反しないとした以下の事例があります。
公訴提起が著しく遅延したとして弁護人を憲法37条違反を主張した事例です。
最高裁は、
- 憲法37条1項違反をいう点は、本件公訴提起が事件発生から相当の長年月を経過した後になされていることは所論(※弁護人の主張)指摘のとおりであるが、本件が複雑な過程を経て発生した未曾有の公害事犯であって、事案の解明に格別の困難があったこと等の特殊事情に照らすと、いまだ公訴提起の遅延が著しいとまでは認められない
とし、弁護人の主張を斥けました。
迅速な裁判を実現するための法
憲法37条1項の迅速な裁判を実現するための法を紹介します。
この条文は、
- この法律(※刑事訴訟法)は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする
と規定し、刑事訴訟法が刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする法であることを示しています。
刑訴規則303条
この条文は、
- 裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる
- 前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当の処置をとるべきことを請求しなければならない
- 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならい
と規定し、裁判を迅速に進行させるための措置を定めていいます。
この条文は、
- 裁判所は、審理に2日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない
- 訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない
と規定し、連日的開廷の確保と訴訟関係人の公判期日の厳守を定めています。
これらの条文は、即決裁判手続を定めています。
即決裁判は、検察官が即決裁判手続の申立を行い、被告人と弁護人が即決裁判をすることに同意がある場合に行うことができ、1回目の公判が行われた日に判決を言い渡すようにするなど、裁判の迅速化を図る制度です。
これらの条文は、公判前整理手続と期日間整理手続を定めています。
公判前整理手続と期日間整理手続は、裁判において集中的審理を行うことができるようにするために、裁判の日以外の期日で、裁判官、検察官、弁護人らが事件の争点と証拠を整理し、明確な審理計画を立てられるようにした制度です。
公判前整理手続は、1回目の裁判を開く前に、前記審理計画を立てることとした場合の手続名称です。
期日間整理手続は、1回目の裁判を行った後に、前記審理計画を立てることとした場合の手続名称です。
なお、公判前整理手続は、裁判員裁判においては、必要的に行われます(最判員の参加する刑事裁判に関する法律49条)。
これは、裁判員裁判においては、裁判員を長期間拘束することは許されないため、裁判が迅速に進むように審理計画を立てる必要があるためです。
この法は、平成15年に制定された法律であり、より一層の裁判の迅速化を目的としています。
第2条において、
- 裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については2年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続についても、それぞれの手続に応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることを目標として、充実した手続を実施すること並びにこれを支える制度及び体制の整備を図ることにより行われるものとする
と規定し、裁判所などの責務を定めています。
次回の記事に続く
今回の記事では、公判手続における6つの基本ルールである
- 公開主義
- 当事者主義
- 口頭弁論主義
- 直接主義
- 継続審理主義
- 予断排除の原則
のうち、④直接主義と⑤継続審理主義を説明しました。
次回の記事では、⑥予断排除の原則を説明します。