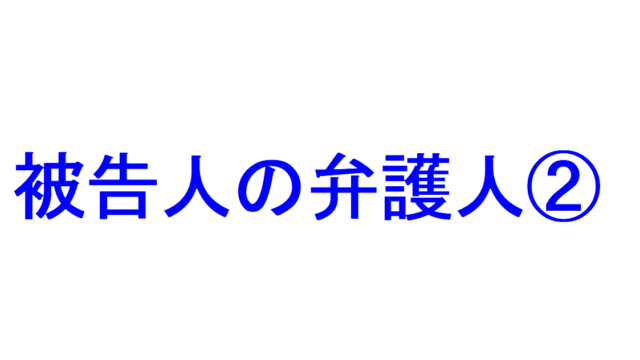裁判④~「裁判は確定によって効力を生じる」「確定判決の既判力、一事不再理の原則」「裁判確定の効力が排除される場合」などを説明
前回の記事の続きです。
裁判は「確定」によって効力を生じる
告知によって外部的に成立した裁判は、それが「確定」することによって、その効力を生じます。
上訴を許さない裁判は、告知と同時に「確定」します。
上訴を許す裁判は、
- 上訴期間の経過
- 上訴権の放棄
- 上訴の取下げ
- 上訴棄却の裁判の確定
によって「確定」し、それ以後は通常の上訴によっては争うことができなくなります。
裁判の確定によって、その裁判に対して争うことができなくなるという効力を
裁判の形式的確定力
といいます。
形式的確定力が生じると、それによって裁判の内容もまた確定し、同一の事項についてそれと異なる裁判をすることは許されなくなります。
つまり、同じ内容でもう一度裁判を起こすことができなくなるということです。
この効力を
裁判の内容的確定力
といいます。
参考となる判例として、勾留の裁判に対する異議申立てが棄却され、これに対する特別抗告も棄却されて確定した場合には、この異議申立てと同一の論拠に基づいて勾留を違法として取り消すことはできなくなることを明示したものがあります(最高裁決定 平成12年9月27日)。
内容的確定力が、有罪判決・無罪判決(実体裁判)について生じた場合を
裁判の実体的確定力
といいます。
裁判は確定することによって効力を生じることの例外
裁判の執行力は、裁判の確定によって生じるのが原則です(刑訴法471条)。
しかし、以下の①、②の例外があります。
① 決定・命令の執行力は、裁判の告知によって生じる
判決ではなく、決定・命令の執行力は、裁判の確定で効力が生じるのではなく、裁判の告知の段階で効力が生じます(判決・決定・命令の違いは前の記事参照)。
決定・命令の執行力は、裁判の告知によって生じることから、その決定・命令に対して不服申立てをしても、執行力は停止しません。
具体的には、検察官、被告人又は弁護人から、
あったとしても、裁判の執行は停止されません。
この場合、裁判所又は裁判官は、決定に対する抗告、命令に対する準抗告があった場合、執行を停止する判断を行うことになります(刑訴法424条ただし書き)。
※ 抗告と準抗告が区別されるのは、予断排除の原則が背景としてあるためです(この点については前の記事で詳しく説明しています)。
② 罰金・科料・追徴の裁判について、仮納付が命ぜられたときは、裁判の確定を待たず、直ちに執行力が生じる
罰金・科料・追徴の裁判について、仮納付が命ぜられたときは、裁判の確定を待たず、直ちに執行力を生じます(刑訴法348条3項)。
確定判決の既判力、一事不再理の原則
裁判の実体的確定力(有罪判決の確定の効力)は、刑の執行力となって現れます。
裁判が有罪判決(例えば、「懲役1年に処す」「罰金50万円に処す」など)であるときは、裁判で言い渡された刑の「執行力」という効果が生じます。
例えば、「1年間刑務所に服役させる」「罰金50万円を納めさせる」などの刑の執行力が生じます。
裁判の実体的確定力は、既判力又は一事不再理となって現れます(憲法39条)。
裁判の実体的確定力が生じると、同一の事件については、再び公訴を提起することも、審理を行うことも許されなくなります。
これを
「確定判決の既判力」や「一事不再理の原則」
といいます。
これは、
- 裁判の権威を維持するため
- 被告人の法的安定性を保障するため
のものです。
確定判決の既判力が生じるのは、
についてです。
「確定判決の既判力」の具体的説明
確定判決の既判力は、実体判決が確定した事件については再度の審判が許されないという効力です。
確定判決の既判力は、判決が言い渡された事件の公訴事実の全部について生じます。
なので、同一の公訴事実については、別の訴因を掲げて再起訴することはできません。
継続犯・常習犯・包括一罪などの一罪の場合や、観念的競合・牽連犯のような科刑上一罪の場合も、その一部の訴因について確定判決があれば、他の部分にも既判力が及ぶため、他の訴因についての再起訴はできなくなります。
※ 訴因と公訴事実の関係は前の記事参照
公訴事実が別であれば、既判力は及ばず、起訴ができる
確定判決の既判力が及ぶ範囲は、公訴事実の同一性の範囲内に限られます。
なので、公訴事実が別であれば(言い換えると、併合罪の関係に立つ犯罪事実であれば)、確定判決の既判力は及ばす、事件を起訴することができます。
この点を判示したのが以下の判例です。
裁判官は、
- 数個の窃盗行為が数日の期間を経て行われたときは、たとえその被害者が同一人であるにしてもこれを併合罪として処断すべきものであり、併合罪の関係にある一部の罪について判決がなされても、その判決の既判力は他の部分の罪には及ばないのである
- 確定判決を経た犯行と原判決の是認した犯行とは同一の犯罪ではなく別個の犯罪であり併合罪として処断さるべきものであるから、本件犯行を審理裁判したことは前記確定判決に判示された各犯行につき再び審理裁判をしたものということはできない
と判示しました。
常習累犯窃盗罪の場合は、既判力が及び、起訴はできない
常習累犯窃盗罪などの常習罪は、数個の犯罪行為を合わせて一罪(集合犯)として扱うので、常習罪として一罪の関係にある事件は、判決確定の既判力が及び、起訴はできません。
この点を判示したのが以下の判例です。
この判例は、常習累犯窃盗罪として起訴された数個の窃盗行為の中間に、同種態様の犯行による単純窃盗罪の確定判決が存在し、確定判決前の窃盗行為は確定判決に係る窃盗行為と共に常習累犯窃盗罪の一部を構成すべきものと認められるときには、確定判決前の窃盗行為については確定判決の既判カが及ぶため、起訴はできないとしました。
既判力の及ぶ範囲は、被告人についてのみである
確定判決の既判力の及ぶ人的範囲は、その事件の被告人についてのみです(刑訴法249条)。
なので、その事件の被告人に対して有罪、無罪の判決が確定しても、その既判力は共犯者には及ばないので、共犯者について同一の公訴事実で起訴することができます。
判決言渡しの後に行われた犯行には、既判力が及ばず、起訴できる
確定判決の既判力の及ぶ時間的範囲は、同時審判の可能性のある範囲(複数の事件をまとめて同時に審理する可能性があった範囲)に限られます。
なので、継続犯・常習犯などの複数の犯罪行為を合わせて一罪と認定する事件(包括一罪)について、一罪の関係になる新たな犯行が判決の後に行われたものである場合は、判決確定前のものであっても、別罪として起訴することができなす。
より正確に言うと、確定判決の既判力は、
までの範囲について及びます。
この点について判示した以下の裁判例があります。
東京高裁判決(昭和46年11月29日)
一個の常習賭博罪を構成する数個の賭博行為が一個の判決の前後にまたがって行なわれた場合の既判力の範囲について判示した事例です。
裁判官は、
- 賭博の常習性を有する者が数回にわたって賭博行為をした場合に、原則として一個の常習賭博罪を構成するが、このような数個の常習賭博行為によって構成された常習犯たる集合犯の一部につき公訴提起があって審理判決があり、その後さらに他の犯行があってこの部分につき公訴提起があって審理判決があった場合のように、判決の前後にまたがって数個の常習賭博行為が行われた場合には、さきの判決の既判力の時間的限界は、原則として、事実審理の可能性がある最後の時、すなわち、第一審判決言渡の当時、例外として上訴審における破棄自判の判決言渡当時と解するのが相当である
- 事実審理の対象となり得ない事実にまで既判力を及ぼすことは、不当に既判力の範囲を拡大するものとして許されないと解すべきところ、控訴審は原則として、原判決の時を標準としてその当否を判断する事後審であって、破棄自判する場合に限り、例外的に続審として控訴審判決の時を標準としてさらに判決するに止まり、控訴審が破棄自判しない限り、事実審理をなし得る可能性のある最後の時は第一審判決の時であるからである
と判示しました。
確定判決のある事件について、再起訴(二重起訴)がなされた場合、「免訴」の裁判によって訴訟係属が打ち切られる
確定判決のある事件について、再起訴(二重起訴)がなされた場合は、審理ができないので、免訴の裁判によって訴訟係属が打ち切られます。
二重起訴について、誤って判決がなされたときは、後に確定した判決に対して、非常上告(刑訴法454条)を行い、判決の破棄と免訴を求めることになります(最高裁判決 昭和28年 12月18日)。
二重起訴した事件について、先に起訴した事件と後に起訴した事件の判決が同時に確定した場合には、後に起訴した事件に対して、非常上告を行い、判決破棄と公訴棄却を求めことになります(最高裁判決 昭和40年7月1日)。
裁判確定の効力が排除される場合
裁判裁判の効力は、以下の①~④の場合に、例外的に排除されます。
① 上訴権が回復した場合(刑訴法362条、363条、364条、365条)
② 再審の場合(刑訴法435条~453条)
③ 非常上告の場合(刑訴法454条~460条)
次回の記事に続く
次回の記事では、
終局裁判の附随的効力(有罪判決に伴う保釈・勾留執行停止の効力失効による被告人の収容、無罪判決に伴う被告人の釈放など)
を説明します。