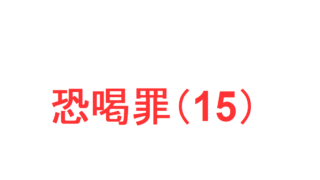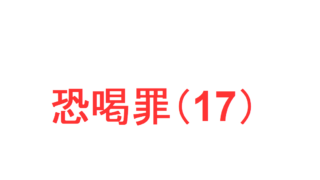権利行使と恐喝罪の成否(社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度を逸脱すれば恐喝罪が成立する)
恐喝罪(刑法249条)において、他人に対して権利を有する者が、恐喝手段を用いて権利の実現を図った場合、恐喝罪の成立を認めることができるかが問題になります。
たとえば、相手が占有している自己の所有物を取り戻すために、恐喝手段を用いた場合に、恐喝罪が成立するかという問題です。
この点について、最高裁判例は、
権利行使のため執った手段が、権利行使の方法として、社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、恐喝罪が成立する
という判断基準を採用して、恐喝罪の成否を判断しています。
この点を示した判例として、以下の判例があります。
被告人Eが、被害者Mと会社を設立し、共同事業を始めたところ、その後Mと不仲になり、会社を退くに当たり、18万円の出資を主張し、争いはあったものの、結局、Mから18万円の支払を受けることになり、15万円の支払を受けたが、その後、Mが残金3万円を支払わないので、第三者に取立てを依頼し、その第三者の知人2名と共に計4名で、Mに対し、身体に危害を加えるような態度を示して、かつ取立てを依頼された者らが「俺達の顔を立てろ」などと申し向け、債権の残額3万円を含む6万円を交付させた事案です。
裁判で、被告人の弁護人は、
- 原判決が残債権3万円を認めながら6万円について恐喝罪が成立するものとしているのは、恐喝手段を施用しても権利の範囲内であれば恐喝罪は成立せず、権利の範囲を越えても、その超過部分についてのみ恐喝罪が成立するという大審院、最高裁判所、高等裁判所の判例と相反する
と主張したのに対して、裁判官は、
- 他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を越えない限り、何ら違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする
- 本件において、被告人らが債権取立のために執った手段は、原判決の確定するところによれば、もし債務者Mにおいて被告人らの要求に応じないときは、同人の身体に危害を加えるような態度を示し、かつ同人に対し、被告人0及び被告人U等は『俺達の顔を立てろ』などと申向け、Mをして、もしその要求に応じない時は自己の身体に危害を加えられるかも知れないと畏怖せしめたというのであるから、もとより、権利行使の手段として社会通念上、一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した手段であることに論はない
- 従って、原判決が右の手段によりMをして金6万円を交付せしめた被告人らの行為に対し、被告人EのMに対する債権額のいかんにかかわらず、右金6万円の全額について恐喝罪の成立をみとめたのは正当である
と説明して、債権取立てのため執った手段が、権利行使の方法として社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、債権額のいかんにかかわらず、恐喝手段により債務者から交付を受けた金員の全額につき恐喝罪が成立することを明確に判示しました。
判例の紹介
上記最高裁判決が出された後も、恐喝者の権利行使にかかる恐喝罪の成否について、「社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度」という判断基準が用いられています。
この判断基準は、抽象的・概括的であるので、その具体的な適用は、裁判を担当する裁判官の判断に任されることになります。
なので、事件の内容によって、恐喝罪が成立するのか、恐喝罪が成立しないのかの判断が分かれます。
そこで、恐喝罪の成立を認めた判例と否定した判例を紹介します。
恐喝罪の成立を認めた判例
東京高裁判決(昭和32年3月20日)
被告人らは、A女から慰謝料の取立てを依頼され、相手方Bに対し、「話は分かっていると思うが、今日はAに渡す2000円の金を受け取りに来たんだ。話が分からなければ、今から徹底的にやっつけてやるぞ」と怒鳴りつけ、卓上の茶碗を振り上げてBに投げつけるような態度を示し、更に「分からないから外に出ろ」と言って、Bを付近の寺の境内に連行した上、「どうしても話がわかんねいなら、ここで喧嘩やっぺい。親爺が勝てば、あの2000円はいらない。その代わり俺が勝てば直ぐ金を出せ」と言ってBを畏怖させた事案です。
裁判官は、
- 被告人らのこの所為は、既にBにおいて、債務者として、社会通念上認容しなければならない程度及び範囲を越え、たとえ、その所為が当初においては債権者としての権利の実行であったとしても、既にその過程においてその実行は濫用に変化し、違法なものとなり、恐喝の実行の手段として相手方Bをして畏怖の念を生ぜしめる害悪の通知があったものといわなければならない
- 然らば、恐喝未遂の事実を認定した原判決は正当である
と判示し、「社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度」の判断基準を用いた上で、恐喝罪の成立を認めました。
東京高裁判決(昭和31年5月9日)
この判例で、裁判官は、
- 他人に対し権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり、かつその手段方法が社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を超えないかぎり、何ら違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする
- しかして、被告人がA、Bに対し手形金支払請求及び債権取立のためにとった手段としての原判示各所為は、権利行使の手段としては明らかに社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱しているものと認められるので、その各所為につき恐喝罪が成立することは明らかであって、正当な権利の行使に伴う行為であるとか、あるいは脅迫罪のみが成立するに過ぎないということはできない
と判示しました。
名古屋高裁金沢支部判決(昭和31年12月11日)
被告人が、A及びBに対し、脅迫の言動を示して畏怖させ、Aから1000円を、Bから1200円を仲介手数料分配金名下に喝取した事案です。
まず、被告人の弁護人は、
- 被告人はA及びBに対し、仲介手数料の分配を請求すべき民法上の権利を有するものである
として恐喝罪は成立しないとしました。
この主張に対し、裁判官は、
- 被告人は、A及びBに対し、仲介手数料の分配を請求すべき民法上の権利を有するものでもなければ、またかかる権利があると自ら信じていたものでもなかったことが明かであるのみならず、たとえ被告人において、かかる権利を有しており、または、かかる権利を有していると自ら信じていたとしても、権利者が権利行使の方法として、義務者に暴行又は脅迫を加えるなど、社会通念上認容すべき程度を逸脱する手段に訴えた場合、なお該行為について恐喝罪の成立を妨げないと解すべきである
と判示しまし、「社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度」の判断基準を用いた上で、恐喝罪の成立を認めました。
名古屋高裁金沢支部判決(昭和45年7月30日)
債権者から債権の取立委任を受けた組織暴力団構成員Aが、債務者方を訪れ、「わしは遊んでいるものや」と自己を紹介しながら「ニ代目柳川組北陸理事A」と記載した名刺を示し、借務者から債権者に直接債務の支払をする旨告げられるや、債務者をにらみつけ、ドスの効いた怒声で「わしが来ているのに払わんというのか、そんなら明日から毎日若衆を来させる」「わしがここまで来て話がつかんというのでは若い者にしめしがつかん」などと申し向けて、暴力団の威力を背景とし、債務者を脅迫して債権の取立てを行い、取り立てた全額を債権者から謝礼の名目で領得した事案です。
裁判官は、
- 本件の如く、本来の債権者でもなく、また、健全な社会常識に照らし債権の取立受任者としても一般に容認し難い組織暴力団構成員である被告人において、脅迫手段をもって債務の弁済を迫ることは、社会通念上債務者の忍容すべき程度を越えたものであることが明白であって、被告人の本件所為は権利の正当な行使と認めるを得ず、恐喝罪に当たるものといわねばならない
と判示して、「社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度」の判断基準を用いた上で、恐喝罪の成立を認めました。
恐喝罪の成立を否定した判例
大阪高裁判決(昭和34年12月18日)
被告人Aが、強姦された女性Bから相手方Cを告訴すること及びCに対する損害賠償請求を依頼され、DにCを旅館に連れて来させ、Bが告訴するといっていると告げて、暗に賠償金の交付を要求し、 Cが既にBに対し1万円を渡して解決済みであると答えると、1万円くらいでは解決できぬと激語し、次いで、DがCを廊下に連れ出し、「これは相当問題が大きくなる。告訴されれば新聞にも出されるし、勾留もされる。Aは一任されているからAに聞かなければ分からないが、10万円くらい出さなければ納まるまい」と言って、金員を要求して遂げなかった恐喝未遂の事案です。
裁判官は、
- 被告人が、Cに対して執った言動は、前記のとおりBがCから強姦された事実につき告訴すると言っているとか、また、既に支払った前記1万円くらいでは納まらないという程度であり、その表現に多少の激越性があったとしても、右請求の額及び方法において右損害賠償請求権の行使の範囲を逸脱し、社会通念上忍容すべき程度を越えたものとは認められず、またDのC に対する言動も同様と認められ、これらはいずれも、いまだ恐喝罪を構成するものとなるべき限りではないとするを相当とする
と判示して、「社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度」の判断基準を用いた上で、恐喝未遂罪の成立を否定しました。
東京高裁判決(昭和36年11月27日)
被告人Aが、相手方Cに対し、相当額の飲食代金、接待料などの債権を有しており、何回もCに対し支払を請求していたが、Cは何らの反応もしないのみならず、ついに所在をも明らかにしないようになったので、相被告人Bに取立てを依頼し、BはCの所在をつきとめた上、喫茶店にCを呼び出し、Aからの委任状を示し、2、3時間にわたり債権の支払を受けるべく談判をし、その間、話の成行き上、双方語気を強めて言い合った事案です。
裁判官は、
- 元来、本件は、Cがバー女給に対し、相当額に達する飲食代金などの借金を負いながら、数か月にもわたって、その支払いを拒み、あまつさえその所在をも明らかにしなかったというが如き態度に出でたことに第一の原因があり、Cのその態度は非難を免れない
- 更に本件におけるBとの談判に際しても、Cが言を左右にして支払を免れんと努めたので、談判が長びいたと認められる節もあり、右談判の間において、Bが多少不穏な言辞を吐いたのではないかと疑うべき点はあるが、この点に関するCの証言並びに被告人らの捜査官に対する各供述調書の供述記載については、必ずしも信をおき難いものがある
- 結局、被告人Bのその際における言動が債権の要求、すなわち、いわゆる権利の行使として社会観念上許された範囲を逸脱したものであったということについては、これを認め難いというべきであるから、ひっきょう本件公訴事実については、犯罪事実の証明を得ざるに帰し、被告人両名に対しては無罪を言い渡すべきである
と判示し、「社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度」の判断基準を用いた上で、恐喝未遂罪の成立を否定しました。
東京地裁判決(昭和42年9月5日)
被告人は、クラブMのホステスIが有限会社Nの従業員の運転する自動車により負傷したことから、同会社の社長Wに対し、Iの休業補補償として金20万円を支払われたい旨接渉していたものであるところ、Wにおいて、右要求に応じないとみるや、休業補償名下に金員を喝取しようと企て、同会社にいたWに対し、電話で「お前は誠意がないな、どうしたのだ。」「お前は言ってもわからないんだなあ、お前年頃になれば娘も年頃になつているだろう、娘がいなければお前の女房でもいいから渋谷まですぐ連れてこい。お前の見ている前で車で轢き殺してやるからな。一度で死ななければ二度でも三度でも轢いて殺してみせる。聞いているのか」などと申し向けたうえ、更にIの居室において、Wに対し「誠意がない」、「今まで金を持って来たことがあるか」「俺は一回言ったことは取消すということをしないのだ」、「俺も気が短い方だからこんなことでぐずぐず話をしているのはきらいだ」などと申し向けて、休業補償名下に現金20万円を要求して脅迫したが、Wが要求に応じなかったため、目的を遂げなかった恐喝未遂の事案です。
裁判官は、
- 被告人の所為は、あくまで自己とかねてから同棲中のIの依頼により、Iのため休業補償請求権を行使した権利行使行為の範囲内にとどまるものであり、休業補償金名下に金員を喝取せんとしたものとは認め得ない
- 被告人がIの依頼を受け、Iのために社長Wに休業補償支払の接渉をし、その具体的としてIの希望する20万円を要求したことは、社会通念上必ずしもこれを不当かつ過大とは言い得ず、通常考えられる権利行使行為と言うべきである
- もっとも、接渉の際における被告人の言動に高圧的なものがあり、しかも申し向けた文言も前示のとおり、かなり穏当を欠くもののあったことは否定しがたいところである
- しかし、被告人が社長Wに対して電話で申し向けた文言は、証人及び被告人の当公判廷における供述によれば、前記のとおり社長Wが3月23日までに休業補償の返事をすると約束しながら何の返事をしなかったことなどから、社長Wの態度に不満を感じた被告人が「あんたの年頃になれば娘も年頃になっているだろう。また、娘がいなければあんたの女房でもいい、娘や女房が目の前でひかれるのを見たあんたはどう思うか」という趣旨で申し向けたものであって、社長Wが休業補償につき誠意のないことを難詰したにとどまり、本当に「お前の見ている前で娘や女房を轢き殺してやる。」等社長Wの家族に危害を加える趣旨の発言とは認められないし、Iの居室内でもかなり語気あらく社長Wの不誠実を非難はしたが、前記認定の経緯に徴し、この程度のことは社会通念上許容し得るものであり、被告人がいわける恐喝行為として渡辺をして畏怖をさせるに足る脅迫行為をしたことについてはこれを確認するに足る証拠はなく、結局、右の如き3月30日の接渉にいたるまでの経緯や、それに加えて被告人とIとの特殊の関係を考えた場合、被告人の本件所為はIの依頼を受け同女のため休業補償請求権を行使した権利行使行為として社会通念上受忍される範囲を出てなかったものと認めるのが相当である
と判示し、「社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度」の判断基準を用いた上で、恐喝未遂罪の成立を否定しました。
福岡地裁小倉支部(昭和47年4月28日)
この判例は、債権の取立に際し、共謀の上、若干の恐喝手段を用いた場合において、債権者については右手段が未だ社会通念上一般に受忍すべき程度を逸脱したものとは認められないとして、恐喝罪は成立しないとして無罪を言渡した事例です。
裁判官は、
- およそ権利者が権利の実行にあたり脅迫等の恐喝手段をとった場合、権利行使の目的の故に常に恐喝罪の成立を否定すべきではないこともちろんであるが、他面、その手段が構成要件に該当する故に常に同罪の成立を肯定すべきものでもなく、結局は当該行為を全体として観察し、社会的相当性の範囲内に止まるか否か(判例の表現によれば、社会通念上一般に忍容すべき程度を超えないか否か)によって同罪の成否を判断すべきものである
- 換言すれば、権利行使のための恐喝手段(脅迫等)は、社会通念上忍容すべき程度のものとこれを逸脱するものとに区別することが可能かつ必要であり、後者の場合にのみ恐喝罪の成立を肯定すべきものである
- そしてまた、右にいう社会的相当性の有無の判断に当たっては、当該行為の主観客観の両側面、すなわち、その目的と手段の双方を総合的に判断すべきはもちろん、場合によっては、当該権利義務の内容・性質・成立原因等、当事者双方の生活に対するかかわりの軽重、当該行為に至るまでの当事者間の交渉経緯、その努力の有無程度、双方の資産地位、権利義務に関する知識の深浅その他の力関係等にまで立ち入って仔細に吟味する必要があり、権利義務関係の支配原理である信義則がこの場合にも有力な指標を提供するものと考えられる
- 被告人のとった手段は、共謀による恐喝にあたることは否定できないとしても、その共謀は当初からの確定的なものではなく、ことの推移に応じて暗黙に意思の連絡を遂げたとみるべきものであり、また自ら何らかの実行行為を分担することはなく、共犯者らに対し終始著しく依存的であって、全体として関与の程度は低く、むしろ薄弱なものであったと言って差し支えない
- 翻って考えるに、被告人の債権は、その生業とする大工仕事によって得たものであり、仕事の完成は約定の期限に遅れたとはいえ、遅延の原因は古材として使用する家屋の明渡が遅れるといういわば第三者によるものであり、被告人としては、そのことを被害者に説明した上、その代りに割安の条件で新材による家屋一棟を建てることを申し出てこれを完成する等、むしろ誠実ともいうべき態度に終始している
- また、その請負代金については、関係業者への支払等に絶えず追われ、極めて切実なものがあったことが窺われる
- 被告人のとった手段は、共犯者との共謀による恐喝の外形を充足することを否定できないとしても、なお、さきに述べた社会的相当性(社会通念上一般に忍容すべき程度)を超えたものと断ずることはできず、他に右を積極に認定するに足る証拠はない
と判示し、「社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度」の判断基準を用いた上で、恐喝未遂罪の成立を否定しました。
東京地裁判決(平成14年3月15日)
この判例は、経営権譲渡契約の違約金名下に金員を喝取しようとした恐喝未遂の公訴事実について、被害者二人の供述の信用性は低く、被告人らの請求が権利行使の相当性を欠く恐喝行為に当たると解することは困難であるなどとして、被告人三人がいずれも無罪とされた事例です。
公訴事実は、被告人3名は、共謀の上、社会福祉法人の経営権の譲渡契約に関し、知人のDから依頼されて右経営権の譲渡契約名義上の譲受人となったE及び同契約の仲介人であるFから同契約の違約金名下に金員を喝取しようと企て、「てめえ、ふざけたことを言ってるとぶっ殺すぞ。」、「てめぇがこのことを警察やヤクザに泣きついてもそんなことは握り潰してやる。」、「てめぇはおとなしく2600万円払えばいいんじゃ。」、「明日の昼までに親戚中かけずり回って、できるだけ金を用意しろ。」、「昼の12時にいくら集まったか連絡して、2時までに東麻布の事務所に持ってこい。」、「Dは台湾マフィアを使って消しますから。」、「私が持っているルートを使うか、A会長のルートを使うか後でご相談しましょう。」、「日本人を使うと後で足がつきますから。」などと語気鋭く申し向けて金員を要求し、もしこの要求に応じなければ、E及びFの身体等にいかなる危害を加えるかもしれない気勢を示して同人らを畏怖させたが、同人らが警察に届けたため、その目的を遂げなかったというものです。
裁判官は、
- 本件におけるE及びFの証言には、その信用性に疑問を抱かざるを得ない点が多々見受けられるのであって、両名が場所を変えながら長時間にわたり繰り返し同じような内容の文言を言われ続けたことから、細部にわたる記憶が混乱するのはやむを得ない旨の検察官の主張や、両名が直ちに警察に被害届をしていることなどを考慮しても、その信用性はやはり低いといわざるを得ない
- 権利行使の方法として相当といえるためには、請求の根拠となる権利の確実性、相手方の態度の誠実性、請求する際の言動の相当性などの事情を総合的に考慮する必要があるものと解される
- 本件においては、恐喝行為を構成する脅迫文言に係るE及びFの供述の信用性に少なからぬ疑問があり、被告人らがそれ自体で脅迫と評されるような発言をしたとまでは認め難いこと、被告人らが請求の根拠とした協定書が当然無効のものとはいい難いこと、E、Fらの側にも、通常の契約における健全な買主とは同視し難い事情がうかがわれることなどの事情があり、こうした事情に照らすと被告人らの請求が権利行使の相当性を欠く恐喝行為に当たると解するのは困難である
と判示し、「社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度」の判断基準を用いた上で、恐喝未遂罪の成立を否定しました。
大阪地裁判決(平成17年5月25日)
被告人Dらが、会社総務課長Yから、被告人が出社しないことや仕事の能力不足を理由に解雇通告を受け、自己都合による退職を了承させられたことに因縁をつけ、同会社から解雇予告手当名下に、被告人の給与分11万5706円を含む28万4272円の振込入金を受けて喝取した事案です。
裁判官は、
- DがX社に対して解雇予告手当を請求しうる地位を有していたことは既に検討したとおりであるが、被告人4名の要求はこの範囲内にとどまっており、過大な要求をしたものとはいえない
- すなわち、被告人4名は、例えば「迷惑料」、「足代」あるいは「日当」など名目の如何を問わず、解雇予告手当以外の金銭要求を一切していないのである。
- そして、Dが最終的にX社から振込送金を受けた金額も、稼働日数に見合った給与相当分を除けば、解雇予告手当そのものとしてX社において算出したものと推認され、これに反する証拠はない
- したがって、Dの権利行使は、その金額の範囲内にとどまっている
- X社応接室における被告人4名の言動が、解雇予告手当請求権行使の方法として社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱しているとまでいうことはできない
- 検討によれば、本件において、Dが、X社に対して、解雇予告手当の支払を請求しうる地位を有し、かつ、X社応接室における被告人4名の言動が、そのような権利を行使する方法として社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱していないことになるのであるから、正当行為として、恐喝罪の違法性は阻却されるというべきである
と判示し、「社会通念上一般に忍容すべきものと認められる限度」の判断基準を用いた上で、恐喝罪の成立を否定しました。