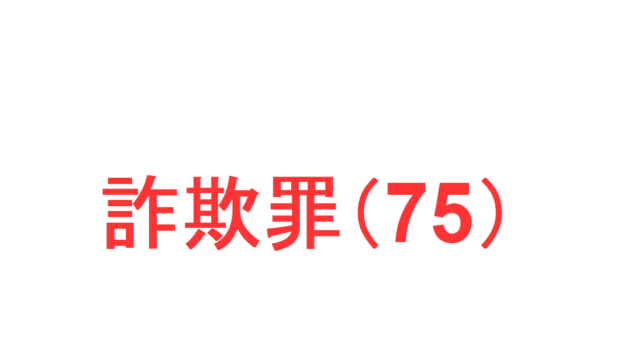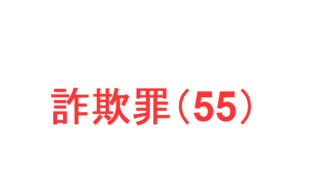詐欺罪が既遂となるための要件
詐欺罪が既遂に達するためには、
行為者の人を欺く行為によって相手方が錯誤に陥り、それに基づいて処分行為を行い、その結果、財物の占有が行為者又は第三者に移転したこと
が必要です。
さらに、
- 行為者の人を欺く行為によって相手方が錯誤に陥る
- それに基づいて処分行為を行う
- その結果、財物の占有が行為者又は第三者に移転する
の過程の間には、因果関係が存在することが必要です。
因果関係が欠けるときは、どの部分で欠けても、詐欺罪は既遂とならず、詐欺未遂罪が成立するにとどまります。
人を欺く行為は行われたが、相手方が錯誤に陥ることなく、単に憐愍の情から財物を与えたような場合は、詐欺罪は既遂とならず、詐欺未遂罪が成立するにとどまります。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(大正11年12月22日)
この判例の事案は、
- 被告人が、甲を借主、乙らを連帯保証人として800円を貸与し、その後、乙から全額の弁済を受け、その債権は消滅したのに、その貸金証書がそのまま手元に残っていたのを奇貨として、甲をだまして貸金請求名下に金員を詐取しようと企て、甲に対して、まだその貸金の完済を受けていないように装って、その元利金の請求をしたところ、甲は乙に問い合わせ、すでに弁済をした旨の回答を得、さらに、被告人の人柄からして10年間も貸金を請求しないで放任するはずはないことを知っていたので、その貸金は弁済ずみと思い錯誤に陥らなかったが、受取証書が見つからなかったので、証拠を捜すまでに差押えをされては世間体が悪いから一応支払っておこうと思い980円を支払った
という事案です。
裁判官は、
- 甲は、被告人が虚偽の貸金債権を主張し、支払を請求したるにかかわらず錯誤に陥らざりしものなるをもって、被告人の行為は詐欺罪の未遂に該当するものとす
- 甲が被告人にその請求に係る金額を支払いたるが如きは、被告人の詐欺罪が未遂をもって終了したる以後の行為に関し、被告人の欺罔の効を奏したるによるにあらず
- 被告人の詐欺行為とは、全然因果関係なきものなり故に、この金額を受領したる被告人の行為が既遂として詐欺罪を構成するいわれはなきはもちろんである
と判示し、詐欺既遂罪の成立を否定し、詐欺未遂罪の成立を認めました。
この判例の事案は、
- 山林等の権利書を担保として当座貸越を受けていた者がその返済を迫られ、偽造の増資新株式申込証拠金領収証を真正なもののように装い、担保に差し入れて相手方を欺き、金員の貸出しを受け、現実交付に代えて先の貸越額の返済に充当し、その結果、山林等の権利書の返還を受けた
という事案です。
裁判官は、
- 当座貸越債務の返済を免れた点においては、人を欺く手段と直接の因果関係が存在するから詐欺罪は成立するが、山林等の権利書の返還を受けた点については、当座貸越債務関係終了に伴う当然の後始末としてなされただけのことで、人を欺く手段との間に直接因果関係を認めがたいから詐欺罪は成立しない
としました。
大審院判決(大正3年5月16日)
第三者が病気であるのに、これを秘して生命保険契約を締結し、秘した病気と異なる原因に基づく被保険者の死亡により保険金の交付を受けたという事案で、裁判官は、
- 犯人が病者なる第三者をあたかも健康者なるが如く装い、もって保険業者を欺き、生命保険契約を締結し、その結果、被保険者の死亡により保険金の交付を受けたるときは、その死亡の原因が犯人の秘したる病症に基づくと否とにかかわらず、詐欺罪を構成するものとす
- 保険金の交付は、保険契約の結果にして、保険契約は犯人の欺罔に基けるものなれば、すなわち人を欺罔して金員騙取したるにほかならざればなり
と判示、不告知という人を欺く行為と保険金受領との間の因果関係を肯定し、詐欺既遂罪の成立を認めました。
疾病に罹患していることを告知すれば、生命保険契約は不成立に終わっているであろうから、その不告知という人を欺く行為と保険金受領との間に因果関係の存在を認めることができると考えられます。
財物の占有移転
詐欺罪が既遂となるための要件である
財物の占有が行為者又は第三者に移転する
について詳しく説明します。
財物の占有が行為者又は第三者に移転するとは、
財物に対する被害者の支配を排除して、行為自身又は行為者と一定の関係にある第三者がその支配を設定すること
をいいます。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(大正12年11月20日)
この判例で、裁判官は、
- 刑法第246条に、いわゆる財物の騙取(詐取)ありとするには、犯人の施用せる欺罔(人を欺く)手段により、他人を錯誤に陥れ、財物を犯人自身又はその代人もしくは第三者に交付せしむるか、あるいは、こられの者の自由なる支配内に置かしむる事実なかるべからず(※事実がないようではいけない)
- 而して、被欺罔者たる他人が、なお財物につき支配力を失はわざる限りは、未だその財物の騙取ありというべからず
と判示しました。
この例で、裁判官は、上記の大審院判決(大正12年11月20日)を引用し、
- 刑法246条1項に定むる財物の騙取とは、犯人の施用した欺罔手段により、他人を錯誤に陥れ、財物を犯人自身又はその代人若くは第三者に交付せしむるか、あるいはこれらの者の自由支配内に置かしむることをいうのであって(論旨引用の大正12年(れ)1272号同年11月20日大審院判決大審院判例集2巻86頁)、原判決もまた本件について「被告人Aが判示Cに虚言を弄し、同人をしてその旨誤信させた結果、同人をして任意に判示の現金を同被告人の事実上自由に支配させることができる状態に置かせた上で、これを自己の占有内に収めた事実であるから、刑法246条1項にあたる」と判断しているのであって、大審院判決と相反する判断を示めしたものではない
- されば、原判決が本件について、右Cが被告人Aの判示の欺罔手段に基き、判示の現金を同被告人の自由に支配できる状態に置く意思で判示の玄関上り口に置いたものと認定したことの当否は格別、原判決が大審院判例と相反する判断をしたとの論旨は理由のないこと明らかである
と判示しました。
仙台高裁判決(昭和31年10月31日)
この判例で、裁判官は、
- 財物の騙取とは、常に必ずしも現実に財物自体を受領することを必要とせず、これを現実に受領したと同一視せられる財物受領の可能な状態にある場合においても同罪の既遂を構成すべきものであるが、それには犯人において該財物に対する現実の支配力を獲得したことを要する
と判示して、食糧事務所を欺いて米穀を詐取しようと企て、偽造の請書を提出して荷渡指図書の交付を受けたとしても、それによって現品の引渡しを受けない限り、米穀の詐欺の既遂とならないとしました。
このことから、動産、不動産を問わず、「詐取した」といえるためには、単なる意思表示があっただけでは足りず、詐欺被害品となる財物の支配が、犯人の支配に現実に移転したことが必要となります。
次回記事に続く
次回の記事では、
- 不動産
- 有価証券
- 荷物切符
- 保険詐欺
についての詐欺罪の既遂時期について説明します。