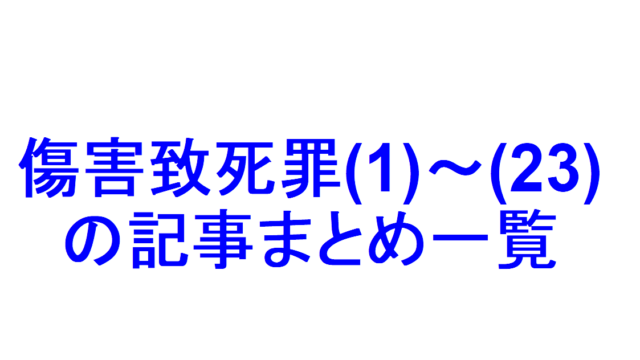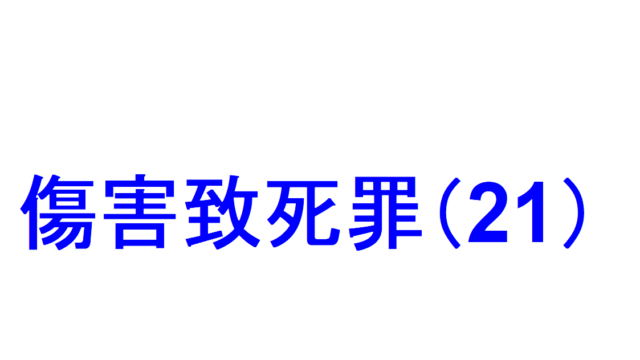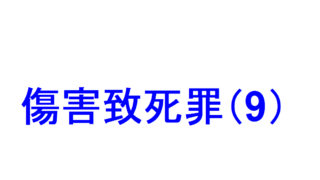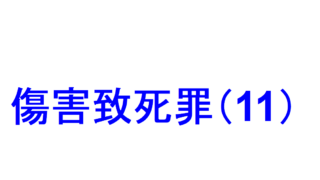前回の記事では、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした最高裁判例を紹介しました。
今回の記事では、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした下級審判例を紹介します。
暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした下級審判例
暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした下級審判例として、以下の判例があります。
①福岡高裁判決(昭和25年11月21日)
頭部を警棒で殴打され、医師の診療を受けたものの、その後、戸外で寝ていたため、寒気により傷害の程度が高じて、まもなく死亡した事案で、裁判官は、
- 被告人の行為と被害者の死の結果との間に被害者の不注意な行動が介在していても、被告人の行為が死の結果に対する有力な原因である以上、 もとよりその間の因果関係は遮断されるわけではない
とし、被害者の不注意な行為があったとしても、暴行と致死の因果関係は中断されないとして、傷害致死罪の成立を認めました。
②仙台高裁判決(昭和26年4月11日)
この判例は、傷害に対する医師の治療上の過誤と死との間の因果関係の中断を否定した事例です。
弁護人が、
- 被害者Hの死は、医師Kの治療上における過誤によるものであるから、被告人の傷害行為と死との間の因果関係は、医療過誤により中断されたため、被告人に傷害罪は成立しても、傷害致死罪は成立しない
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 医師Kの被害者Hに対する診療に過誤があったことは窺知しえない訳ではないが、通常、被告人の加害行為により死の結果が発生しうべきことが実験則上予想される本件においては、これにより被告人の所為と被害者の死との因果関係は中断され被告人の刑事責任は免脱されたものと認める訳にはいかない
と判示し、通常、被告人の加害行為により死の結果が発生しうべきことが実験則上(経験則上)予想されることであるとして、弁護人が主張する因果関係の中断を否定し、傷害致死罪が成立するとしました。
③名古屋高裁判決(昭和28年12月28日)
被告人の暴行による脳内出血が一時停止した後、手術により再出血を誘発した事案について、暴行と被害者の死との間に因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
④東京高裁判決(昭和30年3月1日)
医療施設の乏しい建設工事現場における傷害事案において、被害者を遠隔地の大病院に運んだものの、約半月後に死亡した事例について、傷害と被害者の死との間の因果関係の中断を認めず、因果関係が認められるとして、傷害致死罪が成立するとしました。
⑤東京高裁判決(昭和31年2月9日)
受傷後の医師の措置や家族の対応が不十分であったことが、傷害と致死の間の因果関係を中断しないとした事例です。
裁判官は、
- 被告人がSの頸部を絞め、これによって喉頭浮腫を生じ、それがT医師の切開手術も功を奏せず、増悪の一路をたどり窒息死亡するに至ったものとして、その間、因果関係の存すること明白である
- T医師が、あらかじめ適切な対策をたて、浮腫の増悪を来した場合、気管切開の機を逸しないようにSを入院させておくとか、または、Sの家族が医師を迎えることのみに狂弄することなしに、直ちにSを医者のもとに送り、再手術を受ければ、あるいはSの一命を取り止め得たかも判らないこと所論(※弁護人の主張)のとおりとしても、医師並びにS家族の措置が適切でなかったことが、被告人の暴行により浮腫を発生したこと及びSの死亡との間の因果関係を中断するものとは認められない
と判示し、因果関係の中断が認められないとして、傷害致死罪が成立するとしました。
⑥大阪地裁判決(平成8年10月11日)
傷害致死の事案につき、医師の措置に適切さを欠く点がみられ、また、被害者自身の医師に対する態度にも非協力的な点があり、それらもまた被害者の死亡という結果の発生を促進し、あるいはその一因をなす点があったとしても、被告人の暴行による傷害と被害者死亡との間には因果関係があるとして、傷害致死罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 患者Y(※被害者)が腹部外傷を受け、かつ、その腹腔内に液体貯留が認められる場合には、実質、臓器による腹腔内出血、または、消化管穿孔による消化液の腹腔内貯留が考えられること、いずれの場合であっても腹膜炎を含む重篤な結果を招来するおそれがあり、開腹手術を実施する必要性の生ずる可能性があることから、レントゲン写真、CT撮影等で腹部の状態を検査し、あるいは、約2時間ごとに触診、問診を実施して、腹部膨満の程度、腹痛の程度等を把握する必要があること、腹膜炎の場合、患者は激しい腹痛とともに脱水症状を伴い、口渇感を覚え、腹部には筋性防御が生ずることから、触診等で比較的容易に診断できる状況にあることが、それぞれ認められる
- 以上を総合すると、Yが腹痛と口渇感を訴えていることを知り、しかも、その腹部に液体貯留を認めていたA医師としては、少なくともYの身体の状態の経過を注意深く観察すべきであったといえ、Y自身が拒否する態度を示していたという事情があったものの、Yの腹部の触診を頻回に試み、また、Yの腹痛が激しくなった時点で外科医に連絡する等の措置をとることが望ましかったと考えられ、その意味でA医師の一連の措置は医師として適切さを欠く点の見られるものであったとのそしりを免れ難いところである
- しかしながら、医師E作成による死体検案書をも含む前掲の関係各証拠によれば、被告人の判示暴行により、Yの小腸に穿孔が生じ、右穿孔から消嚢性腹膜炎が発症し、急速に症状が悪化した結果、被告人の暴行による受傷後わずか53時間余りでYが亡するに至ったことが明らかである
- このことに照らせば、被告人の暴行によって生じた傷害自体が、Yの死亡という結果を惹起する程度の危険性を具有していたものであることも明らかであるから、A医師の措置に適切さを欠く点がみられ、Y自身の医師に対する態度にも非協力的な点があり、それらもまたYの死亡という結果の発生を促進し、あるいはその一因をなす点があったとしても、被告人の暴行による傷害とYの死亡との間には、刑法上の因果関係のあることが肯認されるといわなければならない
と判示しました。
⑦大阪高裁判決(昭和53年10月25日)
この判例で、裁判官は、
- 適切な医療措置によって必ずしも被害者を救命し得たとは限らず、被害者に対してとられた診療措置は、一般病院における診療態勢では稀な事例といえないから、死亡の結果が発生するおそれのあることは当然予想されるところであって、被害者に対する治療の過程に医師の誤診と治療行為の遅延が介入し、これが被害者の死の結果の発生を促進し、 あるいはその一因となったとしても、暴行と死の間に刑法上の因果関係が存する
と認め、傷害致死罪が成立するとしました。
⑧東京高裁判決(昭和61年4月24日)
不慮の事故により重傷を負った場合に、いつどこでも遅滞なく完全無欠、理想的な救急医療措置を受けられるものではないことも、公知の事実であり、治療の遅延、過誤医師に対する被害者による虚偽の訴えがあっても因果関係が認められるとした事例です。
まず、弁護人は、
- 被害者Aが死亡したのは、その治療にあたった医師Hが、(イ)被害者が十分な輸血、補液を必要とする腹腔内臓器合併損傷を負っていたのに、早期に十分な輸血、補液をなすことを怠り、(ロ)損傷の部位について誤診し、局所麻酔の方法で開腹手術をして患者の手術侵襲ならびに精神的負担を増大させ、(ハ)十二指腸の裂創を縫合しただけで、その他の腹腔内臓器の出血損傷について止血措置を施さず放置したという重大な過失を犯したことによるものであるから、被告人の暴行と被害者の死亡との間には因果関係がないのに、これを認めた原判決には事実の誤認があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 被告人の踏みつけ行為により、被害者は致命傷となった膵臓破裂、十二指腸破裂等の創傷を負い、それらの創傷はいずれも極めて重傷であつて、その創傷からの出血により被害者が死亡したことが認められる
- すなわち、本件において被告人の右暴行による傷害が被害者の死亡を引き起こしたものであることは明白である
- しかも、人が右のような重傷を負ったときは、放置すれば確実に死に至ることはもちろん、適時適切な治療措置を受けたとしても、多くの場合、死を免れないものであることが認められる
- そして、本件のように不慮の事故により重傷を負った場合に、いつどこでも遅滞なく完全無欠、理想的な救急医療措置を受けられるものではないことも、公知の事実である
- そうしてみると、本件暴行終了時において、本件被害者の死亡の結果の生じうることは、経験則上、十分予想することが可能であったというべきである
- したがって、本件において、被害者が受傷後4時間近くを経過して救急車で○△厚生病院に運び込まれ、しかも治療に当たったH医師に対し、胃けいれんであると虚偽の訴えをしたことが認められるのではあるが、また、かりにH医師のとった措置になんらかの過誤が存したとしても、その措置が現在の通常の医療技術水準ないし医療上の常識から甚だしく隔たった異常なものであったために被害者の状態を悪化させ死亡するに至らせたというような特段の事情が認められない限り、本件暴行による傷害と死亡との間には刑法上の因果関係があると認めるのが相当である
- 右の見地に立ち、所論(※弁護人の主張)にかんがみ検討してみても、本件被害者の治療に当たったH医師の診断及び手術を含む措置が極めて不適当で、右のように異常なものであったとは認められず、右特段の事情は認められないから、右の因果関係があるというべきであつて、この点に関する原判決の説示も正当である
と判示し、傷害と致死の間の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
⑨東京高裁判決(昭和31年2月29日)
被害者の持病が相まって死亡の結果を発生した場合に因果関係を認めた事例です。
肺壊疽で数日後に死ぬかも知れないと言われていた病者の頭部を殴打して脳震盪を起こさせた行為と死の結果の間に因果関係を認めました。
裁判官は
- もっとも被害者Eが通常人の健康体であったとすれば、被告人の加えた程度の暴行によっては死の転帰を見ることは稀であろうが絶無とはいえない訳であり、 ことにEは、病弱者であったのであるから、これに対し、暴行を加えれば死の転帰を見るに至るべきことは実験法則上(※経験則上)明らかである故に、被告人の暴行とEの死との間には法律上因果関係があると認めるべきである
と判示し、傷害と致死の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
高血圧の上、心臓肥大症でわずかな興奮等により心臓麻痺を誘発する状態にあった被害者に対する暴行と心臓麻痺による死亡との間に因果関係を認めました。
裁判官は、
- 被害者が血圧も高く心臓が慢性大症で、わずかな精神的又は肉体的感動や興奮によっても心臓麻痺の起り得る状態にあったこと、被害者の死因が心臓麻痺であったこと、並びに被告人が被害者と口論の末、同人を1回殴打し、被害者がこれに応じて喧嘩闘争をしたこと、被害者がその直後死亡したこと等の事実を認むることができる
- 従って、被告人の右暴行が被害者を興奮せしめ、心臓麻痺の誘発原因となったことは疑を容れないところであり、しかも傷害致死罪における致死の原因たる傷害は、それが唯一の死亡原因たることを要するのではなく、他の原因と相俟って死の結果を惹起した場合をも含むものと解すべきであるから、たとえ本件被害者が前述の如く心臓慢性肥大症でわずかな興奮等により心臓麻痺を誘発する状態にあったとしても、それがため被告人の右暴行と被害者の死因との間に因果関係がなかったとはいえないから、原審が被告人の原判示所為を傷害致死として認定処断したのは正当である
と判示し、傷害致死罪の成立を認めました。
⑪大阪地裁判決(平成5年7月9日)
被害者が脳死になった後、人工呼吸器が取り外され、心臓死となった事案について、暴行と心臓死との因果関係を肯定して傷害致死罪の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- 弁護人は、被害者が心臓停止に至るにつき人工呼吸器の取り外し措置が介在しているところから、被告人の暴行と被害者の心臓死との間に因果関係があるというにはなお疑問が残ると主張する
- しかし、被告人の眉間部打撲行為により、被害者は、びまん性脳損傷を惹起して脳死状態に陥り、二度にわたる脳死判定の結果脳死が確定されて、もはや脳機能を回復することは全く不可能であり、心臓死が確実に切迫してこれを回避することが全く不可能な状態に立ち至っているのであるから、人工呼吸器の取り外し措置によって被害者の心臓死の時期が多少なりとも早められたとしても、被告人の眉間部打撲と被害者の心臓死との間の因果関係を肯定することができるというべきである。
- よって、被告人には傷害致死罪が成立する
と判示し、人工呼吸器の取り外しによって心臓死の時期が多少早められたとしても、暴行と被害者の心臓死との間の因果関係を認めらるとし、傷害致死罪が成立するとしました。
⑫札幌地裁判決(平成12年1月27日)
傷害致死被告事件において、被害者の体質の特異性や最善の治療を受けていれば死亡の結果が発生しなかった可能性があったとしても、これらの事情は被告人らの傷害行為(複数人による殴打、足蹴など)と相まって、被害者の死亡の結果発生を助長させた事情にすぎず、被告人らの傷害行為と被害者の死亡結果との間には因果関係があるとしました。
裁判官は、
- 一般的に、被害者に重い傷害を負わせた場合、被害者が右傷害を直接の原因として死亡する場合に加え、右傷害に起因する合併症を原因として死亡する場合も考えられるのてあるから、右合併症が医学上、通常起こり得るものであり、かつ当初の傷害が死亡の危険性が高いものであれば、当初の傷害とこれに起因する合併症による死亡との間には、刑法上の因果関係を認めることがてきる
- これは、本件のように、頭部外傷を負った者が、肉体的なあるいは精神的なストレスから消化性潰瘍を併発したり、急性粘膜病変等が起こり、これらから消化管出血が生じて死亡の危険が生じる場合があることが医学的な常識てあり、臨床的にもよく見られる場合、頭部外傷を負わせるという行為自体に、これを直接の原因として死亡する危険性のみならず、胃などの消化器が病変を引き起こし、大量の出血が生じて、ひいては死に至らしめるということについての危険性も当然に内包していると認められるからである
- 本件において、被害者Sが被告人らによって受けた傷害は、それ自体、Sの死亡という結果を惹起する程度の危険性を十分有するくらい非常に重い傷害であった
- そして、Sが、胃の動脈血管が破綻し大量出血を引き起こし、その出血性ショックにより死亡したことは明らかであり、Sが肉体的・精神的ストレスを相当蓄積している状態にあり、他方、Sには、頭部外傷の他に、胃から大量出血を起こす原因として考えられるような既往症などは見当たらないのである
- だとすれば、Sの死亡の結果は、まさに、被告人らの傷害行為によって惹起されたものと認められ、したがって、被告人らの傷害行為とSの死亡との結果の間には刑法上の因果関係が優に認められる
- たとえ、Sが、デュラフォイ潰瘍による大量出血の前提として考えられる胃の血管の走行異常といった特異質であったとし、最善の医療を受けていればSの死亡の結果が発生しなかった可能性があったとしても、こうした事情は、被告人らの傷害行為と相俟ってSの死亡の結果発生を助長させた事情にすぎないから、被告人らの傷害行為とSの死亡の結果との間の刑法上の因果関係が否定されることはない
と判示し、傷害致死罪の成立を認めました。
直接の暴行によらない傷害と傷害致死との間の因果関係を肯定した事例です。
暴行を加えられた被害者が逃げ場を失い、やむなく川に飛び込み溺死した事案で、裁判官は、
- 被告人らは、Dを殴打し又は足蹴にする等の暴行をなし、Dがその場に倒れるや、Aに命じてDを監視させ、その間にEを約20m北方の堤防東側低地に運れ出し、青年団会合の際の連絡が悪いなどと因縁をつけてEの顔面を平手でそれぞれ殴打し、更に同所から約20m離れた河原にEを連行した
- その場所で再び同様詰問を続けようとしたところ、Eは、なおも被告人らから暴行されるものと考え、突然隙をみて、その場から川縁に向かって「bのみなさん助けて下さい」と連呼しながら逃走したので、被告人らのうち、被告人Fは川上から、被告人Gは川下から、被告人HはEの背後から、それぞれ川縁に向い包囲するような体勢をとってEを追跡した結果、Eは逃げ場を失い、やむを得ず川内に飛び込んだため、Eを溺死するに至らしめたことを認めることができるのである
- Eが逃走した川堤防東側斜面から東方川縁までの距離が約100mあり、その川上も、川下もいずれも一面の草生地であるとしても、被告人らが右のように包囲するような体勢をとってEを追跡した状況の下においては、Eが逃げ場を失うことはあり得ないものということはできないし、また原審証人Dの原審公判廷における供述によると、Eも当時飲酒していたことを認めることができるけれども、Eが川堤防東側の河原を川縁に向って走り出した際、飲酒のため誤って川に転落したものと認めるべき証拠はない
- そしてEは、被告人らから暴行を受け、なおも被告人らから危害を受けることを恐れ、これを避けるため、救を求めながら逃走したが、被告人らから包囲体勢をとって追跡された結果、逃げ場を失い、やむなく川に飛び込み溺死したものであるから、Eは被告人らの暴行に関する動作により溺死するに至ったものにほかならないものというべきである
- 従って、被告人らの暴行とEの死亡との間に因果関係があるものと認めるを相当とするのである
と判示し、暴行とEが暴行から逃れるため川に飛び込んで溺死したことの因果関係を認め、傷害致死が成立するとしました。
⑭神戸地裁姫路支部判決(昭和37年7月16日)
暴行を加えられて、その危害を避けるため逃走した者が、追いつめられてやむなく川に飛び込み溺死した事案で、暴行と溺死との間に因果関係を認め、傷害致死が成立するとしました。
裁判官は、
- 被害者としては、客観的には、岸沿いに南方へ逃避する方法はないことはないが、それは、いちじるしく困難であると認められるのみならず、被告人らのような屈強の青年二人から、暴行を加えられ、県道上への退路を断たれたうえ、なおも、追撃の手をゆるめないという態勢を示された場合において、陸上での逃路がないと考え、とっさの判断により、被告人らの暴行からのがれるための唯一の手段として、付近の流水に飛び込み、その結果、増水した川の激流に流され、溺死するに至るべきことは、本犯行の際、経験則上、当然予想し得られる場合に当たるといわなければならない
- しからば、被告人両名の被害者Dに対する暴行と、D死亡の結果との間には、いわゆる因果関係があるから、被告人らは、その結果について傷害致死の罪責を負わなければならない
と判示しました。
⑮大阪高裁判決(昭和41年1月31日)
犯人が、被害者を2階事務所に連れ込み、暴行・脅迫を加え、被害者をしてその危害から身を守るために2階の窓から地上に飛び降りるに至らしめ、その衝撃により傷害を負わせた場合に傷害罪の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- 被害者M子の司法巡査に対する供述調書の記載によると「私がニ階から飛び降りましたのは二人の者に蹴られたり、また、はさみを持って来て坊主にする等言われるし、何度謝ってもゆるしてくれず、このままここに居ればどの様な目にあわさるかも知れないと思ってKに続いて飛び降りたのです」というのであるから、M子は更に加えられんとする被告人らの暴行から身を避けるため唯一の逃げ場所である窓から飛び降り、その結果傷害を負ったということができる
- そして、かように被告人らが被害者を拉致し、不法監禁にも等しい状態において、継続して暴行脅迫を加えた状況の下にあっては、被害者が自己の生命身体をその危害から守るため危険を顧みず脱出を図ることのあることは、実験則上当然予想される事柄であるから、たとえ被告人らにおいて不注意のためM子が窓から飛び降りることを予期しなかったとしても、被告人らの前記暴行脅迫の継続により引き続き加えられる暴行を避けるため、M子を階下路上に飛び降りるの止むなきに至らしめ、その結果、M子に傷害を負わせたものである以上、その暴行脅迫と傷害との間に相当因果関係があり、かつ被告人らに脅迫だけではなく暴行の犯意が認められる本件においては傷害の結果について認識がなくとも、M子の傷害につき刑責のあることはけだし当然であるといわねばならない
- 従って、原判決が被告人両名のM子に対する暴行、脅迫と傷害との間に因果関係の存在を否定し無罪を言渡したのは、事実を誤認したものというほかなく、この点においても原判決は破棄を免れない
と判示しました。
喧嘩して海中でたがいに殴りもみ合ううち、相手方が知らず知らず深みに落ち溺れ死んだ事案で、裁判官は、
- 本件は、被告人と被害者が海中において喧嘩闘争中に、知らず知らず深みに落ち、泳ぎのできない被害者がついに溺死するに至ったもので、深みに落ちるまでの喧嘩闘争中の暴行と溺死との間に因果関係が認められるため、被告人に傷害致死の責を負わすべき事案である
と判示し、暴行と溺死の因果関係を認め、霜害致死が成立するとしました。
⑰広島地裁判決(昭和47年12月20日)
遠洋船上で暴行を受けた被害者が、被告人から逃れるために船体にぶら下がり、その後転落した事案につき、死体未発見で死因が確定できないまま、死亡事実を認め、傷害致死の成立を認めた事例です。
また、海中に転落した被害者の死体が発見されていない点につき、致死の結果を認めた事例です。
裁判官は、
- 弁護人は、被告人の暴行行為と被害者Hが海中に転落、死亡したこととの間には法律上の因果関係がないと主張する
- その要旨は、Hは被告人に追われて船室外に通ずるドアを開けて船上甲板に出たものであるが、同所からは船首方向に通ずる二つの通路があり、また士官室のあるプープデツキに通ずる階段もあって、そのいずれかへ逃走するのが通常であるにもかかわらず敢えて右船ブルワークを越えて船体外にぶら下ったものであり、果して被告人から逃れるためかかる行為に出たものか否か疑問であるのみならず、仮に逃走のためであつたとしても極めて異常なものであり、被告人はもとより通常人の予見可能な範囲を越えた行為であって、被告人にはその結果起こったHの転落および死亡の点については責任を問いえないというものである
- Hは過失により手を滑らせたか、飲酒していたため身体を支えきれず転落したとも考えられるが、隠れて被告人をやり過そうと考えていたにもかかわらず、被告人と顔が合ったため驚いて、あるいは諦めて手を離したものと考えるのが最も自然であると思われる
- しかし、Hは被告人に追われて止むを得ずこのような海中に転落する危険性の極めて高い不安定な場所に逃れたものである以上、手を離した直接の原因が右のいずれであるとしても、なお同人の転落と被告人の暴行行為(追跡行為を含む)との間には法律上の因果関係があるものといわなければならない
- 本件公訴事実は傷害致死であるが、Hの死亡の事実については直接これを証明する証拠がないので右事実の認定につき付言する
- 証拠によれば、Hの転落直後、被告人およびYからの報告にもとづき、ほぼ乗員全員が船長の指示でその後約12時間にわたり付近海上を懸命に捜索したが、ついにHを発見するに至らなかったことが明らかである
- Hがスクリューに巻きこまれて死亡したか、あるいは溺死したか、その死因がいずれであるかは確定しがたいが、Hが死亡した事実は合理的な疑を入れないものと認められる
と判示し、傷害致死罪の成立を認めました。
⑱水戸地裁土浦支部判決(昭和63年12月13日)
被告人の暴行により川に落とされた被害者が、対岸に渡ろうとする途中、嘔吐して窒息死した事案につき、傷害致死罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 弁護人は、被害者が川を渡って対岸に向かった行動は、被害者の自由意思によるもので、被告人の行為によるものではない旨主張するのであるが、当時の川の水温、川幅、水深などをみるだけでも、格別泳ぎが達者ではない被害者が、その自由意思で間近の岸から上がらず、ことさら対岸を目指すことは考えにくいことであり、さらに、被告人による激しい殴打等の暴行と川の中への落下、上陸しようとした際の被告人の妨害、対岸へ向かうように仕向けた被告人の言動等の事情を併せ考えると、被害者が背の立たない川の中央部を敢えて渡ってまで対岸へ行こうとしたのは、右のような被告人による一連の暴行や言動により、被告人のいる側の岸に上がることを断念して対岸へ向かうほかないという心理状態に追い込まれた結果と認めるのが相当であって、弁護人の前記主張は採用できない
- 【被告人の予見可能性】一般的に飲酒により酩酊状態にある者を、寒い季節に冷たい川の中に入れ、相当距離のある対岸まで向かわせれば、途中で水没、溺死することがありうるのは通常十分に予見可能なものといえる
- 本件においても、被害者は酒に酔って、しかも上半身裸となっていたもので、また本件当時の気温や現場付近の川の状況は、被告人も十分認識し、また認識し得たものである
- 加えて、被告人は、再度川の中に落ちた被害者に対岸まで泳いで行くように怒鳴りつけたうえ、着衣を水中に投げつけるなどしているのであるから、被害者が水深が深く背の立たない川の中央部を通って対岸に向かうことは、被告人によって仕向けられたとおりの行動に出たものということができ、その結果、被害者が水没して死亡することも十分にありうることとして予見し得たものと認められ、被告人にとって何ら予見不可能な事態ということはできない。
- 以上認定説示したとおり、被告人による被害者に対する本件暴行等の行為によって、同人の死の結果が生じたものであることは十分に肯認できるものというべきである
と判示し、因果関係と予見可能性を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
⑲大阪高裁判決(昭和44年5月20日)
殴打暴行の結果、仮死状態に陥った被害者を死亡したものと誤信し、犯跡隠蔽の目的で、被害者を水中に投棄して死亡させた事案につき、殴打暴行と死亡との間に刑法上因果関係があるとして傷害致死罪の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- およそ犯人が被害者に暴行を加え、重篤な傷害を与えた結果、被害者を仮死的状態に陥らせ、これが死亡したものと誤信して犯跡隠ぺいの目的で山林、砂中、水中等に遺棄し、よつて被害者を凍死、窒素死、溺死させるに至ることは、自然的な通常ありうべき経過であり、社会通念上相当程度ありうるものであって、犯人の予想しえたであろうことが多いと考えられる
- 本件についても全くこれと同様であって、その直後の死因は溺水吸引による窒息であるが、被告人が被害者を殴打昏倒させて失神状態に陥らせ、そのうえ失神した被害者を死亡したものと誤信して水中に投棄し死亡させたものであるから、被告人の殴打暴行と死亡との間に刑法上因果の関係があることは明らかである
- したがって、被告人の所為は単一の傷害致死罪を構成するものであって、原判決が暴行と致死との間に因果関係がないとして傷害罪の成立のみを認め、かつ水中投棄行為を切り離し過失の有無、程度を審査して過失致死罪あるいは重過失致死罪の成否を問題にしようとするのは、刑法205条の解釈適用を誤ったものであり、この誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない
と判示しました。
相当因果関係説の立場から、因果関係が否定された事例
相当因果関係説の立場から、因果関係が否定された事例として、
岐阜地裁判決(昭和45年10月15日)
被害者が血友病にかかっており、かつ受傷後の処置が適切でなかったため、革靴で蹴られた下腹部及び拳で突かれた頸部の各皮下筋肉内血管の破綻により出血死したのに対し、死亡については因果関係を否定し、傷害罪のみを認めた事例です。
裁判官は、
- 被害者Mは、ひとたび受傷すれば、それが通常人であれば容易に治癒するような軽度の傷害であっても、重大な死亡の結果を招来するという極めて稀な病気の一である血友病に罹患していたもので、Mの死亡については、この血友病が最重要の影響を及ぼし、これに同人とその家族ならびに医師の不注意が加わって不幸な結果を発生させたものと疑う余地が十分に存するのである
- 被害者の死亡に血友病が最重要の影響を及ぼしたもので、被害者が血友病に罹患していた事実を被告人が本件当時知っていた、あるいは知り得るべき状態にあったと認められる証拠は全くない
- そして、Mが血友病に罹患していた事実を、被告人が本件犯行当時知っていた、あるいは知り得べき状態にあったと認められる証拠は全くない
- 従って、被告人の傷害の行為は、Mの死の結果につき、自然的には一の原因として挙げるには足りるが、法律的には因果の連鎖においてはなはだしく遠隔で、及ぼす影響も微少であつて、刑法上の因果関係は肯定するのが困難であり、被告人に致死の点までの責任を負わせることは当を得ないとするのが法の理念に合する
- 従って傷害致死の訴因に対し、傷害罪の成立のみを認めることとする
と判示し、死亡については因果関係を否定し、傷害致死罪は成立せず、傷害罪が成立するとしました。
次回記事に続く
次回の記事では、暴行・傷害と死の結果の因果関係について、
- 暴行と死亡の間に時間的経過がある場合の因果関係の認定
- 死体の発見されない場合の因果関係の認定
- 因果関係の認定に結果の予見可能性は必要ない
について説明します。