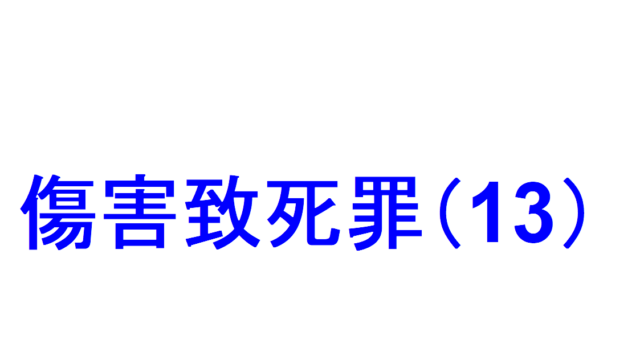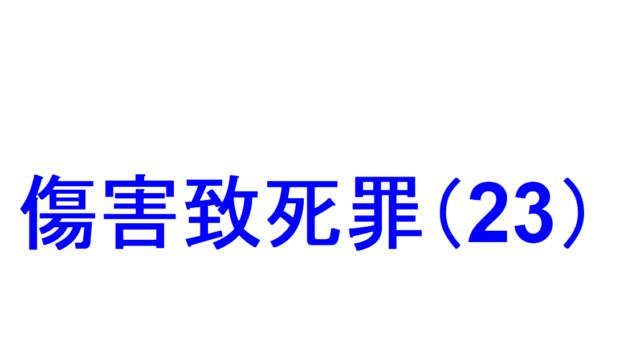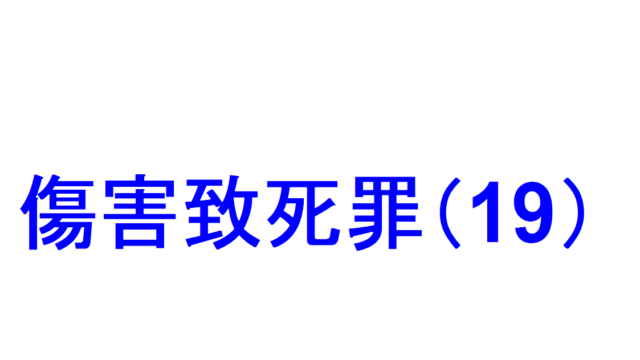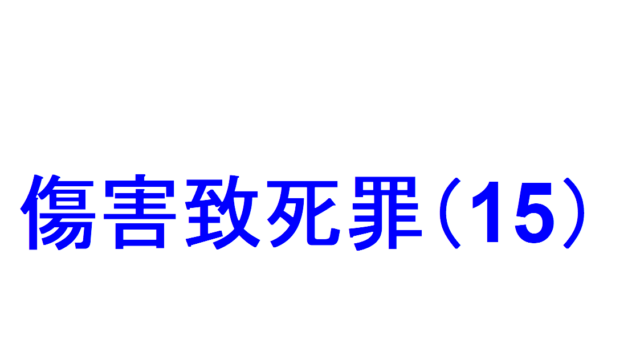前回の記事では、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした大審院判例を紹介しました。
今回の記事では、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした最高裁判例を紹介します。
暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした最高裁判例
暴行・傷害と死の結果の因果関係を認定について、最高裁判例は、前回の記事で紹介した大審院判決と同様、条件説を採用しているといわれています。
しかし、条件説を採用するとしながら、相当因果関係説の考え方を取り入れてた判決が言い渡されています。
以下の判例は、条件説を採用したと評価され、その主要判例とされている判例です
被害者は老人で骨が脆弱である上、多量の飲酒により出血が多く、通常人であれば傷害の程度に至らないものであったとの弁護人の主張に対し、裁判官は、
- ある行為が他の事実と相まって結果を生ぜしめたときでも、その行為と結果の間に因果関係を認めることを妨げない
- ある行為が原因となって、ある結果を発生した場合に、その行為のみで結果が発生したのではなくて、他の原因と相まって結果が発生した場合でも、その行為は結果の発生に原因を与へたものと言ふべきであるから、被害者の体質が普通人よりも脆弱であるために死亡したものだとしても、原判決の認定した被告人の行為は傷害致死の原因となったものだと認定することは正当である
と判示し、 傷害と致死との因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
これは、条件説による判例であると理解されていますが、相手が老人であり、しかも酔っていることを行為者が認識し得たのであれば、相当因果関係が認められる判例であると評価されています。
この判例の翌年、相当因果関係説による思われる以下の判例が出てきました。
被告人が、メチルアルコールを酒の代用品としてAに販売し(これをAがBに飲ませることを分かって販売)、AがこれをBに飲ませ、死に至らしめた事案で、裁判官は、
- 特定の行為に起因して特定の結果が発生した場合に、これを一般的に観察してその行為によって、その結果が発生するおそれのあることが実験法上(経験則上)当然予想し得られるにおいては、たとえ、その間、他人の行為が介入して、その結果の発生を助長したとしても、これによって因果関係は中断せられず、先の行為を為した者はその結果につき責任を負うべきものと解するのが相当である
- 本件において、被告人は、酒の代用として燃料用アルコールを、人体に生理上の障害を与えるおそれのあることを認識しながら、Aに販売したというのであって、当時Aから更にこれを譲り受けて飲用する者のあるべきことは、一般的に観て当然予想し得られるところであるから、事実、Aから右アルコールを譲り受けて飲用したBがその中毒によって死亡した以上、被告人が右Bの飲用の事実を予見したと否とに関係なく、被告人としてBの傷害致死の結果につき責任を負はねばならない
と判示し、メチルアルコールを酒の代用品として販売した場合、相手方から譲り受けて飲用する者のあることは、一般に当然予想できるとして、その者の死亡につき傷害致死罪の成立を認めました。
そして、この判例の次に出た判例は、条件説を採用した判例でした。
通常であれば10日くらいで治癒する傷害を負わせたところ、たまたま被害者が高度の脳梅毒にかかっていたため、外傷が脳組織の破壊をもたらし、死亡するに至った事案において、裁判官は、
- 被告人が被害者の脳梅毒という特殊事情のあることを知らず、また予測もできなかったとしても、その特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときは、その行為と結果の間に因果関係を認めることができるのである
と判示し、傷害致死罪の成立を認めました。
この判決で用いられた表現は、典型的な条件説的説示であり、傷害と致死の因果関係について、条件説の考え方に従ったものと理解されています。
この判例の次の判例では、相当因果関係説に立つと読めるような判例となっています。
最高裁判決(昭和25年11月9日)
被告人の暴行を避けようと逃げ出す途中に被害者がつまずいて転倒して負傷した事案について、因果関係を認めました。
裁判官は、
- 被告人が被害者に対して大声で「何をボヤっとしているのだ」等と悪口を浴せ、矢庭に拳大の瓦の破片を投げつけ、なおも「殺すぞ」等と怒鳴りながら側にあつた鍬を振りあげて追いかける気勢を示したので、被害者がこれに驚いて難を避けようとして夢中で逃げ出し、走り続けるうち、過って鉄棒につまづいて転倒し、打撲傷を負った場合には、傷害の結果は被告人の暴行にって生じたものと解するのが相当である
旨判示し、暴行と傷害の結果との間に因果関係があると認め、傷害罪が成立するとしました。
上記2つの判例から分かるように、最高裁は、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認定するに当たって、最高裁判例は、条件説を採用しつつ、相当因果関係説の考え方にも立つという立場をとっているといえます。
その後の最高裁判例は、以下のようになっています。
仰向けに引き倒して馬乗りとなり両手でその頸部を圧迫したところ、被害者が心臓肥大、特異体質等であったため、ショック死したとの事実を認め、因果関係を肯定しました。
裁判官は、
- 被告人のAに対する頸部圧迫の暴行が間接的誘因となり、同人のショック死を惹起した事実は明らかで、その間に間接的ながら因果関係が認められる
- そして、傷害罪の成立には暴行と死亡との間に因果関係の存在を必要とするが、致死の結果についての予見を必要としないことは当裁判所の判例とするところであるから(昭和26年9月20日判決)、因果関係の存する以上、被告人において致死の結果をあらかじめ認識することの可能性ある場合でなくても、被告人の所為が傷害致死罪を構成することはいうまでもない
と判示し、傷害致死の成立を認めました。
②最高裁判決(昭和32年3月14日)
両手掌で被害者の顔面を殴打したところ、被害者には脳底部動脈硬化症があり、その上、当日の飲酒によって脳血管の血圧上昇を来たしていた被害者をして蜘蛛膜下腔出血に基づく脳圧迫により死亡させたという事案において、裁判官は、
と判示し、傷害致死罪の成立を認めました。
被害者の着衣の襟を両手でつかんで強く首を締めつけたうえ、突き飛ばして、仰向けに転倒させるなどの暴行を加え、心筋梗塞のため死亡させた事案において、裁判官は、
- たとえ、被害者の心臓に高度の肥大等の高度重篤な病変があったとしても、被告人の暴行と被害者の死亡との間に因果関係が存する
と認め、傷害致死罪が成立するとしました。
この判例は、他人の行為の介入があった場合に刑法上の因果関係が否定された事例です。
自動車を運転していた甲が、自転車で通行中の乙と衝突し、乙を自車の屋根の上にはね上げたまま走行中、これに気づいた同乗者丙が、乙の身体をさかさまに引きずり降ろし、舗装道路上に転落させた場合において、乙が右自動車との衝突および右道路面への転落等によつて頭部等に傷害を負い、右頭部の打撲に基づく脳くも膜下出血等によつて死亡したときは、甲の前記過失行為と被害者の死との間に、刑法上の因果関係があるとはいえないとしました。
裁判官は、
- 同乗者が進行中の自動車の屋根の上から被害者をさかさまに引きずり降ろし、アスファルト舖装道路上に転落させるというがごときことは、経験上、普通、予想しえられるところではない
- ことに、本件においては、被害者の死因となった頭部の傷害が、最初の被告人の自動車との衝突の際に生じたものか、同乗者が被害者を自動車の屋根から引きずり降ろし路上に転落させた際に生じたものか確定しがたいというのであって、このような場合に被告人の過失行為から被害者の死の結果の発生することが、われわれの経験則上、当然予想しえられるところであるとは到底いえない
- したがって、原判決が右のような判断のもとに、被告人の業務上過失致死の罪責を肯定したのは、刑法上の因果関係の判断をあやまった結果、法令の適用をあやまったものというべきである
- しかし、本件では、被告人は、道路交通法72条1項前段、117条の救護義務違反の刑によって処断されているのみならず、業務上過失致死と業務上過失傷害の法定刑は同一であり、被告人の刑責が業務上過失傷害にとどまるにしても、本件犯行の態様等からみて、一審判決のした量刑は不当とは認められないから、右あやまりは、いまだ原判決を破棄しなければ、著しく正義に反するものとはいえない
と判示し、被告人である自動車運転者に対し、被害者に衝突した行為と致死との間の因果関係は認められないとし、業務上過失致死罪ではなく、業務上過失傷害罪を認定しました。
⑤最高裁判決(昭和46年6月17日)
心臓に疾患のある64歳の老女に対し、その顔面をふとんでおおい、頸部を絞めるなどの暴行を加え、その結果、急性心臓死に致らしめた事案で、相当因果関係説によることを明示して被告人の暴行と致死の結果との間の因果関係を否定した二審判決を判例違反として破棄し、
- 致死の原因たる暴行は、必ずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に高度の病変があったため、これとあいまって死亡の結果を生じた場合であっても、右暴行による致死の罪を妨げない
旨判示し、条件説に近い見解を示し、傷害致死罪の成立を認めました。
被告人が被害者を地上に突き倒し、被害者の大腿部・腰部などを地下足袋で数回踏みつけるなどの暴行を加え、同人に対し左血胸部等の傷害を負わせたところ、治療のため医師が投与した薬剤の作用により、かねて同人の体内にあった未知の結核性病巣が変異して左胸膜炎を起こし、 これに起因する心機能不全のため同人が死亡した場合において、被告人の暴行と被害者の死亡との間には因果関係があるとしました。
被害者に病変のあることが知られていなかったとしても、被害者が81歳の高齢者である以上は、外面上は健康体に見えても、少なくとも一旦受傷すると何らかの余病を併発するおそれのあることは、通常、予見し得る場合に該当するといえます。
この判例で、裁判官は、
- 本件被害者の死因となったくも膜下出血の原因となった頭部擦過打撲傷が、たとえ、被告人及び共犯者2名による足蹴り等の暴行に耐えかねた被害者が逃亡しようとして池に落ち込み、露出した岩石に頭部を打ちつけたため生じたものであるとしても、被告人ら3 名の右暴行と被害者の右受傷に基づく死亡との間に因果関係を認めるのを相当とした原判決の判断は、正当である
と判示し、条件説の考え方で、傷害と致死との因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
頭部を殴打して脳出血による意識不明となった被害者を資材置場に運んで放置したところ、その後、死亡までの間に、何者かが頭部を殴打したという事案で、裁判官は、
- 犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後、第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる
と判示し、傷害と致死との因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
公園内及びマンション居室内で暴行を受けた被害者が、すきをみて逃走し、被告人らによる追跡を逃れるためにマンション付近の高速道路に進入し、進行してきた自動車に衝突、礫過されて死亡した事案で、裁判官は、
- 被害者が逃走しようとして高速道路に進入したことは、それ自体極めて危険な行為であるというほかないが、被害者は、被告人らから長時間激しくかつ執ような暴行を受け、被告人らに対し、極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で、とっさにそのような行動を選択したものと認められ、その行動が、被告人らの暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえない
- そうすると、被害者が高速道路に進入して死亡したのは、被告人らの暴行に起因するものと評価することができるから、被告人らの暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定した原判決は、正当である
と判示し、暴行と致死との因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
この判例で、裁判官は、
- 被告人らの行為により被害者の受けた傷害は、それ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であって、仮に被害者の死亡の結果発生までの間に、被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、被告人らの暴行による傷害と被害者の死亡との間には因果関係があるというべきである
と判示し、傷害と致死との因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
次回記事に続く
次回の記事では、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした下級審判例を紹介します。