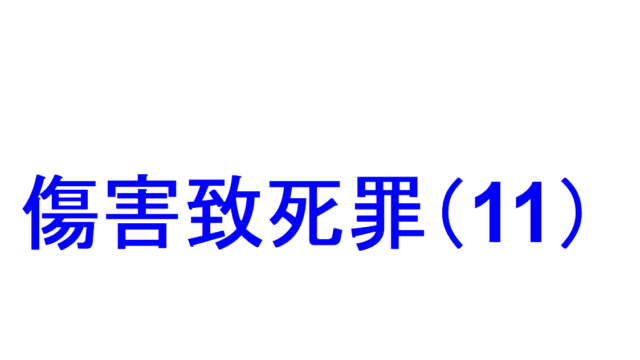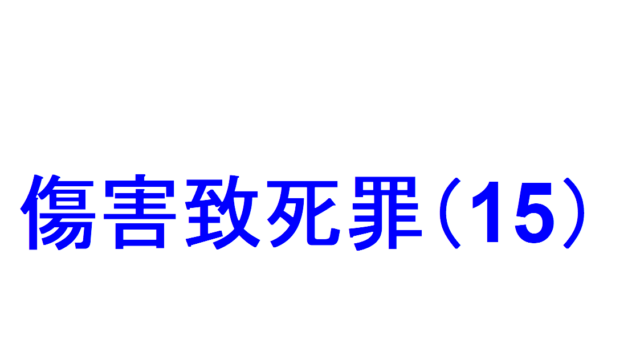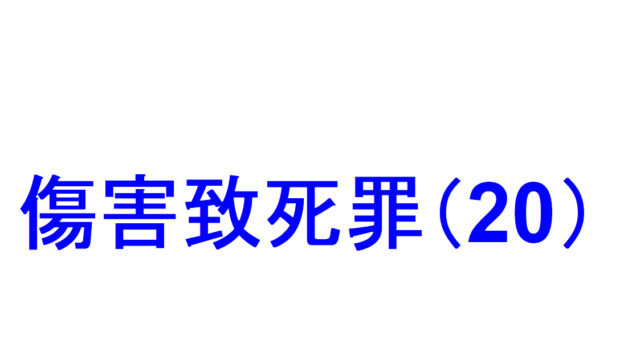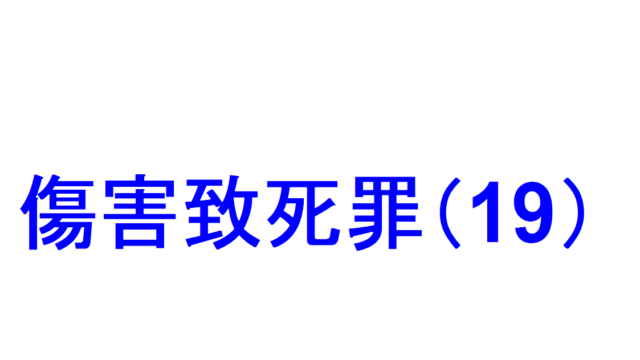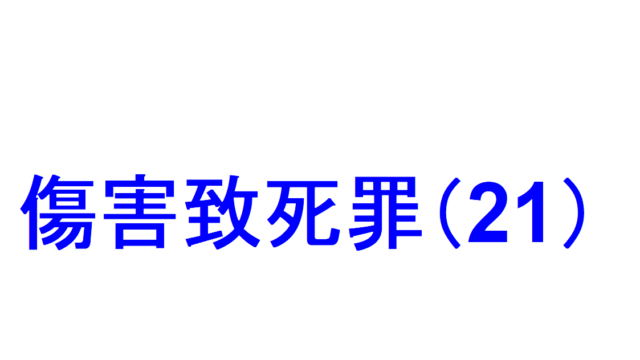前回の記事では、違法性阻却事由である「私的領域における行為(家族内トラブル)」について説明しました。
今回の記事では、違法性阻却事由である「懲戒権の行使(監督者による罰)」について説明します。
懲戒権の行使(監督者による罰)の違法性阻却
懲戒目的に出た有形力の行使であっても、死亡の結果を生ずるようなものが、正当な懲戒権の行使として社会通念上相当な範囲のものであると認められるケースは想定しえません。
なので、傷害致死罪において、懲戒権の行使(監督者による罰)として違法性が阻却され、無罪が言い渡されることはないでしょう。
傷害致死罪において、懲戒権の行使が争点となった事例として、以下の判例があります。
東京高裁判決(昭和35年2月1日)
親権者の、5歳の子に加えた暴行が、監護教育権又は懲戒権の行使とは認められないとされた事例です。
裁判官は、
- 被害者Tの性格挙動に不満をもった被告人が、子が昼寝中、小便をしたことを素直に言わなかったことに憤慨し、またT子が風呂から上がってからもぼんやりと裸のまま風呂場の脇の廊下に立っていたことに激昂して、T子に対して、かずかずの暴行を加えたことは、まことに明らかである
- その動機において、T子の親権者として、専らT子の性格、動作習癖などを矯正しようとする監護教育的配慮に出たものであるというがごとき事実は認められない
- 従って、Tに対する深い愛情によって支えられた所為であったとは、とうてい、いい得ないところである
- 仮りに、被告人が、終始T子に対する親権者として、いわゆる懲戒権を行使する意図に出でたものであるとしても、それにはおのずから限度があり、社会通念上正当と認められる程度並びに範囲のものでなければならないことは、あえて言うまでもない
- しかるに、被告人は、当時5歳のT子に対して、板の間及び風呂場に突き倒し、さらに手でその顔面及び臀部を殴打し、さらに裸にして浴槽内に頭まで押し込み、はては風呂から上ってぼんやりと裸のまま風呂場の廊下に立っているT子を後から突き倒すなどの所為に及んだのであって、かくのごときは、まさにT子に対する懲戒権の行使として正当な範囲を越えた処置であり、社会通念上許すべからざる行為であるというのほかない
- 従って、違法性を阻却すべきわけのものではない
- ところで、親権者が監護教育権又は懲戒権の行使としての程度を超えたために、子に傷害の結果を生ぜしめた場合に過失傷害罪の成立を認むべき事案もあるであろうけれど、本件はこれと異り、被告人は当初より暴行の意思に出でて致死の結果を惹起させたのであるから、被告人の責任たるや過失犯をもって論ずべき筋合ではない
と判示し、5歳の子に対して暴行を加えて死亡させた行為が、愛情に支えられ、監護教育的配慮に出た行為であるとは認められないとして、違法性を阻却せず、傷害致死罪が成立するとしました。
京都地裁判決(昭和47年1月26日)
継母の継子に対する懲戒権を認めたが、頭部を手挙(しゅけん)で強打するなどして、死亡させた懲戒行為は、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱しているとされた事例です。
裁判官は、
- 被告人は、被害児童Aの継母として、姻族一親等の関係にあり、しかも、夫Tと結婚して以来、児童Aとも同居し、実際上、母親としての立場で、現実に児童Aを監護教育していたのであるから、これらの事情に照らし合わせれば、被告人は、夫Tより、児童Aに対する親権行使を補助する権限を委託されていたと認めるべきである
- したがって、児童Aに対し、これが懲戒権を有していたものと解するのが相当である
- ところで、およそ親権を行う者は、その子の悪癖等を矯正するため殴る、ひねるなど適宜の手段方法を用いて、その身体に対し、ある程度の有形力を行使する等の措置に出ることは、法が親権者に懲戒権を認めた趣旨に鑑みて許されるものと解すべきである
- しかし、その手段方法や程度は、その親子の境遇、子の年令、性格、体質、悪癖の種類および態様等個々の具体的事情に依拠して、社会通念上相当と認められる範囲のものでなければならない
- 児童Aが、いつものように理由もなく、めそめそ泣きだしてやまないからといって、当時わずか満4歳になったばかりの身体虚弱児に対し、その悪癖等を矯正するためとはいえ、判示のような部位にその方法および程度の暴行を加えたことが、果して子に対する懲戒権行使の許された範囲にとどまるものと称しうるであろうか
- この点について、医師K作成の鑑定書等関係資料を総合すると、被告人の児童Aに対する左側頭部の殴打行為は、大脳右半球脳硬膜下出血および大脳くも膜下出血等を生じさせ、死の結果を招来するに至った程度の強打であったことが推認されるのであるから、このような身体虚弱児に対する頭部に加えられた手拳による3、4回にわたる殴打行為は、正当な懲戒権行使としての範囲を逸脱したものと認めるのが相当である
- したがって、被告人の本件行為が、刑法上違法性を有することは明白といわなければならない
と判示し、傷害致死罪の成立を認めました。
横浜地裁川崎支部判決(昭和62年8月26日)
教師の生徒に対する体罰による死亡事案において、傷害致死罪の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- 本件は、小学校の教諭である被告人が、自らの担任する特殊学級に通級していた8歳の児童の頭部を数回殴打する暴行を加え、死亡させたという事案である
- 被告人は、被害児童に、書初め展に展示する予定の作品を書かせようと指導していた際に、同児がこれに従わなかったことに立腹すると同時に、同児に対し、強く指導することが必要であると考え本件犯行に及んだもので、純粋に教育的懲戒を加える目的で行ったものとは認められず、私的感情を加えたうえ、怒りにまかせて暴行を加えたものである
と判示し、教育的懲戒の目的でなく、怒りにまかせた暴行であると認定し、傷害致死罪の成立を認めました。
福岡高裁判決(平成8年6月25日)
教師が高校の女性生徒に暴力を振るい、死亡させた事案です。
裁判官は、
- 被告人が被害者に暴行を加えるに至った経緯及びその態様についてみると、右関係各証拠によれば、平成7年7月17日当時、被告人は学校法人K大学附属女子高等学校で商業簿記を担当し、2年1組の副担任をしていた教諭であり、被害者は同校2年1組の生徒であったこと、被告人は一学期の簿記のテストで所定の成績に達していなかった2年1組の生徒を対象として正規のカリキュラムには属しない再々テストをすることを考え、同日放課後の午後3時40分から2年1組の教室において被告人の監督の下でこれを実施したこと、被害者は右テストを受けなければならない対象者に含まれていなかったが、同テストが始まったとき教室内の自分の席に座っていて、下校時の身だしなみのために机の上に鏡を立てて櫛で髪の毛をといていたこと、これを見つけた被告人は被害者に「早く帰らんか」と言い、すぐに被害者が立ち上がらなかったことから被害者の席に近寄り重ねて同様のことを申し向けたこと、これに対し、被害者は「わかっちょうちゃ」と答え、カバンを肩にかけて教室の後ろの出口に向かって歩いていったが、出口近くの教室の壁に設置されていた鏡の前で立ち止まり再びそこで髪を両手で整えるような仕草をしたこと、その際、被害者のスカートのウエスト部分が外側に折り返されているのが見え、このような方法でスカー卜丈を短くすることは校則で禁止されているところから、被告人は「お前スカートを折り曲げちょろうが、下ろせ。早くおろさんか。」などといって、教室から出ようとしていた被害者の背中を押したため、被害者は教室の出入口付近で四つんばいの形で倒れ、肩にかけていたカバンが床に落ち、在中のエチケットブラシ等が廊下に散乱したこと、倒れた被害者はすぐに立ち上がって被告人に対し、「そんなんしたら、直されんやん」などといいながら教室から廊下に出ると、被告人は「何ちや」といいながら被害者を押すようにして続いて廊下に出たこと、廊下で被告人は被害者と向き合って立った状態で、肩より高く腕を振り上げて被害者の頬付近を平手で数回殴打し、叩かれて後ずさりする同女の肩部付近を突いたところ、同女は窓に設置された鉄製の手すりに後頭部を打ちつけ、同女が被告人の更なる暴行を避けようとして被告人の身体を押し返すようにすると、更に同女の右側頭部付近を下から上に突き上げたため、同女はコンクリートの柱に頭頂部あたりをぶつけた上、廊下の床上に倒れ顔面蒼白となって失神し、翌18日午後2時37分収容先の病院で急性脳腫脹のため死亡したこと、以上の各事実が認められる
- 生徒に対する懲戒権について定めた学校教育法11条がただし書で体罰を禁止しているのは、体罰がとかく感情的行為と区別し難い一面を具有している上、それらを加えられる者の人格の尊厳を著しく傷つけ、相互の信頼と尊敬を基調とする教育の根本理念と背馳し、その自己否定につながるおそれがあるからであって、問題生徒の数が増え、問題性もより深化して教師の指導がますます困難の度を加えつつある原状を前提としても、その趣旨は学校教育の現場において、なによりも尊重、遵守されなければならないことはいうまでもない
- ましてや、生徒が反抗的態度を取ったからといって、教師が感情的になって暴行を振るうことは厳に戒められるべきことである
- 被告人の本件における暴行は、被害者が被告人の指導に直ちに素直に従わなかったという事情かあるにしても、それ以上に出て教師に対して実力をもって反抗したような事情は認められず、せいぜい被告人に突き転ばされた被害者が「そんなんしたら、直されんやん」と抗議し、更に加えられた暴行を被害者か避けようとして被告人を押し返すようにした事情が窺われるだけであるのに、被告人はこれを反抗的態度と受け取り、「なめられてたまるか」という気持ちから被害者に対し一方的に暴行を加えたものであって、当初の目的は正当であったかも知れないが、その手段方法は被害者を突き転ばした以降は明らかに正当性の範囲を逸脱していた上、被害者との対応の過程でその当初の目的すら忘れ去り、遂には教育の名に値しない私憤に由来する暴行に終わったもので、まさしく違法な体罰であったといわなければならない
と判示し、被告人の暴行は懲戒行為とは認められず、違法性を阻却せず、傷害致死罪が成立するとしました。
名古屋高裁判決(平成9年3月12日)
ヨットスクールの校長やコーチらが、スパルタ式のヨット訓練などを生徒に対して行った結果、生徒らが死亡したり行方不明になるなどしたことにつき、校長らに対し、傷害致死、監禁致死、監禁致傷、監禁、傷害、暴行、暴力行為等処罰に関する法律違反、強要罪の成立を認めた事例です(戸塚ヨットスクール事件)。
裁判官は、
- 情緒障害児等の治療等を目的とするヨット訓練に際し、逃走した訓練生に対する制裁等の体罰があまりにも過酷かつ危険であり、健全な社会通念上到底許容される余地はない
と判示し、正当業務行為として違法性を阻却しないとし、傷害致死罪等の成立を認めました。
次回記事に続く
次回の記事では、「治療行為」に関する違法性阻却について説明します。