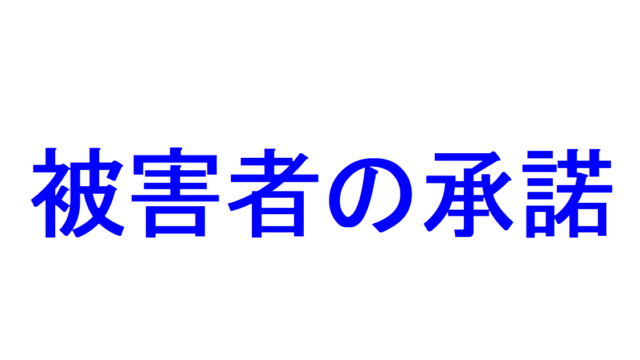前回の記事では、故意(犯罪を犯そうとする意志)について説明しました。
故意がなければ、犯罪行為を行っても無罪になります。
そして、故意があると認定するためには、犯罪事実の認識・容認が必要になります。
しかし、ときに、犯人が認識していた犯罪事実と、実際に発生した犯罪事実が食い違う場合があります。
これを『事実の錯誤』といいます。
たとえば、
夫を殺すつもりで食事に毒をもったのに、友人が毒をもった食事を食べてしまい、友人を殺してしまった…
というケースの場合、犯人が認識していた犯罪事実と、実際に発生した犯罪事実とが食い違うので、『事実の錯誤』となります。
『事実の錯誤』が起こった場合、犯罪の故意は認められるのでしょうか?
今回は、『事実の錯誤』について詳しく説明します。
事実の錯誤とは?
事実の錯誤とは、
犯罪の行為者が認識・容認していた犯罪事実と、実際に発生した犯罪事実とが食い違うこと
をいいます。
事実の錯誤が起こった場合、
故意(犯罪を犯そうとする意志)が認められるかどうか
という争点が生まれます。
この争点が重要になる理由は、故意(犯罪を犯そうとする意志)が認められなければ、犯罪は無罪になるからです。
「事実の錯誤」の種類
「具体的事実の錯誤」と「抽象的事実の錯誤」
事実の錯誤は、
- 具体的事実の錯誤
- 抽象的事実の錯誤
に分類できます。
具体的事実の錯誤とは?
具体的事実の錯誤とは、
Aを殺すつもりだったのに、Bを殺してしまった…というように、同一構成要件内の錯誤
をいいます。
この場合、殺す相手は間違ってしまったものの、殺人罪を犯したことに間違いはないので、殺人罪という「同一構成要件内」における錯誤になります。
抽象的事実の錯誤とは?
抽象的事実の錯誤とは、
物を壊すつもりであったが、対象物が物ではなく、人であり、人を殺してしまった…というように、異なる構成要件間の錯誤
をいいます。
たとえば、器物損壊罪(物を壊す)を犯すつもりで、殺人罪(人を殺す)を犯してしまった場合、器物損壊罪と殺人罪は、構成要件が異なるので、抽象的事実の錯誤になります。
まとめると、
- 具体的事実の錯誤は、同一構成要件内の錯誤
- 抽象的事実の錯誤は、異なる構成要件間の錯誤
と考えればOKです。
「客体の錯誤」「方法の錯誤」「因果関係の錯誤」
事実の錯誤は、錯誤がどの要素に対して起こっているかで、
- 客体の錯誤
- 方法の錯誤
- 因果関係の錯誤
に分類されます。
客体の錯誤とは?
客体の錯誤とは、
Aを殺すつもりだったのに、人違いをしてBを殺してしまった…
というように、犯罪行為の客体に錯誤があった場合の錯誤
のことをいいます。
方法の錯誤とは?
方法の錯誤とは、
Aを殺すつもりで拳銃を発砲したが、Aの近くにいたBに弾が当たってしまい、Bを殺してしまった…
というように犯罪行為の向き・方向に錯誤があった場合の錯誤
のことをいいます。
因果関係の錯誤とは?
因果関係の錯誤とは、
Aを殺そうと思って首を絞めた。死んだと思ったので屋外に放置したところ、実は死んでおらず、屋外に放置したことで凍死した…
というに、犯罪行為者が認識していた因果関係の経路と、実際に発生した因果関係の経路との間に食い違いがあった場合の錯誤
のことをいいます。
結局、「事実の錯誤」が起こると犯罪の故意は阻却され、無罪となるのか?
ざっくりした結論をいうと、
「事実の錯誤」を起こして犯罪を実現したとしても、故意(犯罪を犯そうとする意志)を阻却せず、犯罪が成立する
となります。
「事実の錯誤」を起こしても、犯罪の故意はしっかりと認められ、無罪ではなく、有罪になります。
「事実の錯誤」を起こしても、故意が阻却されな理由
1⃣ Aを殺すつもりが、人違いをしてBを殺してしまった場合(客体の錯誤)
2⃣ Aを殺すつもりで拳銃を発砲したが、弾丸がそれて、近くにいたCに当たり、Cを殺してしまった場合(方法の錯誤)
3⃣ Aを溺死させようとして、橋の上から川に投げ込んだが、水面にあったボートにぶつかり、頭部打撲により死亡した場合(因果関係の錯誤)
といった殺人罪の例で考えてみると、殺人罪の構成要件である「人を殺した」という点においては、認識と現実に発生した事実は一致しています。
そこで、法は、殺した相手が誰であるかは重要ではなく、人を殺したこと事態が重要であると考えるので、殺人罪の故意を認めるという結論を導くのです。
このような考え方で、「事実の錯誤」を起こしても、故意は阻却されないという結論になります。
「人を殺すな」というルールを破って人を殺したのであるから、犯罪行為者は非難されるべきであり、故意責任を問うべきだという考え方になるのです。
ちなみに、このような考え方を「法定的符合説」といいます。
法定的符合説とは?
法定的符合説とは、
- 故意があるとするためには、犯罪行為者の認識した内容と、現実に発生した事実とが、具体的に符合していることは必要ではない
- 認識した事実と発生した事実とが、構成要件を同じくする限り、「客体の錯誤」と「方法の錯誤」であるとを問わず、故意を阻却せず、犯罪を成立させる
- 「因果関係の錯誤」については、認識した因果関係の経路(溺死)が、現実に発生した因果関係の経路(頭部打撲による死)の範囲内にあるなら、同一構成要件内の錯誤となるので、故意を阻却せず、犯罪を成立させる
という説です。
判例(最高裁 昭和25年7月11日)も、
犯罪の故意ありとするには、必ずしも犯人が認識した事実と、現に発生した事実とが、具体的に一致(符合)することを要するものではなく、両者が犯罪の類型(定型)として規定している規範において一致(符合)することをもって足りる
としています。
法定的符合説は、法律が禁止すること(規範)に直面したのに、敢えてそれを乗り越えて犯罪行為に及んだことに対して犯罪行為者を非難します。
例えば、殺人罪でいえば、「人を殺すな」という規範に直面したのに、敢えて人を殺したのであるから、殺す相手が間違ったとしても、行為者を非難し、刑事責任を問うことができるという考え方になります。
判例は、法定的符合説の考え方と採っているとされます。
法律が禁止しているのは、人を殺すことであって、誰を殺すかではありません。
このような考え方から、具体的事実の一致ではなく、規範(ルール)の一致を重視する「法定的符合説」の立場を採る判例の立場は妥当といえます。
なお、「法定的符合説」に相対する考え方として「具体的符合説」という考え方があります。
具体的符合説とは?
具体的符合説とは、
犯罪行為者の認識した内容と、現実に発生した事実とが、具体的に符合していることが必要であり、この具体的符合がなければ、故意を阻却する
という説です。
たとえば、
Aを殺すつもりで拳銃を発砲したが、弾丸がそれて、近くにいたCに当たり、Cを殺してしまった(方法の錯誤)
という「方法の錯誤」の例の場合、具体的符合説では、
- 現実に存在するのは、「Aを殺害する故意」であって、「Cを殺害する故意」ではない
- にもかかわらず、Cに対する殺人罪の成立を認めるのは、存在しない故意を存在するものとして擬制している
という考え方が採用されます。
具体的符合説では、狙いどおりの結果が発生しなかったのだから、認識したところと、発生した結果は、具体的に一致していないので、殺人罪の故意は阻却するという考え方になります。
(ただし、この場合、殺人罪は成立しないものの、Aに対する殺人未遂罪と、Cに対する過失致死罪が成立します)
なお、
Aを殺すつもりが、人違いをしてBを殺してしまった(客体の錯誤)
という「客体の錯誤」の例の場合は、人違いだとしても、狙った対象のBを殺すという
狙いどおりの結果
が発生しているので、故意を阻却せず、殺人罪が成立することになります(ややこしいですが…)。
いずれにしても、具体的符合説の考え方は優位に立ちません。
法定的符合説の「認識と発生した結果は、具体的事実の一致ではなく、規範(ルール)が一致していれば足りる」という考え方が優位に立ちます。
過剰結果の発生
たとえば、
Aを殺すつもりで拳銃を発砲し、弾丸がAを貫通し、Aの後ろにいたBにも命中して、AとBの両方を殺してしまった状況
を「過剰結果の発生」といいます。
過剰結果が発生したことで、予期せずにBも殺してしまった場合、Bに対する殺人罪の故意が認められ、Bに対する殺人罪が成立するでしょうか?
このような事案に対しては、殺人罪が成立するという結論が判例で出ています。
事件の内容
警察官から拳銃を奪おうとして、歩道上で、警察官に対し、建設用びょう打銃を発射した。
弾丸は、警察官に命中し、警察官にケガをさせた上、警察官を貫通して歩道を歩いていた通行人にも命中してケガをさせた。
判決の内容
裁判官は、
- 犯罪の故意があるとするためには、罪となるべき事実の認識を必要とするが、犯人が認識した罪となるべき事実と、現実に発生した事実とが、必ずしも具体的に一致することを要しない
- 両者が法定の範囲内で一致することをもって足りる
- 人を殺す意志のもとに殺害行為に出た以上、犯人の認識しなかった人に対して結果が発生した場合にも、殺人の故意があるというべきである
と判示しました。
次回
次回は、
物を壊すつもりであったが(器物損壊罪)、対象が物ではなく、人であり、人を殺してしまった(殺人罪)…
というように、異なる構成要件間における錯誤(抽象的事実の錯誤)があった場合の故意の成立について説明します。