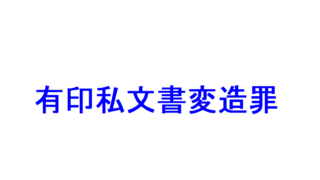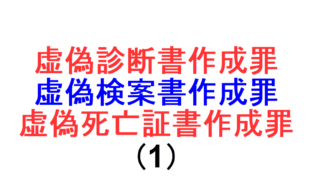無印私文書偽造・変造罪~「無印私文書偽造罪、無印私文書変造罪とは?」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、無印私文書偽造罪、無印私文書変造罪(刑法159条3項)を説明します。
無印私文書偽造罪、無印私文書変造罪を適宜「本罪」といって説明します。
無印私文書偽造罪、無印私文書変造罪とは?
無印私文書偽造罪、無印私文書変造罪は、刑法159条の第3項に規定があり、
第1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する
第2項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする
第3項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する
と規定されます。
罪名
第1項の罪名は「有印私文書偽造罪」となります。
第2項の罪名は「有印私文書変造罪」となります。
第3項の罪名は「無印私文書偽造罪」「無印私文書変造罪」となります。
法定刑
有印私文書偽造罪(第1項)、有印私文書変造罪(第2項)の法定刑は「3月以上5年以下の拘禁刑」です。
無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪(第3項)の法定刑は「1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」です。
有印私文書偽造罪(第1項)、有印私文書変造罪(第2項)は、無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪(第3項)より重く処罰されます。
これは、他人の印章・署名のある私文書の方がそれらを欠く私文書に比べて高い信用性が認められるためです。
客体
1⃣ 本罪の客体は、
他人の印章及び署名のない権利、義務又は事実証明に関する文書、図画(とが)
です。
2⃣ 刑法159条3項の条文中にある「前二項に規定するもののほか」とは、
他人の印章及び署名のないこと
を意味します。
印章又は署名のどちらかがあるときは、本罪(第3項)は成立せず、前二項(有印私文書偽造罪:第1項、有印私文書変造罪:第2項)の罪が成立します。
3⃣ 権利、義務又は事実証明に関する文書、図画とは、重要性のある文書を意味するので、名義人の印章も署名もないものはそう多くはありません。
判例に認められたこの種の文書の例として、
- 銀行の出金票(大審院判決 明治43年2月10日)
- 銀行の支払伝票(大審院判決 大正3年4月6日)
- 他人の署名をした封筒に封入した、署名のない文書(大審院判決 明治42年3月25日)
- 製造会社名のある焼酎瓶に貼付された、作成名義の表示されていない酒精含有飲料証のペーパー(大審院判決 昭和7年5月23日)
があります。
4⃣ 文書、図画は、それ自体、あるいはそれに密接に付随する物体から、その作成名義のうかがわれるものでなければなりません。
これに関連し、封筒に他人の署名を偽造し、その中に署名のない私文書を封入したときは、両者相まって一個の私文書となるとみるべきでなく、私印偽造罪(刑法167条1項:署名偽造)及び無印私文書偽造罪が成立すると解すべきであるとした判例がります。
大審院判決(大正11年10月16日)
裁判所は、
- 他人の署名なき事実証明に関する文書を偽造し、これを他人の署名を偽造したる封筒に入れて行使したる場合に、その偽造は刑法第159条第1項に規定する一罪を成すものに非ずして、前者は同条第3項、後者は同法第167条第1項に該当す
と判示しました。
なお、この判例に対して、学説では、一体として観察して署名ある文書偽造罪一罪が成立するとすべきであるとする見解があります。
5⃣ 代理・代表権のない者が権限ありと偽って文書を作成した場合、本条(刑法159条)にいう印章・署名は本人(当該文書の作成名義人)のものをいうので、本人の印章・署名を冒用していない場合は、無印私文書偽造罪に当たると解されています。
この点に関する以下の判例があります。
学校理事会を代理・代表する権限のない者が、これを代表するものと誤信させるに足りる「議事録署名人」という資格を冒用して、自己の署名・捺印をもって理事会名義の議事録を作成した事案です。
裁判官は、
- 右のような、いわゆる代表名義を冒用して本人名義の文書を偽造した場合において、これを刑法159条1項の他人の印章もしくは署名を使用していたものとするためには、その文書自体に、当該本人の印章もしくは署名が使用されていなければならない
として、右文書に理事会の印章や署名が使用された証跡のない当該事案の場合は、第3項の無印私文書偽造罪に該当するとしました。
行為
偽造、変造は、行使の目的を持って行われることを要します。
偽造・変造の概念については、以下の有印私文書偽造罪(第1項)、有印私文書変造罪(第2項)の記事で説明しています。
偽造の概念の記事
有印私文書偽造罪(5)~行為①「『他人の印章・署名を使用して』とは?」「『偽造した他人の印章、署名を使用して』とは?」を説明
有印私文書偽造罪(6)~行為②「『行使の目的』とは?」を説明
有印私文書偽造罪(7)~行為③「私文書偽造の「偽造」とは?」を説明
有印私文書偽造罪(8)~行為④「偽造文書を作成するに当たり、文書の名義人の承諾があった場合の私文書偽造罪の成否」を説明
有印私文書偽造罪(9)~行為⑤「名義人の承諾があっても私文書偽造罪が成立する場合の共同正犯(共犯)の成否」を説明
有印私文書偽造罪(10)~行為⑥「代理・代表資格を冒用して文書を作成した場合、文書偽造罪が成立する」を説明
有印私文書偽造罪(11)~行為⑦「代理権・代表権を超越・濫用した場合の文書偽造罪の成否」を説明
有印私文書偽造罪(12)~行為⑧「肩書や資格を冒用・詐称して文書を作成した場合、文書偽造罪が成立する」を説明
有印私文書偽造罪(13)~行為⑨「通称名、仮名、偽名の使用して文書を作成した場合において、人格の同一性のそごが認められるときは文書偽造罪が成立する」を説明
変造の概念の記事
有印私文書変造罪~「有印私文書変造罪とは?」を説明