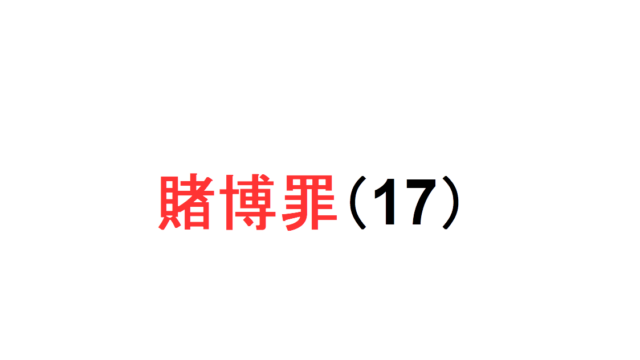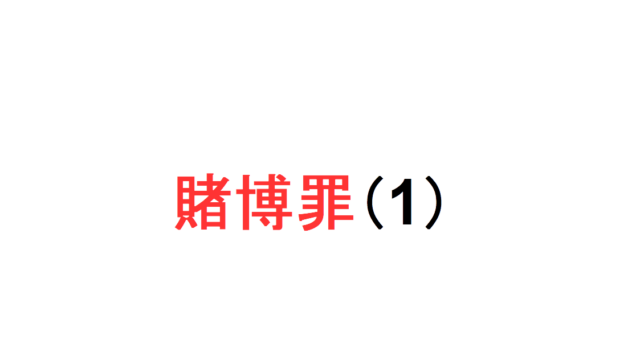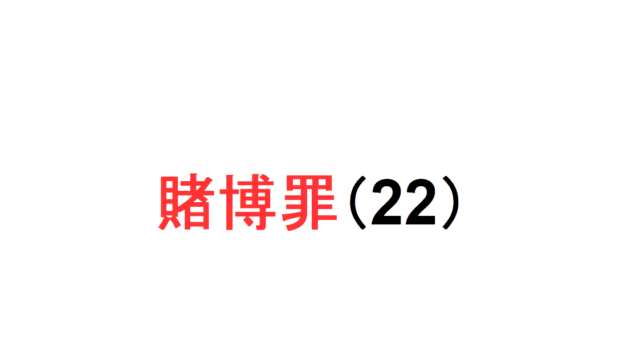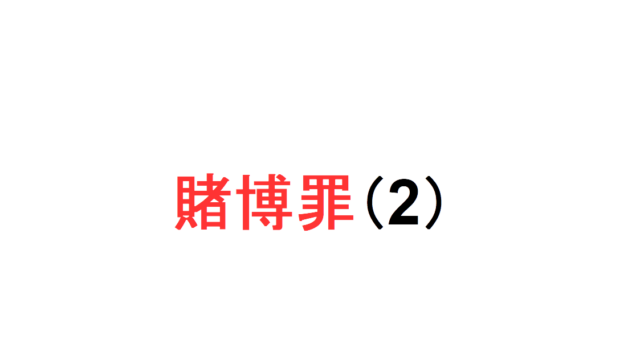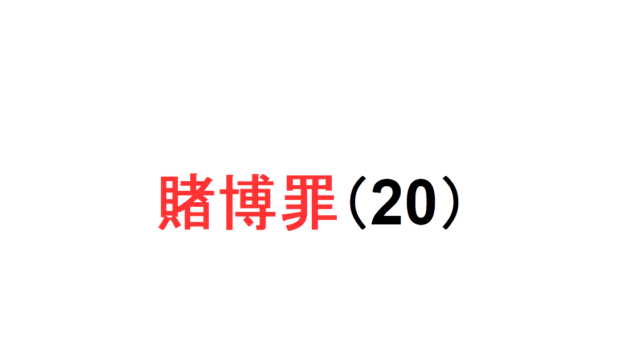賭博罪(15)~「賭博罪における共謀共同正犯」を説明
前回の記事の続きです。
賭博罪における共謀共同正犯
1⃣ 賭博罪(刑法185条)における共同正犯(共犯)の要点について説明します。
賭博罪は、直接賭博の実行行為に当たらなかった者についても共謀共同正犯の形態で共同正犯が成立し得ます。
この点を判示しのが以下の判例です。
大審院判決(大正4年11月1日)
裁判所は、
- 苟も二人共謀し、一体となりて賭博の犯行を為す以上は、たとい直接に実行の局に当たる者は共謀者中一人なりとすると、その犯行は共謀者全員の意思を実行したるものにして、この場合に直接に実行の局に当たらざる一人は他一人を使用して自己の意思を実行したるものにほかならず、故に共謀者全員はいずれも実行正犯としてその罪責に任ずべきものとす
と判示しました。
2⃣ どのような場合に共謀共同正犯が成立するかは、具体的事案において、共謀共同正犯の成立要件を充足するものであるか否かによって決されます(共謀共同正犯の説明は前の記事参照)。
参考となる以下の裁判例があります。
名古屋高裁金沢支部判決(昭和59年10月23日)
他人の設置したポーカー式遊技機による賭博行為について共謀共同正犯を認めた事例です。
裁判所は、
- 本件ポーカー式遊技機はもともと被告人の属する暴力団のA及びB が、奥茶店(中略)の経営者Cとの間で「儲けは折半する、機械の電気代はCが負担する、儲けの集金は月1、2回とする、客が勝った場合はCの方で立替払するが、ゲーム機の中の料金箱から払ってもよく、後日精算する」旨の約束で同店に設置して賭博を行わせていたものであるが、その後同人らが行方をくらましたため、(中略)被告人がBらの跡を継ぐという形で、右機械がいわゆる賭博ゲーム機であることを十分認識しつつ、Bらと同じ条件で引き続き同店に右機械を設置し、約束に従い被告人において同店に毎月1、2回取得した賭金の集金に赴き、これをいずれも自己の遊興費等に費消したものであることが認められ、叙上の事実関係に徴すれば、被告人が自らの手で右機械を設置せず、またその処分権能を有するかどうかにかかわりなく、被告人は原審相被告人Cと共謀のうえ本件賭博を行ったものといわなければならない
と判示しました。