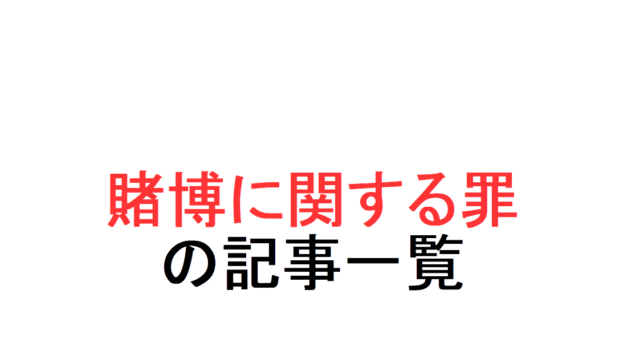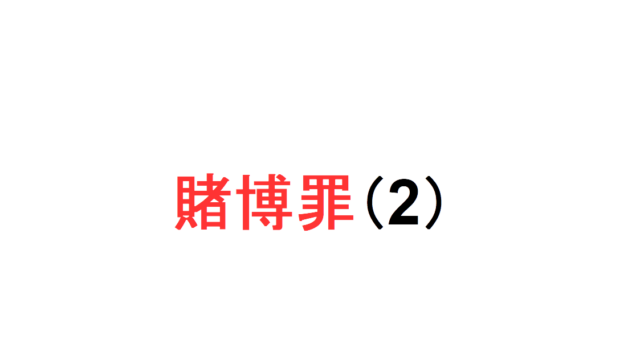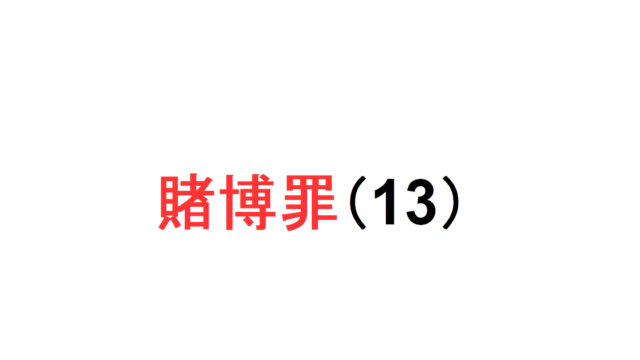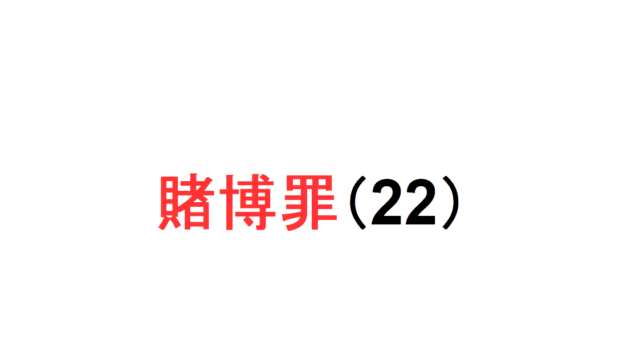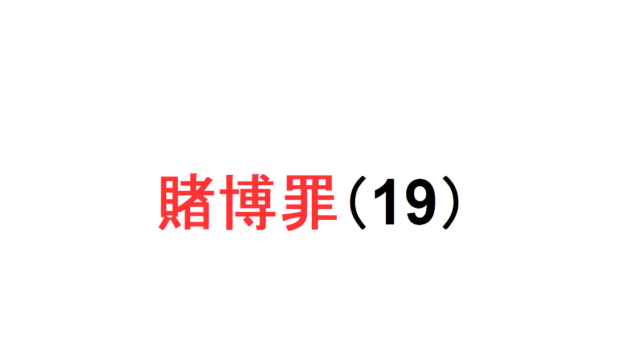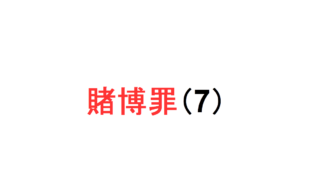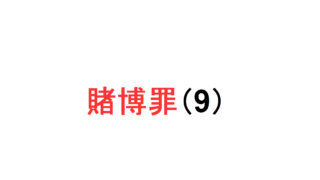賭博罪(8)~「賭博罪の成否を決するに当たり、財物の得喪の有無が争われた判例・裁判例」を説明
前回の記事の続きです。
賭博罪の成否を決するに当たり、財物の得喪の有無が争われた判例・裁判例
賭博罪(刑法185条)の成立要件として、
- 「偶然の勝敗」に関するものであること
- 財物を賭けてその得喪を争うこと
という要件が必要になります。
前回は、②の「財物を賭けてその得喪を争うこと」の意義を説明しました。
今回は、賭博罪の成否を決するに当たり、財物の得喪の有無が争われた判例・裁判例を説明します。
1⃣ 財物の得喪を争ったものであることを認めた判例・裁判例
① 当事者全員が勝者又は敗者のいずれかになることは要せず、全員について勝者又は敗者となる可能性があればよいとしたもの
大審院判決(大正3年6月13日)
当事者中、最も先に所持する駒を全部を場に出した者が勝者となり、最後まで駒を所持している者が敗者となり、その中間のものについては勝敗なしとする方法による「駒揚り」と称する賭博について、裁判所は、
と判示しました。
② 数回の勝負の結果として勝金額が対当する可能性があるとしても、賭博ではないとはいえないとしたもの
大審院判決(昭和2年11月17日)
裁判所は、
- 数次の勝敗ありたる後に至り、偶その取得したる金額が対当することありとするも、これ賭博における一勝一敗の結果にして普通の賭博においても往々見るところなれば、そのこれあるの故をもって賭博にあらずというを得ず
と判示しました。
③ 本来勝者の負担すべき費用を敗者が負担し支払うこととするのは、その敗者が支払うべき金員についての財物の得喪であるとしたもの
大審院判決(昭和4年2月18日)
裁判所は、
- 必ずしも敗者より勝者に対し直接に財物を交付することを要するものに非ずして、勝者の負担すべき費用を敗者において支弁するにおいては、勝者及び敗者の間においては縦し直接財物の授受なしとするも、勝者はその支弁を免れ敗者はこれを勝者に代わって支弁するものなるが故い、二者の関係はその支弁する金員をもって財物の得喪なりと認むるに足る
と判示しました。
④ 物品販売に藉口した賞品獲得ゲームについて、財物の得喪を争うものであるとしたもの
以下の裁判例は、いずれも、時価250円程度の万年筆を1000円で販売した上、客にゲームを行わせ、客が当該ゲームに勝ったときは時計又は現金2000円を与えるといった形態の営業行為に係るものであり、いずれも賭博罪の成立が認められています。
高松高裁判決(昭和31年1月20日)
裁判所は、
- 物品の販売に藉ロし、客から現金を徴し、前記人形探しの方法に依って被告人の提供する時計又は現金の得喪を争うことは結局その本質において客と被告人が偶然の勝負に関し財物(客は千円、被告人は時計又は現金2千円)を賭けたものというべき
としました。
広島高裁岡山支部判決(昭和31年10月9日)
裁判所は、
- 被告人が売買名義で交付する万年筆は実は安価のものであって、1本千円などという価格で売買することを目的とするものではなく、万年筆の売買とは単に表面を仮装するものに過ぎないのであって、これを全体的に観察すると、その実はトランプからなる原判示のくじを引かせることを目的とするものであることは容易に知ることができる
としました。
広島高裁判決(昭和31年12月26日)
裁判所は、
- 被告人が売買名義で交付する万年筆は1本千円又は2千円などという価格で真実売買することを目的とするものではなく、万年筆の売買は単に表面を仮装するに過ぎないものであって、その実は巧妙な方法で前記たばこくじを引かせるために出金(売買代金名下に賭金)をさせ賞品又は賞金の得喪を目的とするものであることを容易に知ることができる
- 従って所論のように売買に付随する景品というのとは全くその性質を異にし、前記「たばこくじ」に当たるか否かの偶然な勝敗に関し金銭を賭するものにほかならないものであるから賭博にあたることは明らかである
としました。
2⃣ 財物の得喪を争うものであることを否定した判例
胴元が客から金銭等を得て、その合計額の範囲内の価額の金品を勝者に与える形態の射倖行為においては、金銭等の所有権が射倖行為開始前に胴元に移転するとみられることが多く、そうすると客どうしで財物の得喪を争うものとはいえず、また胴元は常に危険を負担しない(財物を失わない)ことから客と胴元とで財物の得喪を争うものともいえず、財物の得喪を争うものとは認められないとされ、財物の得喪を争うものではないとして、賭博罪の成立が否定される場合があります。
この点、参考となる以下の判例があります。
① 紋形紙の買受名下に掛金を拠出させてこれを胴元が取得し、48種の紋形のうちあらかじめ封じてあった紋形に符合する紋形紙に掛金を拠出した者に胴元から掛金合計額を下回る価額の賞品を与える射倖行為は、胴元側に危険負担がなく、かつ掛金は的中者の決定に先立って胴元の所有に帰するのであるから、勝敗を争って財物の得喪を決するものとはいえないとしたもの
大審院判決(大正6年4月30日)
裁判所は、
- 胴元たるAと掛金者たる被告ら各個人との間において、輸贏(勝敗)を争い、財物の得喪を決するものにあらず
- 仮に所論の如くAと被告ら各個人との間において輪贏を争うべき関係ありと観察するも、Aは被告ら各個人と輸贏を争うに先立ち、対手者の持ち込みたる財物につき所有権を取得せるをもって判示事実関係は賭したる財物の得喪を偶然の事情に繋がらしめたるものに非ず
- 従って、賭博罪構成の一要素を具備せざるものといわざるべからず
- しかもまた被告ら相互において財物を賭し、その得喪を偶然の事情に繋がらしむるの約束を為したる事実なきをもって論旨後段にいえる如く掛金者たる被告ら相互の間に輸羸を争いたるものに非ず
- 要するに、被告らの判示行為は、Aの行為と共に賭博罪を構成するものというを得ざる
として、原審が当時の北海道庁警察犯処罰令1条3号(賭博類似行為)を問擬(もんぎ)したのは相当であるとしました。
② 勝馬投票券を密売して的中者に勝馬投票券密売代金の範囲内で支弁調整する景品券を取得させた事例につき、密売代金は支払と同時に開催者の所有に帰し、購入者相互間で得喪の目的となる賭金となり得ず、景品券も勝馬投票券密売代金の範囲内で勝者に交付されるにすぎないとして、密売者及び購入者らの行為は賭博罪を構成しないとしたもの
大審院判決(大正9年10月26日)
裁判所は、
- 右引替券の代金は、支払と同時に質渡人の所得に帰し、各密買者間に得喪の目的となる賭金たらざるは明かなれば、もとより密買者相互間に賭銭行為ありと論ずべからず
- また該密買者が取得を争う景品券は、競馬開催者が勝馬投票引替券の売渡によりて得たる代金の範囲内をもって支弁調整したる一種の財物にして、単に勝馬投票者に交付すべきものなれば、これまた各投票者間及び競馬開催者間相互に得喪の目的として賭したる財物なりというを得ず
として、原審が当時の福島県警察犯処罰令1条2号、2条等(賭博類似行為)を問擬したのは相当であるとしました。
③ あらかじめ購入した遊技券により玉突等の遊技をさせ勝者に景品を提供する事案につき、右遊技券は遊技に先立って営業者の所有に帰するのであるから、当該遊技券は遊技者及び営業者等相互間で得喪の目的として賭した財物とはいえないとしたもの
大審院判決(昭和8年12月22日)
裁判所は、
- 右いわゆる遊技券は、これを判示いずれかの一画に置き、判示射倖的行為を為すときな、それぞれ右遊技場の営業者たる被告人らの所得に帰し、遊技者及び営業者たる被告人ら相互間に得喪の目的として賭したる財物なりということを得ず
- 単に遊技者たる客の勝ちたる場合において客が所定の煙草を取得するのみにして、遊技者たる客においては何ら財物を賭したる事実なきをもって原判決に認定する右行為はいずれも賭博類似行為をもって論ずることを得べきも、未だもって賭博罪の構成要件を具備するものということを得ず
として、賭博罪ではなく、当時の鹿児島県条例3号、遊技場営業取締規則9条、12条の罪に当たるとしました。