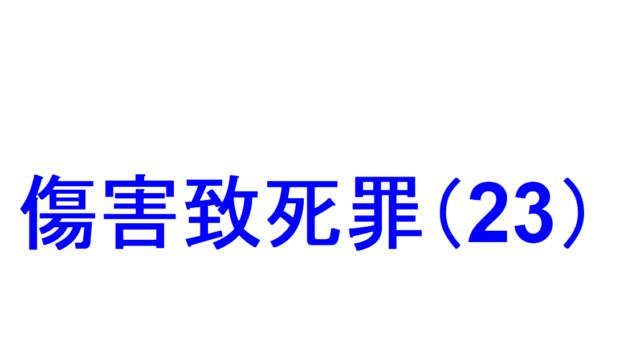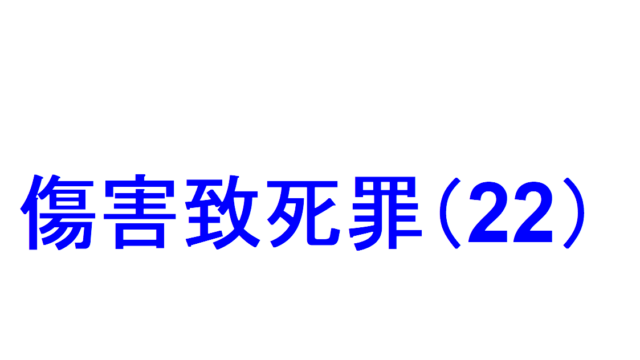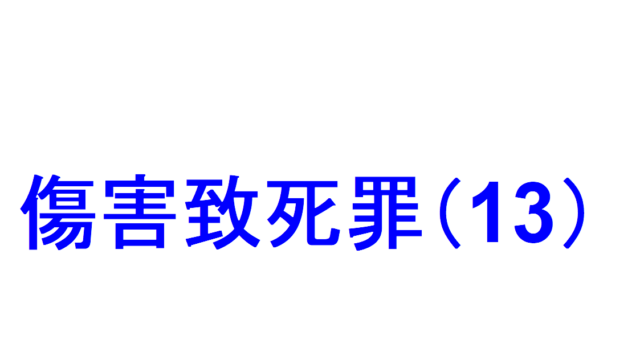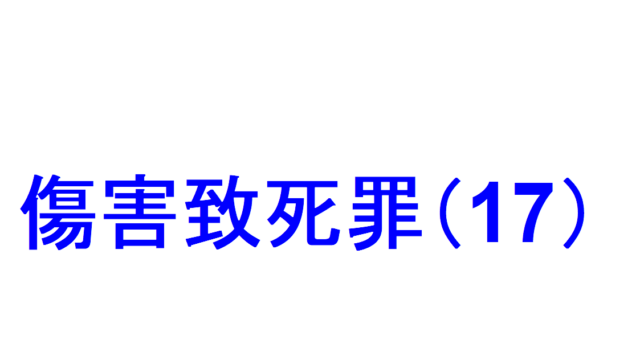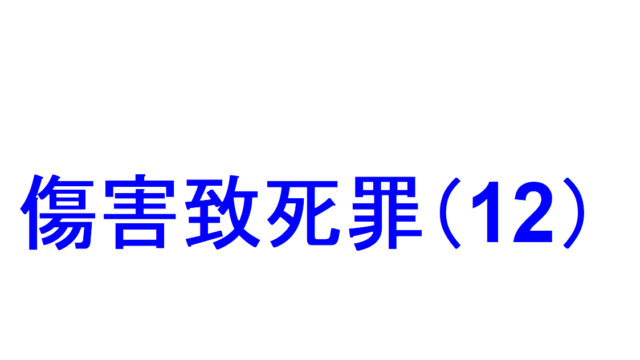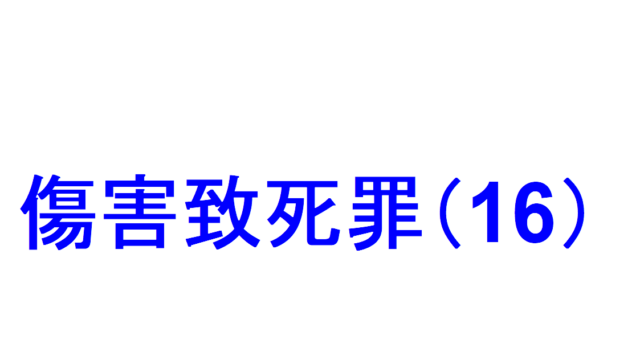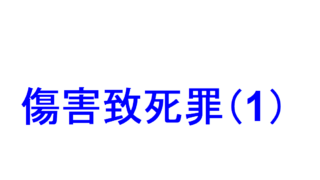傷害致死罪(2) ~「傷害致死罪の故意(暴行の故意で足りる)」「暴行の故意で傷害致死の結果を生じさせた事例」を判例で解説~
傷害致死罪の故意
暴行罪、傷害罪、傷害致死罪などの故意犯については、犯罪を犯す意思(故意)がなければ、犯罪は成立しません(詳しくは前の記事参照)。
傷害致死罪の故意は、
暴行の故意で足りる
とされます。
傷害の故意はもちろんのこと、暴行の故意で相手を攻撃し、相手に傷害を負わせた上、死に至らしめれば、傷害致死罪の故意が認められることになります。
傷害致死罪は、暴行罪と傷害罪の結果的加重犯なので、少なくとも、暴行の故意がベースにあれば、傷害致死罪の故意も認められることになります。
暴行罪、傷害罪、傷害致死罪の故意と各犯罪の成立関係を表すと、以下のようになります。
- 暴行を加える故意で暴行を加え、相手が傷害を負なければ、暴行罪が成立する
- 暴行を加える故意で暴行を加え、相手が傷害を負えば、傷害罪が成立する
- 傷害を負わせる故意で暴行を加え、相手が傷害を負なければ、暴行罪が成立する
- 傷害を負わせる故意で暴行を加え、相手が傷害を負えば、傷害罪が成立する
- 暴行を加える故意で暴行を加え、結果として、相手に傷害を負わせた上、死に至らしめた場合、傷害致死罪が成立する
- 傷害を負わせる故意で暴行を加え、結果として、相手に傷害を負わせた上、死に至らしめた場合、傷害致死罪が成立する
ちなみに、致死の結果について、認識・認容がある場合は、殺人罪の故意が認められることになりますので、そのような場合は、傷害致死罪ではなく、殺人罪が成立することになります。
傷害致死罪の故意に関する判例
傷害致死罪の故意に関する判例として、以下の判例があります。
大審院判決(明治42年4月15日)
この判例で、裁判官は、
- 他人の身体に暴行を加えたる以上は、その結果につき責任を負わざるべからざるは事理の当然なるが故に、傷害を生ぜしむるの意思をもって、傷害罪の構成要素を為すが如きは、立法の精神にあらざることもちろんなるのみならず、刑法204条、同205条、同208条等の法文を対照せば、故意に暴行を加えたる以上は、傷害を予期すると否とにかかわらず、傷害の結果を生じたると否とにより、その制裁を区別したるものなること自ずから明なり
と判示し、暴行を加えた以上は、傷害を予期するかどうかにかかわらず、傷害(傷害致死)の結果が生じたかどうかにより、制裁(暴行罪、傷害罪、傷害致死罪)を区別するものであるとしました。
大審院判決(昭和4年2月4日)
被害者の肩を突いたところ、被害者が壁の釘に頭部を打ちつけて大脳血管を損傷して死亡したという傷害致死の事案で、裁判官は、
- 暴行を加えるの意思ありて暴行を加え、傷害又は致死の結果を生じたる以上、たとえ傷害の意思なき場合といえども、傷害罪又は傷害致死罪成立す
- 傷害罪又は傷害致死罪の成立には、暴行を加えるの意思あることを要するも、その暴行が傷害の結果を生ずることあるべき性質を有することを認識するを要せず
と判示しました。
大審院判決(昭和17年4月11日)
喧嘩の末、川に突き落とされて激怒し、報復のため相手を川に突き落とし、その結果、溺死させた事案において、暴行と死の因果関係及び故意を認め、傷害致死罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 人の身体に対し、暴行を加える認識ありて暴行を加え、よって溺死の結果を生じせしめたる以上、刑法第205条の傷害致死罪が成立する
と判示しました。
この判例で、裁判官は、
- 傷害罪又は傷害致死罪の成立に必要な主観的要件としては、暴行の意思を必要とし、かつ、これをもって充分である
- 暴行の意思以外に、さらに傷害の意思を要するものではない
と判示しました。
夫婦喧嘩の末、夫が妻Aを仰向けに引き倒して馬乗りとなり、両手で妻Aの頸部を圧迫するなどの暴行を加え、特異体質である妻をショック死するに致らしめたときは、致死の結果を予見する可能性がなかったとしても傷害致死罪を構成するとしました。
裁判官は、
- 被告人のAに対する頸部圧迫の暴行が間接的誘因となり、同人のショック死を惹起した事実は明らかで、その間に間接的ながら因果関係が認められる
- 傷害罪の成立には暴行と死亡との間に因果関係の存在を必要とするが、致死の結果についての予見を必要としないこと当裁判所の判例とするところであるから(昭和26年9月20日判決)、因果関係の存する以上、被告人において致死の結果をあらかじめ認識することの可能性ある場合でなくても、被告人の所為が傷害致死罪を構成するこというまでもない
と判示しました。
暴行の故意で傷害致死の結果を生じさせた事例
傷害致死罪は、傷害の故意がなくても、暴行の故意があれば成立することがポイントになります。
暴行の故意は、
人の身体に対して有形力を行使することの認識
と定義されます(詳しくは前の記事参照)。
暴行の行為で傷害致死の結果を生じさせた事例について紹介します。
裁判官は、狭い4畳半の室内で被害者を脅かすために、日本刀の抜き身を数回振り回した行為は、被害者に対する暴行というべきであるとし、その行為の結果として被害者を死に至らしめたとして、暴行の故意による傷害致死罪の成立を認めました。
東京高裁判決(昭和59年2月14日)
飲酒中、相客である被害者に対し、その言動が騒々しいと感じていたことを背景として、冗談半分ではあるが、半ば脅しの気持ちで柳刃包丁の刃先を胸部付近に突き出したところ、手加減が狂い、その刃先が被害者の胸部に突き刺さり、同人を死亡するに至らしめた事案で、裁判官は、
- 他人に対し、暴行の意思で暴行を加え、その結果、他人に傷害を負わせ、死亡するに至らしめた場合、傷害致死罪の罪責を負うべきことは当然であるが、右の暴行とは、人の身体に対する有形力の行使をいうものであるところ、その有形力の行使には、物理的な力を人の身体に直接加える場合だけでなく、人の身体を侵害し、苦痛を与える危険性の高い有形力を人の身体の直近において行使する場合も含まれると解されるのである
- 本件における被告人の所為のように、鋭利な柳刃包丁の刃先を人の胸部付近に近付け、2度、3度と突き出す行為も有形力の行使であって、前記の暴行に該当するものといわなければならない
と判示し、暴行の故意による傷害致死罪の成立を認めました。
東京地裁八王子支部(平成8年3月8日)
6歳の養女に対し、せっかんのためシャワーで熱湯を浴びせて熱傷等の傷害を負わせ、ショツク死させたとの事案で、「被告人にはシャワーの湯が熱湯であることの認識がなかったから暴行の故意を欠く」とする弁護人の主張を排斥して、傷害致死罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 被告人は、洗面台のつまみを回して湯を出してからシャワー用にコックを回した際、足元にシャワーの湯がかかったが水に近く感じ、また、本件時、自己がシャワーを浴びる際と同様の操作をしたにすぎなかったから、被害者にシャワーの熱湯がかかったことは認識していなかった旨供述する
- しかしながら、関係証拠によると、被告人は、本件当時、判示アパートには約2か月間居住していて、本件のシャワーの使用方法を十分知っていたと認められるから、本件シャワーは、湯用のつまみのみを回した場合、当初は水であるものの、その後次第に湯温が上がってくるものであることを認識していたと推認され、また、自己がシャワーを浴びる際と同様の操作をしたにすぎないのであれば、本件のように、摂氏約50度以上の熱湯を1分間ないし2分間継続的にかけるといった事態が生ずるわけがない
- また、関係証拠によると、被告人は、被害者にシャワーの湯をかけている間、シャワーホースを手に持って、浴室の入り口付近で、おおむね被害者の状況を見ていて、被害者が、浴室の奥に向かうように、被告人に背を向けて、悲鳴を上げながら、熱さから逃れようと、左右に逃げまどっているのを認めながらも、その背部、顔面等にシャワーで湯をかけ続けていたものと認めることができるから、このような被告人が、本件時、シャワーの湯が水に近いと感じ、被害者にシャワーの熱湯がかかったことは認識していなかったとは到底信じられない
- さらに、これに加えるに、被告人は、本件犯行に至るまでの間、被害者に対して、頻繁に、殴る、蹴る、叩くなどの激しい暴行を加えていたこと、本件時においても、被害者が、夜なかなか寝つかずにいる傾向があり、出掛ける際、「今日は寝ちゃだめだよ。帰ってきて寝ていたら怒るからね。」などと言いつけてあったにせよ、妻と共に、被害者らの幼い子供らを自室に置いたまま、午前4時過ぎまで遊び回り、この間、わずか6歳の被害者が寝入ることなく、起きたままで待っていることはおよそ考え難いのに、帰宅するや、言いつけを守らないで寝てしまったとして、これに立腹し、寝ていた被害者を起こして、その頭部、顔面、尻部を殴打した上、被害者を抱え上げて、浴室まで連れて行き、着衣の上からシャワーの湯を浴びせかけるということ自体、冷静な合理的思考をはるかに越えた行動というほかないことなどにも照らすと、被告人が、シャワーから熱湯が出ていることを十分認識しながら、これを被害者に向けて浴びせかけたものと推認するに難くない
- 以上、要するに、被告人の前記弁解は信用することができず、被告人は、被害者の背部、顔面等に熱湯をかける暴行を加えたものと優に認定することができ、この認定に合理的な疑いを差し挟む余地はないというべきである
と判示し、傷害致死罪の成立を認めました。