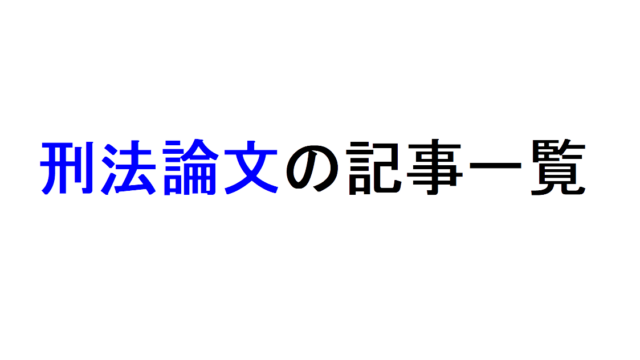刑法論文(16)~令和2年司法予備試験の刑法論文問題から学ぶ~
令和2年司法予備試験の刑法論文問題から学ぶ
令和2年司法予備試験の刑法論文問題の答案を作成してみました。
この論文からは以下のテーマが学べます。
1⃣ 有印私文書偽造罪(刑法159条1項)、偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)
2⃣ 詐欺罪(刑法246条2項)(2項詐欺)
3⃣ 正当防衛・誤想防衛と傷害致死罪(刑法205条)又は過失致死罪(刑法210条)の成否
4⃣ 誤想過剰防衛
5⃣ 正当防衛後、相手方が更なる侵害行為に出る可能性のないことを認識した上で及んだ暴行行為は正当防衛が否定される
問題
以下の事例に基づき、甲の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲(28歳、男性、身長165センチメートル、体重60キログラム)は、2年前に養子縁組によって氏を変更し、当該変更後の氏名(以下「変更後の氏名」という。)を用いて暴力団X組組員として活動を始めた。甲は、自営していた人材派遣業や日常生活においては、専ら当該変更前の氏名(以下「変更前の氏名」という。)を用いていた。
2 甲は、X組と抗争中の暴力団Y組の組長乙を襲撃する計画を立てていたところ、乙が、交際中のA宅に足繁く通っているとの情報を入手した。甲は、A宅を監視する目的で、A宅の向かいにあるB所有のマンション居室(以下「本件居室」という。)を借りるため、某月1日、Bに会い、「部屋を借りたい。」と申し込んだ。Bは、暴力団員やその関係者とは本件居室の賃貸借契約を締結する意思はなく、準備していた賃貸借契約書にも「賃借人は暴力団員又はその関係者ではなく、本物件を暴力団と関係する活動に使いません。賃借人が以上に反した場合、何らの催告も要せずして本契約を解除することに同意します。」との条項(以下「本件条項」という。)を設けていた。Bは、甲に対し、本件条項の内容を説明した上、身分や資力を証明する書類の提示のほか、家賃の引落しで使用する口座の指定を求めた。
甲は、自己がX組組員であり、A宅を監視する目的で本件居室を使用する予定である旨告げれば、前記契約の締結ができないと考え、Bに対し、X組組員であることは告げず、その目的を秘しつつ本件居室を人材派遣業の事務所として使用する予定である旨告げた。甲は、Bに変更後の氏名を名乗れば、暴力団員であることが発覚する可能性があると考え、Bに対し、変更前の氏名を名乗った上、養子縁組前に取得し、氏名欄に変更前の氏名が記載された正規の有効な自動車運転免許証を示した。また、甲は、養子縁組前に開設し、口座名義を変更していない預金口座の通帳に十分な残高が記帳されていたため、Bに対し、同通帳を示し、同口座を家賃の引落しで使用する口座として指定した。甲は、同日、前記契約書の賃借人欄に現住所及び変更前の氏名を記入した上、その認印を押し、同契約書をBに渡した。Bは、甲が暴力団員やその関係者でなく、本件居室を暴力団と関係する活動に使うつもりもない旨誤信し、甲との間で上記契約を締結した。この際、甲には家賃等必要な費用を支払う意思も資力もあった。
なお、前記マンションが所在する某県では、暴力団排除の観点から、不動産賃貸借契約には本件条項を設けることが推奨されていた。また、実際にも、同県の不動産賃貸借契約においては、暴力団員又はその関係者が不動産を賃借して居住することによりその資産価値が低下するのを避けたいとの賃貸人側の意向も踏まえ、本件条項が設けられるのが一般的であった。
3 乙の警護役であるY組組員の丙(20歳、男性、身長180センチメートル、体重85キログラム)は、同月9日午前1時頃、A宅前路上に停めた自動車に乗り、A宅にいた乙を待っていたところ、前記マンション敷地から同路上に出てきた甲を見掛けた。その際、丙は、甲のことを、風貌が甲と酷似する後輩の丁と勘違いし、甲に対し、「おい、こんな時間にどこに行くんだ。」と声を掛けた。これに対し、甲は、無言で上記路上から立ち去ろうとした。これを見た丙は、丁に無視されたと思い込み、同車から降りて甲を追い掛け、「無視すんなよ。こら。」と威圧的に言い、上記路上から約30メートル先の路上において、甲の前に立ち塞がった。丙は、その時、甲が丁でないことに気付くとともに、暴力団員風で見慣れない人物であったことから、その行動を不審に思い、乙に電話で報告しようと考え、着衣のポケットからスマートフォンを取り出した。他方、甲は、丙が取り出したものがスタンガン(高電圧によって相手にショックを与える護身具)であると勘違いし、それまでの丙の態度から、直ちにスタンガンで攻撃され、火傷を負わされたり、意識を失わされたりするのではないかと思い込み、同日午前1時3分頃自己の身を守るため、丙に対し、とっさに拳でその顔面を1回殴ったところ、丙は、転倒して路面に頭部を強く打ち付け、急性硬膜下血腫の傷害を負い、そのまま意識を失った。なお、甲は、丙の態度を注視していれば、丙が取り出したものがスマートフォンであり、丙が直ちに自己に暴行を加える意思がないことを容易に認識することができた。
甲は、同日午前1時4分頃、丙が身動きせず、意識を失っていることを認識したが、丙に対する怒りから、丙に対し、足でその腹部を3回蹴り、丙に加療約1週間を要する腹部打撲の傷害を負わせた。
丙は、同日午前9時頃、搬送先の病院において、前記急性硬膜下血腫により死亡したが、甲の足蹴り行為により死期が早まることはなかった。
答案
第1 甲が変更前の氏名を用いて賃貸借契約書を作成した行為につき、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)及び偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)が成立しないか。
1 「偽造」とは、「文書の名義人」と「文書の作成者」との間の人格の同一性を偽ることをいう。
「文書の名義人」は、文書の意識内容の主体となる者をいう。
意識内容の主体となるかは、文書の記載内容から理解される。
「文書の作成者」は、文書の内容を表示した者をいう。
賃貸借契約書は、賃貸借契約を締結する者が作成することが予定されている文書であり、本件賃貸契約書の記載内容から理解され、文書の意識内容の主体となる「文書の名義人」は甲である。
しかしながら、甲は、本件賃貸借契約書の変更前の氏名を記入した上、認印を押している。
通常、旧姓などの変更前の氏名を使用して私文書を作成することは、日常生活の中で行われることであり、それが直ちに人格の同一性を偽ることにはならず、文書偽造罪は成立しないと解する。
しかしながら、甲は、真実は本件居室を人材派遣業の事務所として使用するのではなく、暴力団組員としてXを監視する目的で本件居室を賃貸しようとている。
本件居室の賃貸借契約は、暴力団組員の活動と考えるべきであり、文書偽造罪の保護法益が「文書に対する公共の信用」であることに鑑みると、甲が暴力団組員であることが発覚しないように変更前の氏名を本件賃貸借契約書に記入した行為は、「文書に対する公共の信用」を害するものであり、本罪の保護法益を害する。
そうすると、本件賃貸借契約書においては、甲が暴力団組員ではないことが重要事項であるから、「文書の作成者」は暴力団員甲(変更後の氏名)というべきである。
その上で、「文書の名義人」を暴力団組員ではない甲(変更前の氏名)として本件賃貸借契約書を作成する行為は、「文書の作成者」と「文書の名義人」との間の人格の同一性を偽るものであり、「偽造」に当たる。
2 有印私文書の「有印」とは、印章若しくは署名をいう。
本件賃貸借契約書は、甲が署名・押印をしていることから、有印私文書である。
3 有印私文書偽造罪の客体は、他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画である。
本件賃貸借契約書は、本件居室の賃貸借契約の当事者間の合意を証明し、権利義務を明確にする文書なので「権利、義務、事実証明に関する文書」であり、本罪の客体となる。
4 「行使の目的」とは、偽造・変造文書を真正な文書と誤信させ、偽造・変造文書を内容が真実である文書と誤信させようとする目的をいう。
甲は、自己が暴力団組員ではなく、正当に本件居室を賃貸借できる権利があるとする虚偽の賃貸借契約書を作成し、それをBに真正な文書であると誤信させようとする目的が認められる。
よって、「行使の目的」が認められる。
5 偽造文書の「行使」とは、偽造に係る文書を真正な文書として使用することをいう。
ここでいう「使用」とは、文書を真正に成立したものとして他人に交付・提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させ又はこれを認識し得る状態に置くことをいう。
甲は、偽造した本件賃貸借契約書を真正なものとしてBに交付し、その内容を認識さていることから、偽造有印私文書を行使している。
6 よって、甲に有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪が成立する。
第2 甲が暴力団組員であることを秘し、Bと本件居室の賃貸借契約を締結した行為につき、詐欺罪(刑法246条2項)が成立しないか。
1 詐欺罪が成立するには、①欺罔行為、②被害者の錯誤、③被害者の錯誤に基づく財産的処分行為、 ④財物・財産上の不法の利益の取得、⑤財産上の損害の発生という因果的連鎖が必要となる。
「欺罔行為」とは、詐欺犯人の希望する財産的処分行為に向けて被害者を錯誤に陥らせる行為をいう。
欺罔行為は、交付の判断の基礎となる重要な事項について欺かなければならない。
本件賃貸借契約は、暴力団排除の観点から、暴力団組員やその関係者ではないこと、及び本件居室を暴力団と関係する活動に使わないことを誓約する本件条項が設けられていた。
そして、B自身も暴力団関係者には本件居室の賃貸借契約を締結する意思はなかったのであるから、甲が暴力団関係者であるか否か、及び甲が本件居室を暴力団と関係する活動に使うか否かは、Bが本件賃貸借契約を締結するか否かを判断する上で重要事項であるといえる。
それにもかかわらず、甲はこれを認識しつつ、変更前の氏名を用いて自己が暴力団関係者でないかのように装い、本件居室を暴力団Yの組長乙を監視するという真の目的を秘し、人材派遣事業の事務所として使用するとの虚偽の目的を述べて契約を締結したことは、交付の判断の基礎となる重要な事項を欺いたといえ、「欺罔行為」に当たる(①充足)。
甲の欺罔行為により、Bは、甲が暴力団組員ではなく、暴力団組員の活動として本件居室が活用されないと錯誤している(②充足)。
Bは錯誤に基づき、本件賃貸借契約を締結し、本件居室を甲に賃貸するという財産的処分行為を行っている(③充足)。
甲は、本件居室の賃借する権利を獲得し、財産上の不法の利益を取得している(④充足)。
Bは、本来であれば賃貸することを拒否するはずの暴力団組員である甲に本件居室を賃貸することになり、財産上の損害が発生している(⑤充足)。
2 2項詐欺において、「財産上…の利益」は、財物以外の財産的利益を意味する。
「不法の利益」の「不法」とは、「不法の手段によって」という意味である。
B居室の賃借権は、財物ではなく、財産上の利益であり、甲が自己が暴力団組員であることを偽るという不法な手段によって得たものなので、「財産上の不法の利益」に当たる。
3 詐欺罪の故意は、詐欺犯人が他人の財物を詐取することを表象・認容することである。
甲は、暴力団組員であることを秘し、本件居室の賃借権をBから詐取することの表象・認識を有するといえ、故意が認められる。
4 よって、上記①~⑤の因果的連鎖が認められ、構成要件も満たすことから、刑法246条2項の詐欺罪が成立する。
第3 甲が丙の顔面を1回殴り、急性硬膜下血腫を負わせて死亡させた行為につき、傷害致死罪(刑法205条)又は過失致死罪(刑法210条)が成立しないか。
1 傷害致死罪が成立しないか。
⑴ 傷害罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいう。
「傷害」とは、人に生理機能障害や健康状態の不良な変更を与えることをいう。
甲は丙の顔面を1回殴るという不法な有形力を行使し、急性硬膜下血腫という生理機能障害を負わせていることから「傷害」に当たる。
⑵ 傷害罪の故意は、暴行罪の故意があれば足りる。
暴行罪の故意は、人の身体に対して有形力を行使することの認識をいう。
相手に傷害を負わせる意思で暴力を振るうことが傷害罪の故意になることはもちろんだが、相手に傷害を負わせる意思はなく、暴力を振るう意思で暴行を行い、結果的に相手に傷害を負わせた場合でも、傷害罪の故意を認めることができる。
甲が丙の顔面を1回殴るという行為は、少なくとも甲に暴行の故意が認められる行為であり、丙は結果的に傷害を負っているので、傷害の故意が認められる。
⑶ 傷害罪が成立するためには、暴行と身体傷害との間に因果関係が認められることが必要となる。
「因果関係」とは、犯罪行為と犯罪結果との間にある原因と結果の関係をいう。
甲の暴行で丙が急性硬膜下血腫を負ったことは明らかであり、暴行と傷害の間に因果関係が認められる。
⑷ よって、傷害罪の構成要件を満たす。
⑸ 傷害致死罪の構成要件を満たすか。
傷害致死罪は、暴行罪または傷害罪の結果的加重犯であり、身体傷害の結果として人を死亡させる罪である。
傷害致死罪が成立するためには、傷害と死の結果の間に、因果関係が認められることを要する。
「因果関係」とは、犯罪行為と犯罪結果との間にある原因と結果の関係をいう。
丙の死因である急性硬膜下血腫は、甲が丙の顔面を1回殴り、丙が転倒して路面に頭を強く打ち付けて生じたものであるので、甲の暴行・傷害と丙が急性硬膜下血腫の傷害を負ったことによる死亡との間に因果関係が認められる。
よって、傷害致死罪の構成要件を満たす。
⑹ もっとも、甲は、丙がスタンガンを取り出したと勘違いし、自己の身を守るとために丙の顔面を1回殴る行為に及んでいるので、正当防衛(刑法36条1項)が成立し、傷害致死罪の違法性が阻却されないか。
「正当防衛」とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人を守るためにやむを得ずにした反撃行為をいう。
「急迫不正の侵害」とは、違法な法益侵害が現に存在するか、目の前に差し迫っていることをいう。
甲の防衛行為は、丙が電話をしようとしてスマートフォンを取り出したのをスタンガンを取り出したと勘違いして行ったものであり、急迫不正の侵害が存在しない。
よって、正当防衛は成立しない。
⑺ では、誤想防衛が成立し、傷害致死罪の故意責任(刑法38条1項)が阻却されないか。
「誤想防衛」とは、侵害行為が存在しないのに、存在すると誤信して行った正当防衛行為をいう。
誤想防衛は、①急迫不正の侵害がなく、②防衛行為の相当性を超えていることから、正当防衛の成立要件を満たさないため、違法性を阻却しない。
しかし、誤想防衛は、行為者に犯罪を行う故意が存在しないため、誤想防衛が成立する場合、故意が阻却され、行為者は故意犯の責任を負わない。
もっとも、行為者は故意犯の責任を負わないとしても、誤想防衛をしたことに過失が認められる場合、過失犯の責任を負う場合がある。
甲は、丙がスタンガンを取り出したと勘違いし、自己の身を守るために丙の顔面を1回殴るという暴行を行っている。
故意責任の本質は、規範に直面し、犯行を思いとどまるという反対動機を形成できる状況にありながら、あえて犯行に及んだことに対する道義的非難にあるところ、行為者が違法性を阻却する事由を認識しているのであれば、規範に直面しておらず、故意責任を問うことはできない。
甲は、前に立ちふさがる丙にスタンガンで襲われると考え、丙の顔面を殴っており、その状況からすると、自己を防衛するためにやむを得ずにした行為であったといえる。
よって、誤想防衛が成立し、故意責任が阻却される。
したがって、故意犯である傷害致死罪は成立しない。
⑻ では、過失犯である過失致死罪が成立しないか。
甲は、丙が着衣のポケットから取り出したのがスマートフォンであったこと、及び丙が自己に暴行を加える意思がないことは、社会通念上、注意を向けてよく観察すれば分かったことであるといえ、誤想防衛をしたことに過失が認められることから、過失責任を負う。
よって、甲は、過失により誤想防衛を行い、丙の顔面を1回殴る暴行を加え、丙に硬膜下血腫の傷害を負わせ、結果的に同傷害で死亡させていることから、甲に過失致死罪が成立する。
第4 甲が丙の腹部を3回蹴って腹部打撲の傷害を負わせた行為につき、傷害罪が成立しないか。
1 傷害罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいうところ、甲は丙の腹部を3回蹴っており、不法な有形力の行使を行っていることから「暴行」に当たる。
「傷害」とは、人に生理機能障害や健康状態の不良な変更を与えることをいうところ、丙の傷害は加療約1週間を要する腹部打撲であり、生理機能障害を与えていることから「傷害」に当たる。
甲の腹部を3回蹴る暴行により腹部打撲が生じていることは明らかであり、暴行と身体傷害との間に因果関係が認められる。
甲は、丙に対する怒りから腹部を3回蹴っており、暴行・傷害の故意も認められる。
よって、傷害罪の構成要件を満たす。
2 もっとも、誤想防衛である丙の顔面を1回殴る暴行(以下、「1回目の暴行」という。)と腹部を3回蹴る暴行(以下、「2回目の暴行」という。)とが、全体的に考察して1個の防衛行為として、誤想過剰防衛が成立するのではないか。
「誤想過剰防衛」とは、急迫不正の侵害がないのに、侵害があるものと誤信して反撃し(誤想防衛)、しかも、その反撃が不相当である防衛行為(過剰防衛)をいう。
誤想過剰防衛が成立する場合、正当防衛との均衡上、過剰防衛に関する刑法36条2項が準用され、任意的に刑が減軽又は免除される。
相手方の急迫不正の侵害に対し、正当防衛(誤想防衛)に当たる暴行を加えた後(第1暴行)、これと時間的・場所的に連続して更に暴行を加えた場合(第2暴行)において、相手方が更なる侵害行為に出る可能性のないことを認識した上、防衛の意思ではなく、専ら攻撃の意思に基づき第2暴行を加えたという状況であれば、第1暴行と第2暴行の間には断絶があり、急迫不正の侵害に対して反撃を継続するうちに、その反撃が量的に過剰になったものとは認められず、両暴行を全体的に考察して1個の過剰防衛(誤想過剰防衛)の成立を認めるのは相当ではないと解する。
本件につき、1回目の暴行により丙は失神し、甲はそのこと認識した上で、怒りの感情から2回目の暴行を行っている。
なお、2回目の暴行を防衛行為としてみた場合、暴行態様は過剰であり、過剰防衛である。
よって、甲は、防衛の意思ではなく、専ら攻撃の意思に基づき2回目の暴行を加えており、1回目の暴行と2回目の暴行との間には断絶があり、急迫不正の侵害に対して反撃行為をしているうちに、その反撃が量的に過剰になったものとは認められず、全体を考察して1個の誤想過剰防衛の成立を認めることはできない。
したがって、2回目の暴行は、1回目の暴行とは独立、別個の暴行であると認められ、傷害罪が成立する。
第5 以上より、甲に、①有印私文書偽造罪、②偽造有印私文書行使罪、③刑法246条2項の詐欺罪、④過失致死罪、⑤傷害罪が成立する。
①②は手段と結果の関係にあるので牽連犯(刑法54条後段)となる。
②③は手段と結果の関係にあるので牽連犯(刑法54条後段)となる。
①②③はまとめて科刑上一罪となる。