鑑定留置とは? ~「鑑定留置を行う理由と手続き」「鑑定留置中の勾留の停止・接見禁止・弁護人との接見交通権」を刑事訴訟法で解説~
鑑定留置とは?
鑑定留置とは、
被疑者・被告人が精神障害などで刑事責任能力を問えない可能性がある場合に、被疑者・被告人の身体を拘束し、強制的に精神科医による精神鑑定を受けさせるために、病院などの施設に留置すること
をいいます(刑訴法167条1項)。
鑑定留置を行う理由
犯罪は、
- 構成要件該当性
- 違法性
- 有責性
の3つの要素が全てそろったときに成立します。
※ 詳細は「犯罪の成立要件」参照
有責性とは、
違法行為について、責任を問いうること(非難可能性)
をいいます。
たとえば、
- 幼児
- 高度の精神病者
が犯罪を犯したとしても、有責性がないため、無罪になります。
被疑者が幼児かどうかは、生年月日を確認すれば分かります。
しかし、被疑者が高度の精神病者かどうかは、精神科医に見てもらわなければ分かりません。
もし、被疑者が高度の精神病者であれば、犯人に責任能力がないため、法律のルール上、裁判所は犯人を有罪にし、刑事処罰を与えることができません。
ここで、被疑者が高度の精神病者であるかどうかを判断するために行われるのが、
精神鑑定
です。
被疑者が精神鑑定に任意に応じれば問題はないですが、
「ふざけるな!精神鑑定なんて受けるか!!」
などと言って、精神鑑定に応じなかったときが問題になります。
そこで、被疑者が精神鑑定に任意に応じなかったときに、被疑者の身体を拘束し、強制的に行う精神鑑定が
鑑定留置
になります。
鑑定留置の手続き
捜査機関(検察官、検察事務官、警察官)は、被疑者の鑑定留置が必要と判断した場合に、裁判所に対し、鑑定留置請求書を提出し、鑑定留置を請求します(刑訴法224条1項)。
鑑定留置請求書に記載する事項は、刑訴規則158条の2に規定があります。
刑訴規則158条の2(鑑定留置請求書の記載要件)
鑑定のためにする被疑者の留置の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居
2 罪名及び被疑事実の要旨
3 請求者の官公職氏名
4 留置の場所
5 留置を必要とする期間
6 鑑定の目的
7 鑑定人の氏名及び職業
8 被疑者に弁護人があるときは、その氏名
鑑定留置は、被疑者の身体を拘束する強制処分なので、裁判官による令状が必要になります。
なので、捜査機関から鑑定留置の請求を受けた裁判官は、鑑定留置をすることが相当と認めるときは、鑑定留置状という令状を発付することになります(刑訴法167条2項、224条2項)。
刑訴法167条の鑑定留置の規定は被疑者にも適用される
鑑定留置を定める刑訴法167条1項の条文は、
『被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる』
と規定し、主語を「被告人」(起訴された後の犯人)としています。
ここで、「被疑者」(起訴される前の犯人)には、刑訴法167条の規定は適用されないのか?という疑問が生じますが、きちんと被疑者にも適用されます。
被告人の規定が被疑者にも適用されることは、刑訴法207条1項から導かれます。
刑訴法207条1項で、
『前三条(刑訴法204条、205条、206条)の規定による逮捕・勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する』
と規定しています。
この規定の意味と考え方は以下のとおりです。
- 裁判官➡被疑者の勾留に関する処分を行う
- 裁判所又は裁判長➡被告人の勾留に関する処分を行う
- 被疑者の勾留に関する処分を行う裁判官は、被告人の勾留に関する処分を行う裁判所又は裁判長と同一の権限を有する
- 裁判官は、勾留に関する処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するのだから、鑑定留置などの条文において「被告人」を主語としている勾留に関する処分については、裁判官でもできる
- 被告人を主語とする刑訴法167条の鑑定留置に関する規定は、被疑者にも適用される
という思考過程になります。
鑑定留置の間は勾留が停止される
鑑定留置を行った犯人が、逮捕・勾留され、身体を拘束されている被疑者である場合、鑑定留置の間は、勾留の執行が停止されます(刑訴法167条の2)。
被疑者は、逮捕・勾留されると、10日の間、警察署の留置施設で留置されます。
さらに、捜査の必要があれば、勾留期間は10日間延長され、最長で20日の間、被疑者は警察署の留置施設で留置されることになります(刑訴法208条)。
この最長20日間の勾留期間中に、鑑定留置を行った場合、勾留の執行が停止される扱いとなることから、鑑定留置された期間は、勾留期間から除かれます。
たとえば、8月1日に勾留され、8月20日までの20日間勾留される予定だったところに、鑑定留置を3日間行ったとします。
鑑定留置を行った3日間の期間は、勾留から除かれるので、結果的に、勾留期間は8月23日までとなります。
鑑定留置が行われると、その分、勾留期間が延びる点がポイントになります。
鑑定留置中の被疑者の接見禁止
被疑者は、逮捕・勾留されても、勾留先の警察署の留置施設で、家族や友人と面会(接見)できるのが通常です。
しかし、逮捕・勾留されている被疑者が、
- 面会人に証拠を捨てるように依頼する
- 面会人と口裏合わせをして自分に都合のいい話をさせようとする
といった証拠隠滅を図るおそれがある場合は、面会人と接見できないようにする
接見禁止
という措置がとられます(刑訴法81条)。
接見禁止は、被疑者が勾留される際に、裁判官による接見禁止決定という決定で付されるものです。
では、ここからが本題です。
鑑定留置と接見禁止の関係について、ここで説明したいことは、
接見禁止は、鑑定留置中には効力を失う
ということです。
理由は、前述のとおり、鑑定留置中は、勾留が停止するためです。
勾留が停止するので、勾留に付随して機能している接見禁止も効力が停止するという考え方になります。
なので、鑑定留置中は、接見禁止の効力がきれるので、被疑者は面会人と接見し、証拠を隠滅する行為ができてしまうことになります。
鑑定留置中に被疑者に証拠隠滅をされてしまっては、被疑者に適正な刑事罰を与えることができなくなります。
そこで、鑑定留置中に被疑者が証拠隠滅行為を行わないように、新たに、鑑定留置中の接見禁止をつけることができます。
鑑定留置の規定である刑訴法167条5項で、
『勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第1項の留置(※鑑定留置のこと)についてこれを準用する』
と規定しています。
勾留に関する規定とは、接見禁止に関する規定(刑訴法81条)が該当します。
このことから、鑑定留置を行う際に、裁判所が鑑定留置期間中用の接見禁止決定を行えば、鑑定留置期間中でも、被疑者の接見禁止を切らすことことなく、接見禁止の状態を継続させることができます。
鑑定留置中の被疑者の弁護人との接見交通権
逮捕・勾留中の被疑者には、弁護人と接見(面会)できる権利があります。
この接見交通権は、鑑定留置中でも消えることなく、有効に機能します。
被疑者が弁護人と接見し、弁護人からアドバイスを受けることは、刑事事件の素人の被疑者が、刑事事件のプロである警察官や検察官の追求に対抗し、適切な防御をするために不可欠だからです。
鑑定留置中でも被疑者の弁護人との接見の日時を指定できる
接見交通権を規定する刑訴法39条3項に、
『検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる』
と規定があります。
この規定は、逮捕・勾留中の被疑者が、弁護人と接見する日時を、捜査上の都合により指定できるというものです。
刑訴法39条は、鑑定留置中でも有効に機能するので、同条3項も有効に機能します。
そのため、鑑定留置中でも、捜査機関は、精神科医や病院の都合を考慮し、鑑定留置中の被疑者が弁護人と接見する日時を指定できることになります。





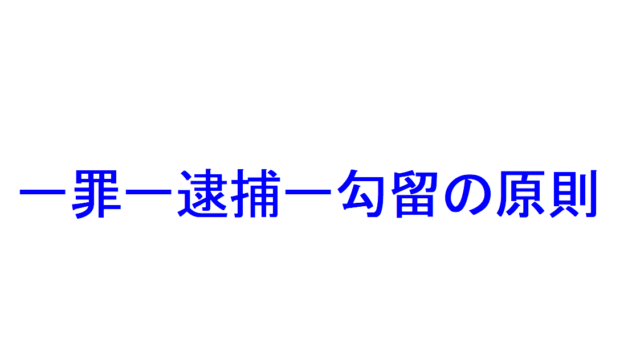

①-320x180.png)