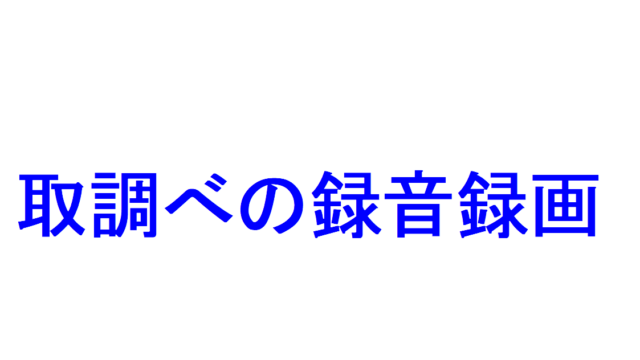自首とは?
自首とは、
- 捜査機関(検察官または警察官)に犯罪事実または犯人が発覚する前に
- 犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し
- 自己の刑事処分を捜査機関に委ねる意思表示
をいいます。
自首の成立要件
自首は、犯罪事実または犯人が発覚する前に行う必要がある
自首が成立するためには、捜査機関に対し、
犯罪事実または犯人が発覚する前
に自首しなければなりません。
捜査機関とは、検察庁に所属する検察官・検察事務官、都道府県警察に所属する警察官(司法警察員・司法巡査)をいいます。
捜査機関以外(裁判官、市役所職員、一般人など)に対して自首をしても、自首は成立しません。
犯罪事実が発覚していても、犯人が特定されていなければ自首は成立する
捜査機関が、既に犯罪事実を知っていても、まだ犯人を特定していなかった場合は、自首をすれば、有効に自首は成立します。
この点、最高裁判例(昭和24年5月14日)があり、裁判官は、
『(刑法42条1項の「捜査機関に発覚する前」とは)犯罪の事実が全く官に発覚しない場合はもちろん、犯罪の事実は発覚していても、犯人の何人たるかが発覚していない場合をも包含する』
と判示しています。
氏名や所在を明らかにする必要がある
自首は、自首後、すぐに捜査機関の支配下に入り、取調べなどの捜査を素直に受ける態勢である必要があります。
なので、たとえば、
- 警察署に行って自首しても氏名を隠したり
- 警察署に自首の書面を送りつけるだけで、自分がどこにいる分からない自首
は、自己の刑事処分を捜査機関に委ねる意思表示とはいえないので、自首が成立しません。
自首が成立するには、犯人が
いつでも捜査機関の支配内に入る態勢
でいることが必要になります。
なので、たとえば、電話や投書で自首をして、犯人がどこにいるか分からなかったり、犯人が外国にいるといった場合は、有効な自首になりません。
自発的に犯罪事実を申告しなければならない
自首は、自発的に自己の犯罪事実を捜査機関に申告しなければ成立しません。
したがって、捜査機関に犯罪事実を申告してみたものの、言い訳をしたり、捜査機関の追求の末に犯罪事実を正直に話したなどの場合では、自首は成立しません。
この点について、最高裁判例(昭和29年7月16日)があり、裁判官は、
『被告人が職務質問に際し、種々弁解した後、結局本件の犯行を自供したのであるから、自首とはいえない』
と判示し、正直かつ素直に犯罪事実を申告しなければ、自首は成立しないことを示しました。
他人に自己の犯罪を申告してもらっても自首は成立する
自首は、必ずしも犯人自身がする必要はなく、他人を介して、自己の犯罪事実を捜査機関に申告しても有効に成立します。
この点について、最高裁判例(昭和23年2月18日)があり、裁判官は、
『被告人は、本件犯行を犯し、いまだ官に発覚しない前に、その次男を介し、司法警察吏に、その犯行を申告している』
『自首は、必ずしも犯人自らこれをなすことを要せず、他人を介して自己の犯罪を官に申告したときにも、その効力はあるものと解すべき』
と判示し、他人を使った自首も有効に成立するとしています。
当然ですが、他人が勝手に、犯人に相談することなく犯罪事実を捜査機関に申告した場合は自首にはなりません。
他人を介した自首が成立するためには、犯人と他人との間に「自首をする」という意思の連絡が必要になります。
捜査中事件の取調べ中に余罪を自供しても、自首には当たらない
犯人が、捜査中の事件の取調べにおいて、「ほかにも犯罪をやっています」という感じで、余罪として犯罪を申告する場合があります。
このような余罪の自供は、自首には当たらないとされます。
自首の申告内容に嘘が含まれていた場合
自首の申告内容に、うそが含まれていた場合に、有効な自首として成立するかどうかは、嘘の程度によりまます。
人は、「とにかく自分を正当化したい」「自分を悪く見せたくない」という正当化バイアスを持っているので、自分を良く見せるための嘘を本能的につく生き物です。
人が、自首したときに、自己の犯罪事実を全く嘘を混ぜずに申告するのは、当然には期待できない部分があります。
そこで、嘘を混ぜた犯罪事実の申告が、自首として成立するか、それとも自首として成立しないかは、嘘の程度によって判断されます。
嘘が軽微であれば、有効な自首として認定されるかもしれませんが、嘘が犯罪事実の重要な部分に関することであれば、有効な自首として認められない可能性が高いと考えられます。
自首の方法
自首の方法は、告訴・告発の手続が適用される
自首の方法は、告訴・告発の手続と同じ方法が適用されます(刑訴法245、241、242)。
刑訴法241条の「告訴又は告発」を「自首」に読み替えると以下のようになります。
『自首は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない』
『検察官又は司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない』
「書面又は口頭」が、どのような手続なのかについては、告訴の記事で解説しています。
自首をすると刑罰が減軽または免除されることがある
自首が有効に成立すると、刑罰が減軽または免除されることがあります。
(必ず刑罰が減軽または免除されるわけではありません)
どのくらい刑罰が減軽されるかは、刑法68条に規定あり、
- 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする
- 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする
- 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる
- 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる
- 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる
- 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる
とされます。
刑が免除されるとは、有罪となった場合に、刑を科すのを免除するということです。
たとえば、窃盗罪を犯して、裁判官から懲役1年の実刑という刑を科せられても、自首をしていて、裁判官が刑を免除するという判決をしていれば、懲役1年の実刑を受けずにすみます。
自首をすれば必ず刑罰が免除される犯罪がある
自首をすれば、必ず刑罰を減軽してもらえる犯罪が2つあります。
その犯罪は、
です。
内乱罪については、刑法80条で、『暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する』と規定し、暴動に至る前の自首であれば、刑が必ず免除されます。
私戦予備・陰謀罪については、刑法93条で、『自首した者は、その刑を免除する』と規定し、自首すれば必ず刑が免除されます。
【追記】首服とは?
これまで、自首について説明してきました。
自首は、捜査機関に対し、自己の犯罪事実を申告するものです。
ここで、自己の犯罪事実を申告するもので、
首服(しゅふく)
があります。
首服とは、
親告罪の告訴権者に対し、犯罪事実を申告し、自己の処分を委ねること
をいいます(刑法42条Ⅱ)。
自首は、捜査機関に対し、犯罪事実を申告するのに対し、首服は、親告罪の告訴権者に対し、犯罪事実を申告する点に違いがあります。
首服が有効に成立すれば、自首と同様に、刑罰が減軽または免除される場合があります。
また、首服が有効に成立するためには、自首と同様に、犯罪事実または犯人が告訴権者に発覚する前に行われることが必要になります。
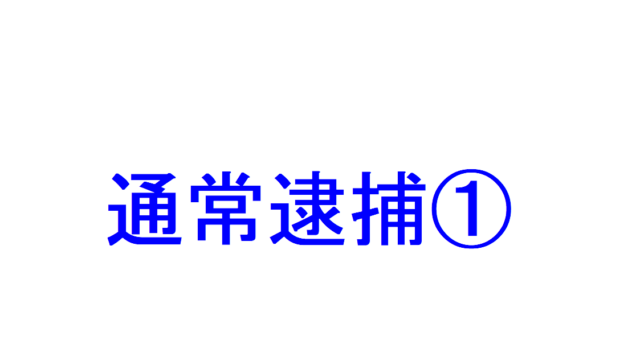

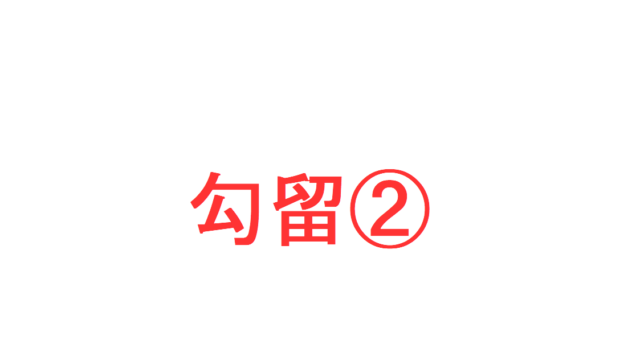
①-640x360.png)