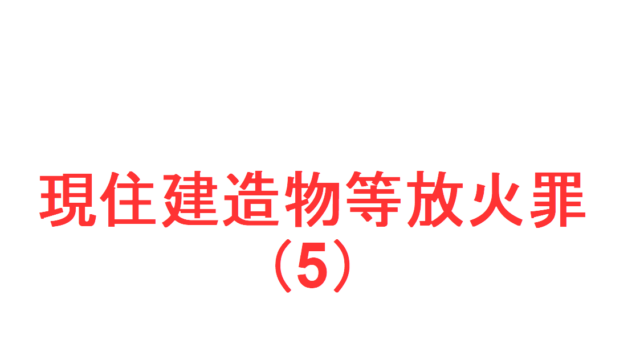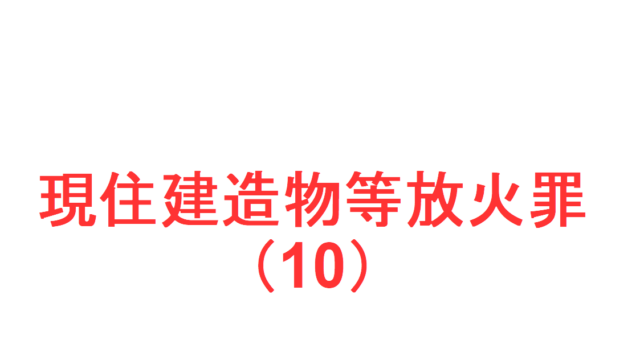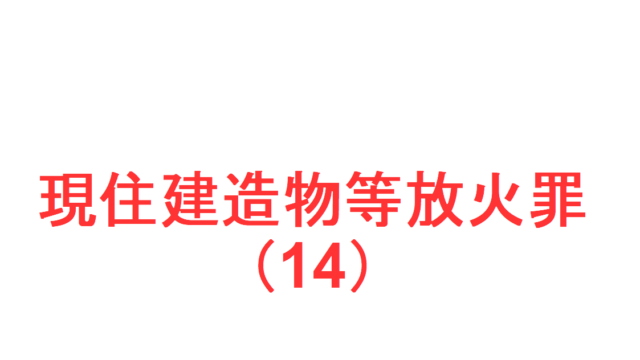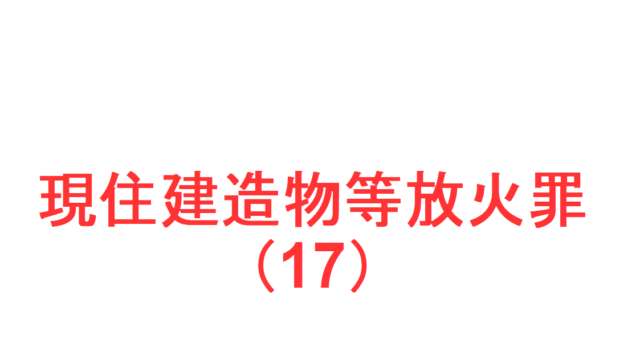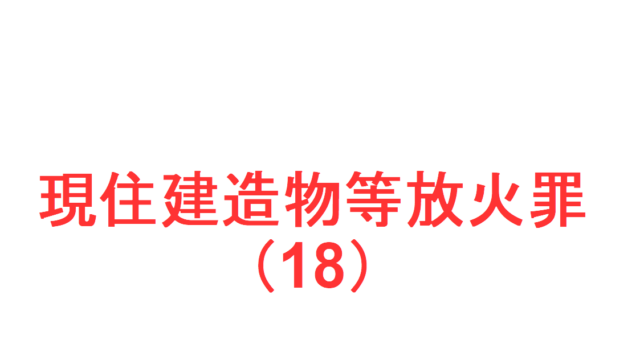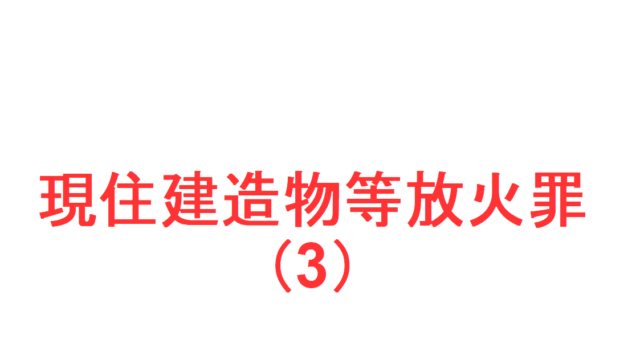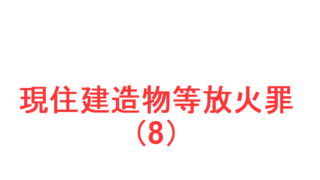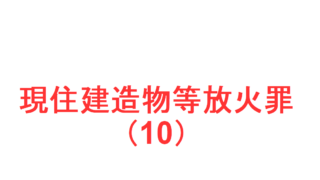現住建造物等放火罪(9) ~実行の着手②「ガソリン散布等による放火」を説明~
前回の記事の続きです。
放火罪の実行の着手の態様は、
- 点火行為による放火
- ガソリン散布等による放火
- 発火装置による放火
- 非現住建造物を媒介とする現住建造物の放火
に分けることができます。
前回の記事では、点火行為による放火を説明しました。
今回の記事では、ガソリン散布等による放火を説明します。
実行の着手の具体例「ガソリン撒布等による放火」
ガソリンあるいは可燃性ガスのように、引火性の高い物質を導火材料とし、これを撤布、放出したときは、被告人の点火行為前に何らかの火源によりそれが引火し、目的物の焼損に至る場合があります。
行為者に放火の主観的意図があり、焼損という結果発生に対する高度の客観的な危険性が現実に認められるにもかかわらず、点火行為がないことを理由に実行の着手なしとして、現住建造物等放火未遂罪(又は火現住建造物放火未遂罪)は成立せず、放火予備罪(刑法113条)、失火罪あるいは重過失失火罪の責任にとどまるとするのは妥当ではありません。
そこで、引火性の高いガソリンや可燃性ガスなどを住宅内で撒布、放出して高度の危険性を生じさせた場合のように、危険発生の程度によっては、放火の実行の着手が認められます。
ガソリン等の撒布行為に実行の着手を認めた裁判例
ガソリン等の撒布行為に実行の着手を認めた裁判例として以下のものがあります。
静岡地裁判決(昭和39年9月1日)
店舗兼住宅に使用している他人の料理店の放火を決意し、店外からその木造の出入口ガラス戸、ガラス窓等にガソリソ約5リットルを撒布している最中に、店内にガソリンが滲出し、これに店内の出入口から1.5メートルの位置に置かれた煉炭にコンロの火が引火して、家屋の一部を焼損した事案です。
裁判官は、
- 被告人は、本件建物燃焼の意思の下にガソリンを散布したものであり、かつ右行為により本件建物の燃焼を惹起すべきおそれある客観的状態に至ったものというべきである
- 従って、被告人は、放火の意思をもって放火罪の構成要件に該当する行為を開始したものとみるのが相当である
とし、ガソリンを散布行為が実行の着手の時点であるとした上、現住建造物等放火罪が成立するとしました。
広島地裁判決(昭和49年4月3日)
放火を決意してガソリン2缶を可燃性の高い木造家屋内(A家)に搬入し、密閉した台所でプロパンガスを多量かつ相当時分にわたって放出し、石油ストーブを使用している部屋の隣室にガソリン1.8リットルを滲出させたところ、隣室の石油ストーブから、充満したガスに引火して出火した事案です。
裁判官は、
- 被告人はA家への放火を決意して、ガソリン2缶を買い、これをA家へ搬入したうえ、前記のとおりガスの放出、ガソリン溢出の行為におよんだものであり、その放火の決意は極めて強度であると認められる
- そのうえ、右家屋は前記のとおり可燃性の高い木造家屋であり、被告人は密閉された右家屋の台所、4.5畳の間にレンジからホースを抜いてプロバンガスを多量にかつ相当時分にわたって放出し、また4.5畳の間にガソリン18リットルを溢出させたものである
- これにより被告人の放火の企図の大半はすでに終了し、あとは点火を残すのみで、しかも点火と同時に既遂に達すると予測されるうえ、前記のとおりの対象物の可燃性および放出、撒布された媒介物の危険性に照らせば、右行為によってもたらされた客観的危険状態はかかる媒介物なしに点火行為がなされたのと差異がないほど高度のものと認められ、未だ点火前とはいえ、右は既に予備の段階をはるかに逸脱し、放火の実行の着手があったものと解するのが相当である
とし、現住建造物等放火罪が成立するとしました。
横浜地裁判決(昭和58年7月20日)
自己の居住する木造家屋内に、約64リットルのガソリンを各和室、廊下、台所等大部分に満遍なく撒布したものの、点火前に心を落ちつけるためライターでタバコに火をつけようとしたところ、その火がガソリンの蒸気に引火して家屋を焼損した事案です。
裁判官は、
- ライター点火は家屋焼損のためとは認められないが、そこに何らかの火気があれば、火災発生は必定の状況にあったから、ガソリン撒布により放火について企図したところの大半を終えたものといってよく、この段階で家屋焼損の切迫した危険が生じたと認められ、放火罪の実行の着手があったものと解するのが相当である
- 本件焼損の結果は、被告人自身がたばこを吸おうとして点火したライターが火に引火して生じたものであるが、前記状況の下でライターを点火すれば引火するであろうことは一般人に客観に理解されるところであって予想し得ないわけでもないから、右のような経緯で引火したことにより本件結果が生じたからといって因果関係が否定されるものではなく、被告人は放火既遂罪の刑責を免れない
とし、現住建造物等放火罪が成立するとしました。
ガソリン等の撒布行為に実行の着手を認めなかった裁判例
上記裁判例とは逆に、実行の着手を否定した以下の裁判例があります。
東京地裁判決(昭和57年7月23日)
自己の居住する木造アパートに放火を決意し、ガスの炎で家具類に放火して部屋全体を燃やすべく、布団の上に座りガスホースから噴出するガスにライターで点火したが、炎の余りの大きさに驚愕、狼狽して当初の放火の意図を喪失し、あわててガスホースを窓から室外に出しガスの元栓を閉じたが、炎が窓の外のすだれに燃え移り、これを放置したため、アパートの一部を焼損した事案です。
ライター点火の時点で実行の着手があるとする主位的訴因(作為による現住建造物等放火罪)に対し、家具等に炎が直接あたる状態でなく、被告人の上記行為がなければ、建物に延焼する可能性を有する可燃物に燃え移る具体的危険性が認められないので、実行の着手があったといえないとし、不作為の放火の予備的訴因(不作為による現住建造物等放火罪)を認定しました。
※ 作為、不作為の説明は前の記事参照
裁判官は、
- 本件主位的訴因の要旨は、「被告人は、昭和57年3月5日午後9時15分ころ、自室において、ガスストーブのホースを取りはずし、ホ-スから放出するガスに所携の電子ライターで点火して火を放ち、その炎を窓にかけてあったすだれに引火させて1階霧除け及び1階天井等に燃え移らせて本件建物を焼燬した。」というにあり、そこでは、(1) ホースから放出するガスに点火した時点で実行の着手があり、以後の経過は犯罪の成否に影響しない、あるいは(2)被告人は放火の故意を有したままホースから噴出する炎をすだれに引火させた、という判断が前提となっている
- そこで、この各点について判断する
- (1)まず、ホースから放出するガスに点火した段階で、現住建造物等放火の実行の着手があったものとみるべきかどうかという点についてであるが、被告人の当公判廷における供述、検察官に対する各供述調書、本所消防署消防士長作成の火災原因判定書等によると、被告人は、自殺を諦めた後、自室内周囲にある家具放火しようと決意し、自室南寄りに敷いた布団の上にすわり、右手でホースを持ち、左手に持ったライターで点火し、炎が50センチメートルから1メートル出たが、家具等に直接炎があたる状態ではなかったと認められ、炎を噴出するホースを未だ自ら握持し、その火を自己の管理下にとどめていて被告人の意思に基づく次の行為がなければ周囲にある建物に延焼する可能性を有する可燃物に燃え移る具体的危険性が認められない以上、この段階で実行の着手があったものとすることはできない
- (2)次に、ガスホースを窓から外へ出し、すだれに引火させた時点で、なお被告人に当初の放火の故意が継続していたものと認められるかという点であるが、前掲証拠を総合すれば、被告人はガスホースから噴出するガスに点火後、その炎の大きさに驚愕・狼狽し、慌てて窓を開けて炎を室外に出し、ガスの元栓を閉め るという行動をとったものと認められ、窓からホースを外へ出した行為は、直後のガスの元栓を閉める行動と併せ考えると、引火を防ぐ消極的過程での一連の行動とみるべきであり、この時点でなお当初の放火の故意を継続して有していたものと認めることは困難である
- 従って、すだれに着火したことを被告人の放火行為に基づくものと評価することはできない
- 以上説示のとおり、ガスへの点火自体を放火行為の着手とし、あるいはすだれに引火させて火を放ったとする主位的訴因はこれを認めることができない
と判示しました。
この裁判例は、ガスの噴出行為自体の危険性ではなく、点火されたガスが導火材料に燃え移る危険性が問題になり、客観的危険性の有無により実行の着手の有無が判断されたものです。
大阪高裁判決(昭和57年6月29日)
放火が殺人の手段となっている殺人事件に関する事例です。
子供部屋に閉じこもった妻(A子)を焼殺すべく、隣接する台所のガス栓から都市ガスを15分間漏出させた事案につき、至近距離に裸火がありガス漏出により直ちに着火する場合は格別、簡易ライターを手に持っていたにとどまる行為は、殺人未遂罪ではなく、殺人予備罪に該当するとしました。
裁判官は、
- 原判決(※一審の判決)は「自宅1階4畳半の子供部屋にA子が逃げ込み、その長男Bと共に同部屋に閉じこもり、A子らに同部屋から出てくるように何度も呼びかけたが、これに応じないことに激高すると共にA子の右態度からA子が浮気をしていてその前夫と同様自分も捨てられるものと思いつめ、そうなるよりむ しろ、ガスを漏出させてそれに点火してA子を焼殺し、自己も焼死して無理心中しようと企て、直ちに、右子供部屋に隣接している台所のガス栓に接続されているガスレンジ及びガス湯沸器のホースを引き抜きガス栓2本を開き、屋内に都市ガス(天然ガス)を約15分間にわたり漏出させ、これに所携の簡易ライターで点火することでA子を焼殺しようとし、その生命に危険を生ぜしめたが、ガスの元栓を閉鎖されて逮捕されたため、A子殺害の目的を遂げなかった」との事実を認定し、これにガス等漏出罪及び殺人未遂罪を観念的競合として適用している
- そのガス等漏出罪の適用は正当であるけれども、殺人未遂の点につき、原判示の挙示する対応証拠及び当審における事実調の結果によれば、天然ガスには一酸化炭素が含まれていないから、これが漏出しても、いわゆるガス中毒死を招く危険はないものであるところ、本件において、被告人は屋内に充満したガスに点火して木造2階建の自宅を燃やし、A子を子供部屋で焼き殺すか、又は火に驚いて出て来ればこれを屋内でつかまえて焼き殺す意図をもって、ガスを漏出させた上、簡易ライターを手に持っていたことが認められ、原判決もこの事実を判示しているものと解される
- そうすると、被告人は建造物に対する放火を手段として、その一室に閉じこもっているA子を焼殺しようと企て、その放火の準備として原判示ガスを漏出させたが、点火するには至らなかったのにほかならず、このように、建造物に対する放火が殺人の手段となっている場合においては、放火の着手が同時に殺人の実行行為の着手にあたるもので、至近距離に裸火があって、ガスを漏出すれば直ちに着火することが明らかであるような場合は格別、右放火の準備として屋内にガスを漏出した上、簡易ライターを手に持っていたにとどまる被告人の右行為は、いまだ殺人の実行行為に着手したものにあたらず、殺人を目的とした殺人予備の行為に該当すると解するのが相当である
と判示しました。
次回の記事に続く
放火罪の実行の着手の態様は、
- 点火行為による放火
- ガソリン散布等による放火
- 発火装置による放火
- 非現住建造物を媒介とする現住建造物の放火
に分けることができます。
次回の記事では、発火装置による放火を説明します。