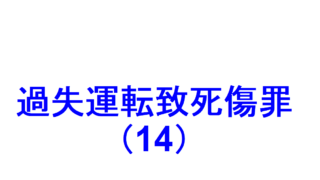過失運転致死傷罪(15)~「大型車両が横断歩道を左折する際に横断歩道上の走行自転車と衝突した際の過失認定」を説明~
前回の記事の続きです。
大型車両が横断歩道を左折する際に横断歩道上の走行自転車と衝突した際の過失認定
大型車両(大型トラック、大型バスなど)が横断歩道を左折する際に横断歩道上を走行してきた自転車と衝突した場合(左巻き込み事故など)は、状況によっては大型車両の運転者の過失が否定され、過失運転致死傷罪が成立が否定される場合があります。
横断歩道上を走行する自転車の扱い(道交法38条1項の保護はない)
1⃣ まず、「横断歩道上を走行する自転車」の扱いについて説明します。
道交法38条1項は、
- 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない
と規定します。
道交法38条は、
「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には」
「横断しようとする歩行者又は自転車が」
といった具合に、自転車横断帯を横断する自転車に対しても、横断歩道上の歩行者と同等の手厚い保護をしています。
したがって、自転転車横断帯上を走行する自転車と衝突する事故が発生した場合、過失の認定の仕方は、基本的には、歩行者の場合と変わりありません。
しかしながら、道交法38条の規定から見て、横断歩道上(自転車横断帯ではない)を走行する自転車を自転車横断帯上を走行する自転車や横断歩道上の歩行者と同視することはできず、横断歩道上を走行する自転車は道路交通法38条の対象になりません。
実際、横断歩道上を横断する自転車は、横断歩道を通過する車両に対して、道路交通法上当然に優先権を主張できる立場にはないと明示した以下の裁判例があります。
東京高裁判決(昭和56年6月10日)
裁判所は、
- 道交法12条1項は横断歩道がある場所付近での横断歩道による歩行者の横断義務を、また、同法63条の6は自転車横断帯がある場所付近での自転車横断帯による自転車の横断義務をそれぞれ定めているので、横断者が右の義務を守り、かつ青色信号に従って横断する限り、接近して来る車両に対し優先権が認められることになるのであるが(道交法38条1項)、本件のように付近に自転車横断帯がない場所で自転車を運転したまま道路横断のため横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていないのであるから、本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車輛に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはないわけであり、従って、自転車を運転したままの速度で横断歩道を横断していた被害者にも落度があったことは否定できないところであり、被害者としては接近して来る被告人車に対して十分な配慮を欠いたうらみがあるといわなければならない
と判示しました。
2⃣ ただし、「自転車横断帯が併設されている横断歩道」を横断中の自転車については、道交法38による保護の対象になると考えられます(少なくとも同条の準用がある)。
併設横断歩道上の自転車は、自転車横断帯の直近を横断する自転車ということになるので、横断歩道直近を横断する歩行者及び自転車横断帯直近を横断する自転車も同条の保護が及ぶと考えるのが相当だからです。
大型車両が横断歩道を左折する際に横断歩道上の走行自転車と衝突した際の過失認定の考え方
横断歩道は、あくまで歩行者専用(道交法2条1項4号)なので、本来、横断歩道を利用して道路を横断しようとする自転車の運転者は、自転車から降りて自転車を押しながら歩いて 横断歩道を横断すべきなのですが、実際には、自転車の運転者が自転車に乗ったまま横断歩道を横断するというのが、いわば「当たり前」になっているので、車両の運転者としても、横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者がいることを念頭に置いて運転する必要があります。
なので、車両の運転者はこのような自転車との衝突事故を回避すべき義務があり、前方左右の注視義務を怠った結果、横断歩道上の走行自転車の発見が遅れ、あるいは未発見のまま衝突させて自転車の運転者を死傷させた場合、過失運転致死傷罪が成立する場合があります。
しかし、横断歩道上の歩行者の場合とは異なり、常に自動車運転者側の過失が肯定されるわけではありません。
交通の実態として、自転車に乗ったまま横断歩道を横断することが許容されているといっても、自転車は軽車両であって(道交法2条1項11号)、歩行者ではなので、横断歩道を利用して道路を横断する場合は、下車した上で自転車を押して徒歩で横断するというのが原則(法の建前)であり、例外的に自転車に乗ったまま横断する場合は、歩行者の通行を妨害してはならないのはもちろん、対車両に関しても、相応の危険を負担しなければならないものです。
自転車は歩行者に比べてずっと高速度で移動可能なので、自動車運転者側でも対歩行者以上に注意を払わないと衝突の危険があり、よって、自転車という交通手段の利便を享受する以上、自転車運転者側にも、適正な危険の分配をするのが相当となります。
被害自転車側の不適切な走行態様が事故発生に相当程度寄与したような場合は、量刑上考慮されることはもとより、自動車運転者側の予見可能性や結果回避義務自体が否定される場合もあります。
大型車両が横断歩道を左折する際に、横断歩道を走行する自転車と衝突した事故に関し、大型車両運転者の過失が否定され、無罪が言い渡された事例
無罪が言い渡された事例として以下のものがあります。
東京地裁判決(昭和47年8月12日)
交差点を左折進行しようとした大型貨物自動車が、同交差点の左折方向出口に設けられた横断歩道上の歩行者を認めて横断歩道手前で一時停止し、この歩行者が自車の前方を通過するのを待って発進したところ、左方歩道から進行してきてそのまま横断歩道の横断を開始した自転車に自車左後輪付近を衝突させたという事故です。
裁判所は、
- 自転車は原則として歩近を通ってはならず、車道左端に沿って通行しなければならないわけで(道路交通法17条1項、3項、17条の3)、本件の場合被害者の自転車が車道を走行していたとすれば、被告人車の後行車となるわけで、同法34条5項の規定により左折車が適式な左折合図をしている場合には、後行車は左折車の左折を妨げてはならないのである
- ただ自転車については、道路の横断にあたっては、その安全上むしろ横断歩道を利用し、自転車を押して渡るよう指導されているところであり(交通の方法に関する教則・交通ルールブック警察庁交通局監修11頁)、本来歩行者の歩行や横断の用に供するため設けられた歩道や横断歩道(同法2条1項2号、4号)を利用する以上歩行者と同様の心得が要求されることは当然のことであり、自転車の運転者が道路を横断するにあたって横断歩道を利用する場合には、自転車に乗ったまま疾徒し、飛び出すような型で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであって、自動車運転者はこのような無暴な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる
- 本件についてみるに、本件横断歩道を横断しようとする者の有無の確認範囲については、 般にこれをある程度の蓋然性をもって認め得るところの横断歩道の外周について認めるべきであるが(横断にあたっては通常の歩行状態だけではなく小走りで横断する者もなくないのでそれらの点は考慮に入れるにしても)別紙図面(ア)点にいる人については、果して同人が本件横断歩道を横断し始めるものか、歩道に沿い大森方左折するか、はたまた川崎方面の横断歩道を渡るつもりでいるのか不明であり、いずれの可能性が高いというようなこともいい得ない状況にあり、(ア)付近の範囲までもみて本件交差点を横断しようとしている人がいるかどうか判断すべき義務あるとまでは認め難いところである
- とりわけ本件の場合のように横断歩道左側端より7ないし9メートル余りの地点に自転車に乗ったまま走って本件横断歩道を横断しようとする者があることまで考慮に入れて(ア)付近まで確認すべきであるとすることには自動車運転者と他の交通関与者との危険分配の原則の観点からいっても疑問である
- また横断歩道に接近した地点にいて当該横断歩道に向かっている者についてはその場所的接近性、歩行者の体勢からいって横断しようとしている蓋然性がある程度の強さをもって推測できるので、この場合はこれを打消す要素がうかがえるまでは発進をさし控えるのが通常であろうが、本件のように横断歩道からある程度離れた地点にいていまだ予測が十分できかねるような人については、むしろその明確化を待っというより速やかに発進するのが現下の交通事情のもとでは普通ではなかろうかとも考えられ、発進をさし控えなかったことをもって可罰的な不注意であるとはいい得ないと考える
- そしてまた、本件の場合の左折車の運転者が仮に別紙図面(ア)に自転車に乗って走行して 来る人を認めたとしても、本件横断歩道を横断しようとすることの明確性およびその切迫性およびその切迫性を認め難い以上は、その人が自車の発進を知り得る状況となってから避譲の措置に出たとしても十分避譲することが可能な時間的距離的余裕のある限り自車の左折を妨げることはないものと信頼して左折を始めることは許されてよいのではないかとも考えられるのである
- 本件においては被害者が別紙図面(ア)地点を通るあたりで被告人車は発進を開始し(2)点から(3)点に向け進行を始めたわけであり、同車が車長9.85メートルもの大型車であり、被害者が(ア)地点から本件横断歩道にさしかかった時点においては被告人車の発進を容易に認識し得たのではないかとの合理的な疑いをさしはさみ得る余地があり、被告人車と被害者の衝突地点が被告人車の左後輪付近であることからいって被害者が歩道上より横断歩道上におりようとするころには被告人車はかなり左折し切って横断歩道をふさぎつつあった状況にあり、他方被害者被害者の自転車の速度は時速9キロメートル、秒速2.5メートル程度であったのであるから、その速度と自転車の制動力、被告人車が発進しようとした地点における被害者の位置、関係距離からみて、被害者が被告人車の発進に対処してこれとの衝突・接触を避けるに十分な余裕があったのではないかとの強い疑問があり、被告人が被害者の通過を待たないで発進したことをもって被告人の過失と認め得るまでの心証はとれないのである
- そして左折車の運転者としては左折開始後は前方左右を注視することになるので、その後被害者が被告人車の左後輪付近に接触・転倒するまで気付かなかったとしてもこの点をもって過失とすることもできないと考えられるのである(本件を大局的に見ると、被害者は前記認定のように停止中の被告人車の前をおばあさんが横断中であるのを認め自分も早く横断してしまおうとするのあまり被告人車の動静についてじゅうぶん注意せずむしろ加速するようにして先を急いだため、予期に反して被告人車が発進してしまい、そのうえ内輪差の関係で被告人車の車体が急に迫って来たため、ろうばいして適切な衝突回避の措置もとり得ないまま被告人車と接触してしまったのではないかとの疑をぬぐい去ることができないのである。)
- 結局本件については被告人に本件事故発生について別紙図面(ア)の付近を確認しなかったことをもって過失とすることには疑問があり、かつまた被告人が横断歩道上およびこれに近接する周辺について確認しなかった不注意な行為と結果発生との間に刑法上の因果関係を認め難いので、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになり、刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡をする
と判示しました。
この事故は、
- 事故車両が自転車運転者側からも容易に認識可能な大型貨物自動車であったこと
- 自転車運転者において、大型貨物自動車の発進を認めた時点でブレーキをかければ、横断歩道手前で停止することが容易な位置関係にあったこと
- 衝突部位が大型貨物自動車の左後輪付近であって、衝突時、既に同車が横断歩道の相当範囲を塞いだ状態であった
ことなどの事情があり、自転車運転者の方が、著しい前方不注視により大型貨物自動車が発進して進路前方を塞いでいる状況に気付かず、その左側後輪付近に激突した事故だったので、事故発生の主因は、自転車運転者の無謀な運転にあったといわざるを得なかった事案でした。
大型車両と横断歩道上の走行自転車と衝突した事故に関し、過失を認定した事例
上記裁判例とは反対に、大型車両運転者の過失を認定した事例として、以下の裁判例があります。
福岡高裁判決(昭和52年4月26日)
左側に死角のある大型貨物自動車を運転して交差点を左折進行中、左折方向出口に設けられた横断歩道の手前で一時停止後発進した際、死角内を進行してきた自転車と衝突した事案です。
この判決では、助手席側に移動するなどして死角を解消し、四囲の安全を確認して発進す べき注意義務を認めて大型車両の運転者の過失を認定したものです。
この判決は上記東京地裁判決と異なる事情として、
- 事故時、当該横断歩道を利用する通行者が比較的多かったこと
- 大型貨物自動車の運転者において、交差点の左折を開始する前に、自車左側の歩道上を同 横断歩道に向かって進行してくる被害自転車を認めていたこと
などを理由に挙げて大型車両運転者の過失を認定しました。
具体的衝突状況までは判文上明らかではありませんが、被害自転車が横断歩道上を横断中に被疑車両と接触した事故のようであり、横断歩道を自転車に乗ったまま進行したことを除いては被害者側に落ち度はなかった事案と考えられます。
こうような事情の違いが、上記東京地裁判決と過失の有無についての判断が分かれた理由と考えれます。
判決内容は以下のとおりです。
まず、被告人の弁護人は、
- 原判決は、大型貨物自動車を運転し原判示の如く交差点を左折進行中に 歩行者の通過を待っために横断歩道の手前で一時停止した被告人に対し、右通過後再び自車を発進進行する場合には助手席に移動する等して、自車の死角圏内を含めて四囲の安全を確認したうえ発進すべき業務上の注意義務がある旨判示するが、右は誤りであって、被告人にはかかる注意義務は存しない
- (1)まず原判決は、死角圏内の安全を確認する具体的方法として「助手席に移動すること」を要求するのであるが、右は本件大型貨物自動車の運転台の構造上相当に困難であるばかりでなく、誤って車を発進させる虞れもあって危険であるから、かかる行為を運転者に要求することは相当でなく、その他死角圏内の安全を確認する方法として運転席から下車して自車の周囲を廻ることも考えられるが、これは後続車の渋滞等を招来するので現実的にはたやすく実行できないことである
- (2)そうしてみると、盲人の横断とか幼児の飛び出しなど危険が予見されるが如き特別な状況の場合は別として、そのようなことが予見されない場合をも含め一般的に、大型貨物自動車の運転者に対して自車の死角圏内の安全までを確認すべき注意義務を課することは、交通の実情等に照らして苛酷に過ぎ相当でないものというべきである
- (3)しかして、本件においては危険が予見される特別の状況は存しなかったのであるから、原判示の如き死角圏内の安全を確認すべき注意義務はなく、被告人の注意義務としては運転席から肉眼及びバックミラー等で現認可能な範囲内の安全を確認しながら、危険を感じた場合に直ちに停止できるような速度及び方法で低速進行することで尽きていたものというべきである
- 従って、被告人に対して実行不可能な注意義務を課し、その懈怠を理由に業務上過失傷害罪の成立を肯認した原判決は、注意義務の構成を誤ったものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから破棄を免れない
として無罪を主張しました。
この主張に対し、裁判所は、
- 原判決の認定する関係状況を前提とする限り、被告人が自車の死角圏内を含めて 四囲の安全を確認すべき業務上の注意義務を負っていたことは否定できず、右の死角圏内の安全確認の方法として「助手席に移動すること」を例示したことにも誤りは認められない
- まず所論にかんがみ、本件大型貨物自動車の運転者に対し、助手席に移動することを要求することの当否につき検討するに、関係証拠を精査しても、右の移動が困難にしてこれを要求することが不当なものとは認め難く、この点につき当裁判所の検証調書にも明らかな如く、本件大型貨物自動車の運転席(中央)から左側(助手席側)のドアまでは約1.7メートルの距離が存するところ、ハンドルと運転座席との間隔が狭く、運転席と助手席との間にはフロアシフト式のチェンジ・レバー及びサイドプレーキ・レバーが突出しているので、運転者から坐ったままで助手席に移動することは必ずしも容易とはいえないが、中腰になれば右移動は比較的容易であることが認められる
- したがって、運転台の構造上運転席から助手席の移動がそれほど困難であるとは認められず、また、その移動に際し誤って車を発進させる危険があるとも認め難い
- もっとも、被告人は当審において右の危険を指摘すると共に、かかる安全確認の方法を会社関係者より指示されたことはなかった旨供述するのであるが、右結論を左右するに足りない
- してみれば、原判決が死角圏内の安全確認の方法として、「助手席に移動すること」を例示したことをもって不当ということはできない
- もとより右は例示であって、運転者がとるべき方法としては、その他にも運転席から下車して必要な安全確認をするとか(右は原審において訴因変更後検察官が主張するところである。)又は休憩中の交替運転手を助手として使用するなどして死角部分を除去する手段も存在する
- もっとも、助手席の移動や下車などの方法はいずれにせよ当該運転者にとって運転席を離れる欠点があり、後続車の渋滞等をもたらす虞れがあることも所論指摘のとおりであるから、かかる方法で死角圏内の安全を確認する注意義務が存したかどうかは、なお具体的な関係状況に即してさらに検討すべきものである
- そこで、被告人に右の死角圏内の安全確認義務が存したかどうかを検討するに、原判示挙示の証拠によれば、原判示関係状況がいずれも十分に認められ、これら関係状況を前提とする限り、被告人が一時停止後再発進するに際して、自車の死角圏内にある左側の横断歩道上の安全を確認すべき業務上の注意義務が存したことはたやすく否定できないところである
- すなわち、原判決が認定せる関係状況、とりわけ、(イ)本件事故が発生したのは昭和49年9月26日の午後6時50分頃であり、現場は北九州市門司区内の市街地に存する交通整理の行なわれている交差点及びその西側人口に設置された横断歩道であって、右横断歩道の通行者も比較的多いこと、(ロ)被告人は右交差点を南方から西方に左折しようとして、信号待ちのため同交差点南詰で一旦停止した際、自車左側の歩道上を南方から北方に向い直進しているW(当時13歳)運転の自転車を認めたこと、(ハ)被告人はその後間もなく 自車の対面信号機が左方向への青色矢印信号を現示するのに従って左折進行したものであるが、左折方向の自車前面にあたる本件横断歩道上を青色信号に従って右(北方)から左(南方)に横断してきた歩行者を認めたので、その通過を待つべく同横断歩道の手前で一時停止したこと、(二)被告人は右歩行者が自車の前面を通過したので、再び発進進行しようとしたものであるが、被告車は車体の長さ約11.54メートル、幅約2.49メートル、高さ約3.2メートルの大型貨物自動車であって、運転席からのバックミラーやアンダーによる自車左側方への視認可能範囲が極めて狭く、右再発進の地点においては本件横断歩道の左半分(南側)は死角圏内に入って視認不可能な状態であったこと、これらの関係状況にかんがみると、被告車の左側の横断歩道には渡辺秀樹はもとより他にも青信号に従って南方から北方に進行する歩行者等が存在することが予想され、しかも、かかる歩行者等においては被告車が横断歩道の手前で一時停止したことから当然自己の通行を認めてくれて被告車の前を通過するまで停止してくれるものと考え、これを信頼して行動することが予測されるのであるから、被告人が自車の左側の横断歩道上の安全を確認しないままで発進することは到底許されないものであり、その死角圏内の安全を確認すべき注意義務を負うことは明らかである。(なお、被告人の当審における供述等のうちには原判示関係状況と相容れない部分も存するが、右供述部分はたやすく措信できない。)
- これに対し所論は、原判示の如く助手席に移動したり、下車したりして死角圏内の安全を確認することは、現在の交通事情等にかんがみるとき、現実の問題としては運転者に不可能を強いるものであるし、仮にこれを履践してみてもその後運転席に戻って発進するまでの間に死角圏内に歩行者等が進入すれば、その者との関係で盲発進となるのであるから結局無意味なことであるというのである
- しかし、原判示の如き方法で死角圏内の安全を確認することが当該運転者にとって手間のかかることであり、交通渋滞をもたらす虞れも否定できないとしても、かかる難点は横断歩道上の歩行者等の安全確保のためにはやむをえないものであって(これを除去するためには助手を置くことが望ましいことはいうまでもない。)かかる難点を理由として運転者に不可能を強いるものということはできない
- また、助手席に移動する等して安全を確認してみても発進までの間に新らたに死角圏内に進入する者がいれば、その者との関係で盲発進となることは所論指摘のとおりとしても、少くとも本件における前記関係状況においては、被告人が死角圏内の安全確認を行なうことによって本件事故を防止することができたのであり、所論の如く右の安全確認後発進するまでの間に新たに死角圏内に進入する者がある場合ではない
- もし右の如き状況であれば、それに応じた安全確認を更にすべきものである
- いうまでもなく注意義務はそれぞれの関係状況に応じて生起するものであって、所論の如き状況が考えられる場合がありうるからといって、本件の場合における被告人の前記注意義務を否定すべき理由はない
- また所論は、本件の前記関係状況においても、被告人には原判示の如き死角圏内の安全までを確認すべき注意義務はなく、再発進に際しては運転席から肉眼及びバックミラー等で視認可能な範囲内の安全を確認しながら低速進行すれば足りるものであり、被告人は右の限度でその注意義務を十分に尽したものであるというのである
- しかし、被告人に死角圏内の安全を確認する注意義務が存することはすでに説示したとおりである
- のみならず、原審取調の証拠を仔細に検討するときは、被告人が所論主張の限度における注意義務を十分に尽したものとは認め難いので、所論はいずれにせよ採用するに由ないものである。
- (なお右の点につき、《証拠略》によれば、Wは本件横断歩道の南側歩道上で信号待ちをした上青信号に従い自転車に乗ったまま横断歩道に進入しようとし、若干手間取ったものの右横断歩道上を南方から北方にほぼ真直ぐに進行したものと認められ、同人が被告車と接触するまでの間、終始被告車のバックミラー等の死角圏内だけを進行していたものとは認め難く、換言すれば、被告人が一時停止後発進して左折進行するに際し、左側バックミラー等により自車の左側の横断歩道上の状況を確実に注視し続けていたものであれば、ほとんど瞬間的にせよ自転車に乗った渡辺秀樹の姿を発見できたものと認められるのであって、被告人は右注視を怠り、同人を見落したものと認めるほかないのである。なお、これを否定し、終始バックミラーで左側の安全を確認していた旨の被告人の供述等はたやすく措信できない。)
- 以上のとおりなので、原判決が、被告人に対して助手席に移動する等して自車の死角圏内を含めて四囲の安全を確認して発進すべき業務上の注意義務を課したことは相当であり、被告人がこれを怠ったことも関係証拠上明らかであって、本件事故が被告人の右の注意義務の懈怠に基因するものであることは否定できないから、被告人に対し業務上過失傷害罪の成立を肯認せる原判決には法令適用の誤りは認められず、その他本件記録を精査し、当審における事実取調の結果を参酌しても、原判決には所論の如き誤りは見出せないので論旨は理由がない
と判示し、業務上過失傷害(現行法:過失運転致傷罪)の成立を認めました。
このほか、大型車両で交差点を左折進行する運転者に対し、死角との関係で大型車両運転さの過失を認めた裁判例として以下のものがあります。
東京高裁判決(昭和53年7月10日)
裁判所は、
- 被告人は、右道路に入って中央線付近を進み、右金網柵手前で中央線から右側部分に入り、 同柵の右側で交差点中心から手前約28メートル付近で同交差点を左折するため方向指示器の合図を出し、同時に左サイドミラーにより左および左後方を見たが、人や自転車等特段のものに気付かないまま、時速15キロメートルで前進し、交差点入口付近でやや右にハンドルを切り再びサイドミラーにより左後方を見たが、前同様異常に気付かなかったので、そのまま左にハンドルを切って左折を開始し約10メートル前進して被害者自転車に自車左前部を衝突、転倒させ車の下に巻き込んだことを認めることができ、とくにNの司法警察員並びに検察官に対する各供述調書、司法警察員の作成した昭和51年11月16日付、昭和52年10月15日付各実況見分調書(添付各図面写真を含む)によれば、被告人が前記のように左折合図を出した地点付近で、被害者はアンダーハンドルの自転車に乗って被告人車の左側扉の左側0.5メートル、金網柵から0.5メートル前後のところに身体がある状態で被告人車と同速度で併進し、その約2メートル後方、被告人車の左中後輪付近を永嶋卓位が普通の自転車で同様併進し、そのままの状態で交差点左側入口付近まで進んで行ったことが明らかであり、これに、被告人の司法警察員並びに検察官に対する各供述調書、司法警察員の作成した昭和51年9月9日付、昭和52年12月12日付各実況見分調書(添付図面写真を含む)を併せ検討すると、被告人が交差点内でハンドルを左に切る際には右被害者もNも被告人車の死角に人って認めることができないが、その手前の、方向指示器に合図を出し左折態勢に入った地点では、Nはもとより被害者の身体部分についても左サイドミラーによって十分確認することができたことが明白であり、同地点でも被害者及びその自転車が被告人車の死角内にあったとの所論は到底採用できない
- そして、自動車とくに死角の大きい大型貨物自動車を運転して交差点を左折しようとする者は、自車左側方を併進し、かつ交差点を直進する自転車等が死角内に入り込む可能性のあることに留意し、方向指示器等による左折の合図等左折態勢に人る時点から、左側及び左後方をサイドミラーによって注視し、現実に左折を開始した後の衝突の危険を防止する措置をとりうるよう、死角内に入り込むおそれのある人や自転車等の有無を確認して進行を続けるべき注意義務がある(殊に本件のように下水道工事等により通行帯が狭くなり、併進する人車が、自車運転台左側に近接することが容易に予想されるときは特段の注意をしなければならない)ところ、被告人は前示のように右義務を尽さず、被害者はもとよりその後続のNをも見落した程の重大な不注意を犯し、そのためその後も左方及び左後方の死角内に人や自転車等はないと軽信し、時速15キロメートルのまま左折を開始して前記事故を惹起したものであり、被告人の過失は明らかであるから、その趣旨に出でた原判決には所論のような事実誤認はない
と判示し、業務上過失致死(現行法:過失運転致死罪)の成立を認めました。
東京高裁判決(昭和54年8月20日)
裁判所は、
- 被告人は原判示日時、車長7.16メートル、車幅2.46メートル、車高2.94メートルの大型貨物自動車を運転して原判示の道路を進行して原判示の交差点に差しかかったところで右道路は幅員約8.6メートル(片側約4.3メートル)のアスファルト舗装道路で、その両側に約1メートルの幅の路側帯が設けられており、被告人が左折しようとした南林間方面に通じる道路は歩車道の区別のない幅員約5.5メートルのアスファルト舗装道路であるが、被告人が進行して来た道路は同一方向に向かう車両がかなりこんでいたので、被告人は車が少ないと思われる南林間彷面に通ずる道路に左折しようと考え、原判示交差点の手前でクラクションを鳴らして先行の同僚の車に左折するよう合図し、これに従って左折する先行車の後方で一時停止したあと、時速約10キロメートルの速度で発進し、少し右にふくらむようにして約8メートル進行した地点(前図(2)地点)で左にハンドルを切りつつ約12.5 メートル左折進行した際に前図(x1)地点で自車左側部を被害者に接触・衝突させ、同人を転倒させて轢過し、死亡させるに至った
- 本件被害者は当日朝、勤務先の工場に出勤するため、右交差点に至る道路の左側路側帯を足踏自転車に乗って本件事故現場まで被告人車と同一方向を進行して来たものであって、このことは被害者の住居、事故現場ならびに勤務工場の所在場所の地理的関係、同人の日ごろの通勤経路、当日の自宅出発時から事故発生時までの時間関係等から優に推定できるところであるが、衝突時に接着した地点における同人の動静・行動の詳細は、目撃者がいないため不明である
- しかし、当時道路上に車の渋滞はあったにしても、左側路側帯は人通りがなかったのであるから、被害者は途中停止を余儀なくされることもなく、足踏自転車に乗って普通の速度で左側路側帯をかなりの長い距離、かなりの長い時間をかけて進行して来たものと推認できる
- また被告人は、本件交差点に至る道路上に当時車両が渋滞していたため、いわゆるのろのろ運転をし、交差点の手前で一時停止するまでの間に、かなりの長い時間をかけて、数百メートルもの長い距離を進行して来たものと認められるのであるから、見通しのよい直線道路の左側路側帯を自転車に乗って進行していた被害者の姿をその間に全く見かけることが不可能であったということはありえないことである
- もっとも、被害者が被告人車の左側を並進する形となって死角に入ったため、被告人が被害者の姿を現実に見ることができない状況が一時的に生じることはありうることであるが、本件交差点の手前は少なくとも約110メートル以内には左側から本件道路に出て来る横道はないのであるから、被害者が交差点間近の左側路側帯上に突如出現するはずもなく、また被害者が右の横道から突然路側帯上に現れて瞬時に被告人車の死角内に入り、そのままの状態で衝突時まで110メートルもの距離を並進したというようなことも、およそ考えられないところである
- すなわち、被告人は本件道路を進行して来て本件事故を起こすまでの間に、よく注意しさえすれば、いずれかの時点で、左側路側帯上の被害者が左前方か、左後方かのいずれかの地点にいるのを直接視認によって、あるいはサイドミラー・アンダーミラーを通して見ることによって発見することができたはずであると認められる
- しかるに被告人は、いずれの時点でも、終始全く被害者の姿を見ていないのであるが、仮に被害者が、被告人が左折のため一時停止した時点までに、すでに被告人車より左前方の交差点の方に近づいていて被告人の運転席から視認できる地点にいたとすれば、これを見落とした被告人の過失は極めて重大であるといわなければならないが、このように断定するに足る証拠はないので、被告人が一時停止した時点では被害者はまだ被告人車の停止した地点付近の左側ないし左後方にいたとして考えてみるほかはない
- ところで所論は、左折のため一時停止した時点における被告人の注意義務に触れることなく、専ら現実に左折行為に出た時点における注意義務につき論及し、被告人が先行車に続いて左折した時点(前図(2)地点)で被害者が死角内に入っていた可能性を否定できないとし、先行車に続いて左折する場合に要求される運転者の注意義務は右の時点での左後方の確認義務で足りると解すべきであるとし、被告人は実際右の確認義務を尽くしたのであるか、その時被害者は被告人車の死角内に人っていた可能性があって、そのため同人を発見することができなかったのであるから、被告人には過失の刑責を負わせることはできない、と主張する
- しかしながら本件において過失の有無を決めるについて重要なことは、左折のための一時停止の前後ころの時点も含めて広い意味における左折に際して、運転者として尽くさなければならない注意義務の内容は何かということであって、現実に左折行動に出た時点での左後方に対する確認義務とその履行だけを取りあげて論ずれば、それで足りるというものではない
- そこで、この観点に立って考えてみるに、およそ前部左側部分に死角のある大型貨物自動車を運転して交差点を左折しようとする者は、左折のための一時停止の前後ころから、自車左側方を進行して来る自転車等があることや、それが自車の死角内に入り込むことがあることを考えて、左側路側帯上を通行する軽車両等の有無・動静に留意し、現実に左折を開始した後の接触・衝突の危険を防止するため、サイドミラー・アンダーミラー等によって左側および左後方を注視し、自車の左側ないし左後方から進入して来て死角内に入り込むおそれのある軽車両等の接近の有無・動静を確認し、それとの接触・衝突を回避するための適宜の措置をとりつつ発進し、左折行動に出なければならない業務上の注意義務があるものといわなければならない
- また、先行車に続いて左折する場合でも、その後方から約10メートルもの車間距離をおいて時速約10キロメートルで発進・進行した本件のような状況のもとにおいては、運転者に要求される注意義務としては前示したところと全く同様であって、発進にあたって左後方等を確認する義務がないとか、あるいはその義務が軽減されるとかいうことはないと解すべきである
- そうしてみると、被告人は原判示のように、自車の進人する左折方向の道路に気を取られ、左折のため発進するに際して前示の注意義務を尽くさず、左側路側帯の軽車両等の有無を確認することなく発進した過失があると認めざるをえないのであって、このような過失がある以上、その後の結果発生に至るまでの因果関係の発展経路のなかで、論旨が主張するように、仮に被告人が左折した時点(前図(2)地点)で左後方を確認したが、その時にはすでに被害者が死角内に入っていたため、その姿を見ることができなかったとしても、このことをもって被告人の刑責を否定する理由とすることはできない筋合いであるから、結局その趣旨に出たと思われる原判決には所論のような事実誤認はないといわなければならない
と判示し、業務上過失致死(現行法:過失運転致死罪)の成立を認めました。
総括
前部左側部分に死角の広がる大型車両を運転して交差点を左折する者は、自車左側方を進行して来る自転車等の障害物のあることや、それが自車の死角内に入り込むことのあることを考慮して、左側路側帯上を通行する自転車等の障害物の有無・動静に留意し、現実に左折を開始した後の接触・衝突の危険を防止するため、サイドミラミラー、アンダー等によって左側及び左後方を注視し、自車左側ないし左後方から進入し死角に入り込むおそれのある自転車等障害物の接近の有無・動静を硅認し、接触・衝突を回避するため適宜の措置をとりつつ発進し、左折行動に出なければならないといえます。
発進に際しては、車掌、助手が同乗している場合、これらの者に安全を確認させ、同乗し ていない場合は、運転席から立ち上がったり、左側に寄り助手席の窓から顔を出し、あるい は降車するなどして死角の安全を確認すべきといえます。
助手席に移動し、降車して安全を確認しても、発車での間、更に死角内に進入する歩行者等があれば、それに応じた安全確認を尽くすべきであるといえます。
業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪の記事まとめ一覧