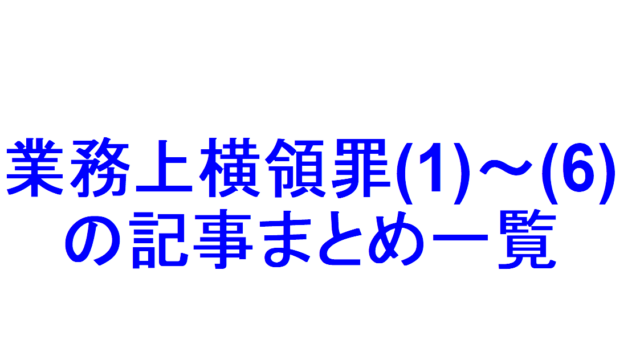業務上横領罪(2) ~「業務上横領罪の『業務性』が認められた具体的な事例」「業務の『継続性』の程度」「業務の根拠は、法令、契約、慣例による必要はない」「業務は、本務、兼務、他人に代わって事実上行う事務でもよい」を判例で解説~
業務上横領罪の「業務性」が認められた具体的な事例
前回の記事において、業務上横領罪の「業務」とは、『社会生活上の地位に基づいて、反復又は継続して行う事務』であることを説明しました。
今回の記事では、業務上横領罪の業務性が認めらられた参考となる判例を紹介します。
業務における継続性について説明した判例
業務上横領罪の業務性を認定するに当たり、業務の「継続性」の程度について説明した以下の判例があります。
大審院判決(明治45年3月4日、大正3年6月17日、昭和13年3月9日)
この判例で、裁判官は、
- 職務又は営業等のように、 これによって自己の生活を維持する業務に限定されず、一定の事務を常業として行っていれば足り、その事務が収入、報酬、生活の利益の享受を目的とするものであることを要せず、また事務の性質自体が継続的なものであることを要しない
と判示し、継続性について、事務の性質自体が継続的なものでなくても、一定の事務を業として行っていれば、継続性が認められるとしました。
大審院判決(明治45年3月4日)
一定の職務を有する一定の地域における住民の共有金を横領した事実で、被告人の弁護人が、
- 「人民総代」という任務は、間断なく行われるものではないし、継続的収入を伴うものではないので、人民の総代たる社会生活上の地位に過ぎずして業にあらず
として、業務上横領罪の業務性がないと主張したのに対し、裁判官は、業務上横領罪の業務性につき、
- その事務の性質が継続的なること、若しくは、その事務をもって収入の目的と為すことを必要とせず
- 人民総代として一定の事務を有し、これを常業として行う以上は、収入の有無と事務の性質とを問わず、これを刑法上の業務というを妨げず
と判示し、業務性を認めるに当たり、事務の性質が継続的であることは必要ではなく、一定の事務を行い、これを業務として行う以上は業務性が認められるとしました。
業務性を認めるに当たり、業務の根拠が、法令、契約、慣例によるものである必要はない
法令、契約、慣例による業務でなければ、業務性が認めらないというものではありません。
法令、契約、慣例によらない業務でも、業務上横領罪における業務性が認められます。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(明治44年10月26日、大正3年6月17日)
この判例で、裁判官は、
- 業務上横領罪における業務の根拠は法令、契約、慣例によるとを問わない
としました。
この判例で、裁判官は、
- 刑法第253条にいわゆる業務とは、法令によると、慣例によると、将た契約によるとを問わず、苟も一定の事務を常業として反覆する場合を指称するのである
- 従って、本件において、判示給与金品の伝達事務が、被告人の民生委員としての法令上当然の業務でなくても、判示a村において、判示日時以降、民生委員を通して給与金品を支給されることになり、被告人が民生委員として、その事務を担当するに至った事実のある以上、その事務は、被告人の業務と解すべきである
- 被告人が民生委員として、判示給与金品を伝達する業務を担当していたものであることを肯認するに十分であるから、原判決が被告人の判示所為を業務上横領罪に問擬したことは正当である
と判示しました。
この判例は、
- 被告人が「農事組合長代理として配給事務その他組合の業務一切を取扱っていたものである」ことは認めている
- それ故、かかる被告人の横領は、業務横領として処罰するは当然である
- 農事実行組合には、法令上、組合長代理が認められていないことは、業務横領を認める妨げとなるものではない
と判示し、被告人の業務が法令上の業務でないとしても、業務性は否定されないとしました。
業務は、本務、兼務、他人に代わって事実上行う事務でもよい
業務上横領罪における業務は、本務、兼務、他人に代わって事実上行う事務でもよいとされます。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 復員事務官で、宇品上陸地連絡所庶務課勤務を命ぜられだ者が、他課の所管ではあるが、復員者に対する旅費の交付及びこれに充てる国庫の前渡資金保管の事務についても、平素から事実上、担当主任事務官の補佐としてこれに従事し、関係上司において、これを認めていた以上、特にその命令に出でたものでなくても、その事務の処理は、刑法第253条のいわゆる業務に該当するものと解すべきである
と判示し、補佐として行う事務について、業務性が認められるとしました。
雇用関係等が消滅した後であっても、後任者にその事務の引継ぎを終えるまでは、他人の物を業務上占有する地位にある
職務上の地位に基づき、業務上他人の物を占有する者は、その職務の根拠になる職務上の地位を離れたり、雇用関係等が消滅した後であっても、後任者等にその事務の引継ぎを終えるまでは、他人の物を業務上占有する地位にあると認められます(大審院判決 明治44年3月16日、大審院判決 大正3年1月23日、大審院判決 大正11年8月3日、名古屋高裁判決 昭和28年2月26日)。