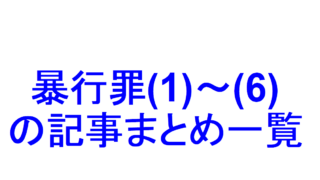傷害罪(1) ~「傷害罪とは?」「保護法益(身体の安全)」「傷害罪の客体(人の身体)」「人の始期(一部露出説)」「国外犯」を判例で解説~
これから複数回にわたり、傷害罪(刑法204条)について解説します。
傷害罪とは?
傷害罪は、人の身体を傷害することによって成立する罪です。
傷害罪の保護法益(身体の安全)
傷害罪の保護法益は、身体の安全です。
保護法益が身体の安全であることは、暴行罪、傷害致死罪などの傷害の罪全般(刑法204条から208条の2)にも当てはまります。
人の身体の安穏は、あらゆる人間の活動の源泉です。
なので、法律により、人の身体の安全を違法な攻撃から保護する必要があります。
傷害罪の客体(人の身体)
傷害罪における行為の客体は、「人の身体」です。
行為の客体が「人の身体」であることは、暴行罪、傷害致死罪などの傷害の罪全般(刑法204条から208条の2)にも当てはまります。
(1) 「人」の意義
傷害罪の客体である「人の身体」における「人」とは、行為者本人を除く「身体」を有する自然人を指します。
法人その他の団体を含みません。
傷害の行為者本人は除きます。
刑法202条(自殺関与罪、同意殺人罪)のような規定がない限り、自傷行為は犯罪になりません。
幼児や精神障害者が自傷行為をするのを、これらの者を保護すべき者がその行為を放任する場合に保護責任者遺棄致死傷罪が成立したり、他人を強制して自傷させる場合に傷害罪の間接正犯が成立する場合はあります。
被害者を強制して自傷させた行為について、傷害罪の間接正犯を認めた判例として、以下のものがあります。
鹿児島地裁判決(昭和59年5月31日)
この判例は、暴行脅迫の結果、自己の指を歯でかみ切らせた行為について、被害者を利用した間接正犯にあたるとして傷害罪の成立を認めました。
事案は、被害者の胸部や腹部をけるなどの暴行を加えた後、被害者に対し、「今日だけは命を助けてやる。そのかわり指を詰めろ、歯でかんで詰めろ。」、「指を詰めんかったら、殺すぞ」などと申し向け、暴行、脅迫により抗拒不能の状態に陥っている被害者にその右手の小指(右第五指)をかみ切らせた事案です。
まず、弁護人は、
- 被害者が自己の小指を歯でかみ切ったのは自傷行為であって、この点につき被告人A、Bに傷害の間接正犯は成立しない
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 被告人Aは、被害者を終始「今日は殺す」などと脅迫し、特に被告人Bをして、被害者に対し、執拗かつ強力なリンチを2時間以上にもわたって行なわせているものであって、こうした徹底したリンチによつて被害者が当時肉体的にも精神的にも死という極限に近い状況に追い詰められていたことは十分に推認することができる
- そのような状況下で被害者が被告人Aの命令に従って自己の右第五指を歯でかみ切ったのは、指一本をかみ切ればそれと引き替えに命が助かるという絶対的命題のもとに、自己の自由意思の存立を失い、その限りで自己を被告人Aの道具と化したからにほかならず、反面、被告人Aの側からしてみれば、自己の脅迫等により生か死かの選択を迫られ抗拒不能の状態に陥っている被害者を利用してその指をかみ切らせたと認めるのが相当である
と判示し、被害者が自己の小指を歯でかみ切った点につき、傷害の間接正犯の成立を認めました。
(2) 人の始期(一部露出説が通説)
人の始期は、出生です。
刑法上、出生前は「胎児」として「人」とは区別されます。
分娩作用が相当の時間的経過を経て完成するものであることから、出生の時期、すなわち「胎児」と「人」とを画する時期については、陣痛説(分娩開始説)、一部露出説、頭部露出説、全部露出説、独立呼吸説の各説があります。
刑法上は、『一部露出説』が通説・判例の考え方になっています。
この考え方は、
- 傷害罪や殺人罪などが、人の生命・身体に対する不法な侵害である以上、そのような不法な侵害を受けることができる状態に達すれば、これらの罪の客体として保護する必要がある
- したがって、胎児が一部でも母体外に現れれば、その時点で、母体とは独立に、その生命・身体を攻撃することができるのであるから、この時期をもって、「人」の始期と捉えるべきである
という考え方に基づきます。
傷害罪、殺人罪などの客体たる「人」になる時期について、『一部露出説』とることを明らかにした判例として、以下のものがあります。
大審院判決(大正8年12月13日)
この判例で、裁判官は、
- 胎児が未だ母体より全然分離して呼吸作用を始めるに至らざるも、既に母体よりその一部を露出したる以上、母体に関係なく外部よりこれに死亡を来すべき侵害を加えるを得べきが故に、殺人罪の客体となり得べき人なりというを妨げず
と判示し、産門から一部露出した胎児の面部を強圧した行為を殺人行為の一部と認めました。
なお、この判例は、胎児が母親の産門から頭頂部を露出し、まさに出産しようとする際に、両手を産門に挿入し、胎児の鼻口を圧迫し、胎児を死に至らせ、胎児の頭部をつかんで引き出した事実に対し、殺人罪を適用せず、堕胎罪を認めた事例になります。
ちなみに、民法においては、人の始期、すなわち、その権利能力が認められる時期の始点は『全部露出説』が通説になっています。
(3) 人の終期
人の終期は死亡です。
死亡の時期は、呼吸・心拍動の終止、瞳孔散大により判定するという考え方(いわゆる三徴候説)が通説になっています。
刑法上は、「心臓死」をもって人の死と解すべきとされます。
参考になる判例として、以下の判例があります。
大阪地裁判決(平成5年7月9日)
この判例は、被告人の暴行により、被害者が脳死になった後、人工呼吸器が取り外され、心臓死となった事案について、暴行と心臓死との因果関係を肯定して傷害致死罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 被害者は、眉間部打撲によるびまん性脳損傷により脳死状態に陥り、9月3日午後7時に第1回目の脳死判定がなされ、次いで9月4日午後7時35分に第2回目の脳死判定がなされ、脳死が確定したこと、そして、被害者の妻であるIらは、E医師らから、被害者が脳死と判定されたこと等について説明を受けた上、9月5日午前9時ころ、被害者の人工呼吸器を取り外すことを承諾したこと、9月5日午後5時40分ころ、被害者の家族の立会いの下に、E医師により被害者の人工呼吸器が取り外され、9月5日午後6時ころ、被害者の心臓停止が確認されたことが認められる
- そこで、弁護人は、被害者が心臓停止に至るにつき、人工呼吸器の取り外し措置が介在しているところから、被告人の暴行と被害者の心臓死(「三徴候」による死、以下同じ。)との間に因果関係があるというにはなお疑問が残ると主張する
- しかし、前記のとおり、被告人の眉間部打撲行為により、被害者は、びまん性脳損傷を惹起して脳死状態に陥り、二度にわたる脳死判定の結果脳死が確定されて、もはや脳機能を回復することは全く不可能であり、心臓死が確実に切迫してこれを回避することが全く不可能な状態に立ち至っているのであるから、人工呼吸器の取り外し措置によって被害者の心臓死の時期が多少なりとも早められたとしても、被告人の眉間部打撲と被害者の心臓死との間の因果関係を肯定することができるというべきである
- よって、被告人には傷害致死罪が成立する
と判示しました。
なお、平成9年に制定された「臓器の移植に関する法律」において、臓器移植に関しては死体に「脳死した者の身体」を含むとし、「脳死した者の身体」を「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう」と定義しました。
これにより、臓器移植に限っては、「脳死」が人の死として取り扱われることとなり、臓器移植を目的として、同法律の定める基準に従い、脳死と判断された場合には、その時点から刑法上も「人」ではなくなることになっています。
余命のない者も傷害罪の客体になる
余命のない者も傷害罪・傷害致死罪の客体になります。
持病のため余命のない者に対して傷害致死罪の成立を認めた以下の判例があります。
東京高判判決(昭和31年2月29日)
数日後に死ぬかも知れないといわれていた病者の頭部を殴って死亡させた事案で、裁判官は、
- 鑑定の結果によれば、Eの死因は肺壊疽で、全身的に生活機能が衰弱している上、頭部殴打により脳震盪を起こし、意識不明のまま心臓呼吸が停止したと推定せられるというのであるから、少くとも被告人の暴行による脳震盪はEの死を早めたもので、同人の死に対し、一原因を与えたものというべきである
- 而して、傷害致死罪において致死の原因たる傷害は、死亡の原因をなしたものであれば足り、それが死亡の唯一又は直接の原因であったことを必要とするものではないから、Eの肺壊疽による病気と相俟って死亡したものとしても、被告人の暴行による脳震盪がEの死亡に対し原因を与えたことを否定し得ない
- もっともEが通常人の健康体であったとすれば、被告人の加えた程度の暴行によっては死亡することは稀であろうが絶無とはいえない訳であり、殊にEは病弱者であったのであるから、これに対し、暴行を加えれば死の転帰を見るに至るべきことは実験法則上明かである
- 故に被告人の暴行と、Eの死との間には法律上相当因果関係があると認めるべきである
と判示し、持病のため余命のない者に対する傷害致死罪の成立を認めました。
国外犯
傷害罪(刑法204条)及び傷害致死罪(刑法205条)は、日本国民が日本国外で犯したときも処罰される犯罪です(刑法3条8号)。
たとえば、アメリカに旅行に行き、現地で人を殴るなどして傷害罪や傷害致死罪を犯せば、日本に帰国した時に、日本の刑法が適用され、日本の刑事裁判で処罰され得るということです。
また、刑法4条の2に「この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する」と規定されるととろから、「人質をとる行為に関する国際条約」、「国際的に保護される者(外交官を含む)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約」などの条約に規定される国際犯罪が傷害罪や傷害致死罪に当たるときは、何人による国外における犯罪であっても、傷害罪や傷害致死罪が適用されることになります。